





作(な)されたものを知ることは
作(な)すことへ参加すること
毎年七月に、福浄寺では作上がり(さくあがり)法要を勤めてきています。私は入寺するまで、この「作上がり」という名称の法要を知りませんでした。例年六月に寺周辺の地区では田植えが行われるなど農繁期です。六月は年間行事としての寺の法要が行われてきていませんので、田植えが終わり、ひと段落をしたところで、「さぁ、寺に参ろう」、「念仏申して、念仏のいわれを聞いていこう」という心でこの法要は勤められてきたのではないかと思います。
仏教では「恩」(おん)という言葉を大切にしています。この恩という言葉のもとになっているといわれるのが、サンスクリット語の「クリタ(kṛta)」です。「作(な)されたる」、「作されたるもの」という意味があるそうです。ですから「恩」とは、私を生かすために「作されたる」恵みを指すのでしょう。私に「作されたるもの」を知り、「作されたる」ことによって育てられた力を上げて、自ら「作す」ことに参加していく。「作上がり」という法要の名には、「知恩」と「報徳」の願いが込められているのではないかと思うのです。
あるところで目にしたのですが、欧米にはこの「恩」という概念がないそうです。もちろん他の人から何かしてもらった時、その具体的な行為に対して「ありがとう」という言葉はあるそうですが、そこに深い恩を感じる、背景を顧みるというような恩の感覚はないそうです。アメリカでは世代間の断絶ということをいかにして解消するかという課題に対して、日本人のもつ「恩」の概念が大切ではないかということで、ローマ字でそのまま、「ON」と表記して、恩の感覚や心を研究している学者がいるそうです。
さらに思い起こすのは「食べ物様には 仏がござる 拝んで食べなされ」という言葉を残された宇野正一氏の言葉です。正一氏の祖父の口癖は「お米粒には仏がござる」で、こぼしたご飯粒も水で洗って食べるように育てられたのだそうです。その正一氏が小学生五年生の時、実際に顕微鏡でお米を見てみたが、仏は見えず、学校の先生に尋ねると「それは君のおじいさんの迷信だ。そんなものが米粒の中にいるわけがない」といい、側にいる友だちからも笑われた。とても悔しくて家に帰り、おじいさんに「おじいちゃんは僕に嘘をついたね」と責めたのだそうです。すると祖父は「この罰当たり」といいながら仏壇に向かって泣きだしてしまった。成人した正一氏は、その時の泣いていた祖父の後ろ姿が忘れられないと語られていました。
あらためて思いますが、現代は目に見える物事、それこそ「それは君のおじいさんの迷信だ。そんなものが米粒の中にいるわけがない」と語った学校の先生のような物の見方しか出来なくなっているように感じます。もちろん私も含めてです。目には見えないけれども食べ物には私を生かすはたらきがある。そのはたらきそのものを正一氏の祖父は仏と呼んだのでしょう。
私自身がこの世に父母を縁として、いのちを恵まれ、数えきれないほどの他のいのちを犠牲にして生きていること。さらに水、光、空気、大地。あらゆるところに私を生かそうとする「作されたる」はたらきがあること。これらの私を私として在らしめている諸々の恩恵に気付かせる、根源のはたらきそのものが「南無阿弥陀仏」であると親鸞聖人は教えているのではないでしょうか。
幼い頃から、無数の諸仏の「ナンマンダブツ」の「作されたる」勧めがあって、今ナンマンダブツと「作す」私がいる重大さを、作上がり法要にあらためておもいます。 令和7年 7月 深草誓弥
食わねば死ぬ 緊急の課題 食っても死ぬ 永遠の問題
一時期、無人島でのサバイバルや秘境から生還する様子を収めた動画に夢中になっていたことがあります。限られた環境の中で、どのように一日を過ごし、生き延びていくのかを見るのはとても興味深く、特に火起こしの方法や食料の確保、雨風をしのぐ住まいづくりなど、サバイバルに必要な技術や知恵に強く惹かれました。そうした動画では、まず「食」を確保し、休息をとれる「住まい」を整え、寒さや害虫から身を守るための「衣類」を用意するという流れが基本となっています。まさに、人が生きる上で欠かせない「衣・食・住」の確保そのものです。
これは、私たちの日常生活でも同様で、衣・食・住を整えることは生活の基盤であり、緊急時や災害時にも真っ先に取り組むべき課題です。最近の"米騒動"では、安い米を求めてスーパーの前に長蛇の列ができるという光景が話題になりました。そうした姿を目の当たりにすると、私たちの「食」への関心や、その重要性を改めて実感させられます。
「生きる」ためには「食べる」ことが欠かせません。しかし、「食べても死ぬ」という現実からは逃れることができません。今月の言葉は、この相反する二つの事実を抱えながら、私たちはいかに生きるべきかを問いかけています。どれだけ食べても、どれだけ健康に気を遣い、努力して生きたとしても、人はやがて死を迎えます。死を避けることは誰にもできません。お釈迦様のお悟りも、この「老・病・死」という人生の現実に正面から向き合われたことがきっかけとなって、「無常」の道理を深く悟られたと伝えられています。
私たちは、「何のために生まれ、何のために生き、死んだらどうなるのか」「人生の目的とは何か」といった根本的な問いを、人生の中で立ち止まり、見つめ直す必要があります。そして「死とどう向き合うか」という大きな問題は、阿弥陀仏の本願に気づくための大切な問いでもあるのです。死という避けられない事実を通してこそ、「人生の意味」「生きる意味」を仏法から問われ、深く見つめ直すことが求められているのです。
加賀の三羽ガラスと称された高光大船師に、次のようなエピソードが残されています。ある時、両親に寺参りを勧められても耳を貸さなかった若者が、高光大船師に「仏法とは何ですか」と尋ねると、師は「仏法とは鉄砲の反対だ」と答えました。「鉄砲は生きている者を殺すが、仏法は死んでいる者を生かすものだ」というのです。若者が「棺桶の中の者を生かすのか」と問うと、「あれは遺体。お前のような者を死んでいる者というのだ」と言います。若者が「自分は生きている」と手足を動かすと、「それは動いているだけで、生きているのではない。機関車に石炭を放り込めば、定められたレールの上を走り出す。あれは"動いている"のであって、"生きている"のではない。お前も三度のご飯を放り込んでやると、習慣という定められたレールの上をカタコトカタコト走り出す。それもまた、動いているだけで、生きているのではない」と返されたそうです。この言葉をきっかけに、若者は仏法を聴くようになったといいます。
ここでの「死んでいる者」とは、外見上は生きているように見えても、何のために生きているのか、人生の意味を知らず、気づきのないまま過ごしている人のことを指します。高光師にとって「生きている」とは、単に肉体が動いている状態ではなく、仏法に目覚めているかどうかが重要なのです。仏法とは、「終わりのある人生を、あなたはどう生きるのか」という問いへの目覚めを促すものです。そして仏法は、この「終わり(死)」から目を逸らすのではなく、むしろ正面から見つめることを勧めています。
たしかに「生きるために食べる」ことは大事です。しかし、高光師の言葉を借りれば、それは「生きる」ためではなく、ただ「動く」ための燃料補給にすぎないのかもしれません。食べることだけに時間を費やしていないか? 食べても死ぬ命だけれども、本当に「今を生きている」のか? その事を問われていると感じました。 令和7年6月 貢清春
老人は 生きづらい世の 救世主
『ゴリラからの警告』山極(やまぎわ)寿一
アンチエイジングという言葉がさかんに用いられるようになりました。年齢を重ねる加齢はいのちある限り誰にでも同じスピードで起ります。しかし、老化は加齢に伴っておこる身体や精神の衰えです。目が見えにくくなったり、耳が聞こえにくくなったり。そして老化するスピードは個人差があります。私自身も段々と老眼が進んでいっています。アンチエイジングは、運動や食生活などの生活習慣を変えることで老化のスピードに抗う、「抗老化」の取り組みのことをいうようです。
もちろん健康で長生きしたいと誰もが思います。しかし、抗っても抗えないものでしょう。先日、病気を患われた年配の御門徒と話をしていると、「年ば、とっとるとやけん、病気にもなるさ。いろいろ、悪かとこの出てくる。」と笑顔で話をされていました。何かその笑顔が不思議と心に残りました。
今月は、長年ゴリラなどの霊長類の研究をされてこられた山極さんの言葉です。「人間から一歩離れて人間を見つめるため」にゴリラの研究を続けられています。山極さんが、かつて野生のニホンザルの調査をしたときのことを著書で次のように紹介されていました。
あるとき一つの群れが分裂して二つの群れができた。血縁の近いメスたちが分派行動をし、それにオスや子どもたちがついていって、はっきり別々の群れになった。暮らす領域が一緒なので、よく群れが衝突し、いがみ合うようになった。その対立の中で、ある老いたメスが不思議な行動をとった。互いに威嚇し、にらみ合う若いオスたちの前をひょうひょうと通り過ぎ、落ち着いて葉っぱを食べはじめた。まるで敵対する現場が目に入らないように。それを見て、他のサルたちはあっけにとられたように戦いをやめた。この老いたメスはどちらの群れにも姿を現した。群れと群れがいがみ合う世界とは全く別の世界に、この老いたメスはいたのである。
山極さんは、このニホンザルの調査を通して、老境の者が若者たちの共存へ重要な意味を持っていることを感じたそうです。人間社会でも、「老人はただ存在することで、目的的な強い束縛から人間を救ってきたのではないだろうか」と述べられています。
青年や壮年期の人とは違う時間軸を生きる老年期の人の姿が、大きなインパクトを与えるのです。目標を立て、いかに効率よく目標を達成するか。それはときに個人を犠牲にして足並みをそろえて目的を達成しようとさえする。目的が過剰になれば、だんだん命や時間の価値が失われていく。その行き過ぎをとがめるために別の時間を生きる老年期の方の存在が必要なのです、と山極さんは語られています。
思えば私が小さい頃、老年期にある人たちは、ゆったりとした時間軸のなかで生きておられました。タイパ、コスパというような効率化、生産性を追い求め、人間性を失い、自ら人が生きづらい世を作り出す私たちに、老年期の人の存在が「あなたがたは、そんなに急いでどこにいこうとしているのか」と問うているのです。 令和7年 5月 深草誓弥
この世に 自分より 劣っている者が 一人でもいると 思っているような人には 仏法は響いてこない (伊藤元)
1月の御正忌報恩講に講師として御出講して下さいました伊藤元先生は、昨年2024年10月にお浄土へと還られました。昨年まで御出講いただきました先生は、ご高齢ではございましたが活気あふれるご法話で、丁寧にお念仏のみ教えをお話し下さいました。先生は常に参詣人の反応を見ながらご法話をして下さり、理解の難しい仏教の言葉でも、生活の具体的な出来事を通して、分かりやすく教えて下さいました。今月の言葉は、伊藤先生が御正忌のご法話の中で、お話し下さった言葉です。しかしなぜ「自分より劣っている人が一人でもいる」と、仏法が響かないのでしょうか。
お寺にお参りし、仏法を聴聞することはとても大切なことです。しかし仏法を聞き続けていると、「ああ、自分は少し分かってきたぞ」とか、「あの人はまだ知らないな」といった思いがふっと湧いてくることがあります。他人よりも知識が豊富になったことで、自分が偉くなったと勘違いするのです。すると知識の無い人、自分より劣っている人を下に見てしまいます。それは人間の自然な心の動きなのかもしれませんが、それは「慢(まん)」という煩悩の一つです。「慢」とは、「慢心」または「おごりたかぶる心」を指します。これは、自分を過大に評価したり、他人を軽んじたりする煩悩を意味します。
蓮如上人は、「心得たと思うは、心得ぬなり。心得ぬと思うは、こころえたるなり」と仰せられますが、私たちが教えを聞くことで、いつの間にか物知り顔をして、「心得たと思っている賢者」になってしまう危うさを指摘されるのだと思います。私たちは知識を求め、他人よりも多くの知識を持っていることが素晴らしいことのように思い込んでしまっているのではないでしょうか。仏法を聞いて「なるほど」と思えることはあるけれども、その「分かったつもり」や「人より知っている」という慢心は、実は仏法の道をふさぐものにもなります。伊藤先生は、教えを聞いている私の姿勢を、あえて厳しく指摘されたのだと思います
仏様の智慧とは、仏様の方から私達を照らし、真実に目覚ましめようと私の心にはたらきかけて下さいます。仏法を聴聞するということは、沢山仏教語を学んで知識をつけて、物知りになることが目的ではありません。教えに遇えば遇うほど私の姿を教えられ、知っていることであっても何度も何度もくりかえし聞いて、我が身の事として教えをいただくことが大切なことです。真実なる仏法に照らされたら、「自分は何も分かってなかった」と気づかされる。その繰り返しこそが、仏法を聞くということなのでしょう。何も分かっていない自分が知らされると、自分より劣っている人は一人もいなくなります。逆に私の身の回りの人は、お念仏を勧めて下さる大切な人として見えてくるのでしょう。伊藤先生はご法話の中で、吉川英治氏の「我以外皆我師(われ以外、皆わが師なり)」という言葉もご紹介下さいました。私以外の方々は、この私をお念仏の世界に導いてくださった師、先生として拝んでいく世界があると教えられます。私の身の回りの一切に対して、手を合わせながら生きていけるということです。
自分より劣っている人が見えてしまう自分、物知り顔をしてしまう自分は、ダメなやつだから仏法から外される、ということではありません。むしろ、そういう私こそが、阿弥陀仏の救いの対象であることも仏法から教えられます。浄土真宗の他力の教えは、「こんな私ではダメだ」と自分を裁くためのものではなく、「このような私でしかない」と気づくとき、「そんなあなたをこそ、捨てはしない」と呼びかけてくるのです。 令和7年4月 貢清春
世の中は 悪人の懺悔の涙によってうるおされて 善人の驕りによってかわいていく (金子大栄)
いつの時代であったとしても、私たち人間は、自分というものを絶対化し、「尊貴自大」と経典に教えられるように、自分ほど尊いものはないと振舞ってきたのでしょうが、今日ほど人間の自己中心性の闇が露呈している時代はないのではないかと思います。
アメリカのトランプ大統領をめぐるニュースが連日報道されていますが、先日は「慈悲の心を持つように」と諭した大聖堂の主教に対して、トランプ氏が強く反発したというニュースがありました。自らの考えや、思いにそぐわないものは徹底排除し、自分の思考に近いものだけを近くに置いているのでしょうから、おかしいと感じても誰も止めることはできない状態ではないかと危惧します。
それと同時に、そのような「自分は正しい、他は間違っている」という強い思い込みが自らの中にもあること。そして、その正しいと思い込んでいる自分の外に、「あの人は悪人で、この人は善人だ」と勝手に決めている私がいることに気付かされます。「トランプ氏は悪だ」といっている当の私は、「自分は正しい」というところに立っているのです。
そのような近代の闇といえる、自己中心性に対し、問題を提起しているのが夏目漱石の『こころ』です。「私」と名のる小説の語り手である若い学生から、「先生」と慕われていた人物が、ある時、「私」に追求するように語りかけます。
「悪い人間という一種の人間が世の中にあると君は思っているんですか。そんな鋳型に入れたような悪人は世の中にあるはずはありませんよ。平生はみんな善人なんです。少なくともみんな普通の人間なんです。それが、いざという間際に、急に悪人に変わるんだから恐ろしいのです。だから油断ができないんです。」(夏目漱石『こころ』より)
この言葉は「先生」自身が、自分は「善きもの」、「正しきもの」だと思っていた、その思い込みが、友人を死に追いやるような心をもつ者になって砕け散った、悲鳴のような言葉だったと小説を読み進めると知らされます。「世の中は 悪人の懺悔の涙によってうるおされて」とありますが、懺悔は自己反省ではありません。省みている自分自身が明らかにされなければなりません。悪人は真理の光に照らされて明らかになった姿であり、その姿は「いざという間際に」人を傷つけかねない現実の私です。煩悩に翻弄されて、誰かを傷つけながら生きざるを得ない自分自身に出あうところに、懺悔の涙が流れるのでしょう。親鸞聖人は「煩悩具足のわれら」と語られています。自分で自分の中に沸き起こってくる煩悩をどうすることもできない懺悔の涙のところに、はじめて「われら」といわれる、如来から大悲されている衆生の現実に立つことができます。
「善人の驕りによってかわいていく」、渇きという言葉がもちいられていますが、渇愛という言葉があります。まるでのどが渇いたものが限りなく水を求めるような自分自身に対する執着です。驕り、自分自身を絶対化するということは、同時に帰依すべきものを見失い、自分自身が批判されることが無くなることでもあります。今日の時代社会は、善と善、正義と正義がぶつかり合い、バラバラになっている感覚を持ちます。だからこそ、夏目漱石が『こころ』で問題提起した自己中心性の闇を自分のこととして見つめていきたいと思います。 令和7年 3月 深草誓弥
人の悪口は嘘でも面白いが 自分の悪口は本当でも腹が立つ
遠慮や気を使う必要がない人たちが集まると、その場にいない人の陰口を言ったり欠点をあげつらったりと、悪口が飛び交うことがあります。他人の悪口は嘘でも面白いものです。しかしその悪口の矛先が自分に向けられた時にはどうでしょう。たとえ自分の本当の事を言い当てられた言葉だとしても、腹を立てて不機嫌になってしまいます。私もそうですが、素直に「はい、その通りでした」と頷けない根性を持っています。自分の本当の姿を受け入れることはとても難しいものです。だれでも自分がかわいいし、自己中心的な生き方をしています。今月の言葉は我が身をするどく言い当てられた言葉で、耳が痛いです。
蓮如上人は、『人の悪き事はよくよく見ゆるなり、我が身の悪き事は覚えざるものなり(蓮如上人御一代記聞書195番)』とおっしゃっています。私たちは誰でもが善悪を計るモノサシを持っていますが、他人に対しての尺度と、自分に対しての尺度が違うので、自分の「悪い」ところは気が付かず、他人の悪い事には敏感に反応し目に付いてしまいます。自分の悪に気が付かないどころか、「自分はいつでも正しい、悪い所は無い」という所に立ち、自分を省みようとしないのが私たちの本当の姿なのではないでしょうか。どこまでも都合よく自分自身を見ようとする、その心を照らす教えに出会わない限り、自分自身の愚かさに気付くことはありません。
仏様は「自分の目で自分の姿を見ることが出来ないから、お経の教えの中に自分の姿を見なさい」と私たちに問いかけています。その事を中国の善導大師は『経教はこれを喩うるに鏡のごとし。しばしば読み、しばしば尋ぬれば、智慧を開発す(観無量寿経疏)』と説かれています。お経は聞いているだけでは何を説いているのかよく分かりませんが、喩えてみれば私を映す「鏡」の様だというのです。
自分の肉眼で自分の体を見ようとすると、見る範囲が限られてきます。後頭部や背中を見ることは出来ませんし、自分の顔を見るには鏡が必要です。毎日見る鏡は外側しか映し出しませんが、経教は私の内面をありのままに映し出す鏡の様なものなのです。お経を何度も読み、何度も仏のお心を尋ねていけば、仏の智慧が開かれていきます。智慧が生み出され開かれていくとは、自分が賢者になって偉い者になっていくのではありません。お聖教をくり返し読み求めていくことによって自身の迷いの姿が知らされ、愚かな凡夫であるという事が教えられるのです。
阿弥陀は、そういう身を生きる凡夫だからこそ見捨てずに、浄土へ迎え取ろうとはたらきかけておられるのです。その事を御経の中には「念仏衆生、摂取不捨」と説き、仏に背を向け逃げている愚かな私であったとしても、追いかけて摂取し捨てないとご本願に誓われました。そしてそのこころを私たちに届けようと回向されたのがお念仏です。お経の教えを鏡とするということは、仰ぐべき教えが明確になり、私が目指すべき方向が浄土であると決定するということでしょう。
悪口は言わないようにしようとか、本当のことを言われても腹を立てないでおこうという道徳の話ではありません。悪口を言ってしまう私、本当の自分を知らない私だからこそ、経教の鏡が必要なのだと問いかけているのが今月の言葉なのだと思います。 令和7年2月 貢清春
南無阿弥陀仏は わたしを 生み 育て 人と成す 久遠の母性 (池田勇諦)
新しい年を今年も迎えることができました。「あけましておめでとう」とお正月には挨拶を交わしますが、いったい何がめでたいことでしょうか。一つ歳を重ねたからでしょうか。御馳走を食べたり、お年玉をもらえるからでしょうか。真にめでたいことは何でしょうか。
「去年はあんまりいいことなかったけど、今年はいいことあるだろう」と新しい年に望みを持つのは当然のことかもしれません。しかし、何でも望み通りになった年などありはしません。思い通りにならない現実の中を思い通りになることを夢見ていきるならば、酔生夢死と教えられるように、もう二度と戻らない今を無駄に過ごしてしまうことになります。
今月の掲示板の言葉は、南無阿弥陀仏について池田勇諦先生が教えられた言葉です。先生は著書の中で南無阿弥陀仏には三つの読み方があるとして、次のようにしめされています。
一つ目は「阿弥陀仏に南無したてまつれ」と読むと、釈迦諸仏がつねに私の背を押してくださる励ましの言葉になること。
二つ目の読み方は「阿弥陀仏に南無せよ」と読むと、そこに阿弥陀の「本願招喚の勅命」、阿弥陀からの至上命令になること。
そして三つ目が「阿弥陀仏に南無したてまつる」と読むと、「私は阿弥陀仏に南無するものとして生きていきます」という決断、告白をあらわす言葉となること。
南無阿弥陀仏は、私という存在を真にこの世に誕生させ、育て、人とならしめる母性である、つまり南無阿弥陀仏が真の親であると掲示板の言葉は教えています。私たちはどんな人も二親を縁としてこの世に生を受けますが、そのことだけでは自分は「産み落とされた者」、「気が付けば生まれていた」という思いにとらわれ、思い通りにいくかいかないかという眼差しで自分の人生を眺める傍観者になるほかありません。
私の存在のはじめに「人として生きよう」という願いのあることを教えるのが南無阿弥陀仏でしょう。久遠の昔より流転していると教えられるように、この世に誕生する前から迷い続けてきている私に、すでにして南無阿弥陀仏が与えられていることの不思議。そのことを親が我が子のことを思うように、私が念ずるよりも先に、阿弥陀仏に念じられていると先達は教えられています。
妙好人の浅原才市さんは「なむあみだぶつ なむあみだぶつ 念仏は 親の呼び声 子の返事」と言葉を残しておられます。真の親として私を念じている、呼んでいる阿弥陀仏。私たちは阿弥陀仏を親と慕い、親を呼ぶのです。子が母をおもうがごとく、仏を憶うのです。
今月、福浄寺は報恩講を迎えます。親鸞聖人は人間が生きていく上でなくてはならないことを「真宗」という言葉で示されました。真宗に出遇えばいつの、どこの、誰でもがどんな状況の中でも自分を失わずに生き活きと生きていけることを、私たちに先立って念仏にあい、念仏に生きた人々が証明されています。すでにして私のところに念仏がいたりとどいていることこそ、真実めでたきことではないでしょうか。さあ、念仏申しましょう。令和7年 1月 深草誓弥
不幸 今の自分に与えられてあるもの 今の自分にめぐっていることが どれだけ幸せなことか わからないこと
「報恩講」の季節となりました。報恩講とは親鸞聖人のご命日を縁として集まって「正信偈」のお勤めをし、仏法を聞き、お斎を味わう。この報恩講を勤めてきた歴史が、浄土真宗という宗派となったと言っても過言ではありません。報恩の「恩」の言葉をひもとくと、インドの言葉で「カタンニュー(為されたることを知る)」という言葉を、中国の漢字である「恩」という字に翻訳されたと伝わります。暁烏敏師は「この世に居るということの一切がご恩である。・・・私共の生活は恩をうくる生活であるともに、恩に報いる生活である。・・・毎日が報恩講である。」と教えて下さいます。報恩講を勤めるということは、今自分自身がいただいているもの、今までなされてきた事を知る事から始まります。報恩の「報」の字は「むくいる・お返しする」という意味と、「しらせる」という意味があります。報恩講をご縁として、ご恩を我が身に知らせ、お念仏を味わっていくという大切な仏事であります。
今月の言葉のテーマは、「私にとって本当の幸せとは」ということです。自分自身に恵まれていること、様々なめぐり合わせに気がつかずに、「あたりまえ、当然」として生活しているということは、不幸なことではないでしょうか、と問いかけています。自分自身を振り返ってみると、日々、足りないものを探しては不足・不満を感じて生活しています。あれが欲しい、これが欲しいと貪り、手に入れたとしてもすぐに他のものを欲しくなってしまいます。ものにあふれ、裕福で恵まれた生活をしていても、愚痴ばかりの人生ならば、どれだけ長く生きても不幸と云わざるを得ません。与えられているものに目を向け、全ての縁を「有り難う」といただく生き方にこそ幸せがあるのではないでしょうか。
私は、中島みゆきさんが歌う「糸」という歌が好きです。
縦の糸はあなた 横の糸は私
織りなす布は いつか誰かを
暖めうるかもしれない
(中略)
縦の糸はあなた 横の糸は私
逢うべき糸に 出逢えることを
人は 仕合わせと呼びます *歌詞抜粋
「縦の糸はあなた、横の糸は私」という歌詞はとても印象深いフレーズです。人間関係を縦糸と横糸に見立てて、そこから織り出される布は「いつか誰かを、暖めうるかもしれない」と、私たちの生活の営みが、他者に対して何らかの暖かさとなって包み込んでいく、そういう可能性をもった人生を生きているのだというのです。とても素晴らしい歌詞です。そして最後には「しあわせ」を「仕合わせ」という言葉で表現してあります。普段「しあわせ」は「幸せ」と書きますが、中島みゆきさんは「仕合わせ」という字の響きを大事にされています。これは、その様になった成り立ちや因縁を表し、自分を超えた目には見えないはたらきの中に自分がここにある、ということを表現されているのだと思います。良いことであろうが悪いことであろうが、全てがめぐり合わせて私の人生となっているということです。
お寺で勤める法要や研修会の最後には、親鸞聖人ご制作の和讃「恩徳讃」を唱和いたします。如来大悲の恩徳、師主知識の恩徳に報い、謝すべきであると歌われます。私を救ってくださる仏さま(如来大悲)、そして私たちに先立って念仏に生きていかれた方々(師主知識)の勧めによって、教えに遇わせていただいているという事実があります。私たちにめぐり合わされた、与えられていたご恩を全て理解することは難しいことですが、この度の報恩講の仏事を通して、先祖から私の所へ仕合わせられた事の幸せを感じつつ、お参りしたいと思います。 令和6年12月 貢清春
「南無」とは思いの執着に気づき
「阿弥陀仏」とは本当の明るい自分をひらく力 (仲野良俊)
南無阿弥陀仏は呪文ではありません。しかし、南無阿弥陀仏を呪文にしてしまう心が私たちのなかにあるようです。人間が人間以外のものにたよって自分の思い、欲望を叶えてもらおうとする、その心が呪文を求め、南無阿弥陀仏を呪文にしてしまうのだと思います。
人間はいろいろなことをできる力を持っていますが、その中でも「思う」ということは大きな力です。様々なものを想像し、夢をもって行動することができます。しかし、「思う」ことができるが故に、その思いや考えに固執する、握りしめて離さないということが出てきます。仏教ではその固執を執着と教えます。
アメリカの大統領選挙も終盤です。トランプ氏の過激な発言が度々報道されてきています。そのようなニュースを見るたびに、「なぜあのように自己主張したり、威張って見せたり、相手をこきおろしたりするのだろう」と思います。しかし同時に「自分の中にもそういう心があるではないか」とも思います。相手を上げたくない、自分を上に置きたいという心です。虚勢を張らずにはおれない心、優越感の奥には劣等感があります。あらためて感じるのは、人間の根本問題は私が私になること、自分に帰ることだと思うのです。
掲示板にあげた言葉には、「南無阿弥陀仏の「南無」とは思いの執着に気づき「阿弥陀仏」とは本当の明るい自分をひらく力」といわれています。「自分のようなものは駄目だ」と思う、思いの執着に気づき、駄目でもなければ、人一倍偉い自分でもない。引き算も足し算もしなくていい。「本当の明るい自分を開いてくる」のが阿弥陀仏であるということでしょう。
「南無」ということを形であらわすと礼拝ですが、たまにこういう事をおっしゃる人がおられます。「自分は何も拝んだりしません。そんな卑屈なことはしない」と、さもそれが立派な人間であるようにいわれますが、問題は拝むとか拝まないではなく、拝むべきものが見いだせないことではないでしょうか。
先にも申しましたが、人間はただ生きているということではなく、思いをもって生きる存在です。苦悩があります。生きていながら生きていることそのものが問題になる、これが人間の人間らしさでしょう。病気で悩む、人間関係で悩む、いろいろなことで悩むのですが、根っこには自分自身を受け取れるかどうかという存在としての苦悩があります。
問題は、私自身の内にある。そのことに目覚めた時に、自分の全体を宗教の世界に投げ出す礼拝ということが成り立つのでしょう。ですから礼拝は人間のほうからは成り立ちません。自分の都合を満たしてもらおう、自分の思いをかなえてもらおうというたくらみをもって拝むならば、自分の思いをかなえてもらうために拝んでいるのですから、思いの執着の延長線上にあるものです。人間を救うどころか、帰って迷いを深めるものになるでしょう。
最初に南無阿弥陀仏は呪文ではありません、と申しましたが、南無阿弥陀仏はすでに阿弥陀のほうからあたえられたものであるが故に、私のせまく、暗い、思いの固執を破るのでしょう。南無阿弥陀仏は、広い世界に連れ出し、自分に帰らせる、如来のはたらきです。 令和6年 11月 深草誓弥
自分を苦しめている 因(もと)が知られた それはほかならぬ 自分自身だった (平野 修)
お釈迦様は29歳の時に道を求めて出家されます。その動機を「四門出遊」という物語で伝えられています。古代インドの町は、町全体を城壁が囲む様な作りでした。東西南北にそれぞれ門があり、お釈迦様がその門を出て外の森へと出かけられた時の出来事です。
物思いにふけるお釈迦様に、父の王は気晴らしに外出をすすめられました。従者を連れてまず東の門から出ようとした時に、老人に出会いました。腰が曲がって、顔がしわだらけになった人の姿を見たお釈迦様は「あれは何だ」と従者に聞くと、「あれは老人です」と答えます。「老人とは何だ」とさらに訪ねると、「あの人も若いときがあったのですが、だんだん年老いてきて、あのようになったのです。だれでも必ず老人になります。お釈迦様も例外ではありません」そのように従者が説明すると、お釈迦様は物思いにふけってしまい、城へ引き返してしまいました。次の日、南の門では病人を、また次の日、西の門では葬式の列を見かけました。「だれでも必ず老人になり、病人になり、最後には死を迎えます。お釈迦様も例外ではありません」その様に従者は答えます。老病死の現実に向き合われたお釈迦様にとっては、大変ショッキングな出来事であったに違いありません。そしてある時、北の門から出ようとされると出家者に出会われます。質素な身なりの出家者のその清らかな姿に心惹かれ、「道を求め修行する生き方があるのか、私もあの人のようになりたい」と出家を決意されたと伝わっています。仏説無量寿経では 「老・病・死を見て世の非常を悟る。国の財位を棄てて山に入りて道を学したまう」と記されています。
私たちは、必ず年をとり、病を身に受け、そして死んでいかねばなりません。しかし日常はどういう生活をしているかというと、老病死に目を背け、目先の幸せばかりを追い求めて生きているのではないでしょうか。お釈迦様は「四門出遊」の出来事を通して、自身の生き方に大きな疑問を感じました。自分の思いが叶う人生であっても、老病死の前ではすべてが無意味なものとなってしまう。苦しむ現実が人生の課題として切実な問いとなったときに、人生の意味を訪ね求めていく歩みが始まるのだと、この四門出遊の物語は伝えているのだと思います。
私の家には一匹の犬を飼っています。ある時その犬が前足の片方を地面に着けずに、三本足で歩いていました。足の裏をよく見ると、指の付け根が赤く腫れあがり腫瘍が出来ていました。怪我をしてばい菌が入ったのか、見た目でも痛々しさがあったので病院へ連れて行こうかと家族で話していましたが、数日後に様子を見ると腫れは引いて、何もなかったように四本足で歩いていました。足が腫れたので痛みはあったかもしれませんが、三本足のままでもありのままに生きていた犬の姿から、我が身が問わている様な気がしました。
犬や猫にも老病死はありますし、痛みを感じる事はあると思いますが、老病死によって苦しむということはありません。人間はというと、いつまでも若くありたい、健康でいたい、死にたくないという思いに執着をしているために苦しみが生じます。私たちを苦しめている原因は、老い、病み、死ぬという体の状況ではなく、思いの執着にあるのだと仏教は教えます。苦しむ因が自分の中にあったのです。私を苦しめている存在が外からやってくると思っているかもしれませんが、本当は自分自身が苦しみを生み出しているという事なのです。
仏様の教えを学ぶという事は、人生の苦悩に真正面から向き合い、それを背負って生きていく人間になるということです。何かに誘惑されたり妥協したりすること無く、人生の問題を我が身の事として引き受けていける人間になるということです。その事が明らかになるときに、老病死の苦しみも超えていける道が開かれていくのです。 令和6年10月 貢清春
地獄が無いと言うている人が
日日毎日煩悩の 炎を燃やして生きている
地獄が有ると言うてる人が
地獄を忘れて暮らしている (正親含英)
9月になり、ようやく朝夕は心地よさを感じることができるようになりました。今月は秋の彼岸会を迎えますので、掲示板にも浄土について教える言葉を選ばさせていただきました。しかしそういわれても掲示板の言葉には、地獄のことが語られていて、浄土のことは何も記されていないではないかと、おしかりを受けるかもしれません。
私たちの中には浄土への往生というと、どうしても「いつか」「どこか」、いいところへ行けると考えてしまう心があります。浄土をここではない、どこかよそにある場所のように思い、対象化して、「どこにあるのだろうか」、「本当にあるのだろうか」という形でしか考えられません。その浄土は、自分自身に目覚めを与える世界であるどころか、自分自身の在り方を不問にしたまま求める個人的な理想郷にとどまるのではないでしょうか。
ある先生が、「地獄や浄土は本当にあるのか」という問いに対して、「造ったからあるのです」とこたえられていたことを思い起こします。
親鸞聖人は、『教行信証』の中で、真実の浄土(真仏土)について、
「謹んで真仏土を案ずれば、(中略)大悲の誓願に酬報するがゆえに、真の報仏土と曰うなり」 (『教行信証』真仏土巻 真宗聖典300頁)
と示しておられます。真実の浄土(真仏土)とは、阿弥陀如来の本願の報い(むくい)として表れた世界、報土であるということがいわれています。浄土は私たちを離れてどこかに思い描かれる世界ではなく、まことの願いを見失った私たちに、まことの願いに目覚ましめんとする仏の願いがあらわれた世界だといえると思います。仏が私たちにはたらきかけ、つくりだされている世界です。そのような意味で、「いつでも」「どこでも」はたらきかけているのが浄土でしょう。
その浄土建立の一番最初の願いとして、無三悪趣の願が掲げられています。「浄土は地獄、餓鬼、畜生なからしめん」とする願です。ここに仏が私たちの世界を地獄とみそなわしていることがうかがえます。ここが一番重要な問題だと思うのですが、掲示板の言葉のように、地獄が有るという人も、無いという人も、「自分が造り出している」という自覚のないことが問題でしょう。思いどおりにいかないと腹をたて、罵り合い、傷つけ合う。また、他者の幸せを素直に喜べない。「わが身一つが可愛い」という我執煩悩で生きている私が、地獄を造り出しているのに、地獄は無いといえるでしょうか。掲示板の言葉では、続けて「地獄が有ると言うてる人が地獄を忘れて暮らしている」と続きますが、地獄が有るという人も、その有るといっている地獄は私がこしらえたものではないというところにいるために、地獄の本質を見失い、忘れてしまうという指摘ではないでしょうか。
浄土を離れて地獄もなく、地獄を離れて浄土もないのでしょう。大切にしたいことは、浄土も地獄も、「どこにあるのだろうか」、「本当にあるのだろうか」ということで問題にするのではなく、なぜ浄土、地獄ということが私に教え示されているのだろうか、と自分自身のこととして問い返すことです。
中国の唐の時代を生きた善導大師は、私たちが生きるこの現実世界を「他郷」あるいは「魔郷」と示しています。浄土は私たちの生きる世界を大悲し、批判する、真の故郷からのはたらきかけです。令和6年 9月 深草誓弥
悲の無いところに 阿弥陀は立たぬ
「火の無いところに、煙は立たぬ」の言葉が思い浮かぶと思います。根拠が無ければ、うわさは立たない。うわさが立つからには、なんらかの根拠があるはずだという意味です。今月の言葉は、阿弥陀様がお立ちになっておられるという根拠には「悲しみ」があるということです。
真宗の寺院にお参りしますと、本堂には阿弥陀様の立像が安置されています。鎌倉の大仏様も阿弥陀様ですが、座った姿の阿弥陀様です。座像としての阿弥陀様は、一般的に瞑想中のお姿、説法をしているお姿だと考えられています。立っておられる阿弥陀様は、苦悩する衆生を救おうとして私たちの前に立ち現れて下さった慈悲の姿を表現してあります。また阿弥陀様のお像を横から見ますと、若干前かがみの姿勢です。しかも片足が半歩前に出て、さあ今から人々を救いに行こうと足を踏み出しておられます。座っては居れず、立ちっぱなしでも居れず、私たちの所へすぐにでも行って救いたい、摂取不捨の大悲本願のおはたらきを、阿弥陀様のお像を通して表現されてあるのです。
仏心を表す言葉に「慈悲」という言葉がありますが、「慈悲」には「抜苦与楽」ともいわれ、楽を与え苦しみを取り除こうという仏のこころを表現します。日常生活でも感じることがありますが、苦しい事があっても一緒に分かち合ってくれる人がいたり、悲しみを共感してくれる存在があると安心できるということがあります。つらい出来事に会っても一緒にいて下さる人が側におられれば、頼もしいと感じます。逆に、側にいてくれる人がいない、分かち合う人がいない時のさみしさは、時間がとても長く感じられます。地獄といわれる世界はそういう場所です。地獄に堕ちたものは、終わることのない責め苦を味わうだけで、同伴する人は一人も居ないと説かれます。孤独の中に沈んで、たった一人で泣かなくてはならないのです。私たちの人生で、本当に楽が与えられる、苦が除かれるということは、どういう事をいうのでしょうか。
「さびしいとき」 (金子みすゞ)
わたしがさびしいとき よその人は知らないの。
わたしがさびしいとき お友だちはわらうの。
わたしがさびしいとき 母さんはやさしいの。
わたしがさびしいとき ほとけさまはさびしいの。
金子みすゞさんが詩の中で表現される様に、わたしがさびしい時には他人は知るよしもありません。友だちは笑って励ましてくれます。そしてお母さんはやさしさをもって抱きしめてくれるのでしょう。しかし金子みすゞさんは、本当に私のさびしさを知り、一緒に悲しさを共有する存在は仏様であると感じておられます。悲しみに寄り添って下さる仏様がいらっしゃって、どんな時にも「南無阿弥陀仏」というお念仏となってはたらいて下さる。そういう阿弥陀様のおこころをいただけばこそ、「私は決して一人ではない。不意に悲しみはやって来るけど、一緒に背負ってくださる阿弥陀様がいらっしゃる。」と、その大いなる慈悲のはたらきを感じたときに、私達の中に本当の安らぎと楽が与えられるのではないでしょうか。 令和6年8月 貢清春
自分の「安心・安全」を守るために 危ないものは徹底排除する
-コロナ・戦争の現実から見えてきた私-
2020年にコロナウイルスが日本に入ってきて、同4月7日に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の都道府県に緊急事態宣言が出て、4月16日には全国が対象になりました。それから3回緊急事態宣言が出されますが、去年の令和5年5月8日に五類感染症になり、行政が様々な要請、関与する仕組みから個人の自主的な取り組みをベースにした対応になり、現在を迎えています。
実は坊守がつい最近コロナになりました。発熱し、咳をしていたので、風邪だと思い、嫌がっていましたが、病院に連れていきました。コロナの検査を病院ですると陽性ということで驚きました。その時私の頭の中にとっさに浮かんだのは、次の日からよそのお寺にお話にいく予定にしていたものですから、自分に感染していないだろうか?という、本当に身勝手な、自己中心的な思いでした。その後も浮かんでくるのは、坊守の心配よりも、自分が感染しないだろうか、子どもたちのお世話も大変だとか、自分のことばかりが頭をよぎっていたのです。帰り道は車の窓を開けるという行動もしました。本当に恥ずかしいですがこれが私の正体だったのです。
どんな大きな問題でも、その自分のところで答えなければならない。問題というのは何でも特殊的であり、ある意味ではニュースペーパー的である。問題は特殊的だが、答えは原理的に答えねばならない。(中略)特殊な問題ということは、それが外ということ、原理的に答えるとは内をあらわす。外を縁として内(自己)を明らかにする。
(安田理深選集15巻下、20頁)
問題とは大きな問題もあれば身近な問題もあります。コロナ、環境破壊、戦争、公害など大きな問題もあれば、家族とのゆきちがい、仏事の問題など、自分と関係ない問題はないのです。大きな問題は、どうしても自分と関係ないと思いがちですが、私の問題なのです。どんな問題も人間が、わたしが引き起こした問題であったり、そうでなくても、必ず関わりがある問題です。一つの問題には必ず背景があり、法則があります。さらに根源的な因があります。ですから安田先生がいわれるように、「外を縁として内(自己)を明らかにする」、外の問題を縁として内の自分自身が問われているのだと思います。
新型コロナウイルスが、人間に感染し、多くの人が亡くなりました。「コロナ禍」と呼ばれ、コロナは「わざわい」として扱われるようになりました。しかし、このわざわいは、誰がもたらしたものでしょうか。病の苦しみだけにとどまらず、コロナウイルス感染者に対する攻撃や差別は想像を超えたものでした。自分に危険が迫ってくると人は攻撃的になります。その問題が遠いときは「差別してはいけない」、「人を攻撃してはいけない」と言えますが、自分の身近に問題が迫ると、私がそうだったように、途端に変わってしまいます。自分を守るために危険なものは徹底排除する心が動いてきます。
「安心・安全」という言葉が、いつの間にか多用されていますが、自分の「安心・安全」を守りたいという心と、自分の「安心・安全」を脅かすものを排除しようとする心があります。自分たちの仲間に入れたくない人を「ばい菌」扱いするいじめがあります。ナチスは、「ユダヤ人は劣等民族だから穢れている」と差別し、虐殺しました。本当の意味での「安心・安全」という世界が明らかにならないまま、個人的、あるいは国家の中だけなど限定のある「安心・安全」を求めるならば、それを脅かすものは徹底排除、つまり戦争を正当化する論理に簡単にすり替わります。「安心・安全」という言葉には、よくよく注意をすべきだと思うのです。
来年被爆、敗戦80年を迎えます。この戦争は当時の人たちの責任だということだけでは済まされません。戦争を非難することも大切なことですが、戦争を引き起こすような心が、戦争を支持するような心が私の中に絶対ないとはいえないのです。「コロナ・戦争の現実から見えてきた私」と掲示板の言葉にありますが、あらゆる問題を縁として内の自分自身が問われているのです。「仰ぐべきものを見失った時代」といわれる現代だからこそ、人間の本質を明らかにする教えを聞かなければなりません。 令和6年 7月 深草誓弥
雨の日には 雨の日の 生き方がある (東井義雄)
梅雨の季節に入ろうとしています。この時期の寺は湿気が多く、除湿機がフル稼働していて、各部屋でうなり声を上げていています。この時期はジメジメしてうっとうしいものですが、私たちは晴れの日は「良い天気」、雨の日は「悪い天気」と言いがちですね。畑に種を蒔いた後に降る雨は「恵みの雨」となり、楽しみにしていた野外イベントが雨で中止になった時には「悪天候」と言う様に、その時々の人間の都合によって評価が変わっていきます。
生き物にとって「雨」はとても大切なものであり、田んぼや畑に育つ作物を育てるためにはとても大切な役割を持っています。しかし時には人の命を奪ってしまう様な災害に結びついてしまうものです。近年は雨の降り方が昔と違って激しくなっていて、「100年に一度の豪雨」と報道される様に、全国で大雨による災害が起こっています。
自然の様々な現象というものは、地球の均衡や安定を保とうとする力がはたらいているそうで、全ての事象が関係し合って動いていると、教えていただいた事がありました。風が吹き雲が生じることや、晴れたり降ったりすること、地震や火山の噴火等も全てが結びついています。
どれだけ天に晴れる様にお願いしても、天は私たちの意見は聞き入れてくれません。長雨の時には雨が止むまで待たなくてはなりません。自然は「あるがまま」です。善し悪し関係のない世界です。また、私たちの身も同じように、その通り成るように成っているのです。どれだけ若さを保とうとがんばっても、時が過ぎれば歳をとります。健康に気をつけても、病気には勝てません。生きることにしがみついていても、死ぬ時期が一刻一刻と近づいています。思い通りにならない「自然界」、そして「この身」だけれども、与えられた状況をそのまま受け止めることだだけが、私たちに出来ることだと感じます。
親鸞聖人は、お手紙の中で、
「生死無常のことわり、くわしく如来のときおかせおわしましてそうろううえは、おどろきおぼしめすべからずそうろう。」(『末燈鈔』真宗聖典P603)
「生死無常の道理(人生ははかなく、生まれた者は死ぬという道理)は、すでに釈迦如来がくわしく説いておられますので、驚かなくてもよいのです。」という意味です。無常とは、全ては移り変わり、変化し続けることを示し、私達は思い通りにはならない人生を生きなくてはならない、という教えです。自分の思いが先に有るのでは無く、与えられた環境、状況の方に自分を合わせて生きていかなければならないのです。
以前、90才を越えられた御門徒の女性から、「晴耕雨読」という四文字熟語を教えていただきました。その女性は言葉の通りに晴れの時には畑を耕し、みかん山へと仕事に出かけ、雨の日には家で新聞や本を読む生活をされているそうです。今月の言葉通りの生活を実践されていて、素晴らしいお方だと感じました。様々な思い通りにならない状況であっても、「雨の日には、雨の日の生き方がある」と、不都合な事もご縁として頂戴し、そのままにいただいていく生き方があるのだということを、今月の言葉は教えて下さいます。 令和6年6月 貢清春
おばあちゃんは(おじいちゃんは) なにに なりたいの? (ある小学一年生からの問い)
五月になりました。今月は一か月遅れですが、花祭りと敬老会を開催いたします。敬老会に関係する言葉を探していて、目にとまった言葉を、今月の掲示板の言葉に選ばさせていただきました。
おそらく、おばあちゃんが、小さい孫に語りかけたのでしょう。「〇〇ちゃんは、大きくなったら、何になりたいの?」孫はその問いかけに、自分の将来の夢を語ったのかもしれません。そして、その後、逆に孫から先に挙げた言葉を投げかけられたのでしょう。
「おばあちゃんは(おじいちゃんは) なにに なりたいの?」
この真っ直ぐな問いかけに、私たちはどのように応答できるでしょうか。「もう、年をとってしまったから、何にもなれないよ」と思われるかもしれません。年を重ねて、今まで出来ていたことが、だんだんできなくなっていきます。
テレビのコマーシャルでは、「アンチエイジング」に関係する広告が多く見られます。「年をとりたくない」という、抗老化が今の時代の気分のようです。「老化しないように、いつまでも若々しくありたい」。しかし、歳を重ねることは、本当にマイナスの価値しかないのでしょうか。
私たちの中には、何かをすること、できること「doing」を重んじる価値観が根深くあります。その人がどんな仕事ができる人か、何を頑張っているのか、何を成し遂げたか、などその人の行いで、その人の価値を決めるような心があります。では「仕事ができない人はダメ」、「何もできない人は価値がない」のでしょうか。思いもよらぬ病気で動くことが出来なくなることもあります。年を重ねると、しようと思っても、すること、出来ることが、だんだん無くなっていきます。
あらためて私たちが見出さなければならないのは、「doing」、何かが出来ることによる価値ではなく、「being」存在や生命そのものの価値だと思います。何が出来るか、否かにばかり目を奪われて、「being」「ある」ことの尊さを忘れてしまっている私に、「ちょっと待て」と立ち止まる契機として、「老・病・死」があるのではないでしょうか。歩みを止めなければならないような、如何ともしがたい自らの「老・病・死」の苦悩が、かえって自分自身の存在の尊さを尋ねるきっかけになるのではないでしょうか。
「おばあちゃんは(おじいちゃんは) なにに なりたいの?」
この問いかけは、これからどんな生き方をしていくのか、と問う言葉なのでしょう。「あなたは、歳を重ねて、病身になったとしても、その自分にどのような態度をとって生きていくのですか?」という問いです。
阿弥陀如来からの呼びかけを「あなたは あなたに なればいい あなたは あなたで あればいい」と聞きとられた先達の言葉が、あらためて思い起こされます。いつでも、どこでも、どんなときも、私が私自身でありうるか、どうかが、私たちの課題なのでしょう。 令和6年 5月 深草誓弥
花咲かす 見えぬ力を 春という 人となす 見えぬ力を 佛という(藤元正樹)
春の彼岸を過ぎた頃から桜のつぼみが膨らみ始め、4月初めの頃には満開となりました。だれかが「春が来た」と号令をかけたかの様に一斉に開花する姿は、不可思議の見えぬ力、自然の大いなる力を感じます。古来の人は、花を咲かせる、目には見えないいのちのうごめきと、躍動する姿に感動を覚え、「春」と名付けたのでありましょう。春は目には見えないけれども、確かに存在しています。
「ものごとはね、心で見なくてはよく見えない。いちばんたいせつなことは、目に見えない。」(『星の王子さま』サン・テグジュペリ)
現代人は目に見えるものだけを信じ、目に見えないものは信じないという傾向がある様に思います。私たちはプレゼントや物をいただくことがありますが、その物の値打ちや善し悪しだけ目を奪われて、その物に込められた思いや心などを推し量ったり、想像したりする事が難しくなっているのかもしれません。心や思いは目には見えません。「いちばんたいせつなことは、目に見えない」からこそ、心を凝らして見なくてはならないのだと思います。
今月の言葉では、続けて「人となす 見えぬ力を 佛という」と教えられます。「佛」とは、私を人として育てて下さる見えないはたらきであるといただかれています。「私は生まれた時から人間です」と仰る方もおられるかもしれませんが、人間ほど不安定な生き物はありません。どういうものに育てられるかによって、何者にでもなる様な存在なのです。
先日あるところでご法事があり、高齢の女性の方とお話をしていました。実家は真宗の御門徒で、結婚をして他宗の家へ嫁いだお方だったのですが、まだ若い頃にお彼岸の志を届けるために、親からの使いで寺にお参りされたことがあったそうです。「寺に参ったら、一席法話を聞いてきなさい」と親から言われ、しぶしぶお参りされたとのことでした。参詣席の一番前に座り、高座に座ってご法話をされた説教師から「悪を転じて徳と成す」という言葉を聞いたそうです。女性はその言葉が今でも忘れらないと語っておられました。思い通りにならない事が起きたり、様々な縁に触れた時に、この言葉を思い出しては力をいただいていると、お話下さいました。その女性は生き生きした表情で、その当時の事を語りながら、仏法のご縁に出会った事を大変喜んでおられました。
親鸞聖人は『教行信証』の総序に、「円融至徳の嘉号は、悪を転じて徳と成す正智」とお示しになります。「円融至徳(えんゆうしとく)の嘉号(かごう)」とは「完全なる徳をそなえた名号」という意味で、「南無阿弥陀仏」のことです。お念仏は「悪を転じて徳に変える正しい智慧のはたらき」があるということを讃嘆しておられます。身に起きる都合の悪いことを断ち切って救われるのではなく、苦しい現実でさえも徳へと転じられていくことが、浄土真宗のお救いということなのです。阿弥陀の願いを「本願」といい、そのはたらきを「本願力」や、「弥陀願力」といいます。その女性のお話を聞きながら、阿弥陀如来がその人の人生を支えている言葉となって、活きてはたらいて下さっているのだと感じられました。
嬉しい事もあれば、悲しい出来事に出会うこともあります。身に起こる全ての事をそのまま引き受け、都合の悪いことであっても、無駄なものは一つもないと転じてゆける智慧をいただいていくことが、お念仏の利益なのです。「佛」のはたらきに出会って欲しい、そして「人」とならせていただこう、そういう願いを今月の言葉からいただきました。 令和6年4月 貢清春
人間心を そのままにしておいて
浄土を求めるということは 成り立たない (仲野良俊)
春の彼岸をむかえる三月の掲示板の言葉に、仲野良俊先生の著作の中の言葉を選ばさせていただきました。著作の中で、先生は人間心について「都合のいいことを求め、都合の悪いことから逃げようとする心」であると押さえられています。「浄土を求めるだけならば、都合のよいことを求めることと区別がつかないだろう。浄土を求めることの裏には穢土を厭う心、都合のよいことを求め、都合の悪いことを逃げようとするような人間心を厭う心というものがなければならぬ。」と述べられています。
あらためて日々の生活の中で、私自身何を中心にして生きているか、と立ち止まってみると、やはり「自分の都合」や「自分の思い」を中心にして生きています。都合のいいことが好きで、都合の悪いことが嫌いという心です。思い通りに事がはこぶと、ニコニコし、思い通りにいかないと腹をたてたり、愚痴をいうのです。こうやって文章にすると、あらためて恐ろしい心だと思いますが、「あの人さえいなければ」と思うことすらあります。この私の心をそのままにして、求められる世界はとても独善的な世界だと思います。
穢土という言葉があります。浄土に対して、煩悩によって穢された世界をあらわす言葉で、私たちの現実の世界を言い当てた言葉です。そして、この穢土をつくり出しているのは誰かというと、私が嫌いなあの人や、この人ではありません。煩悩具足と教えられている他ならぬ私自身です。仏教は、この「都合のいいことを求め、都合の悪いことから逃げようとする心」、人間心が穢であり、その人間心で出来上がっている世界を穢土と批判しているのでしょう。
「助かる」とか「救われる」という言葉を使いますが、どういうことが助かることでしょうか。それこそ、自分なりのイメージで助かる、救われるといっているだけで、本当のすくいはわからないのではないでしょうか。もし「自分の都合」や「自分の思い」がかなうことが、助かること、救われる事ならば、思い通りにならないものが徹底的に排除され、最後は誰もいない世界になり、思うようにならない現実の自分自身も受け取ることはできなくなってしまいます。むしろ自他共に助からなくしているのは、自らの思いではないでしょうか。
浄土はそのような人間心を批判し、真実の願いに目覚ましめるはたらきを持つ世界だといえるのではないでしょうか。「都合のいいことを求め、都合の悪いことから逃げようとする心」という人間心が穢であることを批判するのが浄であり、その如来の悲しみ、願いによって成り立つ世界が浄土です。
私たちは断ちがたい執着をもっています。生きている限り「都合のいいことを求め、都合の悪いことから逃げようとする心」、人間心があり続けるのでしょう。だからこそ、阿弥陀如来は、念仏を一切衆生にあたえ、呼びかけて、凡夫が凡夫に帰っていくことができる世界、浄土を荘厳されているのです。令和6年 3月 深草誓弥
「鬼は外 福は内」 「恵方巻」 問題は
どうなることが 幸せか 分からないこと
節分とは季節の分け目、変わり目のことであり、一年に4度(立春・立夏・立秋・立冬)訪れます。古来中国ではその季節の変わり目には邪気(鬼)が舞い込んでくると信じられていました。季節が変わる前日にその鬼を払う行事として「節分」があり、日本にもその習慣が伝えられ、春の伝統行事として習慣化しました。「鬼は外、福は内」という掛け声とともに豆(魔滅が由来)をまき、年の数だけ豆を食べて厄除けを行います。病気や災難などを鬼に見立てて追い出し、家内安全・健康長寿などの、幸せな福を呼び寄せようという考えから行われる行事です。また最近では、節分の時に恵方を向いて太巻きを食べる「恵方巻」の習慣も流行しています。これも豆まき同様「除災招福」を願う行事だそうですが、浄土真宗ではなじみの無い習慣です。
「除災招福」とは文字通り、災いを除けて福を招くという意味で、心は私たちの素朴な日常感情です。しかし思い通りにならないのが私達の生活です。人は誰しも災難に遭いたくありませんが、縁次第では予期せぬ災難が降りかかることもあります。その中で自分の思い通りになる事が幸せな人生だと思い、逆に都合の悪い事に遭遇すると、不幸な人生だと思ってしまうのではないでしょうか。親鸞聖人は、その様にしか受け止められない人間のこころを「罪福心」と教えられます。罪悪を恐れ、福徳を得る事のみが人生の目的だと信じるこころです。お念仏の教えはそういう私たちの姿を「迷い」と教えます。そしてその様な罪福心にとらわれ、迷信や俗信にとらわれる生き方を悲しまれ、現世祈祷や占い事に頼らずに生きていける道を示して下さいます。親鸞聖人の和讃に、
「かなしきかなや道俗の 良時吉日えらばしめ 天神地祇をあがめつつ ト占祭祀つとめとす」 『正像末和讃』
「何とも悲しいことに、僧侶も俗人も、日の善し悪しを選ぶことにとらわれて、天の神、地の神をあがめながら、占いや祈願をして幸福を招き、災難を除こうと努めています。」という意味です。葬儀の時には「友引」を避けたり、「大安」の日を選んで結婚式を開催する習慣がありますが、なぜでしょうか。何が起こるか分からない未来に対しての不安があるために日を選び、占い等に頼ってしまうのです。その様な迷信に頼ってまでも幸せになりたいと、必死に生きているということなのかもしれません。しかし親鸞聖人は、自分の都合の善いことだけが起こるようにと願う道俗の姿を「かなしきかな」と嘆いておられます。除災招福を神々に祈るとういうことは、結局は自分の欲望を満たすために神様を利用しているということではないでしょうか。むしろ、都合の悪いことが起こったとしても、その出来事を素直に受け止めて、そこから何かを学んでいくことがあるならば、どんな事が身に振りかかかろうとも、自分を育てるご縁としていただけるのではないでしょうか。
くり返しになりますが、浄土真宗ではや「除災招福」のために日を選んだり、方角に善し悪しを決めることはありません。真宗門徒にとって節分や恵方巻は、わざわざする必要がない行事だということです。本来毎日は大切な一日一日であって、掛け替えのない毎日です。善い日も悪い日もありません。無駄な一日というものは無く、自分を存在せしめる為には、大切な一日だと受け止めていくのが念仏の教えです。
何が起こるか分からない時代ですし、何をしでかすか分からない私たちです。嬉しい事に出会うこともあれば、思いもしない出来事に苦しむこともあります。しかし、起こってきた様々な出来事を、ごまかさずに受け止めて生きていける道があることを、お念仏は教えて下さいます。それは、どんな状況に身を置いても、人生が空しく過ぎない生き方が在るということです。その教えに出遇っていくことが本当の幸せではないでしょうか。この機会に、自分にとってどうなることが幸せなのか、真剣に考えてみましょう。 令和6年 2月 貢清春
悲しみは 人と人とをつなぐ 糸である (藤元正樹)
令和6年1月1日に石川県で震度7を観測した能登半島地震がおきました。被害にあわれた被災者の方々に対し、衷心よりお見舞い申し上げます。
北陸地方は浄土真宗の土徳の篤い地域です。能登、金沢、富山、小松大聖寺で約1280もの寺院教会があります。私も知人が多くいる地域です。地震が発生してから、何人かと連絡を取り合っていますが、皆さん能登の方が大変だといわれています。何かできることはないだろうかと思い、ご自身のお寺も被害にあわれる中、被災地に入り炊き出しや防寒用品を届けておられる方のところに、こちらから支援物資を送りました。
しかし、発送作業をする中でも、「かえって迷惑ではないだろうか」、「こんなことしかできないのか」などいろいろな思いがわいてきました。現地に入り、炊き出しに参加している友人を応援することしかできない自分に、もどかしさも感じています。自分自身の無力さや、他者をおもうこころに限界を感じ、切なくなります。
そのような中で、東日本大震災の時、大津波で本堂が全壊となった陸前高田市の佐々木隆道さんが被災後に語られた「忘れないでください。これが被災地一番の願いです」という言葉を思い起こしています。何かが出来た、出来なかったではなくて、被災された方が願っているのは「忘れない」ということだと思い返しました。
今回の掲示板の言葉に、「悲しみは 人と人とをつなぐ 糸である」という言葉を選びました。震災の惨状を見聞きして、胸が締め付けられるような悲しみを感じた、その悲しみのところに他者の存在を感じられているということを教える言葉だと、あらためて思ったからです。さらにいえば、他者の苦しみに「何かできることはないだろうか」というこころが起こることも、決して私が起こそうとして起こした心でもなく、逆に止めようとして抑え込むことのできる心でもありません。悲しみの心は他者との関係の中で起こってくる心です。
お釈迦さまが少年だったころの物語に次のようなお話があります。
お釈迦さまはある時、王様であるお父さんに連れられて、ある農村に出かけられました。その農村では農耕祭が行われていて、農家の人が畑を掘り起こすと、中から虫が出てきました。その様子を何気なくお釈迦さまはご覧になっていたのですが、どこからか鳥が飛んできて、その虫をついばんで、どこかへ飛び去ってしまいました。その様子を見ていた少年のお釈迦さまの胸の中に、悲しみの心が沸き上がってきて、傍らにあった木の下に座って「あわれ、生きものは互いに食み合う」と言葉をつぶやかれた、という物語です。
この「あわれ」という悲しみの心はどこからおこってきたのか、という瞑想をされたのだと思います。互いに相手を犠牲にして生き延びようとするような、別々のいのちを生きていながら、しかし「あわれ」というこころがおこってくるのはなぜか、ということがとても大切なことだと思います。同じ一つのいのちを生きているのもかかわらず、バラバラであることへの痛みを感じるところに悲しみの心がおこってくるということを、この物語は教えているのだと思います。
たとえ何かが出来なくても、悲しみの心を大切にすることが、被災者の方とつながる糸だと思うのです。悲しみの心を大切にすること。「何かできないだろうか」と念じ続けたいと思います。 令和6年 1月 深草誓弥
この世の中 何が起こるか わからないのは
この世の中に 何をしでかすか わからない私が いるから (佛光寺掲示板)
安倍元首相が暗殺されてから1年半が経ちました。その当時はとても衝撃的な事件だったことを記憶しています。後に報道されましたが、犯人の母は旧統一教会に入信し、多額の寄付をしていたことから家族がバラバラになり、犯人は次第に団体への恨みが増していったそうです。その報復として、団体に近い人物とされていた安倍氏の襲撃を思い立ったということでした。人間の苦しみや悩みを救済へと導くことが宗教の役割であるはずなのですが、この様な悲しい事が起きてしまった事は、宗教に携わる私にとってショッキングな事件でした。しかし、この事件の犯行に至った動機や背景を知らされると、この犯人も「被害者」という一面があった様に思われます。
私たちは事件が起こると「加害者」「被害者」という二つの立場で見てしまいますが、厳密にどちらかに分類することは出来ないようにも感じます。その時々の環境や条件、無数の「縁」の重なりの中で事件が発生し、私たちはいつでも「被害者」にも「加害者」にもなり得るのだと思うのです。まさに「この世の中、何が起こるかわからない」時代です。しかし「この世の中」だけの問題として片付けられません。「何をしでかすかわからない、私がいるから」と、問題の根っこを私の中に見つめているのが今月の掲示板の言葉です。
「何をしでかすか分からない」と言われても、日常は悪いことをしない様にして、なるべく善を行おうと心がけて生活しています。今年の流行語に「闇バイト」がありましたが、多くの人は「私にかぎって、闇バイトなどするはずがない」と思うものです。また、もし自分の子供が闇バイトをしていたとしても、親は口をそろえて「まさかあの子にかぎって、そんなことをするはずがない」と否定するでしょう。もし事実だったとしても信じられずに受け止められません。「意思がかたければ、犯罪は犯さない」、「私がしっかりしていたら大丈夫」そういう言葉も聞きます。しかし親鸞聖人は次の様に教えられます。
『「さるべき業縁のもよおせば、いかなるふるまいもすべし」とこそ、聖人は仰せ候ひしに』 歎異抄 第十三条
とあります。「縁に触れたら何をしでかすか分からない」、「どんな振舞いもしかねない煩悩具足の凡夫である」ということを表現された言葉です。ここに「もよおせば」とあるのは、自分の意思決定に関係が無く、そうなっていくということです。私たちの思い通りにはならずに、業縁のままになっていくという事です。そういう私たちの姿を仏教では「業縁存在」と教えられます。それは、私の意思や決断によって全てを決めて実行出来る「意思存在」では無いという事です。「業」とは人間が長い間積み重ねてきた、行為の元となるものです。身体的動作や言語活動や意思のはたらきの元となるものをいいます。そして外からの「縁」があって、行為として起こっているということです。日常生活で善い行いが出来たことも、悪いことを思ったり行ってしまうことも、そういう様々な業縁のもよおしの結果です。本来人間は「縁によって何をしでかすか分からない、非常に不安定な存在なのだ」と教えられています。これは、この世の中で起こっている事と自分はつながっていて、決して他人事ではないということを知っておかなければならないという事です。
この様な自覚が生まれる時に、事件の被害を受けた方々への共感や、罪を犯さざるを得なかった加害者に対する理解も、少なからず出てくるのではないでしょうか。これまで犯罪を犯さずに生きて来られた人は、たまたま犯行に駆り立てられる縁が無かっただけなのかもしれません。私たちに必要な事は、犯罪者への憎しみばかりを増幅させるだけではなく、それぞれの境遇や置かれた状況を知り、理解し共感することなのではないでしょか。そのためには、常に我が身(何をしでかすかわからない私)を見つめる仏の眼(仏の教え)が必要なのだと思います。 令和5年 12月 貢清春
「阿弥陀仏-南無」念仏は仏に念(おも)われて 仏を念(おも)うこと(狐野秀存)
先月10月21日に福浄寺住職継職法要、22日に宗祖親鸞聖人の慶讃法要が厳修されました。その際に講師として来てくださり、御法話をいただいたなかで教えていただいた、狐野秀存先生の言葉を選ばさせてもらいました。
念仏といえばいうまでもなく、言葉自体が示しているように、私どもが仏を念じること、仏に念い(おもい)を係(か)ける行のことなのに違いありませんが、しかし、実をいいますと念仏とは、一応仏に念いを係けることであるといいましても、実は仏から念われて仏を念うことであり、仏の私ども衆生を念う念いに帰して、仏の念う念いの中で、仏と一つに出会うこと、仏の念う念いの中で、仏と一体化して仏に目覚めることを意味する行であるのです。
(信國淳「歎異抄講話」 柏樹社『選集』 二巻176頁)
この言葉は信國淳先生の言葉です。狐野先生は信國先生の教えを受けられておられますので、この信國先生の教えの言葉を思いながら、「念仏とは仏に念(おも)われて、仏を念(おも)うこと」とおっしゃったのだと思います。
浄土真宗の教えをいただく私たちにとって、念仏とはいうまでもなく、南無阿弥陀仏と口に出して申すことですが、その南無阿弥陀仏は、「実をいいますと念仏とは、一応仏に念(おも)いを係けることであるといいましても、実は仏から念(おも)われて 仏を念(おも)うことであ」ると、信國先生はおっしゃられています。
「念仏とは仏に念われて、仏を念うこと」、そのことを踏まえて、狐野先生は、南無阿弥陀仏のすがたを「阿弥陀仏-南無-阿弥陀仏」と表現されました。私たちが念仏申すに先立って、あるいは私が念仏申す根源に、阿弥陀仏が私たちに南無しておられる。私たちを信じ、信頼して、尊敬している阿弥陀のはたらきがあることをあらわすのが南無阿弥陀仏であると教えられました。
浄土真宗、親鸞聖人の教えを一言で表すならば、「如来回向の教え」といえるのだろうと思います。「回向」というのは「パリナーマ」という古いインドの言葉を翻訳したものです。もともとの意味は「転じる」とか、こちらから向こうに「振り向ける」という意味のある言葉だと聞いています。ですから、私の方から仏さまや、何かに念仏を「振り向ける」というのではありません。「如来回向」ですから、如来から私たちの方に、「転じ、振り向けられている」ということだろうと思います。南無阿弥陀仏という念仏そのもの、そしてその念仏を信じる心も、信國先生が教え示されているように、「仏の念う念いの中」、仏から念われて、プレゼントされているということです。
二つの大切な法要が終わりました。この法要を心待ちにしておられながら、亡くなられた御門徒のこと、「念仏相続ですよ」と繰り返し促してくださった御門徒のことを思いかえしています。たくさんの念仏のすすめのなかにいることを、有難く思います。「仏から念われている」ということを、私自身の生活の原点として定めて、念仏申していこうと思います。 南無阿弥陀仏 釋 誓弥(令和5年 11月 深草誓弥)
生きるということは 学ばなくてもわかるような なまやさしいことなのであろうか (児玉暁洋)
私が大谷専修学院で学ばせていただいた時に教えてもらった事がありました。人間は人間によって教育されて初めて人間になる事が出来るのだと。狼に育てられたアマラとカマラは、人間の姿格好はしていても人間とは言えず、狼そのものの生活をしていたというのです。言葉をしゃべれず人間らしさを失い、四本足で生活していたと伝わります。その事を聞いた時には非常にショッキングで、「そんなこと有るはずが無い」「人間に生まれたら人間になるはずだ」と、その時は思っていましたが、教えを学んで行く間に納得せざるを得ませんでした。
私たち人間は、人間の親から生まれても、育てられる環境によって人間になるか否かは分からない、非常に不安定な生き物で、誰に育てられるかによって、何者にでもなる様な存在であるというのです。しかし他の動物は違います。犬に生まれれば犬の生涯を全うします。どれだけ人間世界で生活していても、犬が人間の様に言葉を話すことはありません。人間以外の動物は、生まれた時からすでに完成した生き物として生き、寿命を全うしていきます。
ある方から「人間は誰しもが未熟児のままで生まれてくるのだ」と教えて下さいました。これは、他の動物と違い人間は生まれながらに完成されてはおらず、人として自立するまではとても長い時間が必要だということです。馬や牛は生まれて数時間経つと、母親の乳を飲もうと四本足で立ち上がります。それに比べ人間の赤ん坊は、立ち上がるまでに約1年は必要です。さらに言葉を話す様になるまでには、さらに1~2年は必要となります。そこまで成長するには決して一人で生きてはおれず、様々な人に育てられ守ってもらわないと生きることが出来ません。その事を思うと、人間は他の動物と比較したとき、ものすごく弱い生き物だとも言えます。
子供が大人になることを「成人」と言いますが、文字通り「人に成る」ということです。私たち人間は生まれながらにして人間であるのではなく、多くの人に育てられ、沢山の事を学ばなければ人として成長出来ないのだということを表現しているのだと思います。しかし、人生における学びというものは、18才で終わりではありません。大人になっても年老いても、常に人生に学ぶことが大切です。
以前の掲示板の言葉に「わかってもわからんでもいいから、お念仏申しなさい。そしてお念仏によって育てられなさい」という信國淳先生の言葉がありました。念仏申し、仏法聴聞を大事にされている方々が仰る言葉に、「お育てにあずかる」、「お育てをいただく」という言葉があります。それは、私たち人間は仏法を聴聞して、仏様から育ててもらう事が大事なのだということです。私たちが分かる、分からないという分別はちっちゃいもので、それよりも大きいものがお念仏なのだ。大きく広いお念仏のお育てに触れてはじめて「人として生まれてきてよかった」と、自分の人生を喜びの中で終えることが出来るというのです。その事を親鸞聖人は「浄土真宗」という言葉で教えて下さっているのだと思います。私の中に、浄土という真(まこと)が生きてはたらいてくるということです。その事によって人間として本当に生きる人になる。親鸞聖人は本当の人間になってゆく歩みを「浄土真宗」という言葉で明らかにされたのです。 令和5年 10月 貢清春
浄土に往生するということは
ここで生きられるようになったということです (竹中智秀)
今月の掲示板の言葉は、大谷専修学院の院長をされていた竹中先生の言葉です。9月になり、秋のお彼岸を迎えるにあたり、かねてから折に触れて思い起こしてきた言葉を寺の掲示板の言葉として選びました。
往生という言葉を聞いてどのような事を思われるでしょうか。多く聞く言葉としては、高齢の方が命終された際に、「大往生」といわれる事のように思います。往生イコール死というイメージが定着している事のあらわれかもしれません。ほかにも進退きわまり、どうにも困った様を「往生する」とか、土壇場でのあきらめの悪さを「往生際(ぎわ)が悪い」などいいます。
先達は、「往生とは、我が浄土に生まれよという阿弥陀如来の呼びかけに気づいて、目覚めの世界である阿弥陀如来の浄土(彼岸)に向かって往き生まれよう(往生)との方向をいただいた人の生き様である」と教え示してくださっています。ですから本来、往生とは人々に生きる勇気、希望を与える言葉であったと思うのです。
「浄土に往生するということは ここで生きられるようになったということです」この言葉から教えられることは、「では逆に、ここで生きさせなくさせているものは何か」ということです。「いま、ここの、この私」を生きさせないものこそ、都合のいいことが好きで、都合の悪いことが嫌いという私の根性でしょう。私の物差しです。この物差しを中心に据えて生きる限り、他者も世界も自分自身も「えらび、きらい、みすて」て、「ここではない、これは私ではない」と言い続けるしかありません。
竹中先生は「いつでもない今、どこでもないここ、誰でもない私自身を自分と出来ない。そのことを空過という」とも教えてくださいました。「自分探し」という言葉があります。今の自分とは違う本当の自分がどこかにいるのではないかと錯覚し模索するのですが、実は本当の自分はどこか別にいるのではありません。事実の自分自身を引き受けられない自分がいるだけなのです。いつでもない「今」、どこでもない「ここ」、誰でもない「私自身」と我が身の事実を受け止めて、いのちいっぱいに生きる、これこそ、いのちそのものの願いなのではないでしょうか。
阿弥陀如来は、私たちの問題をよく知られ、新しく自他を見つめることのできる世界として浄土を建立されたのでしょう。浄土という世界にいのちの本来性を知らされ、自分の物差しの誤りや、歪みを絶対化しない生き方をいただくこと。そのことを「浄土に往生するということは ここで生きられるようになったということです」と竹中先生は教えて下さっていたのだと思います。
私たちにとっての一大事の問題とは、実は「いつでも私は私自身でありうるか、どうか」ということに尽きます。聖道、浄土の決判もこの問題にかかわるのです。末法五濁の世というのも、まさに現代のように、何もかもが大状況の中に飲み込まれてしまって、しかも、ただもう一気呵成(いっきかせい)に破滅していってしまうような時代のことで、ひとりひとりが無にされてしまう時代のことです。しかし、そのような時代に於いても、なおかつ私たちをして私たち自身を喪わせないで、いつでも私たち自身でありうることを獲させる、その教えこそが、浄土の教えだというのです。それは、もはや状況と私とを別々にするのではなく、状況をもそっくりそのまま、逆に飲み込んで私自身とすることのできるような、そんな新しい主体を生み出す法こそが、浄土の教えであるからです。ただ念仏のみが、状況の中に呑み込まれて、どのような私になっていこうとも、それをそのまま自己自身とすることができるのです。 竹中智秀『出会い』1974年度
竹中先生は、浄土の教えのみが、どのような状況にあっても、真の意欲を生み出すのだということを教えて下さいました。その教えにふれたものとしての私の「生き様」はどうなっているでしょうか。お恥ずかしいばかりです。南無阿弥陀仏、念仏を申そうと思います。 令和5年 9月 深草誓弥
戦争に 「聖」とか「正義」 付ける嘘 (「毎日川柳」より)
今年、第二次世界大戦の敗戦から78年の年を迎えました。また8月は6日の広島、9日には長崎と原爆忌を迎えることもあり、テレビや新聞では核や戦争を取り上げる特集が報道されています。戦争という行為はいつの時代でも「人が人を殺し」、「命を傷つける」行為であることに変わりありません。人間のいのちだけでは無く山川草木を傷つけ、その国の歴史や文化も破壊していきます。釈尊は「己が身にひきくらべて、殺してはならぬ。殺さしめてはならぬ。」『法句経(ダンマパダ)』と、私たちに呼びかけてくださいます。「己が身にひきくらべて」というのは、自分が傷つけられる側に立ってみなさい、ということです。殺される相手の立場に立ってみれば、他の命を奪うということは決して無いと思います。だからこそ自分自身が誰かを殺してはいけないし、誰か別の人に殺させてもならないというのです。しかしこの「己が身にひきくらべ」ることをさせない巧妙な装置が「聖戦」や「正義」という言葉なのだと思うのです。
この言葉「聖戦」や「正義」が持つエネルギーは凄まじいものです。国民はこの言葉に扇動され高揚感を生み出し、自ら率先して仲間を戦地へと送り出していきます。戦地に動員された兵隊は、正義という言葉があることによって敵に銃口を向けることが正当化されるのです。お国のため、家族のため、正義のためという自分は絶対に正しいという思い込みの中では、恐ろしいほどに凶暴化し、他人の悲鳴や叫び声が聞こえない人間になってしまいます。そういう恐ろしさ危うさが人間にはあるのです。私たちはそういう国家間の戦争や、対立状態になった時に必ず出てくるこの二つの言葉「聖戦、正義」が「嘘」であることを知っておかなかければなりません。
先日の福山雅治さんのラジオ放送(8月6日FM放送)で、とあるリスナーさんがアメリカに滞在していた時に、長崎に原爆を投下したB29(ボックスカー)の展示を見に行ったというお便りを紹介されていました。その人は、日本人としてみておかなければならないという、複雑な思いと怖さをかかえつつ見に行かれたそうです。その飛行機(B29)が普通に展示されていることに言葉が出ず、写真を撮ることも躊躇しましたが、忘れてはならないという思いで写真を撮影したと紹介されました。福山雅治さんも広島に原爆を投下したB29(エノラ・ゲイ)をアメリカで見学したことがあるそうです。「いろんな感情がありました。怖さと戸惑いがありました。見て何をするのか行動を起こすとかではなく・・・拳を振り上げるとか憎しみがあふれ出すとかではなく・・・ただ立ち尽くしましたね。」それから長崎の平和学習の事に触れ、「平和について考えるということは、戦争について考えるという事。戦争について考えるという事は、過去の歴史について考えるという事。過去の歴史について考えるという事は、政治について考えるという事。政治について考えるという事は、人間について考えるという事。その人間とはなんぞや。」と、云われていました。
「人間とはなんぞや」「人間とはいかなる生き物か」を問い考えるということは、仏教が長い間掲げてきたテーマでもあります。もしかすると福山さんはその事を「アーティスト」という立場で表現されているのかもしれません。私たち真宗門徒は教えを聞く聞法するという事で、戦争を繰り返していく「人間」を教えられてきました。私たちが聞法するという事は、人間を知るということであり平和のために何が出来るのか知ることでもあります。つまり私が聞法のご縁に会うことが、平和への一番の近道になるということです。 令和5年 8月 貢清春
僕らは色とりどりの命と この場所で 共に生きている
(「ツバメ」NHKあおきいろ テーマソング)
今月の掲示板の言葉は、NHKのテレビ番組「あおきいろ」のテーマソング、「ツバメ」の歌詞の一節を取り上げています。「あおきいろ」という番組について、公式ホームページでは「「あお」と「きいろ」は、ちがう色だけど、2つかさなると同じ「みどり」になる。いろとりどりな命がかさなり、ひびきあうことで、ともによろこび、ともにたすけあい、ともに生きていく。そんな「共生マインド」を育んでいく番組です」と紹介されています。
今、日本は超高齢社会(65歳以上の高齢者の割合が人口の21%を超えた社会)を迎え、2036年には高齢者の割合が33.3%になる見込みだといいます。医療福祉や社会保障の問題など課題が挙げられますが、先日参加した保育の研修会で、講師が次のようなことを話されていました。「超高齢社会で私たちが目指す共生とは、わかりやすくいうと「チッ」という人がいない世界ではないか」お店のレジや駅の改札で時間がかかる、もたもたする高齢者。その後ろで若者がイライラして、「チッ」と舌打ちをする。寛容さがないことが私たちの大きな問題だという指摘でした。
私は、このお話を聞いて、自分は「チッ」と舌打ちする立場、場所に立っているなと感じたのですが、同時に舌打ちをされる高齢者の立場にどうしても立てないのだとも思えました。私たちは一つの場所にいるようですが、実はそれぞれ一人ひとり、自分の場所に立っているために出会えないのでないでしょうか。
浄土という世界を表現する言葉として、『阿弥陀経』に「俱会一処(くえいっしょ)」(聖典129頁)という言葉があります。「俱に一処に会する」、一つの場所に会するという言葉ですが、「俱に(ともに)」といってありますから、「わたし」と「あなた」というように二つ以上のものが、そこにいるということです。二つ以上に分かれているものが、そのままで、一つの場所で出会うということが仏の浄土であるといわれています。
なぜそういう世界として浄土が願われているのでしょうか。私たちは自分の思いを中心として生きているために、自分の思いにかなうものは受け入れられても、思いにそぐわないものに対しては、いつでも対立的に関わります。その我が思いを「えらび、きらい、みすてる」こころと専修学院で教えてもらいましたが、そのこころをそのままにして、誰かと出会うといっても、各自がそれぞれ異なった我が思いを立場にしている限り、本当に出会えないということを教え示しているのが「俱会一処」という言葉だと思います。仏は私たちの世界をよくよくご覧になられ、苦悩の因を見出し、「私が願う国(浄土)にはそのようなことが無いように」と願いを建てられ成就した世界が浄土です。ですから俱会一処という言葉に、私たちの現実生活の問題の因が浮き彫りにされるのです。
今月、この言葉をえらばせてもらったのは、境内にある鉢に白い蓮と赤い睡蓮が花を咲かせたからです。それを見て思い起こしたのが『阿弥陀経』の言葉でした。
「池の中の蓮華、大きさ車輪のごとし。青き色には青き光、黄なる色には黄なる光、赤き色には赤き光、白き色には白き光あり。微妙香潔なり。」 (『仏説阿弥陀経』聖典126頁)
浄土がどのようなすがたかを教えた言葉ですが、青い蓮華は青く光る、黄色の蓮華は黄色に光る...ということがいわれています。当たり前のことのようですが、この浄土のすがたも私たちの問題をあきらかにする言葉だといえると思います。自分の本当の色を隠して生きなければならない私たちの世界のすがたを見て、仏は「青き色には青き光、黄なる色には黄なる光」と、それぞれがそれぞれの色のまま、輝きを放つ世界を浄土として語りかけられているのでしょう。色とりどりの命と、一つの場所で、共に生きさせなくしているものは何か、という問いかけの言葉として、今回の掲示板の言葉を受け止めたいと思っています。 令和5年 7月 深草誓弥
雨ニモ負ケテ 風ニモ負ケテ 欲張リ腹立テ 自己中心 ソウイウ私ヲ 仏ハ見捨テナイ
ここ長崎では五月末に梅雨へ入りました。例年より早い梅雨入りです。田植えの時期になりましたが、ジメジメとした日が続き、湿気の勢いで心も体もカビが生えてきそうです。七月になり梅雨が過ぎたかと思うと、今度は台風の季節となります。昨年は稲刈り直前に台風の襲来があり、広範囲に稲の倒伏被害がありました。私は田んぼを作っていますが、稲作は時間や手間がかかりますし、収穫量は天候にとても左右されます。また近年、肥料や燃料費等の高騰もあり、収穫してみると赤字になる農家も多いと聞きます。赤字覚悟で割り切って作っている農家は問題はないかもしれませんが、過疎や高齢化も相まって離農する農家も多くなる一方です。現代の稲作は機械化によって大型化し、小人数化となり体力的な負担は減ってきました。しかし新たな問題が起こってきて悩みは尽きません、思い通りにならないいことばかり、様々な逆風が吹いている状況です。
今月の言葉は宮沢賢治の代表作「雨ニモマケズ」を元として書かれています。原文の「雨ニモマケズ、風ニモマケズ.....ソウイウモノニ、ワタシハナリタイ」という有名な詩がありますが、この詩を鏡として自分の姿を見つめてみると今月の言葉にように、雨にも風にも負けっぱなし、欲も多く、ちょっとのことで腹を立てる自分の姿が露わになります。そして、全ての事を自己中心に見てしまう自分がいます。例えば、台風が近づきそうなら心配でなりませんし、長崎を避けて通れば安心します。避けて通った台風が隣国に接近し被害があったとしても「気の毒だな」と思うくらいで、内心では「来なくて良かった」と、ほっとしているのです。私たちの日常は「自分さえ良ければいい」という判断に振り回され、自分の思いがかなう事があったら舞い上がり、思い通りにならない時には腹を立てて愚痴ばかりをこぼしています。
唯円は歎異抄という書物で、こういう私たちのこころを「ひごろのこころ」と表現されます。この日ごろのこころとは、自分を中心として物事を善し悪しと分別し判断するこころで、私たちが日常生活で常識として持ち合わせている感覚です。さらに「日ごろのこころにては、往生かなうべからず」と、そのこころでもって浄土へ生まれよう、助かろうとしてもそれは無理、かなわないといわれるのです。これは、私たちが常識だと思っている日常の感覚、自分中心の物の考え方や行動が、仏の方から問われているということであろうと思います。
そういう善し悪しに迷いながら生きる私たちに思いをかけ、はたらきかけてくださる存在を阿弥陀如来であると親鸞聖人はいただかれました。そして阿弥陀の本願のはたらきが私たちに届いた姿がお念仏です。私たちの口から南無阿弥陀仏と念仏が申されていくということは、いつでも、どこでも、どういう状況に身を置いていたとしても、阿弥陀如来は寄り添っておられるという事です。その事を御経の中には「念仏衆生、摂取不捨」と説き、愚かな私であったとしても阿弥陀の本願は照らし、見捨てずに浄土へ迎え取ろうとはたらきかけておられるのです。さらに親鸞聖人は阿弥陀の摂取のはたらきを、背を向け逃げている者さえも追いかけ、つかまえて、決して離さないとも説かれています。
念仏したら欲張らない人間になれる、腹を立てない人間になれるのではありません。念仏は自己中心でしかない自分自身の生き方を、問い直してくれるのであります。仏の方から呼びかけ問いかけられているからこそ、自身の誤りに目が覚めて軌道修正が出来るのだと思います。雑多な生活で目の前のことに右往左往している私たちでありますけれども、お念仏申す生活を大事にしていきたいものです。 令和5年 6月 貢清春
世の中に「雑草」という草はない どんな草にだって ちゃんと名前がついている
(牧野富太郎) 「朝ドラ『らんまん』のモデル」
今年の四月からNHKの連続テレビ小説で、「らんまん」というドラマが放送されています。主人公のモデルは、日本の植物学の父といわれる牧野富太郎さんです。掲示板の言葉は、その牧野さんが生前に語られた言葉だと伝えられているようです。先日放送されたドラマの中でも、「役立たずの雑草」という言葉に反応して、主人公の槙野万太郎が「そりゃあ違う!名もなき草らあはこの世にないき。人がその名を知らんだけじゃ。」「どんな草やち同じ草らあ、ひとっつもない!一人ひとりみんなあ違う。生きる力を持っちゅう!」と力説する場面がありました。おそらく掲示板に取り上げた牧野さんの言葉が背景にあるセリフだと思いますが、この言葉がとても心に残りました。
寺の境内に芝生を植えているところがあります。暖かくなり、すでに「雑草」が生い茂っていました。やれやれと思いながら、少し草むしりをしましたが、どんどん勢いを増していきます。そこで芝生につかえる除草剤をまこうと思い、購入し、使用方法を見ました。すると、説明書には「芝生内のオオアレチノギク、メヒシバ、スズメノカタビラ、カラスノエンドウ等の退治に効果的」と書いてありました。恥ずかしいことに、どの草の名前も知りませんでしたし、これまで名前を知ろうともしていなかったのです。インターネットで調べると、全て見たことのある草の名前だという事に気付かされ、それまで「雑草」だとひとくくりにしていた芝生の間に生える草に不思議と興味がわいてきました。
アニメ『千と千尋の神隠し』で、名前について印象深い物語が語られています。主人公の萩野千尋が、異世界に迷い込み、湯屋の主人、湯婆婆(ゆばーば)に雇ってもらうように頼みに行く場面があります。湯婆婆は千尋の名前を贅沢な名として、千という数字だけの名にしてしまいます。のちに湯婆婆は相手の名前を奪って、その者を支配しようとするものであることが語られます。本当の名前を完全に奪われると、異世界から帰れなくなってしまうというのです。湯婆婆は名前を奪い、その者の自由や個性を奪い、意のままに操っていました。個性が失われた異世界では、皆、朝から晩まで働き、金をばらまくカオナシが現れると、一斉に奪い合います。一人ひとりが自分の考えを持ち、意見しあうようなことがありません。
あらためて自分の存在と名前は別のものではなく、一つなのだと思います。名前を軽く扱うことは、その者の存在を軽く扱うことですし、名前を奪い、「雑草」と一括りにすることで、いともたやすく「退治」、「支配」してしまう私になれるのかもしれません。
真宗の御本尊、阿弥陀さまは「私の名を広くすべての世界に響かせよう。もし聞こえないところがあるならば、誓って仏にはならない」と、自ら名を名のり、その存在を私たち一人ひとりに知らせようとはたらきかけている仏さまです。自分の全存在をかけて南無阿弥陀仏になられた仏さまです。その阿弥陀さまの名を呼ぶ声を、私も幼いころから聞いてきました。これまで数限りのない人々が、南無阿弥陀仏と名をほめたたえてこられて、その声が私のところまで至りとどいています。不思議なことに名前を軽んじ、他の存在の尊さ、また自分自身の存在の尊さを失い生きる私に、阿弥陀さまは、名前ではたらきかけているのです。 令和5年 5月 深草誓弥
智慧というのは 頭がいいということではない
事実を事実として 生きていける力であり 勇気なのです(宮城 顗 しずか)
今月の言葉を見て、赤塚不二夫さんの代表作「天才バカボン」に出てくるバカボンのパパの有名な決めゼリフ「これでいいのだ」という言葉が浮かんできました。漫画では、どんな事件が起ころうとも、決して良くはないだろうと思われる場合でも最後はこのセリフが登場し、物語が一件落着します。何か開き直った口癖の様に思いますし、場合によっては不謹慎な言葉にもとらえられます。しかし私達もバカボンのパパの様に、「これでいい、このままでいい、私は私でいいのだ」と素直に受け止め、自由自在に生きれたらどれほど楽だろうかと感じます。
仏教では「智慧」と「知恵」を分けて考えます。智慧とは仏智、仏のさとりの智慧の事を云い、知恵とは人間の知恵分別の事を意味します。世の中を渡り歩いていくためには「知恵」は必要ですが、人間の知恵は善し悪しの思いにとらわれて、かたよった人間のはからいであると仏教は教えます。現代は様々な情報に触れる機会が多く、みんなが賢くなり、知識が膨れ上がった状態ではないでしょうか。子供達は先生からも親からも賢くなることを勧められ、頭の良い子はもてはやされるので、ただひたすら試験勉強に明け暮れています。しかし試験で良い点を取ることと、人生を生ていく力と結びついているかは疑問です。いつも理想の自分、未来予想図を描き、「これではダメだ、今のままではダメだ」と、常に今の自分を否定して生きているようにも感じます。そういう人間の知恵の中から「これでいいのだ」と云う言葉は決して出てこないのです。
実はこの「バカボン」という名前の由来は、古いインドの言葉で「バガヴァン」という言葉から名付けられたのではないか伝えられます。この「バガヴァン」とは「大きな徳を有する者」、または「煩悩を滅した者」などの意味があり、中国では「婆伽婆(バカバ)」「薄伽梵(バカボン)」と音写されました。そしてこのバカボンという名前は、仏陀となられたお釈迦様の称号なのです。作者は、どんなことが起きようとも「これでいいのだ」とすべてを受け止めていくバカボンのパパの生き様に、お釈迦様の悟りの智慧を代弁させたと考えると、この漫画がとても味わい深くなります。
また、天才バカボンに登場するレレレのおじさんは、お釈迦様のお弟子であった「周梨槃特(しゅりはんどく)」がモデルであるとも云われます。周梨槃特という人は、自分の名前さえ記憶出来ないほど、物忘れのひどいお方だったそうです。お覚りの言葉を覚えることの出来ない周梨槃特にお釈迦様は、ホウキを渡し掃除をする行を与えました。「塵を払い、垢を除かん」と言いながら毎日毎日掃除をしている時に、塵や垢は自分自身の煩悩であり、汚れていたのは自分の心であったと悟り、神通力を得たと伝えられます。
宮城顗先生がおっしゃる様に、仏教における智慧というのは沢山の言葉を覚えて賢くなることではありません。現在ただ今の自分の姿を教えられ、どの様な私であっても生きる意味を与えられ、生きていることの尊さを実感することにあるのだと思います。事実を事実のままに受け入れたら、あなたはあなたのままで尊い存在であって、他の誰になる事もないのです。若い時は若さを謳歌すれば良いし、年をとれば年をとった所で役割がある。病気になれば病人になっていればいいし、健康になれば健康の有り難さを感じれば良い。そして死ぬ時が来れば素直に死んでいけば良いのだと、そのままの今の自分にいつでも帰っていきなさいということです。仏教の教えの根本は実にシンプルで、これより他にはないのです。 令和5年 4月 貢清春
「浄土」とは「お前はいかなる世界を生きているのか」と問う言葉
3月になり、今月はお彼岸を迎えます。真宗門徒は、彼岸を彼の岸、阿弥陀如来の浄土をあらわす言葉としていただいてきています。今月のお寺の掲示板に選んだ言葉は、その浄土についての言葉です。
お釈迦さまによって明らかにされた仏教は、人間が真実に生きるということはどういうことかを私たちに指し示す教えです。多くの仏伝が伝えているように、お釈迦さまは、国王の子、王子として生まれてこられました。しかし、「老・病・死を見て、世の非常を悟る。国の財位を棄てて山に入りて道を学したまう」(『仏説無量寿経巻上』聖典3頁)とあるように、お釈迦さまはこの世の生活そのものに疑問をもたれ、出家されます。現実生活の中で感じた問いをもって、国、財、位を棄てて求道をはじめられます。
人間の現実生活の中での問いや矛盾。それは、たとえば「生きるために、他のいのちを犠牲にしなければならない」ことであったり、「必ず死をむかえるのに、どうして生きなければならないのか」ということです。このような現実生活で抱える矛盾と仏教が示していることは、本来分けることのできないことだと思います。
ところが、現実生活と深く関わりあっているはずの仏教の言葉が現実生活から切り離されてしまっているように感じるのです。それは現実生活の矛盾を私たちが直視することを避け、空想的、観念的な「いやし」のようなものを仏教に求めた結果、生じたものではないでしょうか。先ほど挙げた、お釈迦さまの出家は、現実生活を捨てたというような単純なものではないと思います。
浄土という世界が建立されていく出発点を、『仏説無量寿経』の法蔵菩薩の物語に見ることができます。注目すべきは、その法蔵菩薩の浄土荘厳の発起もまた、「国を棄て、王を捐(す)てる」ところからはじまっていることです。「棄(捐)てる」といわれるのは、「国」と「王」を徹底的に問題にするということではないでしょうか。浄土が建てられていく根っこには現実生活の「国」を問題にし、新しき「国」を求めた法蔵菩薩の精神があります。私たちの現実生活を地獄(戦争)、餓鬼(欠乏)、畜生(恐怖)と押さえ、法蔵菩薩は地獄、餓鬼、畜生のない国、浄土を建立しようと四十八願の第一願をたてられています。ここにあらためて、浄土は私たちの現実生活と切り離してあるのではないと思うのです。
ロシアによるウクライナ侵攻がはじまって一年が経過し、なおも戦争は続いています。報道では、戦争がはじまって世界的な飢餓(欠乏)がおこると伝えています。深刻な食糧不安を抱える人が3億人を超えています。さらにロシアは核兵器を使用することをちらつかせています。(恐怖)そのロシアに対抗して優れた戦車、優れた戦闘機をウクライナに送って圧力をかけようとする諸国の在り方にも憤りを感じます。お互いに戦争がない世界を願いながら戦争をするのです。
掲示板の言葉は、『「浄土」とは「お前はいかなる世界を生きているのか」と問う言葉』です。浄土は、どこまでも「我と我が世界を問うもの」だと思います。現実生活の中で、この戦争の世界を生き、しかも自らのうちにも戦争を生み出す種をもつものであることをあきらかにします。地獄(戦争)、餓鬼(欠乏)、畜生(恐怖)の中で、いよいよ自分自身を見失い、閉鎖的になり、孤立していく私たちに、万人が共に生まれることのできる世界、「倶(とも)に一つの処(ところ)で会(あ)う」世界、浄土が問いかけていることを、今こそ聞かなければならないと思います。
令和5年 3月 深草誓弥
人間の本当の願いは 「通じあって生きたい」 これだけなんですよ 竹中智秀
親鸞聖人が正依の経典とされた「浄土三部経」の一つ、「仏説阿弥陀経」にはお浄土の有様が丁寧に説かれてあります。このお経には阿弥陀の浄土という国を「倶会一処(くえいっしょ)」する世界、ともに一つの処に会する場だと説かれています。浄土とは出遇う世界であり、ともに生き合い通じあう世界であります。私達人間は、心の底では誰とでも心通わせることのできる関係と、心が安らかになる居場所を求めて生きています。もし子供が病気で苦しんでいるとしたらその親は心配で、何があっても喜べない様に、自分一人だけ救われることはありえません。どんな人とも通じあい一緒に安らぐことがないと、私達は救われることはないのです。そういう衆生の願いを深く知り、受け止めた法蔵菩薩が建立した世界が浄土であります。浄土へ生まれるという事は自分個人の救いにとどまらず、どんな人とでも出遇いを成就し通じあえる、私達みんなにはたらきかけて下さる仏さまの世界が浄土なのです。
現代の生活ではSNS通信などで沢山の人々とコミュニケーションをとる事が出来ます。インターネットの普及で情報を入手するだけでなく、自分からも発信出来る時代となりました。浄土なんか求めなくても、スマホさえ有れば誰とでもつながれるよ、と反論があるかもしれません。とても便利な世の中にはなりましたが、誹謗中傷や嫉みひがみなどの言葉が氾濫し、人々に苦しみをもたらしているのも事実です。仲の良い者だけが集まり、フォロワー数の大小でその人の存在価値が決められていく様な世界に、私達は本当に満足しているのでしょうか。言葉や情報はあふれている現代ですが、心通わせ相手を思う、温もりのある言葉はどれだけあるのでしょうか。
先日、高齢になる御門徒の男性が亡くなりました。その男性は娘さんと二人暮らしで、娘さんが自宅でお父さんの介護をされていたそうです。毎日の正信偈のお勤めが習慣となっておられて、新聞を隅々まで読み、読書が好きなお方だったそうです。とても丁寧で物静かで、お寺の総代も引き受けて下さったお方でした。去年の暮れから体力が弱りはじめ、食事やお風呂の介護も自宅では難しくなってきたので、介護施設に入所する手続きを進められていたそうです。入所に必要な介護認定を受けるためにケアマネージャーさんとの訪問調査の最中に体調を崩され、そのまま息を引き取られたと聞きました。枕経のお参りの時に一部始終を娘さんから聞かせていただき、大変なご苦労をされ突然の悲しいお別れをされたことを聞かせていただきました。
しばらく前に「家で介護をするのが大変になってきたから、お父さん施設に入ろうか」と、娘さんが尋ねた時に思いもよらない返事があったそうです。「おまえは一人になるけど大丈夫か」と。そういう父親からの言葉に娘さんは「私はいつまでたっても子供だったんですね」と目に涙を浮かべながら当時のことをお話し下さいました。子供が親を思う以前に、親が子供のことを念じておって下さる。そして相手を思う感情は決して一方通行ではないということを教えられました。一緒に生きている者同士が、「会えてよかったね、生まれてきて良かったね」と感じられるほど心から通じあい、大事にしあって生きていける場所を求めているのだと思います。
私達は自分の善し悪しの分別を中心としているため、他者とすれ違っていく現実を目の当たりにすることがあります。共同生活をしている者とは衝突することもありますし、家族であっても心が離れていくことさえあります。その様な現実を生きる私達に、親鸞聖人は「浄土往生」をもって人間の救いを明らかにして下さいました。浄土を求め倶会一処する世界に生まれなさい、そういう阿弥陀の願いに触れたとき、通じあえない現実の私を問題として教えに尋ねていくのか、すれ違うのはしょうがないと開き直ってしまうのか、大きな分かれ目がある様に感じます。令和5年2月 貢清春
報恩は 知恩にはじまる 親鸞忌
新しい年になり、今月、1月は福浄寺の報恩講をお迎えする月になります。親鸞聖人の御命日は旧暦の11月28日です。京都の真宗本廟では11月28日までの七昼夜報恩講が勤まります。福浄寺では1月28日までの七昼夜、報恩講を勤めてきています。
1月16日に仏具のおみがきをし、御華束の餅つき、餅盛、仏華という内陣のお荘厳を御門徒が主体になって作り上げてくださいます。内陣の荘厳が整った後、御本尊の前に座ると、たくさんの人の御苦労をあらためて感じます。140年以上前からある本堂の大きな柱や梁を見ていても、当時の人たちの御苦労が感じられます。
報恩は、恩に報いると読みます。報は「むくいる」、「こたえる」、「お返しをする」、「知らせる」という意味があります。いずれにしても、恩に報いるためには、「知恩」恩を知ることが無ければ、報いてみようがない、こたえてみようがありません。今月の掲示板の言葉は、親鸞聖人からの恩、さらにさかのぼって阿弥陀如来からの恩を知るところから、報恩がはじまることを教えて下さっている言葉です。
単純なことかもしれませんが、私より先に、念仏に出遇った人がおられたから、ナムアミダブツが私のところまで届けられています。その人も誰かの念仏にふれて念仏申す人となられたのでしょう。その流れをずっとさかのぼると、親鸞聖人がおられ、法然上人がおられ、さらにさかのぼるとお釈迦さまがおられるのでしょう。無数の人たちの求道が無ければ、私のところにナムアミダブツは届いていません。私たちは、その目の前に届けられた贈り物の大きさ、重さ。贈り物に込められた願いがあることを知ろうとしてきたでしょうか。
私自身、日々の生活は、自分の思いを満たすことに夢中です。面白いテレビ見たり、温泉いったり、おいしいもの食べたり。こういうことが日ごろの私の思いです。阿弥陀さんからの願いを聞こうなんてこころは微塵もないように思われます。でもなぜか、ナムアミダブツに出遇いました。寺に生まれたということも大きな縁だったのかもしれませんが、それだけではないように思います。
いつでも自分中心で、自分の思いが満たされればそれでいいというようなかたちで歩んでいた私が、なぜかナムアミダブツに出遇いました。私が会おうとして、こちらから求めて、出向いて会ったのではなくて、思いがけず遇っていました。親鸞聖人が「正信偈」を綴り、確かめようとされたのは、そのナムアミダブツとの出遇いについてではないでしょうか。
不思議なことに、私の日ごろの思いの奥底に本当を願い求めさせるものがあるようです。日ごろそれは、不安やむなしさというかたちで顕在化しているようです。親鸞聖人が「正信偈」をとおして語りかけられているのは、「本当を願い求める心、ずっとその源を尋ねていくと法蔵菩薩がおられるのですよ。阿弥陀さんが法蔵菩薩となって、あなたの内側からはたらきかけておられるのですよ」ということだと思っています。
幼いころから親しんできた「正信偈」ですが、恩を知るということを手がかりにして、繰り返し、繰り返し、その綴られた言葉を味わっていきたいと思います。
令和5年 1月 深草誓弥
人生 一生 酒 一升 あるかと思えば もう空か
今年も早いもので、もう12月です。蓮如上人は「人間はただ、電光朝露の夢幻のあいだのたのしみぞかし」と、人生の過ぎゆく早さ、はかなさを「御文(お手紙)」の中で記されています。時間の過ぎゆく感覚は面白いもので、1年という年月も過ぎ去った1年間はあっというに感じますが、1年先の事となると長く感じます。「少年老い易く学成り難し」という中国の古語も有る様に、古来から時の移り変わりの早さを説くことわざは数多く存在します。誰しもが過ぎ去った時を惜しみ、近づく人生の終わりの寂しさを言葉にせずにはいられません。今月の言葉は、老境となった作者が空となった一升瓶を片手に、人生を嘆く姿が目に映ります。
呑んべえの人は分かっていただけると思いますが、栓を開けていない一升瓶が手元にあるだけでなんとも言えない安心感があります。その時はお酒が減ることは気にしていませんし、沢山呑めると思っています。そういう思いで一杯二杯と呑み進めていきますが、当然お酒は少しづつ減り始めます。「ある」と思っていたお酒もとうとう飲み干してしまい、「空」になってしまいます。一生も同じで、酒に酔う様に色々あった人生も、あっという間に終わりが近づいていくのです。
相田みつをさんは、人生がその様に終わってしまう事への空しさを「そのうち」という詩に表現されています。
「そのうち」
そのうち、お金がたまったら
そのうち、家でも建てたら
そのうち、子どもから手が離れたら
そのうち、仕事が落ちついたら
そのうち、時間のゆとりが出来たら
そのうち、そのうち、そのうち、......
できない理由を繰り返しているうちに、結局、何もやらなかった
むなしい人生の幕がおりて、頭の上に寂しい墓標が立つ
そのうち、そのうち、日は暮れる
今来たこの道、帰れない (相田みつを)
自分にはまだまだ後先時間があると思って生活をしています。「そのうち、そのうち」と、しなければいけない事を先送りしながらしながら生活しているのです。会社のため、家族のためと思い一生懸命働いてきたけども、一体何のための人生だったのか。何のために生まれてきたのか。ふと立ち止まり、私の人生これでよかったのだろうかと振り返る時が来た時、何とも言えない空しさを感じる事があるのです。しかしその「空しい」と気付いたことが大事なのではないでしょうか。空しいと感じるということは、人生の本当の満足を得、生まれたことの意味を知りたいという、私の深いところから発しているシグナルだと思うのです。
宗祖である親鸞聖人は、比叡山での修行中にこの空しさと真正面から向き合われたのだと思います。29才の時に山を降り、京都の吉水で出遇われた法然上人より、「ただ念仏して阿弥陀様にたすけられなさい」との教えをいただかれました。その念仏の教えは、「あなたをすくいたい」という阿弥陀様の呼び声をいただいてお念仏申すという事です。空しさを私に感じさせるものは何でしょうか。空しさは真実からのはたらき、阿弥陀様からの呼びかけではないでしょうか。本願念仏のみ教えは、いのちの底からわき上がってくる根本的な要求に応える教えです。空しさを感ずるということは、阿弥陀様と共に歩んでいるのだと教えられたのではないでしょうか。
一升瓶はスーパーに行けば売っていますが、私達人生の「一生」はどこにも売っていません。一生とは「一回限りの生」という意味ですから、取り返しの付かない、やり直しの出来ない生です。この「一生」をどう味わうのか、「一升」から呼びかけられていると感じれば、この一日の一杯も深い味わいとなります。 令和4年12月 貢清春
わかっても わからんでも 念仏しなさい
そして念仏から育てられなさい (信國淳)
今月の掲示板の言葉は、大谷専修学院の礎を築かれた信国淳先生の言葉です。実はこの言葉と先日、あらためて対面することになりました。京都の東本願寺、真宗本廟の同朋会館に住職修習の為に福浄寺の総代さまと一緒に入った時です。同朋会館の廊下には、いくつもの言葉が張り出してありましたが、この信國先生の言葉の前に、立ち止まりました。
正直にいいますと、私はこれまで「私が念仏する理由」とか「念仏することが納得できたらいい」ということを考えていました。さらには念仏しておられる人をみては、その人の念仏の品定めをするような心もありました。「あの先生の念仏は本物のようだ」とか、「あの人のいっている念仏は中身がない念仏ではないのか」というような心です。長い間、私自身が口から「ナンマンダブツ」と声に出すことに抵抗を感じていました。
お寺で法要が勤まるときも、御門徒の御法事が勤まるときも、念仏の声が聞こえなくなってきています。もしかしたら私と同じように、多くの人の中にも、「ナンマンダブツ、本気で信じているわけではないからいっても無駄だ」というような心が動いているのではないか、と思います。なかには正信偈のお勤めはよく声が聞こえるのに、お勤めが終わると念仏の声が聞こえてこない時もあります。正信偈の意味や中身はわからなくてもできるのに、念仏は意味がわからないとできないのでしょうか。「私が念仏する理由」とか「念仏することが納得できたら念仏する」というような私の小賢しい解釈をみこして、信國先生は「わかっても わからんでも 念仏しなさい」と声を掛けられていたのだな、とあらためて思います。
お寺に生まれたこともあり、私は幼いころから、朝夕のお勤めをしていました。もちろん偈文の意味などわからないし、南無阿弥陀仏のいわれも知りませんでした。それでも、おしえられるがまま、「ナンマンダブツ」といったとき、私が家族で一番前の座にすわり、お勤めの調声(導師)をしたとき、祖父や祖母、父、母はとても喜んでくれました。また、盆参りで初めて訪れた御門徒のお宅でも、「よう参って下さった」と、とても喜んでくれました。そのときは単純に嬉しかったことを覚えています。しかし、成長すると「意味」や「納得」ということにこだわりだしました。
今、この信國先生の言葉を見ながらあらためて思うことがあります。それは、たくさんの人が、私が阿弥陀仏にであってほしいと念じて下さっていたことです。そして今も「ナンマンダブツを忘れるな」ということを先生や友達、御門徒がすすめて下さっています。「念仏から育てられなさい」という促しだと、今思っています。「どうか私の名、南無阿弥陀仏を呼んでほしい」と願い続ける阿弥陀仏に、まっすぐに出あっていってほしい。念ずる仏から育てられてほしいという促しや励ましが、私が気付くずっと前からあったことでした。
信國淳先生は、「住職道」という文章の中で「寺の生命は念仏だ、念仏こそが我が浄土真宗の寺を寺として生かし、寺として成り立たせる唯一根本の基礎だ」と語られていました。これから「住職道」を歩み続ける者として、何よりもまず私自身が念仏申すものであり続けたいと思います。 令和4年 11月 深草誓弥
「地獄をつくる」(榎本栄一)
私どもには他をかえりみず 自分さえよければのおもいあり
地獄をつくる素因(もと)になるようです
今月の掲示板の言葉は、仏教詩人の榎本栄一さんの言葉が選ばれています。「地獄をつくる」という題ですが、私自身日ごろ地獄をつくっている自覚はあるかと問うと、ありません。自分の思い通りにならず、苦しい事が続くと、自分の置かれた状況を「地獄のようだ」と恨めしく思うときに地獄というばかりです。しかし、「自分さえよければ」というおもいは、持っていないとはいえません。おもいだけでなく、とっさにとる行動を振り返っても、「自分さえよければ」という感覚は、もはや血肉化されています。
地獄の獄の字の成り立ちを辞書で調べると、「二匹の犬が噛み合う」という字であると出てきます。二匹の犬が争い合い、わめきあっているすがたをあらわすのだと思います。この文章を書いている今日も、北朝鮮から弾道ミサイルが発射され、日本の上空を通過するという出来事がありました。二月から始まったロシアのウクライナ侵攻も未だ続いている状況です。多くの市民も巻き添えになっていることをテレビが伝えています。私自身、人間が人間を殺し、殺そうとしていることの悲惨さに目がいかずに、知らず知らず「どちらに正義があるのか」という関心にウエイトがかかってしまっています。
掲示板には、地獄をつくる素因として、「私どもには他をかえりみず 自分さえよければのおもいあり」とありますが、まさにこの言葉と通底しているのが、「自分が生き残るためには相手を殺すしかない」という主張です。この立場から戦争を繰り返してきたのが私たち人間ではなかったでしょうか。それにもかかわらず、弾道ミサイルの発射の後、インターネット上では「これは北朝鮮の宣戦布告だ」とか、「日本も核兵器を持つべきだ」という意見が見られました。私はあらためて戦争放棄を誓った日本国憲法の第九条に思いをいたしました。私は死んでも武器をもちたくありません。
「自分が生き残るためには相手を殺すしかない」という方法で本当に安心できる国、世界が作られるでしょうか。また、その「自分」はいつでも間違いを起こさない、絶対的な正義をもっているといえるでしょうか。私はそうは思いません。ドキュメンタリーディレクターの森達也さんは「自衛の意識は簡単に肥大する。解釈次第でどうにでもなる。かつて日本は戦争の大義として欧米列強からアジアを解放するということを持ち出した。ユダヤ人の殺戮はゲルマン民族を守るため。ブッシュ政権のイラク侵攻も大量破壊兵器を持つテロリストから世界の平和を守るため」だったと指摘し、「人は自衛を大義として人を殺す」と述べられています。
「人間の本当の願いは「通じあって生きたい」これだけなんですよ」と竹中智秀先生は教えられました。私はこの言葉に賛成です。戦争という地獄をつくる素因、「他をかえりみず 自分さえよければ」というおもいをもつ私だからこそ、敵、味方を作り争いを生む私だからこそ、あらゆる人と親しく尊敬しあえる世界を願います。 令和4年 10月 深草誓弥
「道」 ここはもう あともどりできぬ道 この世で 一辺だけ 通る道 (「常照我」榎本栄一)
今年の夏休みは5年ぶりに親子で虚空蔵山へ登りました。虚空蔵山は川棚町と嬉野町の境にある山で、標高も608mと気軽に登れる山です。川棚からと嬉野からと合計4本の登山道があり、今回は川棚から一番険しい「冒険コース」を選びました。切り立った崖を歩いたり、ロープを頼りに岩場を登ったりと、子供達と声を掛け合いながら頂上まで目指しました。普段は使わない体力と身体感覚を総動員して無事登山を終えることができ、適度な疲労感と達成感があって、とても充実した一日でした。
時折、宗教の話になると、次の様な譬え話をされる人がおられます。「山に登る道がたくさんあるけど、どの道を登っても必ず頂上にたどりつくでしょ。スタート地点と道程が違うだけで、行き着くゴールは同じ所。要するに、宗教も同じで、結局どの宗教を信じても行き着くところは一緒なんだから、いろんな宗教の良いところを取り入れて信じていった方がいい」。皆さんもこの様な話を聞いたことがあると思いますが、どうお考えでしょうか。
日本の憲法では信教の自由が保証されていますので、どの宗教を信じても構わないし、同時に複数の宗教を掛け持ちしてもいいわけですから、「確かにごもっとも」と言いたくなる様な感じがします。しかし疑問も残ります。「結局、頂上(ゴール)は一緒だよ」というということです。全ての宗教を完全に知ることも出来ないのに、どうして頂上は一緒だと言えるのでしょうか。各宗派で悟りや救いの内容は違いますし、修行の内容も異なります。宗教を中心とした生活習慣や、ご本尊も違ってくるわけです。到達する頂上も違うのではないかと思うのです。
また、「いろんな宗教の良いところを取り入れて信じた方が良い」という意見については、日本人特有の寛容な宗教感覚から出て来る意見だと思います。クリスマスを祝った数日後には寺で除夜の鐘を突き、次の日には神社に初詣に行くように、宗教行事とは自覚出来ないほどに習慣化しています。しかし取り入れようとするところは結局、自分の都合のいい部分だけをピックアップしているだけの様に感じます。おいしいところだけを食べあさっていく日本人の宗教感覚は、あえていえば「つまみ食い宗教」と言えるかもしれません。
私は、宗教の良いところを取り入れたり、別々の宗教を同時に信じる事は出来ないと思っています。登山で2つの道を同時に登れないのと同じで、私が歩めるのは一つの道しかなく、その宗教の広がりや幅、奥深い部分もしっかりと受け止め、教えに尋ねていくことを努めなければならないと思います。親鸞聖人が著された「唯信鈔文意」には次の様な言葉があります。
『「唯」はただこのことひとつという、ふたつならぶことをきらうことばなり』 唯信鈔文意
唯という言葉は、唯この事一つ「念仏一つ」という人生の拠り所をいただき、他力の信心一つに定まるという意味です。「ふたつならぶことをきらう」という言葉は、あれもこれも取り入れるという様な信心は成立しない、という意味です。さらに蓮如上人はこの事を「余のかたへこころをふらず、一心一向に仏たすけたまへ」(御文、五帳目第一通)と教えて下さいます。ほかの神や仏に心を向けずに、唯ひたすらに阿弥陀をよりどころとして生きていきなさい、ということです。
榎本栄一さんは難聴をわずらいながらも、沢山の念仏の詩を残したお方だと聞かせていただきました。今月の言葉の「道」というのは、「ただこのことひとつ」を知ることが出来た一辺だけ通る道であり、それはお念仏の道だと思います。私達の人生は「あともどりできぬ道」であり「一辺だけ通る道」です。その念仏の道を歩まれ、証してくださった先輩方の姿があればこそ、私達もその道を歩む事が出来るのです。 令和4年9月 貢清春
「悪」はつねに外部にあるなら 経験は何度繰り返しても経験にならない (山本夏彦『毒言独語』)
2歳になる次男、和樹が俗にいう「イヤイヤ期」をむかえています。楽しそうに遊んでいるなと見ていても、思い通りにならなかったりすると、イヤだというよりも癇癪を起して、「もう、おにいちゃんて、もう!」と怒りの矛先を6つ年上の兄にむけて、叱っています。たしかに長男からちょっかいを出されて怒っているときもありますが、よく見ていると自分で抱えきれないイライラを兄に当たることで処理しようとしていることも少なからずあるようです。最近はその矛先が、おばあちゃんや、おじいちゃん、私にも向くようになりました。今はその次男から離れてパソコンに向き合っているため、面白い事とも感じれますが、いざその時、何もしていないはずなのに「もう、おとうさんて、もう!」と怒りをぶつけられると、まいってしまいます。
しかし、ふと気づいたのですが、この次男が周りの家族に怒りをぶつける「もう、和樹!」という言葉は、私たちが次男を叱るときに使っている言葉でした。2歳の次男は、私たちが強い口調で叱る「もう、和樹!」という言葉を、今度は「自分は悪くない。まわりが悪い」として使い、自分の正義を立てようとしているのです。そうすると、思わず考えてしまいます。次男を叱る私は悪くないのでしょうか。そんなことを考えていた時に思い起こした歌の歌詞があります。
人はそれぞれ正義があって 争いあうのは仕方ないのかもしれない
だけど僕の「正義」がきっと 彼を傷つけていたんだね
SEKAI NO OWARI 『Dragon Night』より
掲示板の言葉に教えられることの一つに、『「悪」はつねに外部にある』ということは、こちら(内)には常に正義があるのだという事です。一所懸命に「もう、おにいちゃんて、もう!」と怒る次男が正義に立ち、守ろうとしているのは自分です。そして次男を叱る私も、結局のところ自分を立てるために子を叱っている。2歳の次男と39歳の私。「自分は正しい。悪いのはまわり」何も変わらないものをもっているのでした。「経験は何度繰り返しても経験にならない」とあるように、私自身の思い上がりを知らせるものがなければ、「自分は正しい。悪いのはまわり」という生き方は、他者と共に生きられないばかりか、結局は自分も大切にできず、虚しく人生を終わることになるということを教えている言葉ではないでしょうか。
悪を外部におき、自分のなかに正義を立てようとする。この問題の根っこはどこにあるのでしょうか。私は自分が自分自身にどう態度をとるかという問題だと思います。言葉を変えるなら、自分を本当に愛せるものになるかどうかではないでしょうか。お世話になった先生から繰り返し「事実の自分を大切にしなさい」と教えてもらいました。それは決して自分の思い描いた自分になりなさいという事ではありません。自分を他より能力のある人間と思いこみ、他人を見下して、優越感にひたることではありません。思い通りにならず、人とくらべて自分は駄目だと劣等感をいだくことでもありません。
『涅槃経』というお経には、「一切の衆生、悉(ことごと)く仏性(ぶっしょう)あり」(人間は誰でも仏になろうという願いを持っている)と説かれています。まわりの誰かを悪にして自分一人の正しさを立てようとする私の思い込みを破って、どんな人も「事実の自分を大切に生きていきたい」という願いをもった命を生きていることを教えるのが仏教です。 令和4年 8月 深草誓弥
仏法を聞くということは ありがたい話を聞くのではない 有り難い事実に目覚めること (佐々木蓮磨)
先日亡くなった御門徒のおばあさんの中陰のお参りの時でした。おばあさんには3人の娘さんがいて、それぞれ結婚をして家庭を持っておられますが、その家には数年前から難病を患っておられる60代の娘さんとその旦那さんが同居し、母親の介護をしておられたそうです。中陰のお参りが終わってそのご夫婦と世間話をしていました。話の流れで私の子どもの話題となり、それぞれ大きくなって部活や塾の送り迎えで忙しく、バタバタとせわしい毎日生活していますと話をしていたところ、ふと椅子に座っていた娘さんが「幸せそうですね、これからも幸せが沢山待っていますよ」と、ぽつりと仰いました。その時は「いや、将来の事はわからんですよ、ハハハ」と笑って話をごまかしていたのですが、帰りの車の運転中にその言葉を思い出し、なんだか切なく申し訳なく、やりきれない気持ちになりました。
実はその娘さん夫婦には、お子さんが居られませんでした。その事は気にも止めず自分の話ばかりをしていました。お参りに来た坊さんは子どもの話をうれしそうに語り、自覚はありませんが語る端々で自慢話の様になっていたのかもしれません。忙しい忙しいといいながら、子育ての不満や愚痴をこぼしていたのかもしれません。娘さんの目から見れば、あなたは与えられている家庭の状況を幸せだと思っていない、有り難く頂戴していない。自分自身は夫に介護してもらいながら、そしてだんだんと体の自由がきかなくなってくる病気と付き合いながら生活をしている。しかしこの坊さんは、自分の都合の善し悪しで良かった悪かったということだけで、いつもそこにある日常の有り難さを感じていない。その様に私の姿が映ったのだと思ったのです。
私自身、仏法が身のそばにある仕事をしながら、今月のことばの様に今の自分の生活を「有り難い事」だと受け止めていないのだと知らされたご縁でした。どれだけ仏法を聞いたとしても、教えを自分の身に問うことが無ければただの「タメになる話し」「イイ話し」「ありがたい話し」で片付けてしまうわけです。さらに言えば、仏法を聞いている時は分かった様な顔してありがたそうに頷いているけれども、家に帰れば日頃のこころ(善し悪しと分別するこころ)でいつも右往左往しているのです。
「有り難い」という言葉は、「有ること」が「難い(かたい)(むずかしい)」という意味で、語源では「滅多にないこと」や「珍しく貴重」という意味を表した言葉です。この言葉は法話の前に皆さんと一緒に唱和する「三帰依文」の中にも記されてあります。
「人身受け難し、今すでに受く。仏法聞き難し、今すでに聞く。」
(訳)『人として生まれることの難しい中に、今人として生まれ生きているのです。そしてさらに仏法のご縁に出遇う事はとても難しいのだけれども、今聞くことが出来たのです。』とあります。この三帰依文の言葉は、人として生まれてきたからこそ教えを聞くことが出来た、という一面と、仏法を聴聞するご縁に恵まれたからこそ、人として生まれたことの意味を知らされた、という両方の受け止めが出来ると思います。さらにこのご文は、人として生まれたことも、仏法のご縁に出遇ったことも私が努力して手に入れたものではなく、多くの方々のおはたらきのお陰によっていただく事が出来たのだとも教えています。私の身も環境も、教えを聞くことさえも全てが与えられている事なのだということです。
この「有り難い」の反対になる言葉は何かというと、「当たり前」という言葉になります。自分の周囲にある沢山の当たり前でないことを見つめ直していくことが、本当に有り難く幸せな事なのだと思わされました。 令和4年7月 貢清春
助けあわねば生きていけないお互いが また害しあわねば生きていけない
そこに人間業の悲しさがある (金子大栄)
五月末、長崎市三重町の正林寺に伺いました。ちょうど「いもさし」、サツマイモの植え付けの時期だと御住職から聞いていたこともあり、帰り道、小さな畑で作業されている人のすがたに目が向きました。すると、大きな犂(すき)、かつては牛で引いて使われていたとおもわれるような犂を、一人が縄を引き、二人が押すという、三人がかりで使い、畑を耕しておられるのです。他にも三人ほどが小さな畑で働いておられました。初めて見る光景でしたので驚きました。次の日、御住職にそのことを伝えると、三重町は漁村で、稲作をするような田はほとんどなく、多くの人が狭い土地を先人が開墾して、今も畑を作っておられることを聞きました。おそらく機械化するほど利益が上がらない為、あるいは機械が畑に入らない為ではないかと推測しますが、年配の方が三人、助け合い、力を合わせて畑を耕す姿に、心惹かれるものを感じました。現代は、農業も機械化が進み、無人トラクタ―も登場しています。川棚町内も、田植えの準備が進んでいますが、人影はまばらです。御門徒に聞くと、「近頃は田植えも機械がするので、昔のように人数はいらない」と語られました。
掲示板の言葉の最初に「助けあわねば生きていけない」とありますが、現代はそのことが感じられなくなっているように思います。かつては、一つ屋根の下に何世代もの家族が同居し、互いに気をつかいながら、ときにぶつかり合いながら生活をしてきましたが、今は「互いに気をつかうのが嫌」という理由で核家族化が進んでいます。「迷惑はかけたくない」、「自分のことは自分で」という、あたかも一人で生きていけるようなフレーズを様々な場面で耳にします。さらに今、人間関係の煩わしさを避けたい本音を、コロナウイルス対策をたてまえにして、様々な共同体が解体しています。しかし見えにくくなったとはいえ事実、人は誰かに迷惑をかけ、支えられて生きています。竹中智秀先生は「個人は幻想ですよ」と常々語られていました。
「助けあわねば生きていけないお互いが また害しあわねば生きていけない」。仏教は、自分も他者も、健康な人も病気の人も、お互いに深い因縁に結ばれて、事実共にいるという事を教えるものですし、またその生活の現場で見えてくる自分自身のすがたを教える教えです。「人間業の悲しさ」とありますが、生活の現場で折に触れて出てくるのは、おおよそ人間とは思えない心です。人の不幸をあざ笑ったり、人の幸せを素直に喜べなかったり、自分の考えにそぐわない人を傷つける心すらもっています。このような根性は、誰かに教わったものではありません。生まれた時に、というよりも生まれる前から、この業というものを引きずって生きているのだと思います。
コロナウイルスを通して見えてきた自分がいます。もちろん私も他の人と共に社会を生きている以上、病気は自分ひとりのことではないから、健康に十分な注意を払う必要があります。しかし、ゆき過ぎると、過剰な自己防衛心や、周りの人が病気に罹ることを罪悪視してしまうような心になります。見えてきたのは、ただでさえ病気で身体が弱っている人や家族へ、「みんなが迷惑する」という利己心の刃をふりかざして、病人を孤立させるような心をもった私です。私がお世話になった大谷専修学院という学校は、入学式の際、一人ひとりが、御本尊の前で、「新しく仏教徒として、共同生活の中に、真宗精神を体得すべく努力精進する」ことを宣誓し、学院生活を始めます。そこで見えてきたのは、「助けあわねば生きていけないお互いが また害しあわねば生きていけない」私でした。そういう私を悲しみ、しらせるはたらきがあることを、共同生活の中で教えられたのだと改めて思い返しています。 令和4年 6月 深草誓弥
「宇宙からは 国境線は見えなかった」(毛利衛)
境界線を作るということは、敵を作り出すこと
5月、初夏のこの時期、毎年お寺の境内にツバメが姿を現します。ツバメは夏の時期を日本で過ごす「夏鳥」といわれる渡り鳥で、南方からはるばる海を越え繁殖のために日本列島へと飛来します。ツバメは田んぼの土やワラなどを口ばしで上手に編み込み、軒下や駐車場の天井付近などに巣を作り、田植えが一段落する頃になるとヒナが生まれます。大きな口を開け親鳥がせっせと餌を運び子育てをする姿が愛らしいです。それから秋ごろになると再び南へと飛び去っていきます。
渡り鳥が季節に合わせていのちのままに飛び交い、回遊魚が領海を超えて泳ぎ回るように、本来地球上の全ての生き物には国境などは関係ありません。宇宙から地球を眺めた毛利衛さんは、その様な生き物のいのちがもつ本来性に気が付かれたのだと思います。そして国境を作って争いを繰り返す人間の悲しさを嘆いておられます。
「宇宙から日本を再認識すると同時に、地球の「小ささ」にも思いが及びました。1周するのにわずか90分。地球を外から見れば空気も水もつながっている。そんな小さなところで、国同士が争うことはないんじゃないかと。」 『毛利衛、名言集』
「宇宙船地球号」と私たちの地球を一つの船と譬えられる様に、同じ船に乗っている仲間ならば毛利さんがおっしゃるように争う必要はないのかもしれません。人間は様々な人種や文化があり、言語や思想なども多種多様に別れ、国や地域によって違います。その様な世界の中で私たちは境界や分断を作り、対立が生じています。自分と友達は違いますし、家族であってもそれぞれの生き方です。しかし大事なのは、本来「共に生きている事実」に目を覚ますということではないでしょうか。これからどのように共生していけばいいのかではなく、そもそもいのちは現に深いところで共に生きあっている、そのことを毛利さんは訴えかかけているのだと思うのです。
以前ウクライナ軍に投降したロシア兵士が、ウクライナ住人の配慮に涙を流す写真記事を見たことがあります。写真には若いロシア兵が武器を手放した後、ウクライナ住人の配慮でパンと紅茶を受け取り、別の住人はロシアにいる家族と連絡を取ってくれたりと、降伏した兵士を排除するどころか迎え入れたという記事でした。ウクライナ住人の温もりや思いやりに触れることで兵士も心を開かれて、敵味方のない本来の世界へと目覚めていったのだと思います。
私たちの思いは、相手に対して自分勝手なイメージを作り上げ、そのイメージを押し付けていきます。そしてわが身の善し悪しの判断で、条件に適わなければ相手を敵とみなし排除しようとします。そして今月の言葉のように、自分と相手に合い入れない境界線や壁を作っていくのです。何が本当の善か悪かもわからないのに、自分のモノサシに合わせて他を裁いていくということです。その分かったつもりになっているその思いが、他者との関係を断絶しているのではないでしょうか。
ツバメが国境を越えて海を往来する姿や、敵味方を超えて同じ人として接していたウクライナ住人に感動を覚えるのは、本来私たちもそうありたいという切実な願いがあるからだと思います。そのことを思うと私たちすべてのいのちには境界線は無く、深いところでつながっているのだと思います。 令和4年5月 貢清春
娑婆はこんなもんだと思いくくるのは
堕落の第一歩である。 暁烏敏
四月の掲示板の言葉には、真宗大谷派の僧侶、暁烏敏(あけがらす はや)先生の言葉が選ばれています。二十代から清沢満之に師事され浩々洞を開設されます。晩年、真宗大谷派の宗務総長に就任し、窮地に追い詰められていた宗派の財政を回復させるお仕事をなされた方です。
掲示板の言葉の冒頭に出てくる「娑婆(しゃば)」という言葉は、仏教語です。テレビドラマや映画で、刑務所から出てきた人が「シャバの空気はうまいな」とつぶやくシーンを見たことがある方も多いと思いますが、ここで使われているシャバが娑婆です。シャバは不自由で閉鎖的な場所から解放されて、束縛のない自由な身になったような意味で使われています。本来の仏教語としての「娑婆」はそのような意味ではありません。娑婆は、「サハー」という原語の発音を漢字の音を借りて置き換えた音写語です。「サハー」には、その意味を表す「忍土(にんど)」という意訳語もあります。忍土とは、「苦しみを耐え忍ぶ場所」という意味です。ですから、娑婆は私たちの生活する場所を「苦しみに満ちた耐え忍ぶべき世界」と教えている言葉です。
掲示板の言葉に戻りますと、「娑婆はこんなもんだと思いくくるのは堕落の第一歩である」とあります。私自身、この世に生を受けて三十九年経過しています。気づけば、これまで経験してきたことから、いろんなことを瞬時に判断し、損することが無いように、失敗しないように行動しています。「こういう時は黙っていた方がいい」とか、「こうすればうまく事がはこぶだろう」とかという、はからい事に明け暮れています。世界を向こうに回して、「こんなもんだ」と結果を当てにして、そろばんをはじいて生きています。面倒なことや、困ったことがおこらないようにしているつもりです。どちらかといえば、「堕落」しないように生きているつもりです。
しかし、困ったことは無くなりませんし、面倒なことも次々と起こってきます。何故でしょうか。しまいには「この世界がわるい」とか、「娑婆だから仕方ない」というように世界のせいにしているのではないでしょうか。掲示板にある「思いくくる」というのは、そういうことだと思います。自分勝手に出した結論としての娑婆です。これは教えの言葉でも何でもないでしょう。掲示板には「堕落の第一歩」とあります。刻々と移り変わる世界を「こんなもんだ」と観念的に固定化するところから「堕落」、まともな道が歩めなくなってしまう第一歩がはじまるということではないでしょうか。
大切にしたいことは、この世界は自分の思うように変えることはできない、ということです。本来、「娑婆」という言葉は、その道理を私たちに教え示す言葉としてあるものではないでしょうか。この世界を自分の都合のいいように変えていくことはできません。それは妄念妄想です。逆なのでしょう。世界を自分の思うように変えていくのではなく、思い通りにならない世界を通して、自分がいかに我がままであるかを教えられるのではないでしょうか。
私たちの目は外に向いています。あっち向いたり、こっち向いたりと外ばかり見ています。「世の中はこうだ」とか「他人はどうだ」とか外ばかり気にしています。たちの悪い評論家のようなものです。自分のことは問題にしようともしません。その私に「思い通りにならない」娑婆という世界は、「問題は内にあり」と呼びかけているのではないでしょうか。 令和4年 4月 深草誓弥
みんな「戦さになってしまって」とか「戦さが起こってしまって」とか云っているよ(井上ひさし、戯曲『花よりタンゴ』) みんな責任を負おうとしない
戦争で家を焼かれ家族を失いながらも、銀座で小さなダンスホールを開業する四姉妹の物語がこの「(戯曲)花よりタンゴ」。四姉妹の一人である藤子は、夫である武が戦争で亡くなったという知らせと、弔慰金3万円の為替を配達員から受け取ります。みんなで抱き合い泣きながら怒りがこみ上げてくるのだけれども、その怒りを誰にぶつけて良いか分かりません。「怒りなさい」、「だれに?」、「戦さを始めた連中によ」と、姉妹は語り合います。その時、
『誰一人として「わたしが戦さをはじめました」って云い張る人はいないよ。みんな、「戦さになってしまって」とか、「戦さが起ってしまって」とか云ってるよ。そうでしょ。』
と姉妹の一人はつぶやき、その場は底知れぬ空虚さにつつまれます。この劇の作家、井上ひさし氏は、戦後の東京裁判を調べていく中で、『私が東京裁判の芝居を書いたときに一番困ったことは、戦時中は皆が「聖戦だ」と騒いだはずだったのに、戦後に「あのとき騒いだ一番の責任者は誰だ」と探すとそこには誰もいない、という問題だった。』(2008年3月30日 朝日新聞掲載記事)と述懐します。戦争が始まるきっかけというものは、誰かが言い始めて、誰かが先導して、そして戦争が始まるものではなく、『その時々の「風向き」がメディアや人づてで広められるうちに風が大きくなり、誰も逆らえないほどに強くなった。「みんながそう言っている」という"風向きの原則"が働いたのだと思う。』(同記事)と指摘しています。また、今月の言葉の「戦さになってしまって・・・戦さが起こってしまって・・・」という様に、どこかで戦争を他人事にして、自分で問い考えるという事を止めてしまっているのかもしれません。
2022年2月24日、大統領の演説から始まったロシアのウクライナ侵攻は、二つの国の問題にとどまらず、世界各国が様々な被害を被っている状況です。各国はロシアに対して侵攻中止を求める声明を発表し、経済制裁を行う事によって、ロシア国内の弱体化や、政府の危機的状況を作り出そうとしています。それは武力侵攻を止めさせる一つの手段として実行されていますが、今現在のウクライナ侵攻を強制的に止めさせるまでの即効性は無い状況です。侵攻する側が侵攻を止めるまで破壊行為と殺人行為が行われていることになり、ただ歯がゆいばかりです。
プーチン大統領は演説で「目的はウクライナの"占領"ではなく、ロシアを守るためである・・・今起きていることよりも大きな災難に対する、自己防衛である。」と発言しました。この侵攻の目的は「ロシアを守るため、自己防衛」と演説されているのですが、既に破壊と占領と殺人が行われている現状から、既につじつまが合わなくなっています。しかし考えてみると、この自己防衛・祖国防衛という思想から全ての戦争は始まっているのです。
何も無いところから戦争は始まりません。まずは自国を攻めようとする「悪しき者(国)」、仮想敵を作り出し、国内の不安をあおります。そしてこの不安というものに駆り立てられた民衆は「悪しき者」に対しての偏見や脅迫(ヘイトスピーチ)を興し、政府は自国防衛のためとして武装をしていきます。緊張状態の中、ちょっとした衝突でもあれば、「戦争もやむを得ない」という大衆の雰囲気を作り出してしまう。今の日本ではその気運が次第に高まっているようにも感じます。唯一の被爆国でもある日本国内でも「抑止力のための核は必要だ」という議論もされているそうです。しかしその気運を私達、国民が作り出していくのですから、今回のロシアのウクライナ侵攻は決して対岸の火事ではない様に思います。
戦争を起こしてきた人間の心の中には、自分を「善き者」として、他者を「悪しき者」とする分別の心、差別の心がひそんでいます。自分の都合を中心として全てを見ていく「自是他非」と思う心です。その様な自己中心的な生き方、善し悪しの価値判断でしか生きられない私の姿に気が付くということ、そういう私の姿に一歩立ち止まり、仏様の教えを通してお互いの事を知っていくことが大事なのだと知らされます。
一国の長となる人も、政治家も、私達も同様に、外側から批判してくれるはたらき、仏の教えを聞く事こそが争いの唯一のブレーキとなるのではないでしょうか。今起きている戦争を「遠くの出来事」として片付けてしまうのか。「私たちの問題であり、責任である」として背負っていけるのか、今月の言葉は問いかけています。 令和4年3月 貢清春
怒りは人と人を分裂させ 悲しみは人と人とをつなぐ (玉光順正)
新型コロナウイルスのオミクロン株と思われる感染が拡大しています。毎日ニュースを見ますが、日本地図上で過去最大の感染者数として、赤の数字が私の住む長崎県の上に表示されています。この数字を見て、一喜一憂するようになってどれくらいになるのでしょうか。
しかし、ある時ふと思いました。「この数字の中には、多くの人の生命があり、生活があり、苦悩がある」私は、いつの間にかそんなことすら考えられなくなっていました。数字に何ら「悲しみ」を感じていない私。あらためてテレビを見ていて感じるのは、「コロナのことをどう考えるか」ということをテレビから決めさせられているような感覚です。感覚や発想を知らず知らずに植え付けられているようです。
今月の掲示板の言葉は、玉光順正先生の言葉です。ご縁があり、私も何度か直接話をお聞きすることがありました。そのお話の中で、思い返していたことがあります。先生が親鸞聖人の次の和讃を取り上げてお話しされたことです。
劫濁のときうつるには 有情ようやく身小なり
五濁悪邪まさるゆえ 毒蛇悪龍のごとくなり (『正像末和讃』聖典501頁)
先生は、「劫濁とは時代の汚れをいう。時代が悪くなると人間が小さくなってきたということ。小さくなったというのは具体的にいうと、「自分を守る」ということ」、と教えられました。その「人間が小さくなる」ということと、今回の掲示板の言葉は通底しているように思います。身近でコロナウイルスに感染された人、あるいは感染の疑いがある人に対する過度な忌避意識、心無い言葉を見聞きしました。自分が感染する不安からとはいっても見過ごすことができない事でした。「自分を守る」ため、不安を怒りに変え、暴力的な行動や言動をとる。他方でも感染者や濃厚接触者に対する誹謗中傷は止むことがありません。「怒りは人と人を分裂させ」るということ、そのものでした。コロナが人間関係を分裂させるのではなく、人が人間関係を分裂させているのでした。しかし、相手のことを想像する力を失っている、小さくなっているという点でいえば、冒頭にあげたように私も何ら変わらないのでしょう。
「悲しみは人と人とをつなぐ」という言葉が掲示板には続きます。「悲」はサンスクリット語の「カルナー」(苦しみを同感する)に由来し、「人々の苦を抜きたいと願う心」の意味があります。どんな人も目の前で困っている人、苦しい思いをしている人がいれば、「どうしたのだろうか」「かわいそうだね」と自然に心が動くと思います。しかし、時にどうすることもできないで、力及ばずということもあるでしょう。しかし、大切にしたいことは、「かわいそうだね」という悲しみの心は、ともに生きているといういのちの感覚からおこっている心です。誰に強制されたのでもなく、教えてもらったのでもなく、他のものを気遣う心です。その他者を思い、心を振り向ける「悲しみ」は、自分がおこした心であるようですが、共に生きている人がいて、そしてその共に生きているものとつながるものを感じているからこそ、私の中に悲しみの心がおこってくるのです。悲しみだけが人と人をつなぐのだとも思います。その悲しみの心を失うとき、目の前に人がいるという現実の広い世界に目を閉じ、事の軽重もわからずに自分を守るため、毒の牙で他を攻撃する「毒蛇悪龍」が生まれるのでしょう。 令和4年 2月 深草誓弥
人間は 逆境に遇わぬと 恩というものは 解りません (曽我量深)
あるところで四十九日法要がありました。その時の話です。
亡くなったのは80才半ばの女性、家族親戚集まっての法要が終わった後、納骨へと参りました。墓地には4、5名ほどの近親者が集まり、先に納骨を済ませてお線香を供え、墓石の前でお勤めを始めました。すると突然、大きな声と共に嗚咽する息子さんの声が聞こえてきました。びっくりした私は振り向くわけにもいかず、お経を読むことに集中していました。
「かあーちゃん、ごめんなー、かあーちゃん」
息子さんと言っても60代半ばの方です。涙を流しながら、何度も何度もこの言葉を叫んでおられました。
生前に何があったのか分かりませんし、尋ねもしませんでしたが、もしかすると親不孝があったかもしれません。母親に心配ばかりをかけて来られたのかもしれません。お経の言葉と息子さんの叫びの中で、悲しくも何かあたたかいものを背中に感じながら、お勤めの時間が過ぎていきました。そしてお経の最後、「願以此功徳」の時には、
「かあーちゃん、ありがとー」
落ち着きを取り戻した声で、感謝の言葉が息子さんの口からあふれ出てきました。今まで言わなかった言葉だったのか、言いたくても言えなかった言葉だったのか。四十九日が過ぎて墓石の前に立った時に、親への思いが理性を突き破って出て来たのでしょう。
そのお参りの後、気付かされた事があります。それは、自分自身は身内の者に2つの言葉「ありがとう」と「ごめんなさい」を心から言っているのだろうかと。考えてみると日常生活の中で謝らなければならない時は、必ず計算をしています。今謝っておかなければ後々になって関係がこじれたり、気まずくなったりする。だから今のうちに謝っておこう、そういう計算が入った中での「ごめんなさい」なのです。
墓石の前で涙を流しながら懺悔し、感謝の言葉を語った息子さんの中に、そういう計算は一つも無かったのだと思います。唯々、ご恩に対してお返しすることの出来なかった思いと、愛情を持って育てられ生かされてきた感謝の思いが「ごめんなさい、ありがとう」の言葉になったのだと思います。
恩と言う言葉は以前も紹介したことがありますが、インドの古い言葉で「カタンニュー」と言い(為されたる事を知る)という意味があります。その言葉を中国の漢字である「恩」の字に翻訳されました。「為されたる事を知る」とは、私にしてくださった行為が何であったかを心に深く考え、思い、知るということです。よくよく考えてみると、私達の人生が平穏無事で自分の思い通りになっている時には、そういう「為されたる事」に気が付かずに通り過ぎているのかもしれません。今月の言葉の様に、悲しい出来事や苦しい逆境に出遇わなければ、ご恩が解らない様な生き方をしているのでありましょう。
お念仏を頂かれてきた先輩方は、その様な逆境との出会いを「如来様からのご催促」と頂いて来られました。「催促」とは物事を早く済ませる様に急がせるという意味です。日常の生活で目先のことにとらわれ、忙しい忙しいと右往左往している私に、本当に急がなければならないことがあるのではないか、お慈悲のはたらきに早く気付きなさいと、如来からのご催促として逆境を頂戴していくという事です。親鸞聖人も念仏が弾圧され、流罪に遭われる時に、「これなほ師教の恩致なり。(流罪はまことに法然上人からのご恩であり、如来からのご催促である)『御伝鈔』」と表されています。この弾圧は四人が死罪、七人が流罪というとても厳しい事件でしたが、これを機縁として、沢山の人々に念仏を伝えよというご催促として、素直に受け取めて下さったのでありましょう。 令和4年1月 貢清春
いくら健康が大事だといって
人は健康のために生きているわけではない (医師 中村仁一)
病気にならず長生きをして何をしたいのでしょう?
今月の掲示板は医師の中村仁一さんの言葉が選ばれています。中村さんは医師の立場であられながら、医師による延命治療の拒否を訴えられておられた人です。
「健康で長生きが一番」という声はよく耳にします。私もできることなら、息子たちが大きくなるまでは、それなりに健康でいたいな、と思います。しかし、健康で長生きしておりたいと、どれだけ努力してもそれを飲み込むように病におかされることもあるでしょう。掲示板の言葉の「人は健康のために生きているわけではない」といわれる言葉は、突き詰めると「人は何のために生きているのか」という問いかけであると思います。
精神科医として多くの人たちの死を看取ってこられたキューブラ―・ロスさんは、死を前にした一人のアメリカ人の言葉を紹介されていました。「私はいい生活はしてきたけれど、本当に生きたことがありません」この言葉は、死を他人事としてとらえる立場ではなく、自ら死と直面するなかで、人生そのもの、生きてあること全体が問題になったことを示していると思います。
「いい生活」とは、それこそ私たちが日ごろ思い描くような、健康で、経済的にも恵まれ、温かい家族に囲まれているというような「いい生活」でしょう。しかし、「本当に生きたことがありません」という言葉には、その生活全体がどこに向かって生きているのか、本当に生きたという満足はどこにあるのか、という問題提起が含まれています。健康であろうとすることを決して否定するつもりはありません。しかし、「病気にならず長生きをして何をしたいのでしょう?」とあるように、「何をなすべきか」、「どこにむかっているのか」という問いに対して、「健康」という応答では行き詰まってしまいます。
親鸞聖人の言葉をしるした『歎異抄』という書物があります。その第二条には次のようなことが記されています。自分たちでは解決のできない問題を抱えた関東の弟子たちが、晩年を京都で過ごされた親鸞聖人のもとを訪ねます。その弟子たちに親鸞聖人は「ひとえに往生極楽の道をといきかんがためなり」と声をかけています。はじめに、「あなたたちには願いがあるでしょう」と声をかけるのです。私も教えてもらったことですが、「ひとえに」ということは「ただこのことひとつ」ということをあらわします。親鸞聖人は「ひとえに往生極楽の道をといきかん」、「このことが皆さんの心からの願いでしょう」と問題の根本を押さえておられるのです。
「往はゆくということですね。生はいきる、うまれるということですね。ですから往生というのは、本当の人間生活ということでしょう。」この言葉は曽我量深先生の言葉だったと記憶していますが、往生浄土、往生極楽というところに本当の人間生活が営まれるのだということを教えられているのだと思っています。健康であっても、病気になっても、南無阿弥陀仏とお念仏を申して、念ずる仏の呼びかけを聞いていくこと。年末に近づき、幼いころから目の当たりにしてきた、お寺に聴聞に来られていた、お同行のすがたが尊いものとして浮かんできます。 令和3年 12月 深草誓弥
他人の欠点がよく見えること自体、自らの欠点である
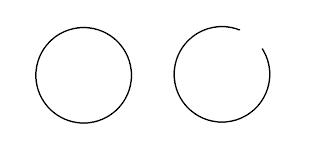
上の2つの図形(真円と一部が欠けた円)で、あなたはどっちが気になりますか?
これはゲシュタルト心理学で使用される心理テストで、「欠けた円」という問題です。ほとんどの人は右の円の欠けている部分を注目すると思います。これは、完全なものよりも、不完全なものや欠けている部分に意識が向く、という心理特性が有ることを確かめるテストです。どうやら私達の目は、瞬時に欠点の方へと注目する様に出来ている様です。日常生活でも食べ物の形が他よりも悪かったり、一部だけ変色していると、腐っているのではないか、古くなっているのではないかと異常を感じたりします。悪いところや欠点に意識が向いてしまうのは、先天的に持っている本能の様なもので、防衛本能として備わっている感覚だと言われています。
この感覚はそのまま他人にも向けられていきます。自分の生活を振り返っても、子供の良いところでは無く、ついつい悪い所に目が行きがちで、「あれが足りない、これが出来ていない」と事あるごとに不満を持ち、そして「ああしなさい、こうしなさいと」命令ばかりをしています。その命令通りに事が進まない時にはさらに子供を責め立てていき、何としてでも自分の思い通りに動かそうと必死になっていきます。
なぜその様になっていくかというと、相手の存在をそのまま受け入れられず、自分の考える正しさと比較して、ついには自分と同じ正しさを他人にも求めていくのです。そして相手の気持ちや状況は考えずに、自分の考える正しさへと導こうとしています。さらに自分が正しい事をしているという思いがエスカレートすると、暴力へと発展していく場合もあります。それはまさに、今月の言葉で指摘される自らの欠点であります。
(前略)
正しいことを言うときは
少しひかえめにするほうがいい
正しいことを言うときは
相手を傷つけやすいものだと
気づいているほうがいい (後略)
この言葉は吉野弘さんの「祝婚歌」という詩の一部で、以前はよく結婚披露宴のスピーチ等で引用されていたそうです。とある講師の先生から教えていただいた詩で、我が身の生活を振り返る大事な言葉がちりばめられているので、時折読む様にしています。
この詩では、正しいことは言ってはいけない、相手を傷つけるので言わない様に、というのではなく、「相手を傷つけやすいものだと、気づいているほうがいい」とあります。欠点を見つけたら言わずにはおれない自分であっても、相手を傷つける事に痛みを感じなさいと教えられます。私といえば正しいと思うことを言うだけ言い、正義の剣を振り回しているような生活をしています。どこまでも自分の都合で相手を判断し、相手の欠点しか見ようとしない私であると教えられることが大事なのです。そういう我が身を教えて、気付かせて下さるのが仏法なのです。自他との出遇いは、そこから始まっていくのではないでしょうか。 令和3年 11月 貢清春
自分の居場所を見いだせない不安は深い
先日、こども園に新しく転入してきたお子さまがおられました。初めて入る園舎や、知らない先生、お友だちに戸惑ったのだと思います。不安だったのでしょう。お母さんと離れてすぐに泣き出してしまいました。30分くらいたってもなかなか泣き止むことができずにいました。対応していた私も戸惑ってしまいましたが、外に出て、手をつないで少し歩くと、こちらから話しかける言葉に反応してくれるようになりました。好きな食べ物のことや、以前に通っていた園のこと、どんどん向こうから話しかけてくれるようになり、私もほっとしました。
その子と接しながら、「もし私が、誰も知らない、見知らぬところで一日過ごすことになったらどうだろうな」と考えていました。表面的には何事もなかったかのように取り繕っていても、内心はやはり落ち着かないものを抱えるのだろうと思います。また、たまに家族と離れて外泊することもありますが、家族のことが気にならないことはありません。
それだけ、家や、家族関係の中で、私は自分の居場所を感じ、安心を感じているのですが、ときにこの家や、家族関係の中にいても、自分の居場所にできないという問題が起こってきます。それは、自分の思い通りにならない出来事がおこるときですし、あるいは家族と対立するときでもあります。そのとき自分の居場所としていた家や家族関係の中で落ち着けなくなってしまいます。それまで親しんできた自分の居場所を居場所とできなくなってしまいます。ですから日ごろ安心を感じている家や家族関係の中での居場所も、実は非常に危うい居場所であるといわざるを得ません。
問題はどこにあるのでしょうか。問題は私の内にあるのではないでしょうか。私自身、家族間で対立したときに発想するのは、「相手が自分の非を感じてくれたらいい」などと外に問題の原因を求めてしまっています。また問題が起こると、いつも「ここは違う、こうではない」と、現実はそうなってしまっているのに、それを拒もうとします。そして「そのうち、ひょっとすると何もかもよくなって、自分の思うようになるにちがいない」と、かすかに希望をつないで、じっと死んだふりをするかのように、時をやり過ごそうとさえしています。
現実には、いま、ここに生きていながら、「これは違う、これは私がほんとうに求めているものではない」といい続けなければならないのですから、非常に虚しい生き方をしているといわざるをえません。以前「私たちの一大事の問題は、いつでも私は私自身でありうるか、どうかということに尽きます」と、竹中智秀先生から教えてもらいました。問題が起こったとき、対立してしまったとき、その問題の当事者にならなければ、何もかもを傍(そば)から見ている、傍生(ぼうしょう)と教えられる畜生的な人生となり、自分の思いの奴隷となるしかありません。
「自分の居場所を見いだせない不安」は「深い」のです。その深さは私の日ごろの、自己中心的な思いよりも、本当の居場所をもとめるこころがもっと深いことをあらわしているのではないでしょうか。本当の居場所は、どのような状況でも、いま、ここの自分を自分としていけるときに開かれるものであり、不安はそのことを問うてきているはたらきだと思うのです。
「人生こそが問いを出し、私たちに問いを提起しているからです。私たちは問われている存在なのです。(中略)私たちが生きていくことは答えることにほかなりません。そしてそれは生きていることに責任を担うことです。」(V.E.フランクル) 令和3年 10月 深草誓弥
恥ずかしいと 思うことが 少なくなってゆく それが 私には 恥ずかしい
もう20年ほど前だったでしょうか、JRで移動中の出来事です。乗車してきた女子高生が数人、ドアから入ってきたと思うと電車内の通路にべたっと座り込み、周りの目を気にすること無く大きな声でしゃべり出しました。初めて見たその光景に「これが、ジベタリアン(地べたに座り込む人達)か」と驚いた事がありました。若者が所構わず地べたに座り込むのが邪魔で迷惑だとは話では聞いていましたが、実際に目の当たりにすると驚きと同時に恥ずかしさを覚えました。
「オバタリアン」という言葉も以前流行しましたが、公衆におけるマナーとかルールよりも、自分達の楽や都合を第一に考えているのは一部のオバサンだけではありません。そのあつかましさはどんどん低年齢化している様にも感じられます。日本では昔から「恥を基調とする文化」を大事にし、人前で恥をかかないために控えめに振る舞うことが「美」とされてきました。しかしこの感覚は、もう既に古い考え方になったのかもしれません。そう思うと、これから日本はどうなってしまうのだろうか、どこに向かって行こうとしているのだろうかと考えさせられます。今月の言葉の様に「恥ずかしいと思うことが少なくなっていく」ことに何か危うさを感じます。
『涅槃経』というお経の言葉が、『教行信証』信巻(真宗聖典P257)に引用してあります。
〔本文〕 「慙」(ざん)は自ら罪を作らず、「愧」(き)は他を教えて作さしめず。「慙」は内に自ら羞恥す、「愧」は発露して人に向かう。「慙」は人に羞ず、「愧」は天に羞ず。これを「慙愧」と名づく。
〔意訳〕 「慙」とは自分から罪を作らない様にするということ、「愧」とは他人に罪をつくらせないこと。「慙」は自分の内面に向かって恥ずかしいと思い、「愧」は恥ずかしいことをして申し訳ないと他人に向かってわびること。「慙」は他人に対して恥ずかしさを感じ、「愧」は天に対して恥ずかしいと感じること。これを「慙愧」というのです。
このお経の言葉は、阿闍世に対し耆婆(ぎば)という大臣が教え諭していく場面での言葉です。父を殺害した事を後悔し、大きな苦悩を抱えた阿闍世は、大変な病気にかかってしまいます。耆婆以外の大臣は「父を殺したことなど気にすることはない、あなたに責任は無い、憂い悩む必要は無い」などと気休めを言うのですが、耆婆大臣だけは違いました。あなたが病気になって苦しんでいるのは慙愧の心があるからだというのです。取り返しのつかないことをしてしまった事を後悔し、「恥ずかしい」と感じる心が慙愧の心であります。その慙愧の心が生じたあなただからこそ、どうか仏陀の真実の法に出会ってほしい、と耆婆大臣は阿闍世に伝えるのです。犯した罪を責任転嫁したり、忘れたりすることで本当に救われるということは決してないのです。そして『涅槃経』には次の言葉が続きます。
〔本文〕 「無慙愧」は名づけて人とせず。名づけて「畜生」とす。
〔意訳〕 「慙愧」の無い者は人とはいわないのです。その様な者は「畜生」というのです。
慙愧が無ければ人とはいわない、畜生であるという言葉は大変重たい言葉です。畜生とは恥ずかしさを感じることの無い生き方をし、仏法に反応する感覚の無い存在です。阿闍世の様に自分の行いに痛みや、恥ずかしさを感じることは、「人」としての大事な感覚であり、それは仏陀の教えを聞いて救われていく「人」であることを証明しているのだと思います。
人間関係が希薄になっていく現代の中で、周囲からどの様に見られているのかという目線があっても、「私達の勝手でしょ」と吐き捨て、「そんなの関係ない」と他者との関係を切り捨てて生きているのかもしれません。恥ずかしいと思う心が人間性を保つ一つの鍵になっている様に感じます。 令和3年 9月 貢清春
剣をとる者は みな 剣で滅びる (マタイによる福音書)
今月8月は、6日に広島に、続けて9日に長崎に原爆が投下された月であり、15日は日本が敗戦した月です。今年は戦後76年に当たりますが、被爆者が高齢化し、亡くなっていく中で、風化という問題がマスコミで報道されています。
しかし、一方で時を重ねて伝えたい願いが固まる、伝えたい願いがはっきりするということもあるのではないかとも思っています。しばらく前の出来事です。あるお婆さんのお宅に月忌参りで伺ったのですが、お勤めが終わってお茶をいただきながら、いつものように会話をしていると、「今の日本の雰囲気は戦争に向かって行っているようだ」と切り出され、ご自身が長崎市内で被爆され、凄惨な状況を目の当たりにされたことを語り始められました。そして最後に「この話は息子たちにも、もちろん孫にも話していない。しかし今の日本の雰囲気がまた戦争に向かっているようで、何とかならないかと思い、あなたに話をしようと思った。戦争はしてはいけない。」ということを語られました。
今回の掲示板の言葉は、キリスト教の教えの言葉です。「剣をとる者は みな 剣で滅びる」十字架を目前にしてイエスが語った言葉のようです。この言葉は決して現実を無視した理想論的な言葉ではなく、むしろ人間の罪の歴史を凝視したところから発せられた言葉だと思います。この言葉の通り、剣をとり、剣で滅びた経験をしたのが私たちです。しかし、その後も国家を守るため、自分を守るために剣にたよる道を歩んでいます。そればかりか、それに合わせて憲法も変えようとしています。
果たしてこの歩みは正しいといえるでしょうか。「侵略のために戦争する」という国はほとんどなく、いつも戦争を引き起こすのは「国防」、「自衛」の意識からではなかったでしょうか。今も世界では殺戮と報復の連鎖が止まりません。なぜ戦争が起きたのかという問いに、武器を持った過剰な自衛意識が戦争を起こしてきたと日本は学びました。だから「何をしでかすかわからない私」たちは武器を捨てるという憲法を作ったのだと私は思っています。ただ「国を守れ、家族を守れ」と叫ぶだけならば、自衛意識のみが高揚し、また剣をとることにならざるを得ません。
「我々が歴史から学ぶことは、人間は決して歴史から学ばないということだ」という言葉を改めて思い返します。「剣をとる者は みな 剣で滅びる」おそらくこの言葉は二千年程前から私たち人間の前にあったのだと思います。『無量寿経』には「兵戈無用」という言葉がありますが、「軍隊も武器もいらない」という言葉です。この言葉も「自らに正義あり」と謳い、「兵戈」を用いて殺戮を正当化するようなことがあってはならないという思想から「兵戈」を捨てるために生まれた言葉ではなかったでしょうか。これらの人間の罪の歴史をくぐって紡ぎ出された言葉も、「解釈」次第でいくらでも捻じ曲げることができるでしょう。いつでも自分の方に正義を持ち出すのが私たちの在り方だと教えられています。
どれだけ美辞麗句を重ねても人が人を殺すことに正義はありません。私は御門徒のお婆さんが被爆体験を私に語られた時の眼差しを忘れることができません。 令和3年 8月 深草誓弥
誰もが安全でない限り、誰も安全でない
昨年2020年9月22日、新型コロナウイルスが世界で猛威を振るう中、第75回国連総会の中で、アントニオ・グテーレス国連事務総長は次の様に演説されました。「国連は世界保健機関(WHO)を中心として、特に開発途上地域の各国政府に対し、命を守り、ウイルスの蔓延を抑えるための支援を行い、130を超える国々に対する個人用防護具やその他医療物資の提供を支援している」「どこでも物理的にも価格的にも入手可能な、人々のためのワクチン開発に向けた取り組みを支援している」と、新型コロナウイルスに対する活動を報告される一方で、
「しかし、自国民だけがワクチンを手に入れられるよう、裏取引をしている国があることも報じられています。このような『ワクチンナショナリズム』は不正だけでなく、自滅にもつながります。誰もが安全でない限り、誰も安全でないことは、周知の事実だからです。」
『ワクチンナショナリズム』とは、コロナワクチンを一部の国が独占しようとしている政治行動で、欧米や中国など裕福な国が製薬会社に巨額の資金を投入しワクチン開発を促進した上で、自国民に優先的に提供する政治的な動き(自国第一主義)のことを意味します。その結果どうなるかというと、中・低所得の国(発展途上国)のワクチン接種が何年にもわたって後回しとなり、最も貧しい地域の多くでコロナウイルスの蔓延が続き、世界的大流行を長引かせることになると予測されます。結果、先進国の感染者は減少しても、世界全体では感染者が増え続け、結局は「自滅」につながっていくというのです。こういう時だからこそ裕福な国が主導となって国際的な協力体制を掲げ、国境を越えてワクチンが行き届くような取り組みが求められています。自国さえ安全だったらいいとワクチンの争奪に各国の指導者は躍起になっているのでしょうが、「誰もが安全でない限り、誰も安全でない」のです。全世界の人々が安全安心な状態にならなければ、自国の安全安心は無いのです。国のトップに立つ指導者の方々には、是非正しい選択をしていただきたいものです。
しかしこの、ワクチンナショナリズム的な考え方は、他人事とは思えません。一時期からすると長崎の感染者数は減少傾向となっているので、自分はコロナに感染しないだろうと、他人事の様に思っていまが、ワクチンが行き届かない国の人々の不安などは考えてもいません。自分や家族さえ助かればいい、自分の住む地域さえ安全ならいいと、狭い範囲しか見ようとしない自分がいます。その様な生き方は、我が思いが満たされればいいという「自国」ならぬ「自分第一主義」の生き方ではないでしょうか。
自分第一主義な在り方から離れることの出来ない私達に対して阿弥陀如来は、「悲しむ」という眼差しで見つめておられます。大谷専修学院の院長先生であった竹中智秀先生は、阿弥陀如来の摂取不捨のはたらきを「えらばず、きらわず、みすてず」と教えて下さいました。先生は、阿弥陀如来はいつでも、どこでも、だれにでも、その願をもって私に呼びかけ続けているのだと仰っておられました。だからこそ私達も呼びかけに応え、念仏の教えによって我が身が照らされていく事が大切なのだと知らされます。
これからの時代、コロナが収束しても、以前の生活様式に完全に戻ることはないだろうと経済学の中では予測されています。今までの歴史や社会の姿は、自分や人間の生き様をうつす鏡の様なものですから、注意して見て選択していかないと、また大変な時代がやってくるかもしれません。何をもって安全なのか、安心な生活とは一体どういうことなのか、教えに尋ねていきたいものです。 令和3年 7月 貢清春
他を責めるのは鬼であり 他を裁くのは閻魔であり
不足を思う心は餓鬼であり 人を利用するのは畜生である (松原 致遠)
今月の掲示板は、浄土真宗本願寺派の学僧の松原到遠氏(1884~1945)の言葉が選ばれています。鬼、閻魔、餓鬼、畜生という地獄の住人たちの名が出ていますが、よく見ると、私が鬼や閻魔から責め裁かれる、というのではなく、私が責め裁いている鬼であり、閻魔になっているということが否定できない日ごろの姿として教えられている言葉であることがうかがえます。
私は幼いころ、水木しげる氏の漫画を通して、地獄の鬼や閻魔、餓鬼の姿を目の当たりにして、「地獄というこんなに恐ろしい世界があるのか」と衝撃を受けました。生前犯した罪を閻魔さまが裁判されること。罪の軽重によって受ける罰が違うことや、様々な鬼がいて様々な責め苦を与える描写をみて、自分も嘘をつくというような身に覚えがある罪を犯していることが思われ、恐ろしくなっていました。しかし、今回の言葉は「悪いことしたら地獄に落ちるぞ」ということを教えているのではないのです。現に、あなたは地獄を作り出しているということを教えているのでしょう。
「他を責めるのは鬼」、自分を中心にして私は悪くない、お前が悪いと考える間もなく思い、行動します。「自分さえよければいい、他人はどうでもいい」という心が根っこにあるようです。こんなとんでもない心があるのに、いざ生活をしている只中では、全く気付いていません。重要なことは、私が自分の周りにいる人にどうふるまっているかで、自分が地獄の住人になるかどうかが決まるということでしょう。
「他を裁くのは閻魔」、他人の悪いところはよく見えますが、自分の悪いところは、よっぽどのことでもなければ気が付きません。先月の随想にあったように他人が茶碗を割ると、「茶碗を割った」と、すぐさま悪いと指摘しますが、自分が茶碗を割ると「茶碗が割れた」と、さも勝手に割れたかのような、身勝手な裁判官が現れます。
「不足を思う心は餓鬼」、満たされることのない思いを中心にして、「もっとこうしてほしい」と相手に注文ばかり。「あの人は薄情だ」といいますが、それは相手に対して自分が勝手に要求している心が先にあるからでしょう。これも他人の不足ばかり目につきますが、自分は棚にあげています。
「人を利用するのは畜生」、他人を犠牲にして自分の利益を求める姿でしょうが、これも実際やっているときは気付けないのです。
このように見ていきますと、毎日地獄の住人の相をあらわして生きていることにうなずかざるを得ません。「自分さえよければいい、他人はどうでもいい」という心で生きている証拠でもあります。この自己中心的な心は、反省して無くなりました、というような質のものではありません。しかし、私は「自分さえよければいい、他人はどうでもいい」というのは本当ではないな、と感じます。そして恥ずかしいなと感じます。
自分が間違っていることを恥じるこころを失えば、もう人間にはもどれないのではないでしょうか。法語に照らされて自分の根性が明らかになり、「恥ずかしい」と感ずる心がある限り、人間の品位が保たれるのではないでしょうか。 令和3年 6月 深草誓弥
人の間違いや 欠点をきびしく 見る眼で 自分が見れたら いいですね (野田風雪)
「自分に厳しく、他人に優しい」、その様な態度で他人と接し、自分を律することができれば、私たちが求める理想の人間関係が築けるのだと思います。きっと集団の中でリーダーシップが発揮できて、他者からも尊敬を集める人になるでしょう。しかし現実は今月の言葉のように、他人の間違いや欠点ばかりが目について、厳し態度をとってしまう事が多いように感じます。
私達の目は外へ向いています。その目から得た情報をもとに、自分が気に入るか気に入らないか、善いか悪いかを判断します。他人の行動や仕草、着ている服や髪型の善し悪しまで、ほんの一瞬「パッと見」で判断しています。また、他人が犯した間違いに対しても、自分のことはそっちのけで責任を追求し押しつけていきます。
その様な心を、寺本 温先生は法座の中で次の様にお話しをされます。「他人が茶碗を割った時は『茶碗ば(を)割ったね』と言うけども、自分が茶碗を割った時は『茶碗の(が)割れた』と言ってしまう。」自分が割った時には、さも自然に茶碗が割れたかの様に、自分には責任が無い様に言ってしまうけども、他人が割った時には「茶碗を割ったのはあなただ」と、割った責任を追及せずにはおれない心が沸き起こってきます。しかし自分が割った時には、「諸行無常、形ある物は必ず壊れるものだ」と、言い訳までして自分を正当化しようとします。
この事を心理学用語では「行為者・観察者バイアス」 (バイアスとは考え方の偏りの事)と呼ぶそうで、同じ行動や結果でも、他人の場合は原因を他人の性格や能力にあると考え、自分の場合は状況や運などの自分以外のものに原因があると考えてしまう、と説明されています。これは誰にでも起こる心の作用で、他人の間違いには厳しく、自分の失敗に甘いのは、心理学では自然な心の動きだと考えるそうです。この事からも分かる様に人間は、他者を見る目線で自分自身を見つめることや、客観的に我が身を見ることが出来ないのです。
その様にしか生きることが出来ない私達に対して、仏教はどの様にアプローチしてきたかというと、「自分の目では自分の姿を見ることが出来ないから、お経の教えの中に自分の姿を見なさい」と問いかけてきました。その事を中国の善導大師は「経教はこれを喩うるに鏡のごとし。しばしば読み、しばしば尋ぬれば、智慧を開発す」〔観無量寿経疏〕と説かれます。仏教の教えは喩えてみれば、鏡の様だというのです。毎日見る鏡は外側しか映し出しませんが、経教は私の内面をありのままに映し出す鏡の様なものなのです。お聖教をくり返し読み求めていくことによって、自身の迷いの姿が知らされ、間違いや欠点が知らされていくと教えられます。
今月の言葉で野田風雪師は、他者を厳しく見る眼で自分自身が見れたらいいですねと、私達にやさしい口調で呼びかけておられます。決して「自分を厳しく見なさい」という命令口調ではありません。自分自身にも言い聞かせておられる様な言葉です。それは、あなたも私も自分を正しく見つめることが出来ないという問題を抱えている仲間(同朋)なのだから、一緒に仏法を聞いていこうじゃないか。お経という鏡に自分を教えられながら、共に生きて行こうじゃないか。その様に、私達をあたたかく応援して下さる言葉としていただきました。 令和3年 5月 貢清春
宗教にとって大切なことは
自分の弱さを知ることである (西谷啓治)
今月も先月の掲示板に引き続き、宗教哲学者の西谷啓治師の言葉が選ばれています。「宗教にとって大切なことは自分の弱さを知ることである」、この言葉は私にどういうことを教え伝えようとしているのでしょうか。
自分の弱さということですが、私は日常生活の中で自分の弱点や出来ないことを隠し、弱点を突かれまいとむしろ強がって生きています。強がって生きていることを教えるのは、「大丈夫」という言葉を私はよく使いますが、この大丈夫、実は仏教語です。学識人徳の備わった人中の最勝者を、漢語で「丈夫」とほめたたえる言葉だったようです。そこに、インドより仏教が伝来したときに、さらに優れたものをあらわす大を付けた「大丈夫」は仏の異名となった、そのような背景のある言葉です。ですから事実としては、仏とは程遠い、全く大丈夫ではないにもかかわらず、大丈夫と言って生活しているわけですから、思い上がりもいいところです。
もう二十年以上前ですが、当時流行した浜崎あゆみさんの曲にこういう一節がありました。
居場所がなかった 見つからなかった
未来には期待できるのか分からずに
いつも強い子だねって言われ続けてた
泣かないで偉いねって褒められたりもしていたよ
そんな言葉ひとつも望んでなかった
だから解らないフリをしていた
流行歌はその時代の人々のこころを映し出すものだと思いますが、現在も世界は「強いもの」「できるもの」が褒められ、評価される世界です。その世界を生きる私も「強くなければならない」という物差しを握りしめて生きています。浜崎さんも「強くなければならない」という観念の中で育ち、その観念の刃に傷ついた幼心が、「そんな言葉ひとつも望んでいなかった」と感じていたのではないでしょうか。この歌詞に多くの人が共感したのは、「強くなければならない」と裁く世界への悲しみであったでしょうし、本当の居場所はそんなところにあるのではないという叫びの代弁のように感じたからではないでしょうか。
「強くなければならない」と周りからも排除され、自分からも見捨てられていく。なかなか事実の自分を自分とすることができずに、「こうでなければならない」という観念の中で生きている私たちを阿弥陀如来は深く悲しまれ、観念、思いの中を生きるのではなく事実の自分を生きていきなさいと願われているのでしょう。大谷専修学院の学院長をされていた竹中智秀先生は、阿弥陀如来のこころを「えらばず、きらわず、みすてず」と繰り返し教えて下さいました。割り切れなさや、不安や、悩みをもつのが事実の自分、裸の自分です。裸になれないと人間は虚飾を求めます。思えば「強くならなければならない」と常に外に自分の根拠を求め続けなければならないことほど、弱いことはないのかもしれません。掲示板の言葉にふれて、あらためて思うのは、私たちは自分で自分を支えているのではありません。この身を支えている大地に依って立っているのです。この身を支えているものに思いを致す時、宗教の言葉が響いてくるのではないでしょうか。 令和3年 4月 深草誓弥
自分が生きているということが本当に言える場合とは
足がちゃんと地面についているという場合でしょう
(西谷啓治『宗教と非宗教の間』)
「幽霊を見たことがありますか?」
以前、御門徒さんから訪ねられた事がありました。僧侶という存在は霊的な感覚があると思われたのか、その様なことに詳しいのだろうと考えられたのかもしれませんが、私は幽霊を見たことはありません。科学や文明が発展した現代でもお盆の頃になると、心霊現象や怪奇現象を取り上げる番組が放送されますし、私が小さい頃は心霊写真や稲川淳二の怪談話しなどが、茶の間を賑わせていた時代もありましたがいかがなものでしょう。皆さんは幽霊を見たことがあるでしょうか。以前寺の法要に来られた講師の先生が、幽霊の姿の特徴を教えて下さったことがありました。
それは、①後ろ髪が長い、②両手を前に伸ばし垂れ下がっている、③腰から下が消えて足が無い、この3点が幽霊の特徴であります。
「後ろ髪が長い」ということは、過去を引きずって執着しているという姿を表現しています。「後ろ髪を引かれる思い」という言葉がありますが、過去の未練が残って思い切れない事をたとえる時にこの言葉を使います。ああしておけば良かったのに、あれはしない方が良かったのかもと愚痴を言いながら、取り返しが付かないことをいつまでも後悔して生きている姿を、長い髪の毛にたとえます。
「両手を前に伸ばし垂れ下がっている」ということは、未来に対する不安から、あれこれと心配して苦しんでいる姿です。これからの子ども達はきちんと育っていくのだろうか、自分が病気したら家族はどうなってしまうんだろうか、私達が年をとった時に年金はもらえるのだろうか・・・等々。そういう未来が不安で希望が無い為に、弱々しく両手が垂れ下がっているのでしょう。
その様な悩みや不安をかかえる幽霊は「腰から下が消えて足が無い」のです。それは現在ただ今「地に足がついていない」ということです。これは過去を悔やみ、未来に望みが無いため、現在ただ今の事実を見失っているということです。その様に生きて行く居場所が無い幽霊は、「うらめしや」と恨みつらみ憎しみからいつまでも解放されず、怖い顔をして周囲を呪っているのです。もう既にお分かりだと思いますが、幽霊とは私達の生きる姿そのものです。依って立つ場所を知らない私の姿を先達の方々は「幽霊」という恐ろしい姿で伝えようとされたのかもしれません。
「過去」と「未来」は、現在の私の力ではどうすることも出来ない、変えることが出来ないものです。そして思いもよらないことや、思いに反することが多々起こって来るのが人生です。世間から切り捨てられ必要とされず、自分を捨てたくなる様な状況に出会うこともあります。その様な思いを超えて、私達に決して見捨てること無く、生きる勇気と力を与えようとする阿弥陀の本願こそ、本当の依り所であり立脚地であります。阿弥陀如来はどの様な境遇にある者も、えらばず、きらわず、みすてずに救う仏であります。その本願のみ教えを聴聞するということは、どの様な人生であっても、どの様なことが待ち受けていても、現在ただ今のここから立ち上がっていける智慧をいただくことなのです。
今月の言葉の「足が地面につく」とは、阿弥陀の本願を私の根拠として生きていく、ということを表現しているのだと思います。依って立つ阿弥陀の大地があるからこそ、目の前の一瞬一瞬の出来事に力を尽くして生きていける。お念仏は唯一の道として伝えられ、今を生きる私達に呼びかけられているのです。 令和3年 2月 貢清春
宗教のことばは時代をこえてひびき
科学のことばは時代とともにかわる (東昇『力の限界』)
今月の掲示板の言葉は東昇(ひがしのぼる)の言葉です。東先生はウイルス学博士、自然科学者でありながら、一方で鹿児島の真宗門徒の家庭に育ち、自らも京都大学在学中に池山榮吉氏と出遇われ、浄土真宗に帰依して生きられた方です。科学者として当時最先端の現場に立っておられた東氏が、「科学のことば」ではなく、「宗教のことば」に普遍性を感じて語られている言葉ですから、重みが違うように感じます。
この掲示板の言葉にふれて思い起こされた安田理深先生の言葉があります。
「そもそも仏教という宗教は、人間に何を与えたのか。それは内観の道ということを教えた。それ以外に教えたものはない。世界というものが如何にゆきづまっても絶望もせず、開けても安心もせん。つまり世界というものを結論としないということです。世界というものを、いつでも縁として、機縁として自己を深めてゆく。ゆきづまったことを結論とせず、ゆきづまったことを縁としてさらに自己を深め、自己を深めたことによってその難関を超えていく、そういうのが内観の道というのです。困ったから困らないようにする、そういうのは外観の道というものです。困ったことを困らないようにするのは科学の道です。内観という道を聞法というのです。」(『内観と念仏』安田理深)
ここで安田先生は「困ったことを困らないようにするのは科学の道」と押さえておられます。この「科学」の受け止めは東先生の受け止めと通底しているものがあるように思います。
私たち人類は現在、コロナウイルス感染症という大問題を抱えています。今、多くの人の関心はワクチン接種がいつになるのか、安全性は問題がないのかというところに集中しています。なんとか人間の知性の集大成である科学でこの問題を解決しようとしているわけですが、一方では変異株が現れ、それに有効なワクチンを作るのにまた時間を要するだろうという問題も起きています。また新たなウイルスが誕生することもあるでしょう。このことは、私たち人間の知性では解決できない問題が絶えず私たちの生きているこの世界にあるということを証明していることのように思います。
先日報恩講の講師としてお話しくださった伊藤元先生が繰り返し次のように語られました。
「私たちがすくわれるのは思い通りになってすくわれるのではありません。道理を受け取ってすくわれるんです。困った問題を除くのではありません。むしろコロナを通してこの世はどういうところかと教えてもらってはじめて生きていく力になるんです。」
現代に生きる私たちはあらゆることに答えを持ち、「たずねる」、「仰ぐ」という姿勢を失っています。自らの思いを満たすことにのみ明け暮れ、世の道理に背を向け生きる生き方はまさに「時代とともにかわる」、気分で生きているような生き方でしかないのでしょう。「時代をこえてひびき」、伝えられてきた経典の書き出しは「如是我聞」です。「私はこのように聞きました」という意の言葉ですが、そこには人間の傲慢さを打ち破り、うなずかざるを得ないような言葉と出会った感動が込められています。 令和3年 2月 深草誓弥
み仏は いつもやわらかに わたしのこころを みつめている
いらいらするわたしを (小野清一郎)
先日、ドラッグストアーでレジ待ちをしていると、私の順番の前でおばあさんが支払いに手間がかかり、しばらくの間待たされたことがありました。その時私は忙しくバタバタしていたので少々焦り気味でした。会計を済ませるとそのおばあさんは、御礼も言わず黙ったまま店を出て行かれたのです。「こういう年寄りには、なりたくないな」と思いながらも私の番に来た時に店員さんから「申し訳ございません、大変お待たせしました」と丁寧な口調で対応してくださったので、「いつか行く道ですから、そのうち私もそうなりますよ、あははは、、、」と、余裕ぶった口調で返事をして、お店を後にしました。しかしその言葉とは裏腹に、時間を奪われた事の腹立たしさと、頭を下げることの無いおばあさんの無神経さにイライラとしていた事を思い出しましていました。
人間の目は外側に付いている為に、外に見える世界の事や、他人の姿などはくまなく見ることが出来ます。その目は事実ありのままの姿を映しているのですが、私の心のものさしを通すとありのままに受け取れません。全てを分別する私のこころのものさしは、自分の都合で「善し、悪し」と瞬時に分けていきます。良い条件がそろえば寛容な心を持つこともありますが、別の不都合な条件がそろえば鬼の様な心になる事もあります。自分のことはいつも棚に上げて、他人の批判をすることばかりをしています。そうやって自分の思いにかなうものならば良い気分になり、思いにかなわない事があると腹を立ててイライラする心をおこすのです。
今月の言葉は、そういう私を仏様は「みつめている」と説かれます。ここで注意していただきたいのは、仏様からやわらかにみつめられて、その結果私の心もやわらかになるとは説かれません。イライラする私をそのままにしてみつめて下さるというのです。これはどういう意味があるかというと、煩悩いっぱいで生きている私達の日常の中に仏様がはたらいておいでになって、煩悩の存在でしかない私をそのままに大悲心をもって呼びかけてくださるお方が仏様であったということです。
正信偈の文には
『煩悩障眼雖不見 大悲無倦常照我 (煩悩、眼を障えて見たてまつらずといえども、大悲ものうきことなく、常に我を照したまう、といえり。)』
とあります。自分が起こす煩悩の目では、仏のはたらきが見えないのだけれども、阿弥陀仏の大悲の光は、決してあきらめることなく、常に私を照らし護ってくださるのだという意味です。イライラする煩悩の心がさまたげとなって仏様に出会えないというわけではありません。この様な私が煩悩のこの身のままで、阿弥陀様の大悲のこころに包まれ、照らされているということです。照らされる、ということは、我が身の姿が明らかになるということです。イライラする煩悩を持ち合わせている私だからこそ、本願の救いの目当てとされていているのです。その事を知らされると煩悩は仏法に出遇っていくための、大きな手がかり「ご縁」と転じられていきます。
お寺に参っている時も参らない時も、仏様を忘れている時も寝ている時も、私が気がつく前から願いをかけてくださる仏様が阿弥陀如来です。イライラは起こさない方が良いことは分かっていますが、ご縁次第でいつでも起す私です。そういう私の為に建てられたのがご本願であり、その心に気付いてほしいと私にお念仏を回向してくださいました。この煩悩を突き破って私の口から「南無阿弥陀仏」とお念仏が出てきてくださる事を有り難く頂戴いたしましょう。 令和3年 1月 貢清春
蛙 榎本栄一
私は地獄をすみかとし 浄土をすみかとする
ぶざいくな 両棲動物です
コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、4月に緊急事態宣言が全国に発令されました。ちょうどその頃でしたが、庭で小学生の長男とメダカを鉢に入れて飼い始めました。家での時間の過ごし方として、他の生き物に関心を持ってもらえばと思ってのことでした。しばらくすると、そのメダカを飼っている鉢にどうやら蛙が卵を産んだらしく、オタマジャクシが沢山孵っていました。それからメダカと一緒に餌を食べながらオタマジャクシはどんどん大きくなっていきました。足が生え、だんだんと蛙の形になっていく姿に、私も息子も興味津々でした。水の中で生まれて、だんだんと浮き草につかまり、陸上で生きていく体になっていく蛙ですが、脅かすと鉢から外に出て隠れてしまっていました。
調べてみると、このころの蛙はエラ呼吸の機能が衰え、肺の機能も育ち切っていない時で、水が深いと死んでしまうそうです。意外でしたが、このころの蛙は非常に弱い存在で、水、陸上どっちにいても苦しかったのでしょう。蛙からすればもう住み慣れた水にも、もうおれない。かといって陸上には天敵が沢山待ち構えている。しかし、外に行くしかない。覚悟を決めて飛び出していたのでしょう。今月の寺の掲示板の言葉に選ばれている念仏者の榎本栄一さんの詩には、そのような、か弱い蛙の姿と、地獄と浄土の間で、いったりきたりしているような人間の姿を重ねて、さらにその弱さをご自身の身に引き当てて「ぶざいく」と表現されている、そのようなことを感じます。
『歎異抄』第九条には、著者唯円が、親鸞聖人に非常に聞きにくいことを聞く場面があります。おおよその要旨は次のようなものです。「長い間親鸞聖人から教えを聞いてきましたが、念仏申しても以前のような身も心も震えるような感動もなくなってしまい、ただ口癖のようになっています。そして念仏申して浄土に往生し、仏なるという教えを聞いているのですが、急いで浄土に生まれたいという心もありません。どうしたらいいのでしょうか。」という問いです。「念仏申し、浄土への往生を願う」ということが、浄土真宗の要なのですが、唯円は正直に「わからなくなりました」と訴えているのです。
この訴えに親鸞聖人は「何を言っているのか。お前の信心が足りないからだ。」と叱責されたのではなく、「そうですか。実は私もかつてあなたと同じような気持ちになったことがあります。それはとても大切なことだと思います」と共感をされています。そしてそのあと、親鸞聖人は「あなたが訴えている問題は煩悩というものを抱えているからです。私もあなたも煩悩具足の凡夫と阿弥陀仏は私たちをかねてから知っておられます。その凡夫をたすけ遂げようと阿弥陀仏は本願念仏を差し向けておられるのです。」と語りかけられたと唯円は述懐しています。ここで親鸞聖人は、煩悩が見えるということが大切なことですと問題の所在を押さえます。
続けて唯円は親鸞聖人の言葉として「久遠劫よりいままで流転せる苦悩の旧里はすてがたく、いまだうまれざる安養の浄土はこいしからずそうろうこと、まことに、よくよく煩悩の興盛にそうろうにこそ。」と記しています。私はこの言葉が掲示板の「地獄をすみかとし 浄土をすみかとする」という言葉と重なっているように思うのです。果てしなく迷いづつけるようなところにおり、地獄だと教えられながら、なかなかそこを捨てて今すぐ浄土に生まれようという心が起こらない、煩悩具足の私。その「ぶざいく」な私にこそ浄土が建立されているのです。「両棲動物」という榎本さんのうなずきは、浄土真宗の教えにふれるなかで明らかになった自身の在り方を素直に吐露しておられる言葉だと思います。 令和2年12月 深草誓弥
生きているということは 誰かに借りをつくること (永六輔)
2016年83才で亡くなられた永六輔さん。このお方は「上を向いて歩こう」や「黄昏のビギン」「こんにちは赤ちゃん」など皆に愛される沢山の歌を残した、昭和の顔とも言うべき偉大な人です。今月の言葉は永六輔さんが作詞し中村八大さんが作曲した歌、「生きているということは」という歌詞の言葉です。1番の歌詞を紹介します。
生きているということは
誰かに借りをつくること
生きていくということは
その借りを返してゆくこと
誰かに借りたら誰かに返そう
誰かにそうして貰ったように
誰かにそうしてあげよう
借りを作る時は必ず相手がいます。その人に借りを返せば借りは無くなります。しかしこの歌詞の中には特定の相手を決めていません。「誰か」となっています。これは家族や友人、仕事仲間や上司など、直接的に出会ったことのある人を超えて、目には見えない様々な人の事を「誰か」と表現されているのだと思います。永六輔さんは「目には見えない誰か」に借りを作りながら生きているのだと、そうしなければ生きていけないと表現されています。しかし私達は一体どんな借りがあるのでしょうか。
「借り」と表現される言葉の内容を、仏教の言葉で「恩」と言い換えても良いかと思います。「恩」とはインドの言葉で「カタンニュー(為されたる事を知る)」という意味があり、中国の漢字である「恩」の字に翻訳されました。「為されたる事を知る」とは、私にしてくださった行為が何であったかを心に深く考え、思い、知るということです。恩という字は「因」と「心」から成り立っているので「因(もと)を知る心」、字そのものが「カタンニュー」の意味を表現しています。生きているという事は、すでに他者から何かしらしていただいているご恩があり、その事を永六輔さんは、「誰かに借りを作って生きている」と表現しておられるのでしょう。
しかし、ご恩をいただいたらその当人にお返しすれば良いのですが、出来ない場合があります。目の前にその人がいなかったり、すでに亡くなってしまった人には返しようがありません。歌には「誰かにそうして貰ったように、誰かにそうしてあげよう」と、してもらった誰かでは無く、他の誰か別の第三者へと恩を送り届け、恩を送られた人はさらに別の人に恩を渡して、恩がこの世間を巡り社会全体が恩に包まれていく。その様な世界を願った歌だと思います。現代は「自分さえ良ければいい、他人はどうなっても構わない」という自分ファーストの時代に、本当はいろんな人のお世話や支えを受けて生活し、いつも借りを作っているんだよ、出来るところから返していこうねと、永六輔さんは歌を通して呼びかけておられます。
毎年、浄土真宗の寺院では親鸞聖人のご命日に報恩講が勤まります。お念仏の教えに出遇えたよろこびから750年以上の長い間、今日まで相続してくださいました。永六輔さんは浄土真宗のお寺の息子さんとしてお生まれなので、お念仏には小さい頃から親しんでおられたと思います。また芸名の六輔は、六字の名号「南無阿弥陀仏」に輔け(たすけ)られるようにという意味で名告られたと伝わっています。
私達真宗門徒にとっては、聴聞するご縁をいただき、お念仏によってたすかる道を聞かせていただいた事への借りがあるのではないでしょうか。親鸞聖人や阿弥陀様に直接その借りをお返しすることは出来ません。報恩講とはお念仏の教えに目覚め、有縁の人達と共有し、そしてご縁があれば他の誰かに伝えていく。その事が「借りを返す」という事になるのではないでしょうか。 令和2年11月 貢 清春
だあれもいない ひとりのとき おねんぶつさまが こうささやく
ひとりじゃないんだよ ひとりじゃ(木村無相)
木村無相さんは、1904年熊本県八代に生まれられています。20歳の時、煩悩を断じて悟りを得ようと発心し、真言の教えを学び始めます。高野山で真言の学びを続けますが、親鸞聖人の念仏の教えに魅力を感じて京都へ下ります。しかし再び高野山に上り、また京都へ下りるというように、何度か京都と高野山を往復して仏法の探求を続けられたようです。その間に、自分の心境を念仏詩の形で発表されました。
「だあれもいない ひとりのとき」に口から出た念仏が、一人でいる私に「ひとりじゃないんだよ」ささやいてくる。とても不思議な詩です。この情景を表面的にみれば、一人でいるときに、一人で念仏している私しか見えないのですが、木村無相さんはそうではないといっておられるのでしょう。大切にしたいのは、念仏申す私に、仏が、念仏を通して私に伝えているメッセージがあるということです。
私が思い起こしたのは、幼いころの記憶でした。私は縁あって真宗寺院に生まれ、幼いころから、仏さまの前に座してお念仏を申してきました。両親、祖父母に連れられて、本堂やお内仏にお参りし、「なんまんだぶつ」と言葉に出す声と、合掌する仕草を真似て、私も「なんまんだぶつ」とお念仏申した微かな記憶があります。小学生になると、朝夕の嘆仏偈の勤行(ごんぎょう)の調声(ちょうしょう、*お勤めの時の導師)を兄と交代で行うようになっていました。
しかし、中学生くらいになると家族の前で声を出すことが恥ずかしくなり、また「なんまんだぶつ」に対して、「こんなことして何になる」というような気持ちがわくようになり、勤行を避けるようになりました。仏さまの前に座ることも少なくなりました。そうして高校生、大学生となっても「なんまんだぶつ」に背を向けていました。「そんなことをして何になる」という思いが絶えずありました。
そのような思いを抱えて大谷専修学院に入学しました。学院で学ぶうちに竹中智秀先生をはじめとした先生方の姿に魅力を感じるようになりました。そして、いくつか忘れられない言葉と出会いました。ある時、竹中先生が「念仏は、逃げるなということですよ」ということをおっしゃられたことがありました。私はそれまで自分のことは自分が一番知っていると思っていましたが、自分でも知らない、事実の自分を受け入れない自分がいることを教えられました。念仏から逃げているのではなくて、自分自身から逃げていたのです。
どんな状況であっても、自分自身をみすてないで生きていってほしい。振り返れば、私に念仏申すことをすすめてくださったのは、父母、祖父母だけではなく、御門徒さん、直接出会ったことのない人々と考えると、無量無数におられます。すでに、私に先立って念仏の教えに遇い、念仏申して生きてこられた人がいます。その方々から「あなたの中にも事実の自分自身と生きていきたいという深い願いがある」と念仏がすすめられているのです。
たとえ私が一人のときでも、この口から出てくる「なんまんだぶつ」に、無量無数のお念仏をすすめてくださった方がおられるのです。木村無相さんが念仏を「おねんぶつさま」という言葉で表現されたのは、もちろん阿弥陀仏のはたらきということを念頭に置いて「さま」なのでしょうが、念仏もうすことをすすめる諸仏の護念ということも大切にされているのだと思います。 令和2年10月 深草誓弥
人間は 間柄を生きる 関係存在である だから人間という
或る人は「人間人」と言った それを失うと 人間でなくなる
世界にコロナ禍が訪れて半年以上が経過しました。集まれない、会えない、会話をしたい、ふれ合いたい・・・けど出来ない、というジレンマの中で、私達はコロナから何を問われたのでしょうか。
2020年のシルバー川柳入賞作品の中に、この様な川柳がありました。
「円満の 秘訣ソーシャルディスタンス」
「我家では 濃厚接触 とんとなし」
クスッと笑いがこみ上げてきた人は、経験のある人だろうと思います。コロナの前からすでに、夫婦間の一定の距離(ディスタンス)を保たないと関係が成り立たないという悲壮感や、同じ家に住んでいても接触すら無い姿に、自分自身も笑ってしまいました。また、高校生が制作したコロナ川柳では、
「自粛中 話す相手は ぬいぐるみ」
友達と出会えない寂しさを誰が癒やしてくれるかというと、ぬいぐるみであることも悲しさを感じました。家の中にあって、本当に言いたいことを聞いてくれる人や、気持ちを分かってくれる人は親や兄弟ではないのです。物を言わずに、じっと話を聞いてくれる(ぬいぐるみ)の方が聞き上手なのかもしれません。自分自身は家族の話し相手になっているのだろうか、と考えさせられました。しかしこれら川柳から、私達の心の底からの願いが明らかになっていると思います。それは、誰とでも心通じる出遇いをしたい、そしてふれ合いながら同じ時を過ごしていきたい、関係を大事にして生きて行きたい、その様に願っているのだと思います。
親子関係、夫婦関係、仕事場での関係、様々な間柄を生きる私達です。日常生活の中では、他者との関係の中で暮らしていることが時には煩わしく、面倒に思うこともありますが、私達はつながりの中で自分が生まれて、育ち、今こうして生きています。そのつながりそのものが自分自身であり、私のいのちであると言っても過言ではありません。親が居るからこそ私がある、妻が居るからこそ私がある。自分と他人との関係、自分と社会との関係、様々なつながりというものを与えられて生きてきたのです。
この半年の期間で葬儀や法事のあり方が変化してきました。まず葬儀は親類だけが会葬し、一般の方は参列を控えられます。遠方におられる親類の方も同様に、県をまたいでの移動を自粛される為、会葬する事が出来ません。その後の中陰等の法事も、家族だけの参加となり小人数の法要が多くなりました。
「三密を 避けてお別れ 家族葬」
というコロナ川柳もありましたが、感染拡大予防の観点からはやむを得ない状態だと思います。しかし今後コロナが終息した後に、今まであった様な沢山の人が集まる葬式や法事を営むことが出来るのか心配です。
葬儀や法事というのは身近な人の死を悼み悲しみ、その事をご縁にして教えに出遇う大切な儀式です。また、様々な人たちとのつながりを再確認する場所でもあります。別れの時に仏事に参加する機会が少なくなるということは、さらなる個人化が進み、「人」は存在していても、人と人をつなぐ「間」が消え去っていくような気がします。「人間人」という言葉をとある先生は「この言葉は"にんげんにん"とは読まずに、"じんかんじん"と読むべきだ」と教えて下さいました。"あいだ"としての"かん"が強調されている読み方だと思います。この言葉は造語ではありますが、人間という存在を深く見つめた言葉です。関係存在として生きている私達の中に「間」がなくなるという事は、人間としてのいのちを失う大変な危機なのです。そしてその危機が、コロナ禍によって速度を増しているような気がしてなりません。 令和2年 9月 貢清春
正義というのは信じがたい 簡単に逆転するんですよ (やなせたかし)
やなせたかしさんは、幼児向けアニメ「それいけ!アンパンマン」の作者です。私も幼い頃から親しんできたアニメです。戦争体験をされたやなせさんは、「本当の正義のヒーローは戦いに勝つことではなく、ひもじい者に食べ物を与える者だ」という思いを持っておられたそうです。そこから、自分の顔を食べさせることによって、飢えから助けてあげる、真のヒーローとしてアンパンマンが誕生したのだそうです。「ほんとうの正義というのは、決してかっこいいものではない。必ず自分も深く傷つくものです」とも語られたそうです。自分の身を差し出し、困った人を助ける姿に、人びと、特に子どもたちはこころを引かれるのだろうと思います。
今月の掲示板の言葉も、やなせさん自身が戦争を体験されたなかで「骨身にしみて思い知らされた」と語っておられた言葉だそうです。やなせさんは次のように語られます。
太平洋戦争に駆り出された時、この戦争は聖戦であり、「日本は苦しんでいる中国の民衆を救うために戦うのだ」と聞かされていたのに戦争が終わったとたんに、正義の論理はあっけなくひっくり返って「日本軍は中国を侵略した」となったのだ。
掲示板の「正義というのは信じがたい」という言葉は、戦争という時には、どの国も自国こそ正義であり、相手国が悪いとしか思っていない、その振りかざした正義こそ不安定なもの、あやしいものではないか、という問いかけの言葉であると思います。
そして、人間は、たとえば自分の心に固く「ウソをつかない」と誓っていたとしても、周囲の状況次第で、自分を守る為にウソをついてしまうことがあります。仏教では、縁に随って生きる「随縁存在」であると教えられていますから、自分で作った正義は時と場合によってコロコロと変わってしまいます。
人間の愚かさは、いつ、どこでも、自分が正しいという立場から、物事を考えていることですし、またその自分は正しいという立場を、自分で問い返すこともできません。そしてその立場で、いつでも自分の思い通りになることを求め、思い通りにならないものを排除することを考えています。
「アンパンマンのマーチ」の歌詞ですが、「なにが君のしあわせ なにをして よろこぶ わからないまま おわる そんなのは いやだ」という歌詞があります。この歌も「なんでも自分の思い通りになることが本当の幸せだと思いますか?本当の喜びといえますか?本当はどうなる事が幸せか、喜びか、知らないまま生きているのではないですか?」という問いかけの言葉だと思います。
やなせさんは50代でアンパンマンを描き始められましたが、当初人気は出ませんでした。アニメ化されブレイクしたのはやなせさんが70歳になる直前だったそうです。しかしその間も、そして大人気アニメとなった後も、アンパンマンというキャラクターによって、「正義とは何か」「何が人間としての喜びか」という人間の大切な課題を提起し、私たちの魂をゆさぶり続けてくださっていたのか、とあらためて気づかされました。 令和2年8月 深草誓弥
お経の中で阿弥陀如来がお出ましになる時、観音菩薩と勢至菩薩が脇侍として出現される場面が数多くあります。この姿は「弥陀三尊」と言われ、観音菩薩、勢至菩薩が中央ご本尊の阿弥陀如来の両脇に控え、両菩薩が中尊の補佐をする役目を担っています。観音菩薩は阿弥陀如来の「慈悲」の徳をあらわす化身とされ、勢至菩薩は「智慧」の徳をあらわす化身とされます。化身というのは生まれ変わりという事では無く、お姿としてはたらき出た身体、という意味です。
観音菩薩として表現される「慈悲」とは「抜苦与楽」という内容を持ち、衆生の様々な苦を抜き、楽を与えるはたらきがあります。勢至菩薩として表現される「智恵」とは、大きな願いの光でこの世を照らし、我々の無明の闇を破るというはたらきがあります。この二つ「慈悲と智慧、観音と勢至」が阿弥陀如来の徳を表現しています。補足ですが弥陀一仏を本尊とする真宗門徒は、脇に控える観音菩薩のみ、勢至菩薩のみを信仰することはありません。根本の阿弥陀如来をご本尊として礼拝の対象とします。
しかしこの二菩薩の中で、日本人に親しまれている菩薩様は観音菩薩の方ではないでしょうか。歴史を振り返ると、戦争で国が乱れたときや、自然災害で大変な時代には、貴族も民衆もこぞって観音菩薩を信仰しました。何故かというと、正式名称の観世音菩薩は「世の音を観じる菩薩」様であるからです。人間から発せられる苦しみの声や、災難に襲われたときのうめき声、助けてほしい、助かってほしいという様々な世の音を聞き届けてくださる菩薩様だからです。苦難の時代を生きる衆生の声に、真摯に耳を傾け声を聞いてきた観音菩薩の慈悲の姿は、時代の要求に応えてきた面があるのではないでしょうか。そして、今まで全く縁の無い人たちに仏教との接点を持つきっかけを作って下さったのは、観音菩薩のお仕事なのかもしれません。
しかし仏教は、人間の要求だけに応えてくださる宗教ではありません。その一面だけだと、自分の願い事を叶えるだけの、人間にとって都合のよい宗教になってしまいます。もし願いが叶えられたならば、もし苦しみが無くなったならば必要とされないものになります。逆に仏教は時代に対して、私達に対して要求すべき事があるのです。それが、勢至菩薩を象徴する智慧の姿としてはたらきかけているのだと思います。智慧とは「おばあちゃんの知恵袋」の様な、生活の中の賢い知恵、人生経験で得た人間の知恵知識という事ではありません。仏が覚られた道理、真理を表現します。その教えによって人間の目では見ることの出来ない自分の内なる姿を知り、心の闇を照らし破って下さいます。迷いの姿を知らせ、生きることの本当の意味と目的が明らかとなり、正しい道へと導いてくださいます。その仏の智慧に育てられて生きて行きなさいと、私たちに求められているのです。
知恵知識を蓄え経験を積んでいく事は、生きていく中でとても大事な事です。人間の賢さは生活を支えてくれますが、気が付けば自分が賢くなった分だけ他人を見下す様な態度で接してしまいます。偉くなった気分になり、頭が上がってしまいます。仏の智慧をいただくと、逆に頭が下がる人に成ると聞き習いました。私の愚かさ、生きる事の悲しさ、罪業の深さに気づかされると、ふんぞり返ってはいられません。仏から私に要求され願われている事は何なのか、もう一度確かめてみなければなりません。 令和2年 7月 貢清春
日曜学校夏の集い
「ほのかな光を楽しむ、キャンドル作り」
毎年、「海の日」はバス遠足を計画しておりますが、今年は新型コロナウイルスの為、中止することになりました。又、夏休みも短縮されることから、今回は夏休み後半に行う「夏の集い」を「海の日」に変更させていただきます。
今年の「夏の集い」は、キャンドルランタン作りを計画しています。牛乳パックに溶かしたロウを入れ、固めて作ります。どうぞご参加いただきます様、ご案内申し上げます。保護者の方の参加もお待ちしております。
日 時:令和2年 7月23日(木・海の日) 午後2時~6時
場 所:福浄寺本堂
参加費:無料
【持参品】
お勤め本、念珠、水筒、はさみ、ふでばこ、色えんぴつ、クレヨン
牛乳パック(1リットルパックで、きれに洗い乾かして、切らずに
上を開けた状態でご持参下さい。)
【参加確認】
材料の準備等がありますので、参加人数を確認いたします。参加(人数も)、不参加の連絡を電話またはメールにてお知らせ下さい。
【日程】午後~
2:00 集合 お勤め
2:30 キャンドル制作開始
4:00 制作終了~後片付け、清掃
4:30 夕食作り
5:00 夕食 ホットドッグ、焼きそば
6:00 恩徳讃 解散(自宅まで送迎します)
顔を寄せ合い対話すること 手を重ね合わせること
それがどれほど貴重で 脆(もろ)いものであるかを
私たちはついに知ってしまった 月永理絵 (5月1日 朝日新聞夕刊から)
国内で初めて新型コロナウイルス感染者が確認されたと発表があったのが1月16日。2月にはクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号での集団感染が発生し、日本国内の感染者数は、3月終盤以降に急増しました。4月7日、東京都や大阪府、福岡県など7都府県を対象に5月6日までの期間、「緊急事態宣言」が出されました。それに合わせて開かれた会見で、安倍首相は「緊急事態宣言」を1か月で脱するために、人と人との接触を「最低7割、極力8割」減らす目標を掲げ、国民に外出自粛などの徹底を呼びかけました。さらに16日にはこの「緊急事態宣言」の対象が全国に拡大されました。新型コロナウイルス感染拡大を受け、それまでの生活で当たり前だった、「顔を寄せ合い対話すること」、「手を重ね合わせること」は、「濃厚接触」、「三密」という状態であることが指摘され、現在も人との触れ合いは最小限にすることが求められています。
私たちも、御門徒の御法事にお参りしますと、マスクを着用し、距離をとってお勤めするようにしています。御門徒も、最小限の人数で法事をむかえられているところが多いように思います。まだまだ予断を許さない状況であると思っています。しかし同時に、これまで当たり前のように、葬儀、法事という仏事の場に多くの人がお参りし、ねんごろな対話やふれあいをしてきたことが、掲示板の言葉にあるように「貴重で脆い」ものであるかを、まざまざと見せつけられています。
振り返れば、私にとって忘れられない学びや、人や言葉との出遇いは、いつも直接対面でした。そして時にそれは向こうから迫ってくるような、濃密なものでした。それこそ、こちらから自分を正当化し、自分を守ろう、距離を取ろう、逃げようとしても、「逃げるな」とおいかけてくるような質のものです。
葬儀、法事の中止や規模の縮小を受けて、私の中で何か喪失感があったのは事実です。おそらく、当たり前にあった様々な人との直接の「対話」や「触れ合い」がなくなったことで、人間関係にも距離感が生じ、信頼関係も揺らいでしまったように感じています。同時に仏教にも距離感が生まれていくのでしょう。また一面では、脈々と受け継がれてきた仏事が、コロナウイルス感染症対策を隠れ蓑にした、快、不快を中心とする、「自分さえよければそれでいい」というような個人主義によって消えていくような感覚もあります。
仏教は、人から人に直に伝わってきました。先日、ある御門徒がお寺に参詣されました。年を取られ、足腰が不自由でありながら、息子さん、奥さんに支えられてお参りされました。
「入院する前に、最後と思うて来ました。
なんまんだぶつ、なんまんだぶつ・・・。」
ずっとお念仏申されていました。お元気だったころからすると細くなられた手を取って、脇を支えながら、体温や息遣いを感じていました。単純に、私も念仏を申そうと思いました。もちろん感染防止に取り組まなければならないのですが、お念仏の教えを生きるものにとって「対話」、「触れ合い」の大切さをあらためて感じています。 令和2年6月 深草誓弥
人間であるということは 自分には関係がないと思われるような不幸な出来事に対して 忸怩たることだ 『人間の土地』 サン・テグジュペリ(堀口大学訳)
*忸怩(じくじ) はじること。ここでは責任を感じるということ
何事も無縁ではない
「星の王子さま」で有名なフランスのサン・テグジュペリは、陸軍飛行隊や航空郵便のパイロットをしながら、作家として様々な作品を世に送り出しました。「人間の土地」という本は、パイロット経験の中での随想集という構成で、文章全体が力強い「詩」の文体となっています。生きることに対しての真剣さ、喜び、自由、一行一行に作者のエネルギーが詰め込まれた深い内容となっていて、読むには大変な時間がかかります。それほどに作者の言葉に対する向き合い方が真摯に伝わってくる本です。
今月の言葉はこの本の第2章「僚友」に出てきます。航路開拓の任を受けた僚友ギヨメが、アンデス山脈横断飛行中に3500m地点で墜落、雪と岩しかない山地で7日間を生き延び、救助隊に発見されます。墜落した後の2日間は飛行機の下に雪穴を掘り、嵐が過ぎ去るのを待ちます。その後、救助を求めに歩くのですが、足は凍傷のために腫れ上がり、意識は朦朧となりながらも歩き続けます。その時ギヨメはすでに死を覚悟して死に場所を探し歩いていたというのです。雪の斜面で倒れて死ねば、夏になって雪解け水と一緒に流されて遺体が発見されず、行方不明のままになってしまう。そうなると妻に支払われる保険金が4年後にしか支払われない。岩場に張り付いて息絶えればすぐに発見されるだろう、と岩場まで歩いて行くのです。もう死ぬしかない、生きる希望が無い極限状態の中で何故生きたのか、何故生きられたのかということを、
「救いをもたらしてくれるのは、一歩一歩踏み出すことだ。一歩また一歩、同じ一歩を繰り返して・・・・」
と、僚友ギヨメは語ります。サン・テグジュペリは生還したその彼の姿に感動し、どんなにつらい時でさえも今の事実を受け止め、そして真面目に、今自分が出来ることを精一杯尽くして生きる事の大事さを、ギヨメの遭難事件を通して語っていかれます。そしてその後に彼の素晴らしいところを「自分には責任があると感じるところ」と記しています。郵便物に対しても、僚友に対しても、人々の間で何か新しいことが行われようとすること対しても自ら参加して、責任を負わなければならない、そう彼は考えていると表現しています。
そしてさらに自らの職務を通して知らされたことを「人間であるということは、自分には関係がないと思われるような不幸な出来事に対して忸怩たる(責任を感じる)ことだ」と表現しています。これはどういう事かというと、渋谷豊訳の本では「自分のせいではないと思えていた貧困を前に赤面すること」と翻訳されていました。他人の喜びや悲しみや苦しみも、私と全てが関係している。無縁なものは一つも無く、自分自身の行動が世界の建設に貢献しているということを、人間として感じなければならないのだと記されます。
新型コロナウイルスが中国で発生して約半年が経過しました。多大な感染者と死者を出したこの病気は誰が蔓延させたのか、その責任問題が大きな問題とされています。政府の対応が遅かったのでは、もっと早く空港を封鎖しておけばよかったのに、国はどう責任をとるのだ等々、全世界が犯人捜しに躍起になっているのではないでしょうか。
しかし元はといえば、棲み分けられていた垣根を越えて人間が自然の奥へと侵入し、人間界にウイルスを持ち帰ったことが始まりだったわけです。コロナウイルスの宿主とされるコウモリは、様々な病原体のウイルスにとても強い個体へと進化したと云われます。そういった野生動物に接触し、ウイルスに弱い人間が仲介役となって、感染を広げていったとされています。自然界全てを人間の手の中に入れようとする思いが、様々な新しい病気を生み出す種になっているのではないでしょうか。私とコロナは無縁だとは、決して言えないと思うのです。私を含めた人間の責任として受け止めていかなければならないと思うのです。だからこそ私達が出来ることを、終息に向けての「一歩一歩」の行動が大事なのです。 令和2年5月 貢清春
「待った」のかすかな御こえに あやうく立ちどまる
勝とう負けまいの方向へ うかうかと行きかけて (榎本栄一)
今、社会では新型コロナウイルス感染症で、不安が広がっている。この事態を受けて、私自身もこれからどうなるのだろうかと「先行き」が見えないことに不安をいだいている。しかし、ふと気付かされたのだが、そもそも私自身に先を見通すような力は備わっていないのではないか。「先行きが不透明」というが、そもそも一瞬先のことも見通せていない。『観無量寿経』で、釈尊は韋提希に対して「未だ天眼を得ず」と語っている。
汝はこれ凡夫なり。心想羸劣(しんそうるいれつ)にして未だ天眼を得ず、遠く観ることあたわず。
(『仏説観無量寿経』 真宗聖典95頁)
その前に「心想羸劣(しんそうるいれつ)」という言葉が出てくる。「羸」は弱い、虚弱という意味だが、よく見ると字に羊という字が使われている。漢和辞典をみると羊から構成されていて、身体が痩せこけた、病気の羊というのが元々の意味のようだ。この「羸」というのはいろんなことに押し流されていく私たちのあり方を示しているように思う。どれだけ私たちが強い意志や行動力をもっていたとしても、それを超えるような状況が訪れると、押し流されて行かざるを得ない。ニュースで報じられる今回のコロナウイルスの流行に改めて感じるのは、この状況の中に、あらゆる人間の生活がなすすべなく呑み込まれていくような、恐怖である。また、自分自身の「よわさ」に唖然とする。
全国各地の寺社で、コロナウイルス退散、撲滅祈願がおこなわれている。まさにコロナウイルスに「勝とう、負けまい」とかすかな希望をつなぐように祈願祈祷を求める心も心情としてわからなくはないのだが、同時に「そうではないだろう」といういかりのこころも生まれてくる。現実はそうなってしまっているし、私が祈ったからといって、何もかもがよくなるということはないだろう。
悲しいことだが、私たちの身の上にめぐってくる出来事は、ほぼ自分で選ぶことができない。「なぜ、このような目にあわなければならないか」と思うが選べない。だから人間は「これは違う。こんなはずではなかった。これはわたしではない。」と、現実の自分と世界とから逃避することを試みる。それが祈願祈祷というかたちで、求められ、あらわれているのでないか。あらためて私は、祈願祈祷では人間を救うことはできないと思っている。「この仏様を拝んでいたらいいことある」というような、私たちの身に何がめぐってくるかを変えることができる宗教は、この世の道理に反するものでないだろうか。
コロナに勝つか負けるかばかりに気を取られている今だからこそ、「待った」がかけられているのだろう。大切にしたい事は、めぐってくる出来事は変えることはできないが、めぐってきた出来事をどう受け止めていくかということだと思うし、何がその出来事から語られているかを聞いていくことだと思う。「勝とう負けまい」の方向に向かい、もし負ければ絶望しかない。
釈尊は、四門出遊の物語にあらわされているように、老病死を見て、避けよう、逃げようとされたのではなかった。勝とう負けまいとされたのではない。もちろん避けることができることは、避けなければならない。努力もしなければならない。しかし、そのような私たちのおこないを超えて、あるいは呑み込んでいくように老病死は迫ってくる。コロナに勝つか負けるかではなく、この世の道理と、自分自身のいのちの相に、どう態度をとるのか。そのことを問題としたのが、この四門出遊の物語が教えることではないか。 令和2年4月 深草誓弥
震災で確信した 人は自然から学ばないと 絶対に賢くなれない 美術家 八巻寿文
今でも当時の巨大津波の映像が目に焼き付いています。黒々とした波が押し寄せ、家や瓦礫もろとも海へと流されていく光景は、今まで見たこともない衝撃の姿でした。あの東日本大震災から、今年3月11日で9年を迎えました。地震の恐ろしさ、津波の強大な破壊力、自然の脅威に全世界がおののいた災害でした。被災され避難生活を続けられている方がおられる中、震災後バラバラとなった生活の回復は、途方もない時間を要していると報道されています。
被災地では今なお様々な復旧活動が行われていますが、これは震災後2、3年たった後の話です。津波の被害にあった気仙沼の海岸に、海面から5、2メートルの高さの防潮堤建設を県が打ち出しました。その住民説明会の時に、「海が見えなくなるじゃないか」「津波が防潮堤を乗り越えてきたときは危険性が増す」など、住民は防潮堤建設に反対を訴え、疑問を投げ掛けました。しかし「住民の生命と財産を守る為」を理由に建設の見直しは考えていないという県の意向と、海と一緒に生きていこうとしている住民の方々の思いとは大きな隔たりがあった、という記事を見たことがあります。それから防潮堤建設は住民の思いとは逆に粛々と進められ、現在では大きなコンクリートの壁が町と海を分断するようにそびえ立っています。海が全く見えないコンクリートの塀に囲まれた町の中で、本当に安心して暮らすことが出来るのでしょうか。
私たちの文明は科学技術を飛躍的に発展させて、自然災害を防ぐ「防災」に大きな力を注いできました。身近なところで言えば、スマートフォンで雨雲レーダーを見れば、いつ、どれくらいの雨が降るかを予測できますし、地震が起こる数秒前には緊急地震速報が流れ、揺れに備えることも出来ます。予測することで小規模の災害は防げるようになりました。しかし9年前の大震災の時には、想定外の巨大津波によってバラバラに壊された防潮堤のコンクリートの塊が海岸に打ち上げられていた姿が報道されていました。このような震災の被害の状況は、現代の私達に「人と自然とがいかに関わるのか」という大きな問題を提起しているように思います。
京都府の南部を流れる木津川に「流れ橋」という橋があります。時代劇のロケ地として有名なので、おそらく誰でもテレビなどで見たことがあると思います。この橋は日本最大の木造建築橋で、川の増水時に橋桁があえて流されるように最初から計算して造られています。これは、初めから頑丈に造らずに流れたら造り直すという発想によるものです。川が増水すると橋桁が簡単に流れるようになっていて、流木やゴミ等の漂流物が橋に引っ掛ることがありません。また堤防の決壊などの損害を未然に防ぐこともできるそうです。また流れた橋桁を紐等(現代はワイヤー)で連結しておくことによって復旧がしやすくなります。これは自然と対立した関係では無く、共存していこうとする先祖の知恵が生み出したものであります。
「自然から学ぶ」ということはこのようなことを言うのかもしれません。最大限の人間の知恵を使いつつも自然には逆らわず、自然の恵みも、災害も全て受け入れていく道を先達の方々は選択してきたのだと思います。大げさな表現かもしれませんが、私達が作った物は壊され流されるものなのだ。壊れたら作り直したらいいのだ、という付き合い方をしてこられたのが、流れ橋を作った方々の思いではないでしょうか。
私たちの分別や計らいをこえて動いているのが自然の営みであります。自然のはたらきに抵抗し、人間との間にコンクリートで壁を作るのではなく、自然の声を聞き、自然と共に生き、自然の力を見直す事が私達には必要なのだと今月の言葉は問いかけている様に思います。 令和2年3月 貢清春
人が生きているって深いことなのだ それゆえにあなどれないのだ 渡辺 一史
今月の掲示板の言葉は、フリーライター、ノンフィクション作家の渡辺一史(わたなべ かずふみ)さんの言葉です。渡辺さんは2003年、札幌で自立生活を送る重度身体障害者とボランティアを描いた『こんな夜更けにバナナかよ 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち』で第25回講談社ノンフィクション賞などを受賞されています。今回の言葉は著書の『なぜ人と人は支え合うのか ─「障害」から考える』からの言葉です。2016年に相模原市で起きた障害者殺傷事件などを通して、障害者に寄り添うなかで、健常者から見た障害者という思想でなく、障害を持つ当事者の思想から人と社会、人と人のあり方を根底から見つめ直していくという内容の本です。
三年ほど前に、たまたま見ていたテレビで、ある番組が放送されていました。難病のため人工呼吸器が片時も手放せない状態で、手足も動かせない青年の生活に密着したドキュメントでした。身の回りのお世話を全て家族にゆだね、食事もお母さんがミキサーですりつぶして食べさせてもらう。その生活の様子を見た私のなかに浮かんできたのは、「かわいそうに」という心でした。しかし、その青年は、ある時一人暮らしがしたいと、親に相談します。両親は困惑していましたが、青年の気持ちを尊重し、話し合って24時間、青年の一人暮らしの部屋にヘルパーが交代で見守ることなどを決め、はじめての一人暮らしを認めました。
それまで、なかなか他の人との関係が開けなかった青年が、一人暮らしをはじめて、様々な人に自分から関わりを持とうと意欲し、充実した生活を送るようになりました。その時に記者から相模原の事件について質問され、応えた言葉に私は衝撃を受けました。
「幸せか、不幸かは、その人自身が決めること。他の人が決めることはできない。障害者を見て「かわいそう」という心が植松被告を生み出している。」
あわててメモを取りました。まさに私自身が「かわいそうに」という目線で、その青年を見ていたからです。言い当てられた言葉でした。私たちが日ごろ思いえがいている幸せとは何でしょうか。自分の思うようになったということもありますが、あの人より優れているとか、周りと比べて特別だ、というような優越感のところに幸せを感じています。しかし、今回の掲示板の言葉にあるように、「人が生きているって深いこと」であって、幸せは決して人と比べて感じるものではないのです。先ほどの青年の言葉にあるように、「幸せか、不幸かは、その人自身が決めること。他の人が決めることはできない」のです。その人自身にしか経験していない苦しみや喜びがあるのです。
仏法は、何時でもない今、どこでもないここに、誰でもない私として存在していること自体に満足があると教えています。掲示板の言葉にある「あなどる」という言葉は相手を軽く見てばかにする。見くびるという言葉です。先の青年の言葉から、「勝手に不幸だと決めないで。見くびらないでほしい。あなたのいう幸せとは何か。」と叱責されているように感じています。 令和2年2月 深草誓弥
ご恩報謝とは 恩を返すことではなく ご恩を無駄にせぬことである 小山法城
一つの物語を紹介いたします。お釈迦様が御在世の時のお話です。お釈迦様のお弟子の中に着物や食べ物等を粗末にする人がありました。その姿勢を見かねたお釈迦様は、そのお弟子に着物を脱がせて町を歩かせます。町の人から笑われるお弟子にお釈迦様は、「今は服を返せない。これをおまえにやるから着物を作りなさい」と言って、綿の花を一束お渡しになりました。お弟子はそれをつくづく眺めて「お釈迦様、私は、魔法使いではありません。とても綿から着物は作れません」と申しました。その時お釈迦様は綿から着物が出来るまでの事を、そしてお米が出来るまでのお百姓さん達のご苦労もお話になりました。
「私達が毎日暮らしていくには、お百姓さんや、着物を作る人、その他いろいろな人のお陰を受けているのだ。その人たちのご恩を忘れたり、その人たちのお陰を受けて出来た物を、決して粗末にしてはなりません。」とお戒めになりました。 「子どものための仏教ハンドブック(東本願寺出版)」より抜粋要約
というお話です。なぜこのお弟子は物を粗末にしていたのかというと、様々なお陰を受けて生きている事のご恩を忘れていたという事が原因でした。そこでお釈迦様は着物が作られ、お米が作られる詳細をお話になったのです。もしかするとこのお弟子は、着物やお米が様々な人と時間を要して作られる詳細を本当に知らなかったのかもしれません。その様なお弟子に対してお釈迦様は「知らせる」そして「気付かせる」という方法で諭されたのです。私達も同じように教えられないと、知らされないと分からないということが沢山あります。
ティク・ナット・ハンというベトナムの僧侶は「この一枚の紙の中に、雲が浮かんでいる」と語られました。一体どういうことでしょうか。紙一枚の中には「雲」という背景が欠かせないという事です。雲から雨が降り森を育て、立派な木となります。その木が紙の原料となります。木を育てる土や、微生物も紙一枚の背景には含まれているでしょう。以前、福浄寺で使っているコピー用紙がどこで作られているか調べたことがありました。コピー用紙の包装紙には「Made in Indonesia(インドネシア産)」とありました。おそらくインドネシア工場の近隣の山からパルプを採り、出来上がった紙が日本へと運ばれて、今ここにあるのだという背景が知らされました。それは想像も出来ないくらいの時間と、様々な人たちのご苦労が組み合わさってここにあるのです。知らされれば知らされるほど、無駄にしてはならないと思わされます。
ご恩報謝の「報」の字は「むくいる(報復、報酬)」という意味と、「しらせる(報道、報告)」という二つの意味があります。いただいているご恩に対して報いていこう、何かお返ししたいという心は大切です。しかし今月の言葉にありますように「ご恩」とは、ただただ如来様から頂戴するのみでありますから、返せるものではありません。私達が出来ることは、自らがお念仏のおこころをいただき、他の人に知らせ伝えていく事なのではないでしょうか。法要の時には必ず法話の席が設けられ、仏法を聴聞いたします。「聞法」とは自分自身にまで届いた念仏の背景や、様々なご恩を知らされ気づかせていただく事ではないでしょうか。
福浄寺の一年の行事は、1月の御正忌報恩講から始まります。1月は上旬が過ぎればすぐに御正忌の準備に取りかかります。仏具のおみがきから、お華束のお餅つき、餅盛りと華立て、お内陣の荘厳清掃等と、沢山の御門徒方々のお手数をいただいて準備が整い、御正忌をお迎えします。法要中は日中と逮夜のご参詣があり、お昼には婦人会の皆様方が作られる精進の御斎をいただきます。まさに御門徒皆様の御懇念と御報謝の総力を結集して、この御正忌報恩講が厳修されます。御門徒方々のご尽力と願いを「無駄にせぬ」ように自分自身が念仏申し、御正忌を大切に勤めさせていただきたいと思います。 令和2年1月 貢清春
恩と無縁で 生きてこられた人はいない 鷲田清一
早いもので今年も12月をむかえています。福浄寺では、門徒報恩講が10日から8日間勤まります。門徒報恩講で一年が終わり、年が明けると福浄寺の報恩講が厳修されますので、報恩講で終わり、報恩講で始まる一年となります。この法要日程を考えられた先達は、この報恩講に特別な願いをもっておられたのでないかと感じます。
その報恩講をむかえる月ですから、恩ということが掲示板の言葉に選ばれています。「恩と無縁で生きてこられた人はいない」という言葉です。まず、恩という言葉についてですが、その字を見てみると原因の因という字の下に心という字を書きます。現在を結果と見ると、現在の自分を育ててくださった因(もと)を知るということが、恩を知るということになるかと思います。
「恩と無縁で生きてこられた人はいない」と教えられるとおり、今の私を育ててくれた縁は計り知れません。自分を育ててくれた父母、祖父母。子どもからも親として育てられています。学校の先生、先輩、友達。今日まで私の血肉となってきた牛、豚、鳥などの生き物、お米や麦などの植物たち。そしてこれらの命をまた育ててきたものと考えると、私の存在の背景には、気の遠くなるようないのちの連鎖がひろがっています。これらの縁無くして私は成り立たないわけです。
しかし、現代社会はこの恩というものを忘れた、あるいは恩ということを顧みない時代になっているように思います。しばらく前にある先生が話されていたことを思い起こしました。学校での出来事だそうですが、給食の時間、最初にいただきますと感謝の言葉をいい、そして食べ終わってお礼の言葉を一緒に言うということが、どこの学校でも習慣づけられていると思いますが、ある学校のPTAの会合で、一人の若いお母さんが「けしからん」と怒られたそうです。子どもが給食を食べているのは、あれはみんな親がきちんと給食費を払っているからだと。だから子どもは給食を受ける権利があるのだと。それを何で、感謝を強制するのか。それはけしからんことだと意見をおっしゃったそうです。
私はこの話を聞いて、さみしさを感じました。そしてあらためて、「いただきます」「ごちそうさまでした」の言葉の重要性を感じました。「いただきます」、「ごちそうさま」にも自分のためにさまざまな命が犠牲になり、また苦労があってのことであることを知りなさい、というメッセージが込められているのでしょう。
先程の話で大切な事は、恩ということを忘れれば、人間は「自分がやっている」ということしか考えない、ということです。あたかも自分一人で、自分の力で生きているかのように思ってしまいます。しかしそれは全くの幻想だということを、恩という言葉は、私たちに教えているのでしょう。恩を忘れるところには、私が生きている事実を「ありがたい」こととして受け止めることもありません。その生き方は、自分を本当に大事にすることもできませんし、私を成り立たせている周りの様々な命を大事にということも開かれてこないのでしょう。 令和1年12月 深草誓弥
「たとい所有者の承諾があったとしても 本当にそれが必要でなければ
他人から何かを受け取るのは盗みです」 ガンディー『獄中からの手紙』
本当に必要なのか 自分でしっかり検証すること
「インド独立の父」とも呼ばれ、身をもって実践した「非暴力不服従主義」の精神でイギリスの植民地であったインドを独立に導いた指導者マハトマ・ガンディー。1930年、イギリスの塩の専売制度に対する抗議行動「塩の行進」を行って逮捕され、60歳を超えていたガンディーは投獄されます。牢獄にとらわれている中、弟子たちに正しい行動原理を教える手紙を書かれました。その言葉をまとめたものが「獄中からの手紙」で、主要な戒律を同志たちに説明しています。
今月の言葉はその手紙の中で「不盗」というテーマの箇所に記されてあります。他人の物を盗むのは当然してはいけない行為ですが、必要でない物を所有する事も盗みに等しいとガンディーは伝えています。まずは何故、仏教が盗みを問題にしているのか考えてみたいと思います。
仏教の戒律(十善戒)の中に、「不偸盗(ふちゅうとう)」があります。他人の物を盗ってはいけないという事ですが、この偸盗を別名「不与取(ふよしゅ)」とも言われ、「与えずして取る」という意味があります。自分は種まきを一つもしていないのに、結果だけを奪い取り所有するということです。物を盗む行為は法律で罰があるからしてはいけないという事だけではありません。盗むとは、他人が時間をこしらえて作った物を奪い取るという事であり、その人の人生そのものを奪い取る行為でもあるわけです。だから他から盗ってきた物は、自分には相応しくない物なのです。ガンディーはさらに深く「無所有即清貧」というテーマ箇所において展開されます。
「たとえ、本来は盗んだ物でなくとも、(たとい所有者の承諾があったとしても)わたしたちが必要でない物を所有しているなら、それは盗品とみなされなければなりません」 と説かれています。私たちの日常感覚として、相手から了解・承諾を得て所有しているのなら別に問題が無いように思われますが、必要でない物を所有する事自体にも問題がある、と説かれるのです。なぜここまで徹底していかれるのかといいますと、この書の中で「もし各人が必要な物だけを所有するなら、ひとりとして困窮する者はなく、万人が満足に暮らしていけましょう」と、皆が安心して生活できる世の中を実現しようと願われたからなのです。
必要以上の物を一部の人が所有することによって貧困が蔓延し、貧富の差が広がっていくという現実は、現代の格差社会にもあてはまります。金持ちはさらに金持ちになり、貧困層はさらに増えていくという状況にガンディーは「万人が満足して暮らせる世界、困窮する者の無い世界」を教えに依りながら求められたのでした。自分に必要な物だけで、自分に相応しい環境の中で生きていく事で「盗まない」という生活を真摯に体現していこうとされたのだと思います。
ここ福浄寺がある川棚の地では、石木ダムの必要性が疑問視される中、建設計画が粛々と進められています。本来ダムというのは「利水」と「治水」という目的のために建造されます。利水というのは生活用水や農業用水等を確保し使用する事を言い、治水とは大雨の時に洪水被害を軽減するために川へ流れる水の量を調整する事を言うそうです。石木ダムで貯めた水は佐世保へ送水する計画ですが、佐世保市の水の需要は減少傾向にあり、本当に水が不足しているのかは疑問視されています。そして治水の面をみますと、川棚川の支流である石木川は、川棚川の水量の10分の1しか流入しないために、石木川にダムを造ったとしても洪水を防ぐ事はできません。ダムを造る目的である「利水・治水」両面からみても必要性は無いように思われます。
ダム建設予定地の川原(こうばる)に住み続ける人たちの人生を奪い、自然環境を奪い、県民から預かった税金(お金は、その人の人生において費やした時間そのもの)を盗んでまで造る必要がどこにあるのでしょうか。しっかりと再検証する必要があるように思われます。現代にもしガンディーが生きていたなら、今月の言葉そのままを私たちに発信されたに違いありません。 令和1年11月 貢清春
文明が進めば進むほど、天然の暴威による災害が、その劇烈の度を増す
(『天災と国防』)物理学者 随筆家 寺田寅彦
今月の掲示板の言葉は、自然と文明の在り方について語った、物理学者の寺田寅雄の言葉です。90年程前の言葉ですが、一つの道理を示していると思います。文明が進めば、自然災害を封じ込めることができると考えている人間の在り方に、「そうではない」と批判されているのです。この言葉の後に次のように述べられています。
「文明が進むに従って人間は次第に自然を征服しようとする野心を生じた。そうして、重力に逆らい、風圧水力に抗するようないろいろの造営物を作った。そうしてあっぱれ自然の暴威を封じ込めたつもりになっていると、どうかした拍子に檻を破った猛獣の大群のように、自然があばれ出して高楼を倒壊せしめ堤防を崩壊させて人命を危うくし財産を滅ぼす。その災禍を起こさせたもとの起こりは天然に反抗する人間の細工であると言っても不当ではないはずである、災害の運動エネルギーとなるべき位置エネルギーを蓄積させ、いやが上にも災害を大きくするように努力しているものはたれあろう文明人そのものなのである。」『天災と国防』
今年も自然が各地で猛威を振るいました。近いところでは隣の佐賀県武雄市で、停滞した線状降水帯がもたらした激しい雨のため、市街地が浸水するということがありました。今回水害の被害にあった地区は、元々水害常襲地であり、1990年の豪雨の時も浸水被害が出ていました。その後、武雄では川沿いにいくつもの排水ポンプ場が整備され、水害の被害が軽減されていたそうですが、今回の大雨はその排水能力を上回る雨量だったのです。
ニュースで伝えられたことですが、避難できずに取り残された人の多くが、避難勧告が出ても、「排水場があるから、大丈夫」だと思っていたことが伝えられていました。まさに寺田氏が指摘する通り、「自然の暴威を封じ込めた」つもりになっていたのでしょう。
さらに私は寺田氏の言葉に、昨年の出来事を思い返していました。愛媛県の肱(ひじ)川で、国土交通省の野村ダムの放水量が一気に増加したことなどにより、川が増水し、逃げ遅れた5人が亡くなられました。治水、利水と様々な理由で作られたダムですが、そのダムによって災害を大きくしているという矛盾が起こっているのです。
人間は文明を進化させるにつれ、あたかも自然を意のままにコントロールできるかのように思いあがってきました。その幻想は豪雨や、台風、地震、津波という想定外の災害が起こるたびに、「そうではない」と破られ続けてきたはずです。しかしそれが徹底しないどころか、さらなる野心で自然に反抗し、人間の思うように自然を変えようとするばかりです。
今日、私たちは自然を人間に対立するものであり、自分たちに都合の良い様に変えることができるものと考えてきました。その結果、地球の温暖化や砂漠化、水や大気の汚染などの様々な問題を引き起こしています。これも人間のわがままに対する自然からの警鐘でしょう。人間は自然を支配しようとしますが、自然は人間の支配の対象ではないのです。
仏教では、自然を(じねん)と訓じて「自(おのずか)ら然(しかあ)る」という意味に解します。人間の思い、野心のまじらない「そのまま」の在り方が自然(じねん)だということです。思い通りにならない自然の中にいる私です。あらためて身のほどをわきまえなければならないと感じています。 令和1年10月 深草誓弥
人として 帰る世界を 彼岸という 「いのちのことばⅡ」
蒸し暑く、雨の多かった8月も過ぎ、お彼岸の季節が近づいて来ました。日を追うごとに日暮れが早まり、秋へと向かいつつあります。お彼岸とは、1日の昼と夜の長さが同じになる「春分の日」と「秋分の日」を中心にして前後3日、計7日間行われる行事です。お中日には太陽が真西に沈む事から、西方極楽浄土を観ずる一週間として伝統されてきた仏事であります。また浄土へ往生された方々(先祖)を思う心から、お墓参りの習慣も定着しています。
「暑さ寒さも彼岸まで」と言われるように、季節の名称として日本に伝わっていますが、時期だけを示した名前という訳ではありません。彼岸とは読んで字の如く「彼の岸(かのきし)」向こう岸、という意味があります。向こう岸があるということは、向こう側と何か隔てるものがあってこちらの岸「此岸」があるわけです。彼の岸は仏の世界(浄土)ならば、此の岸は人間の世界(穢土)という関係があります。しかし何故、人として帰る世界が彼岸の浄土なのかを考えてみたいと思います。
今私は動画配信サイトで、日本や世界の歴史や現代の社会情勢をまとめた講義形式の動画を見ています。東西の冷戦や朝鮮半島問題、中東の歴史など、世界の歩みを順を追って見ていくと、いつの時代もどの国も「自国ファースト」なのだということが知らされました。「自国ファースト」とは常に自国中心で、他の国に対しては排他的な関係でしかありません。自国の繁栄と称して国益となる事ならば、他国と戦争をしてでも領土を手に入れようとします。意見の違う国と話し合って解決しようとか、つながりあって生きていこうという「対話」ではなく、「暴力」で決着を付けようとします。そして侵略され暴力を受けた側は怨みを残し、子孫の代まで消えることはありません。親の敵、祖国の怨みという消えない感情が次の戦争を生んでいく。そういう不安定な情勢が、現代の世界の姿ではないでしょうか。
その様な問題を作ってきた「自国ファースト」の歴史は、「自分ファースト」として生きている私自身と重なる事も知らされました。それは、自分さえ良ければいいという日頃のこころそのものです。このこころで生きていると一番身近なコミュニティー、家庭、地域、職場などで摩擦を生じ、つながりを自分から切り、他者を傷つけてしまうこともあります。それで自分の心が安心し、落ち着くかというと決してそうではありません。よくよく考えてみると、相手を傷つけ悲しませてしまった場合、心の底から喜ぶことは出来ないと思うのです。様々な関係を生きている私達は、自分も他人も一緒に安らぎ喜べる様にならないと、私の本当の救いにはならないのです。
阿弥陀経というお経には、浄土の世界を「倶会一処」する世界だと説かれてあります。ともに一つの処で会う世界がお浄土だということです。「会う」とは、顔を合わせるという事だけではありません。あなたも私もここで一緒に生きることが出来るという事です。どの様な人も、どんな生き方をしていようとも、生きていける居場所を与えて下さるのが浄土のはたらきであり、そういう世界を取り戻すことを願われているのが阿弥陀如来という仏様です。だからこそ「私たちの帰る場所は彼岸の浄土ですよ」と呼びかけておられるのです。
また中国の善導大師は、
「帰去来(いざいなん)、他郷には停まるべからず。仏に従いて、本家に帰せよ。」(「法事讃」聖典P355)
現代語に訳すと「さあ帰ろう。迷いの世界には長居すべきではありません。阿弥陀仏の『浄土へ帰ってきなさい』という命令にしたがって、故郷である彼岸の浄土(本家)へ帰ろうではないか。」という意味です。帰る家(本家)があるということは、現在ただ今の安心につながっているのです。さあ帰ろう。 令和1年9月 貢清春
故郷(ふるさと)は 一人ひとりの 人生の出発点である
ニュースでは、今年も夏休み、お盆を故郷で過ごす方の帰省ラッシュの予想を伝えています。私はお盆の時期、忙しいものですから、お盆を故郷で過ごすことはありません。また、故郷に帰省するといっても、私の里は伊万里なので、40分もあれば行くことができるので苦労することもありません。ですから、毎年の風物詩である、この帰省の混雑のニュースを聞くたび、不思議に感じるのです。多くの人が故郷に混雑することが分かっていながら帰るのです。なぜ故郷はそれだけ苦労してでも帰りたくなる場所なのでしょうか。
帰る場所ということで想起されるのは、源信僧都が著作の『往生要集』のなかで、地獄をあらわす言葉として、
「我、今、帰するところ無く、孤独にして同伴無し」 源信『往生要集』(『真宗聖教全書』一 738頁)
という言葉を残しています。「私は今、もはや帰るべき場所もない。たった一人で、友も無く、地獄に堕ちていくのです。」この言葉は、「阿鼻(あび)地獄」(無間地獄)に堕ちていく罪人が泣き叫ぶ言葉とされています。人間は元来、多くのものと共に在り、支え合いながら生きています。しかし、このような当たり前のことを無視し、自らの欲望にのみ生き、共に在ることを見失った者は、一人、孤独の世界に堕ちていかなければなりません。友も無く、永遠の孤独に満ちた世界で、長い地獄の苦しみを背負っていかなければならないということを教えた言葉です。帰る場所を失った時、私たちは地獄を体験することになるということです。
思えば故郷は、私を待っていてくれる人がいるところでないでしょうか。たとえその人が命を終えていても、故郷で私を待っていてくれるような感覚があります。私の里の父も生前「おかえり」といって、私を迎えてくれました。ですから私たちが故郷に求めているのは、自分を待っていてくれて、迎え入れてくれる世界だと思うのです。そして、その私たちが安心できる世界を求めていることのあらわれが、お盆に苦労してでも帰省し、お内仏、お墓にお参りするという形になっているようにも感じます。「ただいま」といって帰っていける場所をもつことで、安心して出かけていける、外で暮らしていけるのでないでしょうか。
阿弥陀如来は、私たち自らが持つ煩悩のために、帰るべき故郷を見失い、孤独で友を失っている在り方をよく知られ、浄土を荘厳し、一人ひとりを「欲生我国」と、「すぐ来なさい」と呼びかけておられます。浄土を「存在の故郷」と受け取られた先達がおられましたが、今回の掲示板にあるように、浄土こそ「故郷」であり、そこで阿弥陀如来が親として待っていて下さるのです。「人生の出発点」とは、私のことを本当によく知っている方がおられ、私たちが本当に求めている世界があきらかにされている「故郷」なのでしょう。その世界にふれてこそ、どこにいっても安んじて生活ができるのです。
私はお世話になった先生から、「浄土真宗の教えといっても、事実共に生きているのだから、共に生きていきなさいという、単純明快な教えです。」と教えてもらいました。共に生きている事実に背を向けている私に、故郷が「共に生きよ」と呼びかけているのです。 (令和1年8月 深草誓弥)
泥に生き 泥に染まらぬ 蓮の花 「いのちのことばⅡ」
この梅雨の時期、福浄寺の境内には蓮の華が咲きます。とある御門徒の方が、レンコンと泥を入れた数個の火鉢を御寄進して下さり、ここ数年きれいな蓮の華が私たちの目を和ませてくれます。昔はこの川棚の地も蓮畑が数カ所あったのですが、スーパーが建ち、家が建ち、管理する人がいないなど、今ではほとんど残っていないので、蓮の華を見る機会も減ってきています。また、蓮畑はどろどろした沼地なので夏には蚊が大量に発生します。近くの住人にとっては嫌な存在でもあります。
「高原の陸地には、蓮華を生ぜず。卑湿の淤泥に、いまし蓮華を生ず。」
これは『維摩経』(ゆいまきょう)というお経の言葉を、曇鸞大師が『浄土論註』に引用されています。このお経にある高原の陸地とは、からっとしてさわやかで住みやすい、私たちが理想とする快適な土地です。しかしその様な場所には蓮の華は育ちません。蓮華はじめじめとした湿気の多い泥田を大地にして成長します。この事から蓮華は「淤泥華(おでいげ)」と云う別名もあります。
また、親鸞聖人の『入出二門偈頌文』においては、
「これは凡夫、煩悩の泥の中にありて、仏の正覚の華を生ずるに喩うるなり。」
とあり、泥のことを「煩悩の泥」と喩え、華を「正覚(さとり)の華」と喩えられます。私たち凡夫の日常は「貪り、怒り、腹立ち」等の煩悩のこころを起こし、振り回されながら生きています。毎日様々な煩悩がわき出てきて、煩悩を起こさなかった日は、今まで一日たりともなかったのではないでしょうか。聖人も「命終わるその時まで煩悩は消えることはありません」と云われます。その様な世界に身を置きながらも、凡夫が汚れの無い仏の正覚、さとりの華を生ずることが出来ると説かれます。しかしこの煩悩の身のまま、正覚(さとり)をいただけるというのは、何か矛盾したことのように感じます。
『仏説観無量寿経』には「若念仏者 当知此人 是人中分陀利華」と説かれます。もし念仏する者があれば、その人はこの世の中にあって、美しく咲く白蓮華(分陀利華)であるという意味です。また、善導大師はこの念仏者のことを「妙好人、上上人、希有人、最勝人」とも讃歎されています。この煩悩にまみれた世にあってお念仏をいただく人は、すばらしい人、まれな人、最もすぐれた人として、この世に咲く白蓮華の様だと讃えておられます。
様々な苦悩を身にうけ、悩み多きこの煩悩の世界にありながらも、お念仏はこの煩悩の泥に汚れることはありません。なぜならこのお念仏は、仏のお心そのものだからであります。念仏は、私が称えるものではなく、「わが名を称えよ」と阿弥陀仏が私に呼びかけている願いの声なのです。その呼びかけの声に応えて私たちは「南無阿弥陀仏」と申しているのです。合掌して南無阿弥陀仏とお念仏申すなかに、無量の願いがあり、先達の歴史があり、響きがあります。だからこそ念仏者を、この煩悩の泥の中に咲く白蓮華(分陀利華)であるとおさえられるのであります。たとえ煩悩を起こしても、煩悩を起こす我が身の為のお念仏だったと、阿弥陀の願いをいただく事が出来るのです。
今月の言葉の様に、蓮の花は泥に根を張ってはいますが、咲いた華は泥色ではありません。いつも世間という泥にまみれて生活している私たちですが、境内に可憐に咲く蓮の華が「念仏称えているか?、呼び声を聞いているか?」と問いかけているようにも感じます。 (令和1年7月 貢 清春)
日曜学校バス遠足の案内
前略 皆様におかれましてはご健勝にお過ごしの事と拝察致します。また常日頃、日曜学校の会の運営にご協力、ご理解頂きお礼を申し上げます。
この度、日曜学校でバス遠足を計画しました。今年は大村萱瀬町の西教寺様を訪ねます。みんなでたのしく勉強になる一日を過ごしたいと思います。
◎日 時 令和1年 7月15日(月)海の日
8時20分 福浄寺集合
(いつもの時間より30分早くお迎えに来ます)
◎行き先 ・大村 西教寺 (0957)55-3653
・諫早 こどもの城 (0959)-33-2303
◎参加費 1人、500円
◎持参品 お勤め本、お数珠、お賽銭100円
水筒、お弁当、ぼうし、おやつ
*車酔いをする人は、酔い止めの薬を飲んで来て下さい。
*お小遣いは自由とします。
*保護者の皆様のご参加も大歓迎です。ご参加される保護者様の氏名、生年月日を申込みに記入して下さい。
◎申込み 氏名、生年月日、連絡先を記入し、参加費500円を添えて申し込み下さい。
7月7日(日)締め切り、受付は福浄寺です。
日 程 (変更する場合があります) *30分早くお迎えに来ます
8:20 福浄寺集合、出発
9:00 大村、西教寺着
お勤め・仏様のお話
お寺で遊ぼう
12:00 昼食、お弁当
13:30 諫早、こどもの城
16:00 福浄寺着予定 (帰りは自宅まで送ります)
毎日の生活のなかで、「行きづまり」を感じることが度々あります。努力したけれども、うまくいかなかったり、突然思いもしない出来事がおこったりして、身動きが取れないように感じます。どうあがいても、変えることのできないような閉塞感こそが、「行きづまり」でしょう。そしてその「行きづまり」をもたらしたものは外にあると思って、その状況がどうにか変わらないものかと思います。しかし、今月の掲示板の言葉は、その「行きづまり」をもたらすのは、私が思うような他なるものではなく、自分が作った行為であると教えています。
少し前の出来事ですが、軽トラックに乗って、町内のごみ処理場にごみを捨てに行きました。車の調子が悪いことを知っていたので、エンジンを切らないようにして、ごみを捨て、帰路に就いたとき、ついにエンジンが止まって、全く動かなくなってしまいました。私は「くそ!」といって、車の外に出て、迎えをたのんで途方に暮れていました。迎えを待つ間、何人かの知り合いの方から声をかけられました。「車の動かんごてなったとですよ」、「なんで、こがんなるとでしょでしょうね」と、恥ずかしさも抱えながら、憤慨していることを伝えました。まさに行きづまり、困っていました。
この出来事を、今回の掲示板の言葉を通して振り返ってみますと、まず、私は「車の調子が悪い」ことは知っていたわけです。にもかかわらず、「大丈夫だろう」と判断して、車を運転し始めた私。事の発端はここにあるのです。しかし、大丈夫ではなかったから、車は止まったのでしょう。止まるべくして車は止まったのです。それにもかかわらず、私は「大丈夫だと思っていたのに何で止まるのだ」と憤慨したわけです。これも、「大丈夫だろう」と思っていた私の勝手な妄想が、車が止まるという現実によって破れた、ということでしょう。たとえよく整備されて、故障など起こるはずがないと思っていても、止まる時は止まるのでしょう。故障はない方がいいですが、絶対壊れないということは道理に背いています。
この車が故障した出来事は取るに足らない出来事です。今回の掲示板の言葉について考えている時、すぐに思い返されたのですが、この出来事に限らず、私が「行きづまり」を感じ、「困った」と思っているとき、やはり「これが悪い、あの人が悪い、世界が悪い」と外を恨み、外がどうにか自分の思い通りにいかないものか、とにらんでいるのです。しかし、そもそも世界を自分の思い通りに変えてやろうとする魂胆そのものが、妄想だといわざるを得ません。逆に思い通りにならない世界があるからこそ、「わが思い」、わがままがあらわになっていくのでしょう。
「行きづまり」を感じ、「困った」と外に怒りの矛先を向けていたのですが、その前に、「何事もなく事が運ぶであろうと思いながら、行動を起こしている自分が見えますか?」ということを今回の掲示板の言葉は問いかけているのではないでしょうか。 (令和1年6月 深草誓弥)
尊敬できる人間を持ってる人間が光るんです。尊敬される人間は別に光らない。倉本聰
「あなたにとって、尊敬する人は誰ですか?」と質問されたら、誰の名前を挙げますか。
"尊敬する人"をネットで検索すると、【尊敬する人を面接で聞かれたときの答え方。例文有り】や【就活面接で「尊敬する人」の話から効果的に自己PRする方法は?】等と、時代を反映しているのか、就職面接においての例文等の紹介がトップの方に検索されました。"尊敬する人"は就活には必要不可欠であり、用意しておかなければならない自分を表現するアイテムなのでしょう。
しかしなぜ面接で「あなたにとって尊敬する人は?」を質問されるのでしょうか。就職面接ではその人がどの様な人と出会ってきて、どの様な人生を歩んできたのか。どういう言葉に影響を受けて成長して来たのかを知り、社員となった後で向上しながら育つことが出来るかどうかが判断されます。試験や履歴書だけでは見えない人間性を知りたいのです。人が成長することに於いてとても大切な事は「尊敬する人との出会い」だということがこの事からも知らされます。
今月の言葉は、倉本聰さん独自の言葉かも知れませんが、おそらく蓮如上人御一代記聞書の言葉が基礎になっていると思われます。
一 法敬、申され候う。「とうとむ人より、とうとがる人ぞとうとかりける」と。前々住上人、仰せられ候う、「面白きことをいうよ。とうとむ体(てい)、殊勝ぶりする人は、とうとくもなし。ただ、有り難やと、とうとがる人こそ、とうとけれ。面白きことを云うよ。もっとものことを申され候う」との仰せ事に候うと云々。(『蓮如上人御一代記聞書』235)
現代の言葉に翻訳すると、「蓮如上人のお弟子である法敬坊が『尊いお方であると尊ばれるより、あの人は尊いお方だと尊び敬う方が、本当に尊いのです』と申された時、蓮如上人が 『おもしろい事を言うたものだ。いかにも道理のあることを法敬坊は申された』と仰せになられました。」
自分が偉くなってみんなから「あなたすごいね」と尊ばれるよりも、他者の優れている所や美しい点を発見し尊び認めることが出来る事の方が、人として尊いのだということです。一見誰にでも出来る事の様ですが、これが本当に難しいことです。他人の素晴らしい所や才能を見つける事より、あら探しをしたり小さな欠点を見つける方が上手です。自分が褒められるのは嬉しいことですが、他人が褒められるのはあまりおもしろくはありません。失敗や不幸な姿を見て「ざまあみろ」と思う心も持ち合わせています。「尊敬できる人間を持ってる人間」とは、ほど遠い存在です。
親鸞聖人は 「凡夫というは、無明煩悩われらが身にみちみちて、欲もおおく、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおおくひまなくして、臨終の一念にいたるまでとどまらず、きえず、たえずと、水火二河のたとえにあらわれたり」 【一念多念文意】
といわれ、命終わるまで腹立ち妬みの心はなくならない、それが凡夫の姿であると教えて下さいます。 その様な自分であることが知らされるからこそいよいよ仏法を聴聞し、お念仏を申す生活が必要なのです。宗祖親鸞聖人はお念仏申しながら、我が身の浅ましさを教えに知らされつつも、それでも救おうとする如来のはたらきに帰依された人です。その様な聖人の素晴らしい生き方に感動した人達が、次々と念仏者になっていかれたのです。念仏者が次世代の念仏者を無数に生み出し、今日まで相続されてきたのだと思います。それは尊敬の相続とも言えるのではないでしょうか。その相続の歴史の中に私たちがいることに、大きな役割と責任があるように感じます。 (令和元年5月 貢 清春)
願わざれども花は咲き 願えども花は散る 佐々木 蓮麿(ささき はすまろ)
4月になり、入学式、入園式の季節を迎えました。山桜が咲き、学校や公園の近くでも里桜が咲いていますし、テレビではお花見をする人たちの姿を伝えています。古来より日本人は桜の花に心を寄せ、今や天気予報と共に桜の開花予想まで報道されています。
私も大学生の頃にサークルの友人とお花見を毎年していました。しかし、そのお花見の時、桜はいつもすでに散っていました。なぜかというと、新入生歓迎会を兼ねているので、いつも四月下旬くらいになっていたためです。ですから実際はお花見とは名ばかりの、野外の飲み会になっていました。その頃私は、「今がお花見なんだから、もうちょっと遅く咲いてくれればいいのに」と思っていました。今振り返ってみますと、とても傲慢なことです。
ところで、なぜ桜は春に咲くのでしょうか。気になったので調べてみました。桜の花は咲いてその役目を果たして散ると、すぐに来年咲かすための花芽(はなめ)をつけるそうです。葉桜になった時に実は来年用の花の実を持っているのだそうですが、一旦暖かい春から夏は仮眠してしまうようです。そして季節が巡って冬になり寒くなってくると、眠りから覚め花芽が育ち始めます。そして寒さが和らぐ2月後半から3月にどんどん育って、暖かさが増す3月後半になると花が咲き出すのだそうです。
今月の掲示板の言葉は、私たちの勝手な願いとはうらはらに咲き散る花のすがたを通して、私たちの個人的な思いを中心にすることなく、この世の道理に目覚めてほしいというこころが込められているように思います。まず「願わざれども花は咲き」とありますが、私は桜の花が咲く直前になって、桜の木の様子を気に留めていることに気付かされます。それまでは見えていても、見てはいないのでしょう。しかし私が気にしていようといまいと、桜の木は生きているのです。冬の寒空の下でこそ目覚め、つぼみを育てています。そして暖かくなるのをじっと待っているのでしょう。
その生命の営みを、「まだ咲くには早い」といっていく愚かさを指摘しているのが、前半の言葉でしょうか。後半の「願えども花は散る」という言葉も、こちらの都合で「まだ散らないで」といくら思っていても、桜は生きるため、すでに来年の準備を始めています。花は決して私たちの思いでは動かせない、大きな自然のなかの道理にそって咲き散っているのだということを知りなさい、という言葉ではないでしょうか。
そして、この花に譬えられた咲き散るいのちの道理は、人間にも置き換えられます。私が頭でどのように考えていても、いなくても、人の体は生きよう生きようとしています。爪も伸びます。髪も抜け替わります。そして、「まだ死にたくない」と願っても、条件が整えば死をむかえます。花で示された道理を見失っているかぎり、「こんなはずでなかった」という言葉しか出てこないのではないでしょうか。私たちの思い通りになることなどほとんどありません。私たちにできるのは、自分に今あたえられたいのちに目を向けることです。 (平成31年4月 深草誓弥)
一度限りの一方通行 誰も代われぬこの人生は すでに見守られ 照らされ 輝いている (仏光寺)
数年前、元プロ野球選手の清原和博氏が覚せい剤所持の疑いで逮捕された事件がありました。その事件後、高校時代からの親友であり同じくプロ野球選手だった桑田真澄氏は、逮捕される前から清原氏を心配し、小姑のように忠告を続けていた時期があったそうです。逮捕後の取材で桑田氏は次のようにコメントされました。
「今言えるのは、野球のピンチに代打とリリーフはいるけど、自分の人生に代打とリリーフはいない。現役時代に数々のホームランを打ってきた。自分の人生でもきれいな放物線を、逆転満塁ホームランを打ってほしい。」
これは『仏説無量寿経』の、「身自当之 無有代者」(身、自らこれを当《う》くるに、代わる者あることなし)というお経のお心を表現している様に感じます。自分の人生の代わりになってくれる人はいない、誰も代わってくれないこの身なのだから、その時その時の「今」を、そしてこれからの人生を大切に生きて欲しいとの思いでコメントされたのだと思います。同じプロ野球選手として一緒に活躍し、古くからの親友として再起を願う桑田氏のこの言葉は、罪を犯してしまった事への悲しさと、友を思う温かさが感じられます。現在、執行猶予中の清原氏は、依存症の治療をしながら薬物依存症に関する啓発イベントにゲストとして参加するなど、薬物の危険性を伝える活動をしておられるそうです。
大きな失敗をした時は出来る事なら時間を巻き戻し、やり直したいと思ってしまいます。しかし人生をやり直すことは出来ませんし、どれだけ罪を償っても過去の過ちが消える訳ではありません。「これからが これまでを決める」という藤代聰麿師の言葉にもありますが、今から「これから」をどの様に生きていくのかが、「これまで」出会ってきた様々な出来事に意味が与えられていくのだと教えて下さっています。
今月の言葉はその様な私たちの人生が、仏から「見守られ 照らされ 輝いている」と説かれます。『正信偈』には「大悲無倦常照我(だいひむけんじょうしょうが)」というお言葉があります。阿弥陀如来の大悲は私を見捨てずに、倦(あ)きること無く、常に照らして下さると述べられています。大悲とは、迷い苦しみの中に生きる衆生を悲しみ、目覚めさせ救おうとする如来の活動の事をいいます。それは病気に苦しむ子供に寄り添い、一緒に苦しみを共にしている母親の姿と重なる所があります。子供(衆生)が救われるためにはどんなつらい事も厭わず、それが徒労に終わろうとも悔いることは無いという願いが如来のお心です。その大悲の光は「無倦」に、怠ること無く、疲れること無く、退屈せずにはたらきかけておられるというのです。
その光に出会えばこそ人生が輝き出すというのです。「輝く」ということは一つ残らず大切な宝物になっていくということだと思います。人生に無駄なものが一つも無かった、と言えるということです。生きていれば、あれはしなければよかった、やらなければよかったという後悔が沢山出てくるわけです。そして最後には「なんか人生つまらんかったー」と、空しく過ぎて終わってしまうのが本当の悲劇ではないでしょうか。その様な生き方をしてしまう私たちに、輝きをもった人生を生きていける道がありますよ、それは本願信じ念仏申すことですよと、大悲のお心で呼びかけおられるお方が阿弥陀如来という仏様なのです。
桑田氏がコメントされた「逆転満塁ホームラン」を私は打つ事は出来ませんが、一度限りの人生ですから結果三振したとしても、バッターボックスに立てた事を喜べる私になれたらいいなあと思います。 貢 清春 平成31年3月
当てが外れた不満の中に見えてきた 当てにしていた 当てにならない私 (仏光寺)
私たち人間は、今、ここに、それぞれ誕生して、生きています。誕生、生まれるということは、誰の場合でも必ず、いのちが与えられることです。具体的には、この私の身と、この身が生きていく世界が与えられることです。
しかし、いつのころからでしょうか。その与えられたいのちを、我がいのちとして握りしめて生きていきます。私が私のいのちのあるじであるかのようにふるまい、さらには私が生きていく世界も自分の世界と勘違いをして生きています。仏教ではそのような私たちの「我」の意識を、常(じょう)【=いつでも】、一(いつ)【=一貫して】、主(しゅ)【=あるじ】、宰(さい)【=支配しようとする】する意識であると教えています。
掲示板の言葉に示されていますが、私もまわりの人や環境に「こうなってほしい」とか「こうでないといけない」というような「当て」をもって生活しています。しかし、多くの場合、その「当て」、期待は外れたり、裏切られます。すると次に出てくるのは「なんで」という不満です。「なんで私の思うようにならないのか」と外に不満の原因があるように思いをなしてしまいます。
仏教は「その当てにしているあなたが当てにならないのでないか」と教えています。先ほど挙げましたが、我の意識こそが問題なのです。たとえば、今向き合っているパソコンも「自分が買ったパソコン」、「自分の所有物のパソコン」だと思っています。自分が働いて手に入れたものは自分のものだと思っています。
では、「その自分は誰のものか?」と問われたら、どうこたえられるでしょうか。「もちろん、自分は自分のものだ」とこたえるでしょう。ではさらに問います。「では、何時、どのようにして、あなたはその自分を手に入れたのですか?」ここまで問うとこたえに困ってしまうのではないでしょうか。無疑問的に「自分」を握りしめ、目の前に広がっている世界すらも自分の所有物のように振舞っていますが、まさに「当てにならない私」だとしかいいようがありません。
思うように事が進んでいるときは、問題になりませんが、思いがけないことが起こると「当てが外れた」ということになります。まず大切な事は、「当てにしていた」自分がいることを知ることではないでしょうか。そして、問題が起きたり、困ったことがあると途端に「どうにかならないものか」と外の世界を変えようと反応するのですが、そこにはなんでも自分の気に入るように世界を変えられると勘違いしている自分がいることにも気付かされます。世界を自分の気に入るように変えるということはできないでしょう。そしてもっと言えば自分も自分の気に入るように変えることはできません。まさに掲示板の言葉にあるように「当てにならない私」です。
思うようにいかないことにであっても、「当てが外れた」と絶望するのでなく、「当てにならない私」を当てにしていた自分に目覚める機縁ではないか、と教える言葉だと思います。 深草誓弥 平成31年2月
眼前の小さな しあわせは 見えても 背後の大きな おかげさまが 見えない
私の自宅には渋柿の木があります。全く実が付かない年もありますが、去年は沢山に実が付いたので自宅では食べきれず、有縁の人にお配りしました。柿取りの作業は大変なのですが、全ての柿の実を取ってしまわずに頂上に二、三個は残すようにしています。これは小学校の授業の時に聞いた言葉で「木守り(きもり)」と言って、昔から伝わる習わしだと教えてもらいました。来年も沢山実って欲しいという祈りと、人間が全て取って食べてしまうのではなく、鳥たちの食べる分も残しておこうという心使いから始まった習慣だそうです。おかげさまの恵みで生きているのは人間だけではない、鳥や獣たちも同じなのだという優しさも感じる習慣なので、私もその習慣を大切にしています。
しかしその様な「おかげさま」の生活が、私たちの日暮らしの中で消えかけているのではないかと感じます。私がこうして生きているということは実に多くのことに支えられていますが、日頃は特に意識することもありません。思い通りになったら自分の手柄で、都合が悪いことが起こったら他人のせいにしてしまう私の根性では、「おかげさま」の言葉が出てくることはありません。私自身がおかげさまの世界を忘れて生活しているのだと反省させられます。
この「おかげさま」の言葉は漢字で書くと「御陰様」となります。この言葉の意味は、自分の力でそうなったのでは無く、陰なる見えないはたらきによってその様になったということです。そのはたらきに「御」と「様」まで付けて最大限に敬っておられる言葉です。そして陰なる存在を神仏のはたらきとしていただき、無事に生かされている事への感謝の言葉として、先祖の方々は大切に伝えて下さいました。その先祖の方々の精神を考えると、絶やしてはならない言葉の一つだと思います。
そのおかげさまの世界を蓮如上人は「冥加」と表現されています。日常ではほとんど耳にしない言葉ですが、「冥」の字は、くらい・暗くて目に見えないという意味で、「加」は加護、守り助けるという意味があります。人間にははっきりと見えない、分からないけれども、神仏の加護をいただいている事を「冥加」といいます。
また、蓮如上人御一代記聞書には「朝夕、如来聖人の御用にて候あいだ、冥加の方をふかくぞんずべき」という言葉でも教えられます。朝夕(一日中)阿弥陀如来や親鸞聖人のおかげによって、衣食住の全てが与えられているのだから、冥加の世界を忘れてはなりませんという意味です。この世界を忘れてしまったら人間はどこまでも傲慢になり、他の全てのものを際限なく利用しようと考えます。そして現代の自然環境のバランスが壊れるまで資源を搾取し尽くしている結果が、異常気象の姿となって私たちに問題を突きつけているのではないでしょうか。おかげさまを忘れ、感謝の心を忘れている私達への警告なのかも知れません。
新しい一年が始まり、既に半月以上が過ぎました。今年は良い一年でありますようにと願い、正月をお迎えなられたのではないかと思います。しかし目には見えない背後のおかげさまの存在が無かったならば、一年の善し悪しを云々する前に、一日さえも生活は出来ないでしょう。日常の会話にまでなって伝えられた「おかげさま」の言葉を、まずは口に出して生活していきたいと思います。 貢清春 平成31年1月
考えてみると 私一人で最初から作れる物など 身の回りに一つもないのだ
『折々のことば』
仏教の学問の中で「大乗非仏説」ということが、しばしば取り上げられます。それはおおよそこういう説です。「私たちが親しんでいる御経である『大経』、『観経』、『小経』などの大乗経典は、お釈迦様が亡くなってから数百年経ってから作られたものである。だからお釈迦様が直接説かれたとは言えない。だから仏説ということは言えないはずだ」ということです。
しかし、法然上人や親鸞聖人は決してそのように受け止めておられなかったと思います。これらの経典はすべて「仏説」、仏が説かれた教えだと受け止めておられるのです。親鸞聖人は「それ、真実の教を顕さば、すなわち『大無量寿経』これなり」(聖典152頁)とおっしゃられています。『大経』こそ真実のおしえであるという頷きをもっておられるのです。
たしかに私たちが今日仏説といっているのは、ほとんどお釈迦様が直接話した内容ではないと思います。だから、今現にあるお経は信用できないのではないかとなると、私たちが理解していることと、親鸞聖人の頷きとは程遠いことになってしまいます。
しかし、まず大事に見落としてはならないことがあります。『仏説無量寿経』の説法をお釈迦様以外の誰かが創作したとしても、それを作ったのは間違いなく仏教に帰依した人であるはずです。とするならば、その人のところまでお釈迦様亡き後、何百年か経っても仏教が伝わったということだと思います。何も知らない人が『観経』の王舎城の悲劇を作ったりすることはできないでしょう。大事なことは、お釈迦様が亡くなっても、その創作した人のところにまで届いた仏教観、仏陀観があった。その人が、自分が出会った仏教観、仏陀観にもとづいて表現したのが大乗経典だと思います。
もう一つ大事なことは、そうやって生み出されたお経にふれた人が「ああ本当だ」と頷いたということです。そこに表現された言葉から、時代を超えて共に頷くということが生まれてきました。一つのお経が仏説として受け取られ続けてきた背景には、その教えに頷いてきた無量無数の人たちが消えないで現れ続けたからです。
「考えてみると 私一人で最初から作れる物など 身の回りに一つもないのだ」という言葉を掲示板で見て、ここまで確かめてきましたような「お経」の成り立ち、背景のことがすぐに思われたのです。単純にお経に出てくる単語一つとっても、私一人が作り出せるものでは到底ないわけです。もっといえばお釈迦様一人でもお経というものは作り出されなかったと私は思っています。お釈迦様が亡くなった後も、様々な人が生涯を尽くして確かめられたこととして、新たな言葉として紡ぎだされ、そして次にその言葉にふれた人は忘れられない言葉として受け止めてきたのでしょう。
今回の掲示板の言葉は、物事の背景をきちんと見つめていくことが大切であることを伝えるものでした。一例としてお経をあげましたが、「私一人で最初から作れる物など 身の回りに一つもないのだ」の言葉のとおり、身の回りにあるすべてのものに無量無数の背景があるのです。そのことに思いを致す時、古くから大切にされた「有難い」という言葉もいのちをもってきます。 深草誓弥 平成30年12月
自分以外のものをたよるほどはかないものはない。
しかし、その自分ほどあてにならないものはない。 夏目漱石
普通、「他人は当てにならない、誰も信じる事が出来ない」と感じると、「最後に頼れるのは自分だけだ」と自分をよりどころにするものですが、漱石は「しかし、その自分ほどあてにならないものはない」と言われます。「じゃあ、何を頼りにして生きていけば良いの?、何を信じていけばいいの?」と問いたくなる今月の言葉です。
夏目漱石の代表する小説に「こころ」があります。物語は青年が鎌倉の海岸で寂しげな男性と出会い、その男性を「先生」と呼ぶようになった事から二人の関係が始まります。その先生と呼ばれる人は恵まれた環境で育ち、学生の頃に両親と別れ親切な叔父に育てられるのですが、莫大な遺産を奪い取ろうとする叔父に裏切られ、財産を奪われてしまいます。金目当ての優しさだと知って、どんな善人も金がからむと悪人になってしまう人間の悲しい姿を目の当たりにしていきます。一番頼りにしていた叔父に裏切られたことによって、どの様な人も信用できないものだということを、心に深く刻み込んでしまいます。その後勉学のために上京し、下宿先で知り合ったお嬢さんに恋心を抱いた先生は、同じく恋心を寄せる同居人のKを裏切る様にお嬢さんとの結婚を申込み、それを知ったKは自死してしまいます。思い通りにお嬢さんと結婚出来た先生ですが、友人を裏切り、死へと追いやってしまった自責の念に耐えられず、遺書を残して死んでいきます。
自分以外の者に悩まされ、苦悩するがゆえに他の者(親兄弟、友人、恋人)には頼ることが出来ず、信じる事ができない。その外に対して向けられていた眼が、今度は自分の内面に向けられていきます。そこで知られた自分は素晴らしい自分かと言えばそうではありません。他人を裁き、裏切り、殺していくような心を持ち合わせているのです。一番あてにならない存在は自分自身なのだと気が付いていくのです。
人間の持つ深いエゴイズム(利己主義)と、命終わるときまで無くならない自尊心を徹底して見つめられた「こころ」という作品は、私たちの我執を深くえぐり出し、人間の闇の部分をあらわにする物語です。
「私は私自身さえ信用していないのです。つまり自分で自分が信用出来ないから、人も信用出来ないようになっているのです。自分を呪うより外に仕方ないのです。」(『こころ』十四節目)
この言葉を見ていると、生きていることに何の意味も無い、生きていることが暗く悲しい事のように感じます。しかし漱石は晩年に禅の教えに影響され、そんな自分でありながらも、私を生かしめるはたらきに目覚めていきました。その言葉が「則天去私(そくてんきょし)」です。天に則り、私を去る。自他共に頼りにならず信じる事の出来ないこの世を生きていても、天は私の存在をあるがままに受け入れ、無条件に誰でもが生かされているではないか、という世界を発見した喜びの言葉です。お念仏の世界で言えば「如来大悲の恩徳」であろうと思います。当てにならない自分自身を見つめつつも、天から許されて生かされている我が身がある。その世界に眼が開かれるときにこそ、私たちが誰とでも一緒に生きていける居場所が開かれていくのだと思います。
漱石と現代とは100年ほど時代が違います。しかし私たちと同じ様に人生の様々な苦悩を抱え、人間という存在を深く明らかにした人です。そして私たちが生まれる前からこの悩みに生きて、後の人も読める文章にしてくれたということは、現代を生きる私たちや、これから生まれてくる人たちの生きる力にもなり、励ましにもなっていきます。
今月の言葉は「じゃあ、これを頼りにしましょう」という、答えが用意された問いかけでは無く、「そうだ、悲しいけどその通りだ」と頷く他に無い言葉の様に感じました。 貢 清春 平成30年11月
学ぶ暇がないという人は
暇があっても学ばない人である
ある学習会の場で、御門徒に「若院さんは、いつも法話をしたりせんばいかんけん、勉強大変かですね」と声をかけられました。その時は、「そうですね」と軽く受け止めていた言葉が、ちょうど今月お寺に掲げられた掲示板の言葉とあいまって、次のような問いとなって、私を揺さぶっています。
忙しい、「時間がない」と言い訳しているが、暇がないから、学ぶことが出来ないというのは口実で、学ぼうとする意欲を持ち合わせていないのでないか。自分の全体を投げ出すような学びになっているだろうか。「なぜ仏教に学ぶのか」ということを、見失っていないだろうか。
これは仏教の学びだけに限らず、何を学ぶについても同じことがいえるのだと思います。どれだけ素晴らしい先生に恵まれたり、学ぶ環境がととのっていたとしても、そこに臨む私自身が学びたいという「こころざし」を持ち合わせていなければ、先生の前を素通りするしかないでしょうし、どれだけ時間を学びに割いても、無駄ごとに終わってしまいます。
私の日ごろの在り方を顧みますと、仏教を学ぶといっても、自分にとって有用であるか、無用であるか。わかりやすいか、わかりにくいか。いつでも自己中心的な思いを中心にした学び方になっています。もはやこれでは、学ぶというよりも、ただ品定めをするように選別し、使っているだけです。
『歎異抄』の第二条には、私たちの一番深いところにある欲求を、「御こころざし」として親鸞聖人が言い当てておられます。
おのおの十余か国のさかいをこえて、身命をかえりみずして、たずねきたらしめたもう御こころざし、ひとえに往生極楽のみちをといきかんがためなり。(『真宗聖典』626頁)
親鸞聖人はどんな人であっても、心の奥深くに「往生極楽のみち」を問い聞こうとする「御こころざし」があることを信頼して語りかけておられます。大谷専修学院の狐野秀存先生は、この「往生極楽のみち」を次のような言葉で語られています。
「往生極楽のみち」というのは、「念仏往生の道」ということです。「えらばず、きらわず、みすてず」と私どもを丸ごと受け容れる仏の念(おも)いを深く信じて事実の自分を生き始める、そのような「念仏申して立ち上がる」という、そういう本当の人生をいきたいという、誰もみなのこころの内深くにある願いを親鸞聖人は、「御こころざし」と言い当てておられるわけです。(『願生』第171号 入学式学院長告辞)
どんな人も心の奥深くに仏法を求める意欲のあることを親鸞聖人は「御こころざし」と尊敬を込めて呼びかけられました。それは「あなたの中にも仏法に学ばんとする意欲があるのですよ」という呼びかけです。 深草誓弥 平成30年10月
いづくへか 帰る日近きここちして この世のものの なつかしきころ
(与謝野晶子)
与謝野晶子は、明治から昭和にかけて活躍された女流作家で、沢山の詩や歌を残されました。代表作の「みだれ髪」は有名で、出征する弟への想いを綴った「君、死にたもうことなかれ」も有名な作品です。また詩を書きつつも男女平等の必要性を訴え、女性解放運動にも精力的に参加されたお方でもあります。今月の言葉の詩は、晩年の歌を集めた『白桜集』の中の一首です。
この詩を現代語に翻訳すると、「何処に往くか分からないけど、帰る日「死」を迎える時期近づいてきたようだ。その事を思うと、今この世でしてきた様々なことが懐かしく思われる。」という意味になるでしょうか。この詩は与謝野晶子が昭和17年、63才で亡くなる直前の作品ということもあって、死と向き合った素直な感情なのかもしれません。
人生の終わり「死」が近づくと、今までしてきた過去の事が思い出されて、懐かしい、手放したくない、離れたくない、その様な感情が自然とわき出てくるものでありましょう。普段は何ともなく通り過ぎていた当たり前のことが愛おしく、とても大切なものだったと感じさせられるのも、死という世界を身に頂戴してからの眼差しであろうかと思います。
「死は人生の試金石」という言葉を以前聞いたことがあります。死を目の前にして、私はこの人生で一体何を残したのであろうか、何をしてきたのだろうか、何が本当の依り所となるのだろうか、「死」を試金石にした時に、自分の人生まるごとの「生」が見つめられていくのであります。
しかし作者の中で、「いづくへか、帰る日近き」(何処に往くか分からないけど、帰る日が近い)とあるように、往き先が分からない、いのちの故郷が何処なのかが、この詩を見る限りでははっきりしません。
親鸞聖人は「名残惜しくおもえども、娑婆の縁つきて、ちからなくして終わるときに、彼の土へはまいるべきなり」と『歎異抄』の中でおっしゃいます。いのちの帰るべき世界を「彼の土」と示し、彼の土とは阿弥陀の国土、お浄土の世界を表現しています。
お浄土の世界を金子大栄先生は「それはまだ吾々の見ぬ真実の国であり、同時にまた懐かしき魂の郷里である『彼岸の世界』」と示して下さいました。見たことはないけれども必ず人間が帰着すべき懐かしい故郷として阿弥陀の浄土を説かれます。その世界に親鸞聖人は、「娑婆の縁尽き」れば必ず「かの土へはまいるべき」であると、生まれていくのであると教えて下さいます。
この世に生まれたのも娑婆の縁ですし、この世を去って往くのも娑婆の縁であります。この世の縁尽きて命終わるその時に、必ずお浄土に生まれ仏になる身を、今、生きているのだという、大安心の道をいただいた言葉です。この道のことを「往生道」と言い、ご本願のはたらきによっていただく道であります。
彼岸の中日には太陽が真西に沈みます。お浄土を願い想う生活を、自然現象の中で「西方を拝め」と位置づけて下さいました。この身このままで、阿弥陀の本願のはたらきによって浄土へ生まれる我がいのちであったことを、お彼岸の一週間を通して聴聞していきたいものです。 貢清春 平成30年9月
平和のために 何をしたらよいか
君自身が 平和の人と なり給へ (毎田周一)
毎田周一さんは1906年に生まれ、1967年に亡くなられた、昭和の仏教思想家です。四高在学中から暁烏敏に師事され、京都帝大で西田幾多郎に学ばれています。浄土真宗とも深い関係をもたれていたことがうかがえます。
8月に私たちは、広島、長崎への原爆投下の日である6日、9日、そして終戦の日8月15日をむかえます。平和を願う式典や行事が毎年各地で行われています。しかし、最近の日本は、自衛隊を軍隊として憲法9条に付け加える案が出て、いつでもどこでも戦争ができる国にする「集団的自衛権」を国会で強行採決しました。平和の実現のために武器を持って外に出かけることができるようになりました。
「我が国は他国に侵略などしない。でも世界には悪い国もある。その悪い国の軍隊が攻めてきたときのために、あるいは攻めてくるまえに叩き潰す。だから、我が国は軍隊を常備する。兵器を所有する。」
抑止力。これこそ「平和の実現のために軍隊を持つ」という世界が抱えている矛盾の根っこにあるものです。どの国も「自衛のための軍隊」として武器を持っています。ですが、ここではっきりさせなければならないことがあります。自分を守ろうという自衛の意識はいくらでも肥大化します。そして解釈次第で、戦争も正義になりうるのです。そのことは歴史が証明しています。
かつて日本が戦争の大義にしたのは、欧米列強からのアジアの解放でした。ナチスドイツによるポーランドへの侵攻は祖国防衛が名目。ブッシュ政権のイラク侵攻も、大量破壊兵器を持つテロリストから世界の平和を守ることでした。人は自衛を大義にしながら人を殺すことができるのです。武器を持っていると誤った防衛になることも起こってきます。そのことを私たち日本人は、身をもって痛感したのです。だから武器を棄てましょうと、日本は72年前に日本国憲法第9条として決意しました。
毎田周一さんの「君自身が 平和の人と なり給へ」という言葉は、ご自身も戦争の悲惨さを経験され、「なぜ平和を願いながら、人々は戦争を繰り返すのか」と問うなかで紡ぎだされたものでしょう。平和のために、まず私がしなければならないことは、さまざまな論理や正義によって戦い、殺しあうことを正当化し、口実にする「私」を見つめることです。
今日、地球上では、さまざまな論理や正義によって戦いあい、殺しあう人間同士の闘争が続いています。長い歴史の中で育てられてきた人間心理は、簡単に乗り越えられないようですが、それを乗り越えなければ、私たちはこの足下の大地に、いつまでも人間によって殺された死者の白い骨を埋めなければなりません。
張 偉(チャン ウェイ)著『海を越えて響くお念仏』 深草誓弥 平成30年8月
「殺」の上に 成り立っている 日暮らし それが 私たちの 日暮らしである
(広瀬杲)
七月は作上がり法筵をお勤めしました。この法筵は田植えが終了する頃に勤める法要で、自然の営みを自然(じねん)のはたらきとして受け止め、私たちの思いや計らいを超えたものに支えられていることを確かめる仏事です。先祖の方々は、全てのいのちが私たちへはたらきかけ、我がいのちが生かされて来たことをこの法筵において確かめてこられたのだと思います。
作上がり法筵が勤まるこの時期、梅雨を迎え田植えの準備が始まると、田んぼではカエルの大合唱が始まり、ジャンボタニシが畦に卵を産み付け、ホウネンエビが泳ぎ回り、大小様々な虫たちが生活している世界が見えてきます。丁度この頃は気温も上がり、虫たちや生き物の営みが活発になる時期でもあります。しかし人間に都合の良い虫たちばかりが出てくるわけではありません。都合の悪い虫たち、邪魔になる生き物もわき出てくるわけですから、殺さなければなりません。
「殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ、殺して良いいのちは無い」と教えられていても、殺さないと作物が取れません。日常の日暮らしでは「殺」の事実がありながら、「そのようにしなければならないから、しょうがない」という言葉で自己弁護している私がいます。事実、知らされる我が身の姿は今月の言葉のように、「殺の上に成り立っている」日暮らしが、私たちの日暮らしであります。
広瀬先生は「滴々抄」という本の中で、榎本栄一さんの「罪悪深重」の詩を紹介され、自身のことを次のように語られます。
「罪悪深重」 榎本栄一
私はこんにちまで
海の大地の
無数の生きものを食べてきた
私のつみのふかさは
底しれず
......「罪悪深重ということばに、ほとんど何の感情も動かなくなっている私自身を思い知らされて愕然とした。なんという厚顔無恥なる今日を生きていることであろうか......。」
榎本栄一さんは、いのちを殺し食べ、今現に生きている事実を「罪悪深重」という言葉をもって懺悔されています。しかし広瀬先生は何の感情も動かない自分自身を恥ずかしく感じておられます。続けて、仏教教団が「不殺生戒」を第一の戒律として定めたのは何故だろうか、守れることの出来ない決まりを何故定めたのであろうかという問いに対して広瀬先生は、
......「しかし「不殺」は、私の生命にとっての死を意味する。殺さずしては生きることができない。思えば深重なる罪とは、行為における罪ではなく、存在することの罪であった。私の今日の生き死にが罪業の現在でしかない...。」
と述懐されます。不殺生を守り通すと私自身が命を落としてしまう。それは殺さずには生きていけない存在であることの事実に立ちなさいと教えられます。それを「存在することの罪」であると教えられ、これは言い換えれば「生きることの罪」に他ならないのです。この罪は刑法で罰せられる罪ではなく、宗教的生命感覚としての罪としてあるのです。自己を正当化する事ではなく、ただ申し訳ございませんと頭を下げるしか手立てがありません。
先祖の方々は、農作をしながら「殺」の上にしか成り立たない自分のいのちであるからこそ、「作上がり法筵」という仏縁を相続して下さったのではないでしょうか。 平成30年7月 貢清春
日曜学校バス遠足の案内
前略 皆様におかれましてはご健勝にお過ごしの事と拝察致します。また常日頃、日曜学校の会の運営にご協力、ご理解頂きお礼を申し上げます。
この度、日曜学校でバス遠足を計画しました。今年は大瀬戸町の光明寺様を訪ねます。みんなでたのしく勉強になる一日を過ごしたいと思います。
◎日 時 平成30年7月16日(月)海の日
9時 福浄寺集合
(いつもの時間にお迎えに来ます)
◎行き先 ・光明寺 西海市大瀬戸町(0959)-22-0002
・七ツ釜鍾乳洞 (0959)-33-2303
◎参加費 1人、500円
◎持参品 お勤め本、お数珠、お賽銭100円、水筒、ぼうし、おやつ
お弁当(おかず程度)
*車酔いをする人は、酔い止めの薬を飲んで来て下さい。
*お小遣いは持たせて構いませんが、必要以上は
持たせないようにして下さい。
◎申込み 参加費500円を添えて寺へ申し込み下さい。
7月8日締切です。
◎日 程
9:00 福浄寺集合、出発 (いつもの時間にお迎えに来ます)
10:00 大瀬戸、光明寺着 (お勤め・レクレーション)
12:00 昼食、そうめん流し
近くのお店でそうめん流しを食べます。
1人に1束半くらいのそうめんの量だそうです。
おかず、おにぎりが必要な方は別に持参して下さい。
14:00 七ツ釜鍾乳洞~西海橋
17:00 福浄寺着予定 (帰りは自宅まで送ります)
どこまで しあわせの道具をそろえたら
人間は 「しあわせです」と いうのでしょうか (金子大栄)
今月の掲示板の言葉は、「しあわせ」について述べられた金子大栄先生の言葉です。特に目を引くのは「しあわせの道具」という言葉ではないでしょうか。道具とは、太古の人類が用い始めた石器から始まり、近代にいたると工具、文房具、農具、家具、調理器具、実験器具など様々なかたちで私たちの生活、文明を支えています。人類は道具をつくり、使いこなし、発展させて様々な文明をつくってきました。
たしかに様々な道具の登場によって私たちの生活は、より豊かで、快適になったように感じられます。最近登場した道具の代表は、ロボット掃除機や全自動洗濯乾燥機、食器洗い機。自動運転の車。つい十年ほど前では考えられないような道具が次々登場しています。掃除や洗濯をしなくていい、あるいは早く終わらせることができる。早くて便利、何もしなくていい。気が付いてみるとそういう道具がどんどん増えて、実際に私もそれらの道具に囲まれています。
「私の代わりに、道具がしてくれる。では私は何をするのか。」ふと、そのことが気になりました。確かに「早くて便利。何もしなくていい。楽」そういうことは感ずるでしょうが、掲示板の言葉にあるように「しあわせです」といえるか、と問われるとどうでしょうか。
このまま私の代わりにいろんなことをしてくれる道具をそろえ続けたら、最終的に人間はどうなるでしょうか。ボーっとしているだけで、動かないで、食事を食べさせてもらい、おしりも拭いてもらって、テレビでも見ながら、ロボットに指示だけ出すようになるのでないでしょうか。そういう状況を想像してみましたが、私はそこで「しあわせ」といえる自信はありません。
私たちは「しあわせの道具」を手に入れることによって、自分の思いは満たされ、満足すると思っていますが、「私は何のために生まれて、生きているのか」という「人の使命」というものが空白のままでは、決して「しあわせ」とはいえないでしょう。先にも述べましたが、「私は何をするのか」という問題です。
「私の代わりに○○してくれるもの」を追い求め続けて、「私は何のために生きているかわからない」ということでは、私の代わりをしてくれて、支えてくれる道具も台無しにしてしまうことになりませんか。どういう状況がめぐってきても、他人の責任にしたりしないで、自分を捨てないで、与えられた人生を生きていきたい。そういう使命が見いだされて初めて、支えてくれる道具も生きてくると思います。 平成30年6月 深草誓弥
「もったいない」
貧しく愚かで 力のないものが 最高の幸せに 包まれている その実感が 「もったいない」
あなたにとって幸せとは何ですか?と問われたら何と答えられるでしょうか。健康であること、家族が幸せであること、お金が沢山あること、好きなものを腹一杯食べているとき・・・等々。年齢や性別、生まれた環境や国など、人それぞれに幸せと感じる感覚は違うと思います。いずれにしても自分に都合の良い条件が重なり、思い通りに物事が解決していくことで誰しもが幸せを感じていくものです。逆に自分の人生で何一つ自分の思い通りにならない、苦しみ悩みばかりの人生ならば自分は不幸だと感じます。幸福か不幸かは、自分の思いが満たされているか満たされていないかの違いによって変わるようです。しかし今月の言葉には「最高の幸せに、包まれている」とあります。これはどの様な事なのでしょうか。考えてみたいと思います。
皆さんは「青い鳥」の話をご存じでしょうか。ベルギーの作家、メーテルリンク作の童話劇です。チルチルとミチルの2人が、幸福の青い鳥を探す旅に出る話です。様々な世界を探しても、幸せの青い鳥を見つけることができないのですが、夢から覚めて家の鳥かごを見てみると、飼っているハトが探していた青い鳥だったというお話しです。幸せは遠くに求めるものでは無く、本当はすぐそばにあるのだということを教えてくれる童話です。
ところがこの童話の最後には思いもよらない展開が待っています。子供達が鳥にエサをあげようとして、青い鳥の取り合いを始めてしまうのです。すると青い鳥はその隙を見て飛び去ってしまいます。チルチルは最後に「僕たちが幸せに暮らすためには、あの青い鳥が必要なのです」という、悲しいセリフで話が終わっていきます。
一度つかんだ幸せ(青い鳥)に心奪われて、本当の幸せをイメージできなくなってしまう人の姿を表現してある様に思われます。私たちは幸せの条件を用意し、その条件にかなう生活ならば幸せ、条件がそろわなければ不幸だと考えてしまいます。今自分に無い幸せをくっつけて助かろうとするのなら、この物語のエンディングの様に幸せの奪い合いが起こり、幸せはその場から消えてなくなってしまいます。
今月の言葉の「最高の幸せに、包まれている」という言葉は、私たちが追い求めて獲得する幸せではなく、気が付く気が付かない以前に、本来幸せの中に自分がいたのだという喜びを表現してあるのだと思います。親鸞聖人は、自分自身を包み込み、私を見捨てないはたらきを、阿弥陀のはたらきとしていただかれました。真宗の本尊である阿弥陀如来は「摂取不捨」という大慈悲の誓いを建てられた仏様です。その慈悲心は、どの様な環境に身を置いていている人にも無条件にはたらく光です。社会的な能力も経歴も関係なく、念仏するこの身のままで阿弥陀の浄土へ往生させ、仏と成らしめ救い遂げようとはたらいて下さっています。私を決して見捨てることのない、阿弥陀のお心の中に存在していた事の幸せを、聖人はお念仏のひびきとしていただいておられたのです。
その阿弥陀のはたらきを実感した時、今まで気が付かずに「もったいないことをしていた」という懺悔と、「もったいなくも頂戴していた、かたじけなくも有り難い」という感謝の思いが今月の言葉に表現してあるのだと思います。そしてもう1つ、人生に於ける最高の幸せ、阿弥陀のはたらきに気付いて欲しいという願いがあるようにも感じます。
人間誰しも、幸せを追い求めて生きています。しかし求め方が間違っている為に、何が本当の幸せなのかが分からないで生きているのかも知れません。「僕たちはすでに幸せに包まれていました、だから青い鳥は必要ではありません」このセリフを私は胸を張って言えるだろうか。 平成30年5月 貢清春
人間はね、ただ嘘をつくんじゃないんです。
何かを隠してつくんです。
そして事実を直視しないようにする。 カズオ・イシグロ
今月の掲示板の言葉は、イギリスの作家、カズオ・イシグロさんの言葉です。「嘘」ということについて語られています。仏教には在家の仏教徒が守るべき五戒という戒律があります。不殺生戒(殺生をしてはいけない)、不偸盗戒(盗んではいけない)、不邪淫戒(よこしまな交わりをしてはいけない)、不妄語戒(嘘をついてはいけない)、不飲酒戒(お酒を飲んではいけない)
この五戒には様々な解釈がありますが、人はひとりで生きているのではなく、さまざまな関係性を生きています。その関係性を大切にするために定められたルールだと私は受け取っています。この五戒のなかに不妄語戒として、嘘をつくことがいましめられています。
嘘をつくこと。私はどうだろうかと振り返ると、嘘をつくことが頻繁にあるように思います。出来ないのに出来ますと虚勢を張ったり、失敗したことを隠したり。なかでも子供に対しては、日常的に嘘をついているようです。本当は次の機会のことなど考えてもいないのに「また今度ね」といったり、忙しくないのに「いま、忙しいから」といったり。どうやら反射的に、自分を守ったり、自分の都合を通すために嘘をついているようです。
イシグロさんの言葉に「何かを隠して」とありますが、この自分を守ろうとする心や、自分の都合を優先させる心を隠しているということを言っておられるのだと思います。隠そうとしているのは自己正当化のこころ、「私は悪くない」という心でもあるでしょう。掲示板の言葉は「そして事実を直視しないようにする」と続いています。嘘をついて、自分を正当化する心を隠して、そして都合の悪い事実を見ないようにする、ということでしょう。
しかし、ここで大切なことに掲示板の言葉から気付かされます。それは、どれだけ自分の都合を通そうとする心を隠して、嘘をついても、嘘は嘘で、事実にはならないということです。亡くなられた先生ですが、平野修という先生は、
「嘘は百万年かけて固めましても嘘です」
という言葉を残されています。私たちは嘘をついて、どうにか自分の都合のいいように世界を変えていこうとします。しかし事実は変わらない。カズオ・イシグロさんの言葉には、「事実を直視する」ことの重要性が語られているのだと思います。
私たちは「嘘をつかないでおこう」と心に決めても、状況次第、縁次第で自分の意志をこえて反射的に嘘をついてしまいます。嘘をつかないでおれることはもちろん大事ですが、それよりも、嘘をついた自分が、何を隠そうとしているかを知ること、そして嘘は事実にはならないことを知ることの方が重要です。嘘をつくとき、自分のことばかり優先して、他の人を騙して、ないがしろにします。そして、自分を守るどころか、事実の自分も大切にできません。思わずつく嘘。その嘘は他者との関係も、自分も損なうものだということを、私たちは知っておかなければなりません。 深草誓弥 平成30年4月
帰る場所を見失うと 人間は迷う
とある御門徒さんで、認知症になられたお母さんを自宅で介護されているお宅がありました。お母さんが亡くなった後にお嫁さんから聞いたお話ですが、ある時お母さんが荷物をまとめて外出しようとされている姿を見てお嫁さんが「どこに行くとね」と尋ねると、「えんち(自分の家)にかえらんばと」と言われる。「えんちはここよ、ここがえんちよ」と何度言ってもお母さんが、「うんにゃ(いいや)、えんちにかえらんばと」と言って聞かなかったそうです。「そしたら車で送ってやっけんね」と、お母さんを車に乗せて、田んぼを一周して自宅に帰ってきたらやっと落ち着いたのか、布団に入って寝られたという話を聞いたことがあります。
認知症になられた患者さんが「徘徊」を繰り返すのは、「生まれ故郷に帰りたい」という理由があるのだと聞いたことがあります。端から見ればただウロウロとあてもなく歩き回っている様に見えますが、目的を持って自分が生まれ育った場所に帰ろうとしているのだというのです。
人は皆、心の奥底にある深い欲求として、身も心も安心出来る場所に帰りたい、存在の故郷に戻りたいという願望があるのだということを知らされ、考えさせられた事でした。しかし帰りたいという願いはあっても、どこが存在の故郷なのかは、いのちはどこに帰ろうとしているのか、私たちの分別やはからいで知ることは出来ません。
そういう私たちに日本に昔から伝えられた仏教行事がお彼岸です。彼岸の中日には太陽が真東から昇り、真西に沈みます。その自然現象を手がかりにして、西方の浄土を拝みなさいとお釈迦様は教えて下さいました。「西方を拝みなさい」ということは、本来私たちが帰る場所はお浄土ですよと呼びかけられているということです。
「彼岸」は読んで字の如く「彼の岸」で「此の岸」に対した言葉です。彼岸の浄土に対して手を合わせ、お参りするということは、私たちの都合の良い幸せが手に入るための行ではなく、今私たちのいる娑婆「此岸」の生活が照らされ、問われているということです。私の迷いの生き様を知らされ、自分の人生これで良いのか、何をたよりに生きているのか、何のために生まれて何が生きる喜びなのか。浄土の世界、浄土の教えを鏡として知らされていくのであります。また親鸞聖人は「畢竟依を帰命せよ」と浄土和讃に説かれます。「畢竟」とは「究極」という意味で、最終的には阿弥陀の浄土をたよりにして生きなさいという意味です。
私たちの人生に迷いが生じるのは、心身共に帰るべき世界、浄土の世界を見失うことから始まっていくのだと、今月の言葉は教えて下さいます。暑くもなく寒くもない、過ごしやすいこの彼岸の時期にこそ、人間の分別を超えた浄土からの声に耳を傾けてまいりたいと思います。 貢清春 平成30年3月
古人のあとを求めず 古人の求めたるを求めよ
今月の掲示板の言葉は、江戸時代に、俳句の元となった俳諧(はいかい)を発展させた松尾芭蕉の言葉です。芭蕉は、弘法大師の言葉を参考にしながら、この言葉を弟子の武士、森川許六(きょりく)に贈ったと伝えられています。文中にある古人(こじん)とは、過去の偉人というような意味です。「昔の偉人たちが、何をしたかという結果をまねるのではなく、何をなそうとしたかという志(こころざし)を見極めて行動しなさい」という意味でしょうか。
許六という名は、俳諧のみならず様々な活動に優れ、槍術・剣術・馬術・書道・絵画・俳諧の六芸(りくげい)に通じていたとして、芭蕉は「六」の字を与えたのだといわれます。中でも絵画は、芭蕉が許六を師と仰ぐほどです。
ある時、芭蕉は尋ねます。「絵は何のために好むか」と。すると許六は「俳諧のために好む」と答えました。次に芭蕉が「俳諧は何のために愛するのか」と問うと、「絵のために愛する」といいます。芭蕉は「学ぶことが二種類あるのに、その学びの帰するところが一つなのは、感服すべきことではないだろうか。」と、どちらの世界でも本物に近づこうと志す許六を讃えて、「古人のあとを求めず 古人の求めたるを求めよ」という言葉を送ったのだそうです。
私は、この言葉の背景にある物語を知り、ふと考えました。例えば、「なぜ仏教に学ぶのか」ということも、「なぜ社会情勢に学ぶのか」も、「なぜ歴史に学ぶのか」も、「自己をあきらかにする」という点では一つではないかということです。一つの目指す地点が明らかになると、周りにある事柄も、別の登山口のように見えてくるのです。
「真宗を学ぶ者の姿勢は、現実と聖典の間に身を据えるということが大事なことだ。しかし、私たちは現実と聖典との間に寝そべっているのではないだろうか。間に身を据えるということは、真向かいになるということだ。聖典に真向かいになり、現実に真向かいになることだ。」
これは亡くなられた宮城顗先生が仰った言葉ですが、「現実と聖典との間に寝そべっている」と鋭く私の姿勢を言い当てられます。真向かいになることなく、ただ眺めているだけで、動かないということでしょう。真向かいになるならば、私を突き動かすものがあるのではないか、ということです。
学生の時、お世話になった先生が、「どんな仕事でも真剣にやろうとしたら、楽な仕事なんて世の中に一つもないんや」といわれていたことを思い起こしました。「これくらいやったから、もういいだろう」という姿勢を戒めたのが「古人のあとを求めず」ということでないでしょうか。どんなことでも、真向かいになるならば、自分の姿勢が問い返される。「古人」が求めた、真向かいになる姿勢。私は、今、どうであろうか。 (深草誓弥)平成30年2月
小さな恩には 気づいても 大きな恩には 気づかない
まずは「恩」という言葉がどういう意味なのかをひもといてみましょう。恩とは元々インドの言葉で「カタンニュー(為されたる事を知る)」という意味の言葉で、中国の漢字である「恩」という文字に翻訳をされました。恩を知る、恩を感じるということは、私を私にしてくださった原因が何であったかを、心に深く考え、思い、知ることであります。恩という字も「因」と「心」から成り立っています。「因を知る心」、字そのものが「カタンニュー」の意味を表現しています。
また、毎年真宗の寺院で勤められる報恩講は、親鸞聖人からいただいたご恩とは何だったのか、その事を確かめその恩に報いる、一年で最も大切な仏事です。報恩の報の字は「むくいる」という意味とは別に、「報告」や「報道」とも言うように、「しらせる」という意味もあります。様々なご恩をいただきながらも気がつかない私に報恩講という仏事をご縁として、ご恩を報せていただこうという意味にもとれます。
私たちは日々、大小様々なご恩をいただいています。親の恩や師の恩、自然の恩や国土の恩、日常の中で気が付く恩はどれくらいあるでしょうか。例えば、自分にしてもらったことが目に見える形になっていたりすると気が付きやすいです。お中元やお歳暮、お土産などがそうです。お品をいただくと、あの人からこれをいただいた、これをしてもらったという様に、出来る範囲でお礼も恩返しも出来ます。しかし目に見えない恩の方が、手で触れることの出来ない恩の方が大きいのだと、今月の言葉は呼びかけています。しかもそうしたものが私たちの人生を底から支えているらしいのです。
親鸞聖人はその大きなご恩を感じ、報謝する生き方があると示して下さいました。ご和讃に、「如来大悲の恩徳は 身を粉にしても報ずべし」と詠っておられます。「阿弥陀如来のご恩は我が身を粉にしても、感謝しきれないものがある。だから人生をかけて報いなければならない、それほどの大きな恩をいただいたのだ。」という意味があります。この和讃の「報ずべし」の「べし」を注目して現代語訳してみると、「報謝しなさい」という命令の意味として受け取れます。「こうしなさい、ああしなさい、このようにせよ」という他者に対して命令するイメージがあります。しかしこの「べし」には色々な意味があると指摘されます。
ひとつは、推量や当然の意です。「報謝するだろう、報謝するはずだ」という意味になります。もう一つは義務の意。「報謝しなければならない」という意味です。この義務の意は決して他人に対して命令するのではなく、自分に対して「しなければならない」と駆り立てられるような感情です。それは自分自身に大きな恩を受けていると目覚めたときに湧き出てくる、義務感なのではないでしょうか。
報恩講という名称の仏事を勤めますが、返恩講ではありません。恩をお返しすることではありません。もし恩をお返しすることが出来るのなら、返した時に「これで済んだ」という達成された意識が出てきます。もうそこで恩を感じることは無く、終わったことになってしまいます。恩は返すことではなく、気付き、感じ、賜るものです。その事を思うと報恩講と名付けてお勤めしてきた念仏者の歴史に尊さを感じます。私たちに先だって念仏して下さった方々の願いを感じつつ、今年も念仏の教えに出遇わせていただきたいと思います。 (貢 清春)平成30年1月
浄土を本国として この世を生きる 竹中智秀
12月になり、今年もいよいよ終わりが近づいてきました。先月の11月28日は、宗祖親鸞聖人の御命日でした。福浄寺ではこれから門徒報恩講、年明け1月に御正忌報恩講が厳修されますように、各地方の寺院や家々で親鸞聖人の御命日を縁として勤める報恩講の季節です。その報恩講を迎えるにあたり、「親鸞聖人は誰だったのか」ということが、一つの大きなテーマになると思います。
親鸞聖人は、9歳で出家得度され、それから29歳までを比叡山で過ごされました。29歳のとき、念仏者法然上人と出会い、親鸞聖人自身も念仏に生きる歩みを始められます。しかし親鸞聖人が34歳の時に、一つの事件が起こります。「承元の法難」です。奈良の興福寺の僧侶が、法然上人とその弟子たちに九ヶ条の罪を上げて処罰するように朝廷に訴えたのです。そして翌年には院の御所の女房たちが、法然門下の住蓮房・安楽房の念仏会に加わったことが後鳥羽上皇の怒りを呼び、興福寺の訴えが取り上げられて、住蓮房ら4人が死罪、法然上人はじめ8人が流罪に処せられました。師と共に流罪にあった親鸞聖人は、僧の身分を奪われて還俗させられ、さらに罪人としての名前を受けて越後に流されました。
私は、今月の「浄土を本国として この世を生きる」という竹中先生の言葉の背景には、この親鸞聖人の体験された「承元の法難」という事件があるのだろうと思います。
「国とは何か」という問題です。
おそらく親鸞聖人は9歳の時出家して、世間とか国家の仕組みを離れたという意識があられたのだろうと思います。しかし、比叡山も世間的な価値観を中心としていたのでしょう。そのことを知られて山を下りられたのですが、さらに「承元の法難」によって、さらに思い知らされたのだろうと思います。僧侶といっても、それは天皇を中心とした律令制の中での僧であり、政治によって作られた身分としての僧でしかなかったことが、法難による還俗ということによってあらわになったのではないでしょうか。
流罪以後、親鸞聖人は法然上人との出会いのなかで、受け取ったものが何であったのか。それを現実の社会の中で、念仏に生きるものとしての名告りを具体的にどう示すことができるか。その問い返しの中で「非僧非俗」「しかればすでに僧にあらず、俗にあらず」と名告れたのだと思います。単に国の仕組み、世間の仕組みのなかに身分として位置づけられる僧侶でもないし俗人でもない。「このゆえに禿の字をもって姓とす。」「愚禿」というのは凡夫のことでしょう。「非僧非俗、愚禿」という名告りは、ただ世間の仕組みの中での僧俗ということを突き破って、阿弥陀如来が開かれた浄土を本国として、そこに身を据えてみれば、凡夫という事実の自分自身と、そして自と他とが偽りなく出会える場が開かれてくるという叫びのように思えます。
今日も国と国との争いは止むことがありません。私たちは日本という国に生まれ「日本国籍」を生きていますが、真宗の門徒として、この親鸞聖人の名告りを憶うとき、阿弥陀の国「浄土」を本国として、日本を生きる「在日浄土人」という生き方が、聖人によって既に示されていることをあらためて気づかされました。
(深草誓弥)平成29年12月
日曜学校生徒皆様
福浄寺、門徒報恩講参詣のご案内
前略 皆様におかれましては日頃、日曜学校の会の運営にご協力、ご理解頂きお礼を申し上げます。この度、日曜学校のみんなと一緒にお寺の行事としてつとめられる門徒報恩講に参詣いたします。
親鸞聖人のご命日をご縁にしておつとめされる集まりが報恩講です。親鸞さまは「南無阿弥陀仏」の教えを、正信偈や和讃という「うた」で残して下さり、そのおみのりによって、たくさんの人が生きる喜びをいただいておられます。その親鸞聖人のご恩に感謝する、一年の中で一番大切な仏事が報恩講です。
今年は木場地区の方と一緒にお参りします。ご参加頂きます様、よろしくお願いします。
記
○日時 平成29年 12月10日(日) 10時~12時半まで
○日程 10:00 おつとめ
10:40 仏様のお話
12:00 お斎(精進料理)
12:30 解散
○持ってくるもの
・お米1人1合 ・おさいせん100円
・他、いつも日曜学校に持ってくるものを持って来て下さい。
・ゲームやマンガ本は持って来ないでください。
「己れに願いはなくとも、願いをかけられた身である」 藤元正樹
いやいや、私には願いはあります。家内安全、無病息災、商売繁盛、息子が受験合格して欲しい、娘が結婚して欲しい、宝くじも当たって欲しいし、・・・等々。私たち人間は、何事にも思い通りになることが大好きな生き物なので、沢山の願い事が湧き出てきます。そして願いを叶える為に神仏にお祈りを捧げるのだと思っていますが、浄土真宗では仏様に願うのではなく、仏様の願いを聞くことを大切にします。
今月の言葉の藤元正樹先生も「願いをかけられた身だ」と言われます。私たちはどういう願いがかけられているのかを、尋ねてみたいと思います。
1922年(大正11年)に来日したアインシュタインは、真宗大谷派の僧侶、近角常観師(ちかずみ じょうかん)と対談されたことがあったそうです。「仏様とはどんなお方ですか」とのお訪ねに近角師は、「姥(うば)捨て山」の話を例にあげて説明されたそうです。
昔、日本のある地域には、高齢の老人を口減らしのために山へ捨てなければならないという掟がありました。掟の通りに若い息子は、年老いた母を背負って姥捨て山の奥へと入っていきます。ところがその道すがら、背負われた母親がしきりに木の枝を折っては道々に捨てているのを息子は気が付きます。「ひょっとして、母親はこの木の枝をたどって帰って来るつもりではないか」と疑い、さげすむ目で見ていました。
とうとう捨て場所にやってきて母を降ろして帰ろうとしたその時、母親が「山もだいぶん奥まで来た。お前が村に帰るときに道に迷わないように枝を折って道に落としておいたから、それを頼りにしていけば間違えることなく帰れるから、気を付けて帰れよ」やさしい眼差しで、子どもに対し手を合わせ拝んでいる姿に、息子は泣き崩れました。
「なんと私は恐ろしいことを考えていたのだろう。わたしは母を捨てよう、帰ってきてもらっては困ると考えていたのに、母は捨てられるのにも関わらず私のことを案じていてくれる」息子は母に両手をついて謝り、母を再び背中に乗せて山を降りました。
「この母親の姿こそ、仏様の姿であります」と、近角師はおっしゃられたそうです。我が身を捨ててまで、唯ひたすら我が子の無事を心配している。苦悩の衆生に対して願いをかけ続けて下さる存在が仏様だというのです。帰国するアインシュタインは「日本人がこのような温かい深い宗教を持っていることはこの上もない幸せなことです。日本に来てこんな素晴らしい教えに出会えたことは私にとって何にも勝るものでした」と語ったそうです。
真宗宗歌の3番には「み親の徳の尊さを・・・」という歌詞があります。「み親」とは阿弥陀さまをお呼びする尊称です。阿弥陀さまが私を一人子のように心配し、生かそう生かそうと願いをかけ続けてくださる姿は、親心そのものであります。自分勝手な願い(我欲)を叶えて欲しいと祈りを捧げている私たちに、正しい道を歩め、という声に出会うと「み親、親さま」と呼ばずにはおれません。
阿弥陀の本願をたずねていくと、「念仏を称えて浄土へ往生する人となって下さい、それが本当の救いとなるのですよ」と、絶え間ない願いがかけられている事を知らされるのでした。 (貢清春)平成29年11月
生は 死という 同伴者によって その輝きを増す (武満 徹)
今月の掲示板の言葉は武満徹さんという作曲家の言葉です。武満さんは独学で音楽を学ばれ、映画やテレビなどで幅広く前衛的な音楽活動を展開されました。晩年に膀胱癌に侵され65歳で亡くなられました。
この「生は死という 同伴者によって その輝きを増す」という言葉ですが、不思議な言葉だと感じます。普通は「生を脅かす死」であり、死は私たちに不安をもたらすものであるとしか受け取っていないからです。なるべく死を見ないように、考えないように忌み嫌って、「死のない生」として生きていくのが私たちの在り方でないでしょうか。あるとき、竹中智秀先生からこういうお話をお聞きしました。
『ある年、専修学院に一人の学生が入学してこられた。まわりの学生から魂が抜けたような顔をしていると少し避けられたりしていた。その学生はお寺の跡継ぎでもなく、彼自身ある問題を抱えていた。彼は高校時代、医師になることを目指して、医大に入るために夜遅くまで受験勉強をしていた。その彼の家には寝たきりのおばあさんがいて、離れに一人で住まわせて面倒をみていた。
ある冬の夜、遅くまで起きて勉強していたら、大きな声で「火事だ」という声がしたので外へ出ると、おばあさんのいる離れから火が出ていた。急いでいくともう火は完全に回っていた。とても助けられるような状態じゃなかった。すると火の中で立ち上がれるはずのないおばあさんが立っていてどうにか外に出ようとされていた。
彼は飛び込んで助けることが出来なかった。そのうちに屋根が落ちて、おばあさんは亡くなられた。それで彼は医者になろうとしていたが、医者になったとしたも、病人を治療して健康になっても、最後は死んでしまう。それは本当にたすかったことにならない。「医者になって安定した生活を」という人生設計が崩れてしまった。
その学生は目の前でおばあさんの死を見て、自分の中に死の問題が飛び込んできた。「死のある生」をどういきることが真実か、わからなくなって、仏教を学びに専修学院に来られた。まわりの学生は「死のない生」として明るく、元気に生きているが、「死のない生」ではなく「死のある生」だということを知ってしまった彼からすれば、まわりの学生のほうが異様だったのでしょう。どちらが健康だと思いますか。』
私たちは、ほとんどの人が身近な人の死に遇っています。ですから「死のある生」であることは、死にあっている人は誰もが見て知っているはずです。しかし、知ったにも関わらずもう一度「死のない生」としようとすることは、夢の中で拾った財布が、夢が覚めてもあると思っているようなもので、夢の中でいきることになります。竹中先生は、「死のない生をどう生きるかということに目覚めている彼のほうが健康です」といわれていました。
誰もが死なないで済むのでなく、必ず死を迎えます。仏教はその「死のある生」を見極めて、その死のある生をどう生きることが完全燃焼して生ききることになるのかを問うところからはじまります。生きることを輝かせるのは、死のある生という事実です。 (深草誓弥)平成29年10月
「救い」とは 答えではなく 問いがみつかる事である
答えは 一生を決めつける 問いは一生を歩ましめる
今月の言葉をいただいて、自分の中で憶念していた人がいました。その方は現在、71歳を迎えられた星野富弘さんです。中学校教師の頃にクラブ活動の指導中に誤って大けがをされて以来、首から下がマヒし、手足の自由を失われました。以来、車いすの生活をされていますが、入院中に口に筆をくわえて草花の絵や詩を書き始められました。その後作品は公開され、星野さんのすばらしい言葉と絵にふれた様々な人たちは、生きる力と勇気と元気をいただいておられます。その詩の中に、
「いのちが一番大切だと 思っていたころ 生きるのが苦しかった
いのちより大切なものが あると知った日 生きているのが 嬉しかった」
という言葉があります。星野さんは入院中、思い通りにならない体をかかえ、生きていることに絶望して、母親に「自分を殺してくれ」と言おうかどうか悩んだこともあったそうです。しかし聖書との出会いが星野さんを大きく変え、私のいのちを生かしている、大きないのちのはたらきに出会っていかれました。
この詩を公開した後、いろんな人から「いのちよりも大切なものとはなんですか」と質問を受けていたそうです。その時、星野さんは「その答えはこうですよ、と言うことは簡単だけど、きっとそれは意味のないことです。自分で苦しみながら見つけたときにあなたにとって意味があるのです」と答えていたそうです。
私たちは問いを見つけるとすぐに答えが欲しくなります。しかし答えが手に入ると問いは消えて無くなり一つの答えに執着していきます。そこから別の答えを求めたり、問題そのものを問い返したりすることはありません。その様な私たちの姿を知っておられたからこそ、答えではなく、自分で考える「問う」歩みを大事にされたのだと思います。
本来私たちの生活する環境には、問いかけがあふれています。なぜ勉強しなければならないのか、なぜ仕事をするのか、なぜケンカをするのか、なぜ差別がなくならないのか、なぜ子どもは親に反発するのか、なぜ他人と出会えないのか、等々・・・・問いを出していくと限りがありません。しかしそれぞれの問いに、それぞれが答えを持っているためにすれ違いが起こり、相手を決めつけ、意見が違う者に対して排除する心が生まれてしまいます。現代の緊迫した世界情勢がそれを物語っている様にも感じます。
以前の掲示板の言葉で、「私は何の為に生まれてきたんだろう」「生きる喜びとは何だろう」という課題について書かせていただきましたが、この問いには人間の知恵では答えが出ません。経験も常識も役に立たないほど大きな問題です。しかし、生きていれば問わずにはおれない時が必ず来るはずです。しかし答えが出なくても、結論が出なくても、深く考え思索した時間こそが最も大切ではないでしょうか。その一生を歩ましめる問いに出会うことが救いであると、今月の言葉は呼びかけています。
秋の彼岸の講師に来ていただいた藤本愛吉先生に「子どもは大人になるけど、大人になったら何になるの?」と質問されました。答えられずにいると、「大人になったら仏になるんだよ」と教えて下さいました。しかし私にとってこの先生の言葉は答えでは無く、問いかけでした。「私は仏に成るために生まれてきたんだ」という大きな問いを持ち続け、歩んでいきたいと感じました。 貢清春 平成29年9月
地獄を嫌う心が 地獄を造っていたのです
安田理深
今月の掲示板の言葉は地獄について安田理深先生が語られた言葉です。まず地獄についてですが、サンスクリット語ではナラカという言葉で表現されていた、「地下にある牢獄」という言葉の意味をとって地獄と翻訳されました。地獄は犯した罪のむくいとした苦を受ける場所と教えられてきました。源信僧都のあらわされた『往生要集』には八大地獄のことが、まるで見てきたことであるかのように詳しく描写されています。
その八大地獄の一つ目にあげられているのが「等活地獄」です。この地獄はいたずらに殺生をしたものがその罪を懺悔しなければ落ちるという地獄ですが、この地獄に住む者は互いに害心を抱き、自らの身に備わった鉄の爪や刀剣で傷付けあい、殺しあう世界と示されています。生き残った者もさらに地獄の獄卒によって、切り刻まれ、粉砕されて死んでいくのですが、涼しい風が吹いて、獄卒が「活、活」と叫ぶと元の体に戻り、また殺しあう苦しみにあい続けなければならないという地獄です。この責め苦が終わることなく続くために「等活地獄」といわれますが、実は八大地獄全体を通して、何度でも肉体が再生して責め苦が終わることなく続くというのです。
これまで、この地獄の教えは生前犯した罪の報いとして落ちる世界だと受け止められてきました。いのち終えて墜ちる世界としての地獄を恐ろしく感じてきました。しかし、一番の盲点は、落ちる地獄は恐ろしく思えても、その地獄を造りだしているのが自分のこころであることではないでしょうか。
私たちは日ごろ、自分の思い通りになることを一番の中心に据えて生きています。思い通りにならない物事を何とかして変えてやろうとします。その思いは時に他者に対してはたらきます。「あいつさえいなければいいのに。」お互いに思いや利害の共通する時は仲良くできても、少しでも思いにそぐわない者であれば、暴力的に排除しようとしたり、意識の中から消してしまおうとします。このこころこそ、殺生と戒められていることであり、地獄を現に今、作り出しているこころではないでしょうか。
この自己中心的な思いをもって自ら地獄を造っておきながら、「そのような責め苦が続く地獄はまっぴらごめんだ、清らかで、安らかな理想世界を自分の居場所としたい」ということは、また新たな地獄を作り出すことになるでしょう。現に人類はこれまで自らの理想的な世界を求めて、地獄を造り出してきました。日本は戦争の大義として欧米列強からアジアを解放するということを持ち出しました。ナチスドイツのユダヤ人の殺戮はゲルマン民族を守るためでした。ブッシュ政権のイラク侵攻も大量破壊兵器を持つテロリストから世界の平和を守るためでした。
親鸞聖人は「いずれの行もおよびがたき身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし」と語られたと唯円は歎異抄に記しています。仏教に照らし出された自らの在り方を地獄と誠実に述べられたこの言葉に、原爆投下、敗戦後72年の8月を迎えた今日、思いを新たにしています。 深草誓弥 平成29年8月
日曜学校夏の集い 【お数珠作りと映写会】
今年の夏の集いは、お数珠作りを計画しています。仏様にお参りするときは必ず手に持つお数珠です。しかし近頃、葬式や法事でも数珠を持たずにお参りされる方も少なくありません。お数珠を持つ習慣が薄れているような気がしてなりません。姿勢を正し手を合わせ、頭が自然と下がっていく姿は、人間の行いで一番素晴らしい姿ではないでしょうか。上手に合掌をする道具であるお数珠を、今回はおじいさんおばあさん達と一緒に作ってみたいと計画しました。
どうぞご参加いただきます様、ご案内申し上げます。
---------------------------------------------
◎ 日 時:8月24日(木) 午後3時集合~7時30分解散
◎ 参加費:500円 *お数珠の材料費込みです。参加日当日にご持参下さい。
*夕食から参加される家族の方の分は徴収しません。
◎ 持参品:お勤め本、念珠、はさみ、ふでばこ、水筒
お米(1人1合・参加されるご家族の分も持たせて下さい。)
◎ 申込み:8月12日までに電話またはメールにてお願いします。
*夕食・映写会には、保護者、家族の皆様もご一緒にご参加下さい。
*夕食を食べる保護者、ご家族の皆様の参加人数もお知らせ下さい。
お子様と一緒に解散となります。終了後の送迎はしません。
*この案内は、福浄寺御門徒の皆様にも文章で案内しています。
【日程】 午後~(お迎えに来ます)
3:00 集合 勤行
3:30 お数珠制作開始
5:00 制作終了~片付け
5:30 夕食 家族の方も一緒に食べましょう。
門徒会館で食べます。
6:00 映写会 チャップリン 「モダン・タイムス」
家族の方もご一緒にご参加下さい。
7:30 解散 (送りはしません)
いのちが粗末にされているのではなく
いのちに向き合う姿勢が粗末なのだ (佛光寺)
7月初旬には作上がり法要が開催されます。「作上がり」とは田植えの作がほぼ終わった事を意味します。昔から御門徒のほとんどの家が農家だったため、5月から6月にかけての農繁期には寺の法要がありません。その田作りが一段落した頃に勤められる法要が、この作上がり法要です。
田の土や、水や草木、バッタやミミズ等、大自然の大小の生き物に眼を向け、その働きや恵みを"自然(じねん)"の世界として受け止め、私たちの計らいや思惑、分別を超えた世界によって支えられている事を実感していく機縁として、先祖の方々は作上がりを"仏縁"として勤めてこられました。
私の家は田んぼの土地があるので、毎年稲作をしています。畔道の草刈りや田んぼの中に入ると、色んな生き物が顔を出します。その虫たちが出てきたときに何を考えるかというと、その虫が作物を育てる為に都合が良いか悪いか、ということです。もちろん都合の悪い害虫は薬を使って駆除をします。現代は様々な農薬が開発されているため、駆除をするにも効率が良く、その為安定して作物を取れるようになってきました。
作物を作る上で害虫を殺すことは、ごく当たり前の事です。そうしないと私たちは、お米や野菜をいただく事は出来ません。田畑を作ることは、大量の虫たちを殺していくということです。大げさかも知れませんが、その虫たちの犠牲の上に成り立ったいのちを私達はいただいているのだ、と言っても過言ではありません。榎本栄一さんの詩に、
私はこんにちまで
海の 大地の
無数の生き物を食べてきた
私の罪の深さは
底しれず 「詩集 煩悩林」
これは以前も紹介したことのある詩です。榎本栄一さんは、お念仏を申しながら自分自身を深く見つめられたお方です。この詩で、誰もが言い逃れの出来ない「無数のいのちを食べてきた」という、日常の我が身の事実を「罪の深さは底知れず」として懺悔されています。それは単に自虐的視点での言葉ではなく、私が生きてきた中で犠牲になってきたいのちに対する申し訳なさを、生活の中で実感されてきたのだと思います。
おそらくこの方にとっての「いただきます」は、いのちに対して「ありがとう」よりも「ごめんなさい」の思いの方が強いのではないでしょうか。他のいのちを盗って生きてきた私だからこそ、我が身のいのちをいい加減に軽く扱うわけにはいかない。我が人生が空しく過ぎたら、食べてきたいのちに対して申し訳ない。この様な無数のいのちとまじめに向き合う姿勢がこの詩から感じられます。
以前、『ちゃんと給食費を払っているのに、いただきますと言わせるとは何事だ』と学校に怒鳴り込んで来る親がいる、という話を聞いたことがあります。また給食の時に手を合わせることは、宗教的行為にあたるとして疑問を投げかける人もいると聞きます。様々な意見があると思いますが、食事の前の「いただきます」は、「あなたのいのちを、私のいのちとしていただいている」ということを忘れないように生活しさいと、先祖の方々のいのちに向き合う姿勢が、食前の言葉として受け継がれてきたのだと思います。
あなたはどういう姿勢で、どういう態度でいのちと向き合っていますか、生活の中でどの様に受け止めていますか、様々に問われる言葉でした。 (貢 清春) 平成29年7月
日曜学校バス遠足の案内
前略 皆様におかれましてはご健勝にお過ごしの事と拝察致します。また常日頃、日曜学校の会の運営にご協力、ご理解頂きお礼を申し上げます。
この度、日曜学校でバス遠足を計画しました。今年は隣町、波佐見の西圓寺様を訪ねます。みんなでたのしく勉強になる一日を過ごしたいと思います。
◎日 時 平成29年7月17日(月)海の日
9時 福浄寺集合
(いつもの時間にお迎えに来ます)
◎行き先 ・西圓寺 : 波佐見町湯無田郷1116番地(0956)-85-3228
・佐賀県立宇宙科学館:(0954)20-1666
◎参加費 1人、500円
◎持参品 お勤め本、お数珠、お賽銭100円、お弁当、水筒、ぼうし、おやつ
*車酔いをする人は、酔い止めの薬を飲んで来て下さい。
*お小遣いは持たせて構いませんが、必要以上は持たせないようにして下さい。
◎申込み 下の申込書に学年氏名を記入し、参加費500円を添えて申し込み下さい。
7月9日(日)締め切り、受付は福浄寺です。
◎日 程
9:00 福浄寺集合、出発(いつもの時間にお迎えに来ます)
9:30 波佐見、西圓寺様着(お勤めをしてみんなで楽しくゲームをします)
12:00 昼食 (お弁当 )
13:30 佐賀県立宇宙科学館(館内を見学してプラネタリウムを観ます)
16:00 出発
17:00 福浄寺着予定 (帰りは自宅まで送ります)
他人を思い通りにはしたいが、自分を思い通りにはさせない私
授かった子供が、もう四歳になりました。しばらく前から比べると、様々な言葉を発するようになり、自分がしたいことを言葉で訴えかけるようになりました。
先日、こども園に迎えに行き、乳幼児部の前を通りかかったときのことです。「三回だけ、遊んでいい?」と滑り台の前で立ち止まって、遊具で少し遊びたいと言ってきました。「しょうがないなぁ」と思いながら、「いいよ」と答えて、しばらく子供が遊ぶ傍で見ていました。すでに心の中では、「早くしてくれないかな、こっちは疲れているんだぞ」というようなことが浮かんでいましたが、「いいよ」といったのだからと待っていました。
十五分くらいでしょうか、三回といわず何度も滑り台で遊んで、他の遊具でも遊び始めていた子供に、「そろそろ帰ろうか」と言いました。「もういいだろう」と思っていました。しかし、その言葉に子供はニコニコするだけで、帰ろうとするそぶりも見せません。また、しばらく待ちました。
その間、子供は「お父さん、見て見て。」と何度もこちらに声をかけてきます。最初はきちんと応答していましたが、何度も繰り返された後の私の応答は非常におざなりなものでした。まさに掲示板の「他人を思い通りにはしたいが、自分を思い通りにはさせない私」そのもので、この言葉を見て、すぐに思い当たったのが、この子供とのやり取りのことでした。
問題は、自分の思いや都合を最優先させている私にあるように思います。その後、乳幼児部の前を通るたびに、「今日も遊んでいい?」と聞いて、「お父さん、見て。」という子供の行動には、こちらが翻訳しなければならない意味があるように思えてきました。うちの子供は、怖がりなところがあり、友達の後ろからついていくような性格ですので、思い起こすと乳幼児部にいた二年前位は、なかなか遊具で思い通りに遊ぶということが出来ていなかったのでした。この遊びには、「お父さん、僕はこういうことも出来るようになったよ」という気持ちが込められているのかな、と思うと、自分の思いばかりで子供の気持ちに寄り添えなかった自分が恥ずかしくなりました。「お父さん、見て。」といってくる子供は、成長した喜びを私と共有したくて声をかけてくれていたのかもしれません。
私どもの「共に生きるという世界」というものは、手を取り合える理想郷を我々の手で作るんだという方向にはないんでないか。(中略)自分はいかに生きて行くために回りの人々に迷惑をかけているか、そのことをまず深く知る。私の言い方で言えば、そういう事実を深く悲しむ。そういう悲しむ感覚だけが、深く悲しむことが逆に人に向かって自分の心を開いて行く、そういう促しとなって働いてくるのでないか。
『共に生きるということ』宮城顗
子供が親に迷惑をかけているとしか受け取っていなかった私に、私も子供に迷惑をかけていると立ち止まらせてくれたのが、この宮城顗先生の言葉でした。 深草誓弥 平成29年6月
生きるということ それは つねに誕生の意義を 問われ続けることである (広瀬杲師)
福浄寺では、毎年5月に花祭り敬老会を開き、お釈迦様の誕生と敬老者をお祝いする行事を開催しています。花祭り敬老会では本堂でコンサートがあったり、こども園の園児の出し物があったりと、とても賑わう行事です。本堂の御拝口には花御堂をお飾りし、お釈迦様の誕生仏に甘茶をかけてお参りしていただきます。
お釈迦様の誕生は「七歩」あゆまれ立ち止まり、天と地を指さして「天上天下唯我独尊」と声高らかに叫ばれました。その時大地が喜び、雨を降らせお釈迦様を洗い清めたという伝承があります。その話を基にして誕生仏に甘茶をかける習わしが伝わりました。
これは現代人が考えると、仏陀を威厳化するための作り話の様に考えてしまいますが、この物語は仏陀となられた釈尊が誕生したまことの意味を表現しています。誕生し「七歩あゆまれた」というのは「六道」の苦しみを超える「さとりの七歩目」を歩まれる人の誕生を意味し、「天上天下唯我独尊」の声は、いのちの平等の宣言を表現します。「唯我独尊」の言葉は、決してお釈迦様だけが尊く偉いのだというのではありません。ひとりひとりの尊厳を表し、私という存在は誰にも変わることが出来ず、他と比べることが出来ないほど尊いという意味があります。
この誕生の物語は仏陀釈尊の誕生を通して、私たちが人として生まれてきたことの意義と命の尊さを知らせています。そして私たちは何をしに生まれてきて、何のためにここにいるのか、生きるということは如何なる事なのかということが大きく問われています。それは一度考えて、答えを出したらそれで終わることではありません。今月の言葉にあるように、人生の中で誕生の意義を問い続け、いのち終わるまで自分自身に出会い続けなければならないのです。
しかし多忙な生活を送る私たちは、その人生の問いかけにじっと心を掛けることが無いまま、良かった悪かったと一喜一憂しながら生きているのではないでしょうか。ここで兵庫県三木市の村上志染という詩人の、「水馬(ミズスマシ)」という詩を紹介します。
方一尺の天地 水馬しきりに 円を描ける
汝 何処より来たりて 何処へ往かんとするか
ヘイ 忙しゅうおましてな
ミズスマシにとっては、一尺(約30センチ)ほどの水たまりでもそこが「天地」世界の全てです。その小さな世界で忙しく円を描きながら動き回っているわけです。「あなたはどこから来て、どこに行こうとしているのか」と問いかけても「忙しくてそんな事考える暇なんてないよ」と言っているのです。煩悩に振り回され、立ち止まること無く、同じ所を堂々巡りして「忙しい忙しい」と言う私たちの姿は、仏様から見るとミズスマシなのかもしれません。
仏陀釈尊の80年の生涯は、誕生の意義を問い続けた生涯だったのではないでしょうか。誕生仏の姿は、忙しい日常の中で一歩立ち止まり、人生の問いかけに耳を澄ましなさいとの呼びかけなのだと思います。 (貢 清春) 平成29年5月
はやく咲いてほしい ながく咲いてほしい
私のおもいにかかわらず 花は咲き 花は散る
四月の掲示板の言葉です。今年は桜の開花が例年より一週間ほど遅く、しばらく私も「まだ咲いてないな」と思っていましたが、ようやく花が満開になっている桜の木をみつけて、おもわず車を止めて見入ってしまいました。温暖な春の訪れを感じさせる桜の花です。花を待つと同時に早く春になってほしいというような心持でもあるようです。しかし、その満開になったあと、何日か雨が続き、風の強い日もありました。せっかく心待ちにしていた花が、雨風で散ってしまいました。「晴れた日に、子どもとお花見でも」と思っていましたが、私の思いは見事に裏切られました。
日本全国、あちこちでお花見を楽しみにしている人がいるでしょうが、なぜ、これだけたくさんの人が桜の花に心惹かれるのでしょうか。一つは春の訪れを感じさせるからでしょう。もう一つは「はかなさ」ではないでしょうか。桜の花は、たとえ雨風にあたらなくても、十日ほどで散ってしまいます。はかないからこそ、桜の花が咲くことを心待ちにし、咲いた花を見つめる時を大切にするのでしょう。一ヶ月も二ヶ月も咲く花ならば、ここまで人の心をとらえたりしないのではないかと思います。咲いてはかなく散っていく桜であればこそ、私たちは自分の人生の相を照らし合わせるようにしてきました。
仏教ではこの「はかなさ」を無常と教えています。無常とは、生あるものが死するから無常というだけはなく、例えば傍にいて都合のいい人でも、いつでもそうだとは限らないわけです。時には都合の悪い人になることもあります。車をもっていることは楽で便利なことですが、車があるために困ることもたくさんあります。人間関係、状況、物質、その時その時の条件で移り変わるから無常であり、有限であるといくことを教えます。突き詰めると「あらゆるものは移り変わる」ということを教える言葉です。大切なことは、「あらゆるものは移り変わる」と教える無常ということは、どれだけ世界や私の思いが移り変わっても、移り変わりません。「あらゆるものは移り変わる」ということは永遠にかわらない真理であり事実です。疑いようのない確かさをもっています。
私たちが桜の花の「はかなさ」に心を惹かれるのは、自分も同じように、「私のおもいにかかわらず 花は咲き 花は散る」いのちを生きているからであると思います。花も自分も移り変わるいのちを生きている。だからこそ、移り変わらないものに出遇いたいという欲求を私たちはもっていると思います。イギリスの経済学者シュマッハーは「人間が必要とするものは無限であり、その無限性は精神的領域においてのみ達成でき、物質的領域では決して達成できない」としるしています。私たちの内にある「移り変わらないもの」、無限への要求は、お金や、物など移り変わる有限な物では満たされることはありません。花が咲き散る事実に、自分の思いを入れれば「はやく」、「ながく」ということが出てきます。
私自身、今年咲き散る桜の花を見て、仏教に教えられている「あらゆるものは移り変わる」、無常という真理の言葉が改めてリアリティをもって感ぜられました。そして私たちがもとめているのは「移り変わらないもの」であるという思いを新たにしました。 深草誓弥 平成29年4月
無明とは何も分からないことではない、すべて分かったつもりでいる心のことだ 宮城 顗(しずか)師
車で運転中に道を間違えて迷子になることがあります。久しぶりに通る道で、昔の記憶と経験を頼りに進んで行ったら全く違う筋に入ってしまい、知らない別の場所に着いてしまった、という経験は皆さんにはないでしょうか。「道を間違った」と気がついたときにはもう既に遅く、かなり奥に進んでしまっていて自分がどこにいるのかも分かりません。迷子になった原因はただ一つ、「自分の記憶は正しい、自分は全て分かっている、自分は間違わない」という思い込みです。
迷っていることすら気が付いていない、迷っている自覚が無い状態の時が一番危険です。なぜならその様な人は他人の言葉にも耳を貸さずに、この道は正しいと自信満々で進んでいるのですから、たとえ「あなた迷っているよ」と他人から言われても、立ち止まったり、自分の道を振り返る事をしようとしません。自分の力のみを頼りにしていると、どんどん深い迷いへと堕ちてゆくばかりです。
「無明」とは、文字通り「明かりがない、真っ暗闇で何も見えない」ということですが、この言葉は仏教語で、人間の迷いのことを指します。仰ぐべき光(教え)が無く、ただ自分の経験と知識だけを頼りにして生きている人の姿を言い表し、「私は何でも分かっている、教えられなくても知っている」と思う心が、迷いの根っこになっていると教えられています。人間の知恵を最大の依り所にしている現代人の姿を鑑みると、この様な「分かっている、分かったつもり」の人が多いのではないでしょうか。
親鸞聖人は、『教行信証』の総序の文に「無碍の光明は無明の闇を破する慧日なり」(何ものにもさまたげられない阿弥陀の光明は、迷いの根源である無明の闇を破る、太陽そのものである。)と述べておられます。またご和讃の第一首目に「法身の光輪きわもなく、世の盲冥をてらすなり」とも讃歎されます。阿弥陀の智慧の光に遇うということは、私を照らす教えに遇うということです。自分では気がつかなかった心の闇の深さ、迷いの深さを知らされていくのだとこの言葉は語ります。
さらに展開していくと、迷い苦しむ我が身の事実を、誤魔化さずにしっかりと見つめることのできるの眼をいただくということなのです。その眼が開かれた時にはすでに、迷いが迷いで無くなっているのです。私が迷っていたと気が付いたときには、その境遇から離れようとします。そして迷っていることを自覚出来た人は、道を詳しく知る人に尋ねようとするはずです。道を知るその人のお言葉によって、進むべき正しい方向が決められていくのでしょう。
自分の知っている事以外は何も知りません。これは当たり前のようですが、私達はそこに気付いていないのかもしれません。だからこそ阿弥陀の光に遇う、教えに遇うご縁を大事にして生活しなければならないのです。 (貢清春)平成29年3月
過ちが人間を決めるのではなく 過ちの後が人間を決めるのです 東井義雄師
「いいことをした人(因)は、いい目にあう、善い人になる(果)」「過ちを犯した人(因)は、悪い目にあう、悪い人になる(果)」このように私たちは知らず知らず、「いいことをしたらいいことがおこる」と考えています。この考え方を善因善果、悪因悪果といいますが、仏道の因果の教えではありません。しかし、私自身この考えに染まっていることを感じます。
とくに子供に接しているときに「ちゃんとしとったら、いいことあるよ」とか、「悪いことする子は、嫌な目にあうよ」という言葉で出てきます。良いことをしたらほめられて、賞が与えられます。悪いことをすると怒られて罰が与えられます。私たちの世間を支えている善悪の原理です。しかし、よくよく考えなければならないのは、善いことをしても、善い結果がついてくるとは限りません。善いことをして、善い結果が付いてくるのは、善い縁に巡り合ったからです。
この世のことを仏教では娑婆(しゃば)と教えています。これはインドのサハーという言葉の音を写した言葉で、意味を取って訳をされたものは堪忍土(かんにんど)とよばれます。意味は「耐え忍ばないといけない世界、思うようにならない世界」です。善いことをしたら、善いことが起こるという世界でなくて、なんでも起こってくるのがこの世界だと、この世を言い当てた言葉です。ですから何が起こってくるかは誰にもわからないのです。
例えば、ひとたび自然災害が起これば、善いことをしようと心がける人、何にも思っていない人。信仰をもっている人、いない人、祈願していた人、していない人、平等に被災します。厳しいことですが、何が起こってくるかわからないという状況は変えられません。そして、その何が起こってくるかわからない世界と同じで、状況次第で私の心も何が飛び出してくるかわかりません。
例えば、どちらかが避けないと通れない狭い道に車で入っていって、対向車が自分よりも先に避けてくれると、「申し訳ない」「ありがとう」という気持ちが起きますが、逆に避けるそぶりもなく、こちらに来ると腹が立ってきて、絶対に譲りたくないような心が出てきます。私たちは状況次第、出遇った物事で行動がかわります。善いことをしようと思って善いことをする、悪いことをしようと思って悪いことするのではなくて、状況、縁に随うのです。
今月の言葉の、前半にある「過ちが人間を決める」という言葉の裏には、「気を付けてさえいれば、人間は過ちを犯さずに生きれる。過ちを犯す人間は、日ごろのこころがけがなっていなかった」という人間観、世界観があるのでしょう。
仏教は「因はこれ善悪、果はこれ無記」と教えられます。起こってきた結果は、苦楽であって、善でもないし悪でもない。私たち一人一人がその起こってきたことをどう受け止めるかを問題にします。例えば、人を傷つけてしまったという過ちを、罪悪感、苦として受け止めるならば、そのことを恥じるがゆえに、その何が飛び出してくるかわからない私のこころを照らし出す、仏法に教えられていこうという歩みがはじまることになるでしょう。
消してしまいたい過去の過ちも、そのことが自分を大切なことに目覚めさせる出来事に変えていくかどうかは、私たちがそのことをどう受け取るかで決まるのだと思います。 (深草誓弥) 平成29年2月
○歎異の会(歎異抄を学ぶ会)
日時 2月27日(月) 20:00~
学習箇所 第15条を学びます
○法音の会(仏教讃歌を歌う会)
日時 2月9日(木) 19:30~
場所 福浄寺本堂
○仏教青年会
日時 2月16日(木) 19:30~
場所 福浄寺門徒会館
○日曜学校
日時 2月4日(土) 9:00~10:00
2月19日(日) 9:00~10:00
「聞」 耳を澄ませて 自らの深い ところに在る 声を聞く
我が家では、夕飯の時はテレビは付けずに音楽を流すようにしています。クラシックやリラックスミュージック、自分が若いときに聞いたバンドや時には演歌など、子供達の反応も様々です。いつの間にか子供がビートルズを口ずさんでいたり、自分が生まれる前の曲『上を向いて歩こう(坂本九)』を流したら「なんだか懐かしい曲」と言い、親をびっくりさせたりもします。
しかし食事の時の音楽は文字通り曲を流しているので、心を傾けて集中して聞いてはいません。食事が主で音楽はバックミュージックの程度なので、流れている曲の作り手のメッセージや歌詞を味わうことも無いと思います。
これと同様に、他人の声を聞くためには、相手に心を傾け、耳を澄まし、黙して聞かなければ聞こえてこないのかもしれません。しかし現代社会は、様々な声に「耳を澄ませる時間」が少ない様に思います。耳を澄ませ聞くという以前に自己主張が多く、話が饒舌で、大声で喋り、他人が話をしている最中でも割って入るような人が多くはないでしょうか。テレビで放映される政治家の討論番組を見ると、顕著にその姿を見ることが出来ます。
朝日新聞に鷲田清一氏のコラム「折々のことば」があります。今年1月1日の言葉が次の言葉でした。
「Happy New Ears 今年こそ耳の人になろう。長く圧し殺されてきた声、出かけては呑み込まれた声、ぼそっと漏らされた短すぎる声、恐る恐る絞り出されたくぐもった声、今にも途切れそうな声。それらにじっと耳を傾けられる人に。「聡明」には耳がある。「省庁(廳『ちょう』)」にも。そこは天の声、民の語を聴く場所だった。その声を最もよく聴く人が「聖」。」
私達は耳を持っていますが、「今年こそ耳の人になろう」という鷲田氏の言葉は、「私は今まで、聞くことをおろそかにしていた、他者の声を本当に聞いていなかった」という嘆きや悲しみが感じられます。そしてもう一つは、自分自身の深いところにある真実の欲求に耳を澄ませたい、私の本当の願いは何だろうか、そういう意味も含まれているようにも思われます。
明治の親鸞と言われた清沢満之(きよざわ まんし)という方は、「人心の至奥より出づる至盛の要求の為に宗教あるなり」という言葉を残されました。人の心の一番奥から突き上げてくる、最も盛んな要求に応えるために宗教があるのだと言われています。
お念仏は、私達の日常で思う表面的な要求には応えてはくれません。何度お念仏を称えても腹はふくれませんし、お金持ちになるわけではありません。病気も治してはくれません。念仏は自分の思いを叶える道具ではなく、私の中の最も深い要求に応えて下さるのだと言われます。
本当に私が求めているものは何なのだろうか、何のために生まれて何のために生きるのだろうかという、人間の深い願いを聞く身に育てられなければ、どんなにお金持ちになっても、どれだけ長く生きても人生が不安のまま、空しく過ぎてしまうのです。
「ただ、仏法は聴聞にきわまる」と蓮如上人は仰います。「聴」はしっかり耳をそばだててきくという意味、「聞」は自然ときこえてくる、ひびいてくるという意味だと言われます。他の人の声も、自分自身の深い声にも心を傾けて、今年こそは「聞く人、耳の人」でありたいと、私も感じました。 (貢 清春) 平成29年1月
念仏というのは、心を仏様の世界と、つなぐこと。
坂東性純
今月の掲示板の言葉を読んで、私のなかで蓮如上人の「機法一体の南無阿弥陀仏」という言葉が思い起こされました。南無阿弥陀仏の南無はサンスクリット語のナマスの音をうつしたものです。意味は敬うとか帰依をあらわします。
機とは様々な縁に遇うと発動する私たちの可能性です。ですから南無は「帰依したてまつる」、私たちが阿弥陀仏のはたらきに遇い、反応するすがたをあらわします。
法は阿弥陀仏が私たちをすくうはたらきをあらわします。阿弥陀仏、阿弥陀如来ともいいあらわしますが、「如来」の「如」は「真実」という意味です。真実を覚られたのが仏(ブッタ 目覚めた者の意)ですが、仏は覚りに留まることなく、真実に気づかない、本当の満足を知らない「迷い」の状態にある私たちに、「真実」を知らせようと、はたらきかけて来てくださいます。その「はたらき」を「如」(真実)から「来」てくださった方と表現します。
しばらく前に私がきいたエピソードです。長年聞法生活をされてきたおばあさんに、息子さんが「なんで念仏する必要があるんや、念仏したって食えんじゃないか」と言われたそうです。おばあさんはその場で反論できなくて、一晩悩まれた。そして翌日このようにおっしゃったそうです。「念仏では食えんかもしれんが、念仏せんと食べたもんが無駄になるぞ」 息子さんがいっておられる「念仏では食えん」というのは、役に立つか立たないか。損か得か。常に私にとって便利かそうでないか。人間のものさしの立場からの言葉です。自分に都合のいいことならする、都合の悪いことならしない。その奥には「自分はなすべきことはわかっている。必要か必要でないかも判断できる。自分のことは自分が一番よく知っている。」というような、「わかっている」自分がいます。仏教で私たちのなかにある煩悩を「無明」と教えていますが、これは迷っている自覚が全くない、迷っていることに気づかない状態をあらわします。迷っている自覚のない迷いです。
逆に迷ったという自覚があれば、誰でもすぐに道を探しはじめます。人に聞いたり、地図を見たりします。求道は迷いの自覚からはじまりますが、無明はそういう自覚がない。自分が行くべき道をよく知っている、そういう迷い方です。しかし、果たして私たちは自分のなすべきことが本当に分かっているのでしょうか。
そのような息子さんの立場に対して、おばあさんは「念仏せんと食べたもんが無駄になるぞ」といわれたのです。おばあさんは、長年仏法を聞いてこられたそうです。掲示板の言葉にあるように「仏様の世界」からの呼びかけを聞いてこられたのでしょう。その聞法の歩みを支えているのは、仏法に遇って、「わかっている」自分の愚かさを知っておられるからだと思います。「仏様からの呼びかけを聞かないまま、ただ食べて生きとったら、空しく終わってしまうし、自分の生を支えている無数のいのちも無駄にしてしまうぞ。」私は想像します。おばあさんが、「汝、愚かなるものよ」という呼びかけを聞き、その呼びかけに頷いて「ナンマンダブツ」と念仏申されている姿を。 (深草誓弥)
日曜学校生徒皆様
福浄寺、門徒報恩講参詣のご案内
前略 皆様におかれましては日頃、日曜学校の会の運営にご協力、ご理解頂きお礼を申し上げます。この度、日曜学校のみんなと一緒にお寺の行事としてつとめられる門徒報恩講に参詣いたします。
親鸞聖人のご命日をご縁にしておつとめされる集まりが報恩講です。親鸞さまは「南無阿弥陀仏」の教えを、正信偈や和讃という「うた」で残して下さり、そのおみのりによって、たくさんの人が生きる喜びをいただいておられます。その親鸞聖人のご恩に感謝する、一年の中で一番大切な仏事が報恩講です。
今年は川原、石木地区の方と一緒にお参りします。ご参加頂きます様、よろしくお願いします。
記
・日時 平成28年 12月11日(日)
10時~12時半まで
・日程 10:00 おつとめ
10:40 仏様のお話
12:00 お斎、お昼ごはん
(精進料理)
12:30 解散
・持ってくるもの
・お米1人1合 ・おさいせん100円
・筆記用具 ・色えんぴつ
・他、いつも日曜学校に持ってくるものを持って来て下さい。
・ゲームやマンガ本は持って来ないでください。
今年も愈々師走になります。
就きましては、一月の御正忌報恩講から始まり、また本年の最後のしめくくりの法要、「門徒報恩講」を例年の如く下記により勤めさせて頂きます。皆様、宗祖親鸞聖人の御恩徳を憶い、報恩感謝の志をお運び下さい。そして各地区仕出し当番の皆様の、昨今では中々味わえない手作りの精進お斎をいただいて下さい。皆様のお繰り合わせの御参詣を念じます。尚、参詣日は一応の目安です。都合の付かれる日でもかまいません。
当日の勤行は正信偈三首引きでつとめます。御和讃は、赤表紙の勤行本五六頁「三朝浄土の大師等」からの三首です。ご一緒にご唱和下さい。
日程 勤行は午前十時からです。
十二月十日 木場講 (上、下)
十一日 川原、石木講(上、中、下)日校参加
十二日 音琴講(口木田、大音琴、小音琴、彼杵)
十三日 西講ノ上(波佐見、中山、刎田、岡谷、川良、野口)
十四日 西講ノ中(中組、宿、岩立、上百津、下百津)
十五日 西講ノ下(栄町、城山、数石、新百津、山手、旭ヶ丘、若草)
十六日 西講ノ西(下組、平島、琴見ヶ丘、白石、三越、小串、惣津、新谷)
十七日 五反田(上、下)、猪乗講 及び町外
以上
ない ないと 数えはじめると 渇いてくる
ある あると 数えはじめると 満たされてくる
「自分はどっちの立場で生きているだろうか」と考えさせられました。置かれている状況は同じで何も変わりませんが、自分にある、何を、どう数えるのかで人生の受け止め方が180度変わることを教えられます。
この言葉で、はっと思い出した人がいました。それは鈴木章子(あやこ)さんです。この方は北海道斜里町、真宗大谷派西念寺の坊守さんで、49歳という若さで癌で亡くなられたお方です。その病床生活の中で沢山の詩を残しておられます。
「よく新聞などで有名人がガンで亡くなると、「ガンに負けた」といいますが、死が負けであるなら、生きとし生けるものすべて敗者であろうかと思います。私は肺一葉切りとることにより、元気な頃よりも自分の体を自覚し、「手もあった!足もあった!あれもこれもあった!あった!」と、思いもかけずありあまる程の沢山のものをいただくことができました。また、ガンという病気のおかげで、死をみつめなおし、過去46年間の生命をもう一度生きることができました。」 『癌告知のあとで』 探求社
身を痛めつけるガンによって肺の片方を無くしたにも関わらず、今自分にあるものに目覚めて生きられました。「あれもこれもあった!あった!」と、「ありあまる程の沢山のもの」を見つめていかれた鈴木章子さんの言葉からは、今現に生きている喜びと、いのちの躍動感が感じられます。また『変換』という詩には
「・・・今ゼロであって 当然の私が 今生きている ひき算から 足し算の変換・・・」
という言葉もあります。健康な時には気にもしなかった生きていることの喜びと、そして大いなる阿弥陀の働きをを実感し、その「おかげ」によって生かされてあることに気付かれたお方です。ガンに冒されながらも、その病をこの様に味わうことが出来るのかと驚くばかりです。
私自身の生活は、「あれがない、これがない」と、自分にないものを見つけては、「あれがほしい、これがほしい」と不足ばかりを言っています。他者に対しても同じ様に、あなたにはこれが足りない、あれが足りないと催促ばかりをしています。そういう姿を仏教では「貪欲」と教えられ、また「渇愛」とも言います。のどが渇いて水を求めるように、自分にないものをどこまでも求め、執着する心の状態です。この貪欲のこころは、求めていたものを手に入れたとしても飽きることがなく、また別のものが欲しくなります。手に入れた一時的な満足感は次のものを追い求める原動力になり、全てを手に入れたとしても心の底から満足することはありません。今月の言葉の様に「ない、ない」と数えている私の心は、いつまでたっても満たされず常に渇いています。
それでは、自分に満足する為にはどうすれば良いでしょうか。仏陀には「自在人・満足大悲の人」という別名があります。どの様な境遇にあっても自らがここに在りと、自分が自分であることが出来、この身に一切の不平不満がない人のことです。そして他の人に、この満足する世界を共に生きようと勧めてくださる人であり、今あるものに気付いて生きていきなさいと呼びかけておられる方が仏陀なのです。
私達は仏陀のように、心の底から満足する生活をしたいと願って生きています。しかしどうすれば満足できるかが分からず、とりあえず日頃の心を満足させようと走り回っています。でもそんなにあっちこっち外に向かって走り回らなくても、いただいている大事なものがあなたの中にあるんじゃないですかと、今月の言葉から問われているようです。
(貢 清春) H28 11月
因を外に求める限り 苦悩は無くならない
人間とは 自ら苦悩を 生み出す生き物 (平成28年10月)
「人間とは何か」を定義する言葉として、1735年にスウェーデンの植物学者リンネは「ホモ・サピエンス」という学名を与えました。「ホモ」は「人」という意味、「サピエンス」は「知恵のある」という意味です。ですから「人間とは何か」という問いに対して、「知恵あるがゆえに人間である」という回答が挙げられたことになります。
「知恵の人」、確かに人間は自分を知り、他者を知り、事柄を知り、そしてそれらに関わることを知識として蓄え、そしてより良い方向へ改善をはかる知恵を持つのですが、この人間観は一面的であるように思います。人間はその知恵をもって、何ものにも縛られないような状態を求めてきました。科学、医学などの発展はそれを象徴しています。しかし、本当に何ものにも縛られないという自由は実現できませんでした。逆に知恵によって我々が生きていけなくなるようなことも起こっています。人間の「英知」を結集し、「クリーンエネルギー」をうたった原発は、先の震災によって福島に住む人たちの故郷を奪いました。
掲示板の言葉にあるように、人間は自分の外に自分を束縛したり、悩ませたりする「原因」があり、それを取り除いて自由になろうとします。外に自分を妨げる不都合なものがあり、それを都合のいいように、妨げのないようにととのえていこうということで、たしかに科学技術は発展して、不都合は少なくなってきたかに見えますが、無くならないのです。なぜでしょうか。
「人間とは何か」を定義する語として、もう一つの言葉があります。それは「ホモ・パティエンス」「苦悩の存在としての人間」という言葉です。ユダヤ人精神医学者ヴィクトル・フランクルが提唱した用語ですが、この言葉が掲示板の「人間とは自ら苦悩を生み出す生き物」と重なります。「人間の本質は苦悩である」とするこの言葉は、生きている限り、ものを思うということがある限り、苦しみ、悩み以外にありようを持たないという目線で人間を見つめています。
人間は外に自分を縛るいろいろのものがあるとし、それを取り除こうとしてきましたが、なおいっそう「こうでなければならない」という自分のこころに縛られているのではないでしょうか。苦しみ、悩ませる外のものをなくせば、苦悩は無くなると思い込んでいますが、そんなことはありません。憎く、恨めしい人が自分の前からいなくならないことはつらいですが、根っこにある問題は、憎み、恨む自分のこころの始末がつかないことです。
苦悩はどこからおこってくるか。仏教はその原因を私たちの内にある執着(「こうでなければならない」という思い)と見定めました。苦悩の現実を見つめ、解脱した仏陀釈尊は、苦悩をとおして、より深い願いに目覚める道を明らかにされたのです。苦悩させる外なるものの問題ではなく、苦悩の存在として生きるしかない自分を受け止めていく願いが見いだせないことが問題だったのです。「如来の作願をたずぬれば 苦悩の有情をすてずして 回向を首としたまいて 大悲心をば成就せり」(聖典五〇三頁)と、如来の大悲本願のこころをあきらかにされた親鸞聖人も、人間を「苦悩の有情」と見つめられています。 (深草誓弥)
行き先が分かれば 行き方が分かる
往き先が分かれば 生き方が分かる (仏光寺)
「いきさきがわかれば、いきかたがわかる」上段、下段、どちらも読み方は同じですが、使われる漢字が違うために表現されていることが少々違います。
「行く」という「行」の字は、十字路をかたどった象形文字で、道の事を表現します。「行き先が分かれば、行き方が分かる」という事は、例えれば、体の調子が悪かったら、病院へ行こうとします。病院という行き先が決まれば、いつ行こうか、どの道を行こうか、歩いて行こうか、車で行こうか等々、日々の生活の中で考えながら決断し、行動に移しています。今月の言葉の通り、行き先(目的地)が分かれば、行き方(どの道路を行くか)が分かります。
次の往く先の「往」の字は、「むかし」「いにしえ」「いま」「むかう」「のち」「それからあと」という様々な意味があります。これは、過去・未来・現在の三世の歩みを表す言葉です。私達がどこから来て、どこにいて、どこに向かうのかという、人生の往く道を表現します。
人間が心の底から求めるその往き先を、お釈迦様は彼岸の浄土であると明らかにされました。彼岸とは読んで字の如く「彼の岸」、向こう岸の世界を表します。此の岸は娑婆世界で、人間の煩悩に汚された穢土であります。この土が照らされ、彼岸の浄土に心をかけていこうという願いから、全国の寺院で彼岸の法要を営みます。また、お中日には真西に太陽が沈みます。その西方が人生の帰着点、帰る世界なのだと日没の太陽を拝んでこられました。
私達の往く方向が「浄土」と定まり、人生の意味がはっきりしてくれば、今からの生き方がはっきりしてくる。そういう言葉が今月の言葉です。しかし、人生の往き先が分からない為に、生き方を見失うということがあります。
古代ローマ時代、囚人の刑罰に、穴を掘っては埋めて、埋めたらまた掘るという作業があったそうです。この刑罰は体力を消耗し、精神的にも大きな苦痛をともない、気が狂ってしまう囚人もいたそうです。目的がない作業はやる気を失い、生きる力をなくし空しさしかありません。
葬儀の場での弔辞で、「冥土、草葉の陰、冥福を祈る」等の言葉を読まれるときがあります。「冥土」とは、薄暗くてよく分からない世界という意味で、その暗い世界で幸せになってね、というのが「冥福を祈る」という意味であります。冥土と呼ばれる暗い世界が、人生の往くべき世界であるならば、人生そのものも暗いとしか言いようがありません。
仏は私達に「浄土」という往き先がある、我が国である浄土へ帰ってこいと阿弥陀如来は呼びかけておられます。そしてこの「往く先・浄土」への道は、自分で発見して切り開いていく必要がない道です。親鸞聖人も往かれた道であり、先祖の方々もたどった道でもあります。諸仏方は、ただ念仏を称えながら、彼岸の浄土からの呼びかけに応え歩まれて往かれました。そして私達も同じ道を歩ませてもらえばいいわけです。その先達の後ろ姿をじっと見つめながら、唯々安心の中で念仏申す生活をしてまいりたいものです。 (貢清春)平成28年9月
秋季彼岸会法要の御案内
足でけとばしていたものを
あら勿(もつ)体(たい)なやと頂ける世界を
浄土という
春の気配は大地からうごき、秋の気配は空と、風と、雲とからしのびよる。今年も秋の彼岸がきます。彼岸とは浄土をさし、極楽の世界をいいます。私達は極楽が有るか無いかを問題にします。極楽とは人間の一生を終るところにあって仏様からあたえられる最後の落ちつく場所です。帰って行ける故郷です。
それは人生の終りにあるところにおいて、実は人生のよりどころであります。私の生きていく、よって立つ地盤であります。真実の人生は、その上にはじめて成り立つのです。
終りとなるところが実は出発点であります。浄土を思うとき人生がわかり、私の一生の終るところにかぎりなく極楽浄土が慕(した)わしいのです。そのことを知ることのできたのが仏の本願の念仏と言われます。
齢をとった人が、お浄土へまいらさせて頂きますと、往生浄土をよろこぶ。そのことを若い人達は嘲笑(ちようしよう)してはならないと思います。そこには限りない人生への深さが、しみじみとくみとることができます。 (伊那教雄)
拝啓 皆様ご健勝にお過ごしのことと拝察いたします。さて、今年もお彼岸の時期となりました。毎年この時期になりますとお墓参りが恒例ですが、彼岸を単なる通過儀礼として過ごすのでなく、亡き人を通して、自分自身の生き方を見つめなおす大事な御縁としていきたいものです。秋の彼岸会法要を下記の如く厳修致します。何卒、有縁の皆様をお誘い合わせの上、御参詣下さり、聞法の御縁にお遇い下さいませ。合掌
記
日時 平成28年 9月19日~25日の七日間 午前九時半開筵
講師 三重県 正寶寺住職 藤本愛吉師 (23日~25日)
住職・寺中 (19日~22日)
かれあれば これあり 子あれば 親あり
亡き人あれば 生者あり 私だけでは 存在しない
2006年、京都の大谷専修学院の学院長を務められていた竹中智秀先生が還浄されました。おりに触れて先生がおっしゃっておられた言葉が思い起こされてきますが、今回の掲示板の言葉を見て、「個人は幻想ですよ」と語っておられたことを思い起こしました。この個人というのは、自分を中心に据えて生きているもののことを教えられています。
私たちは、日ごろ自分というものがまずこちら側にあって、その自分のむこう側に世界があり、そこに他の人々が居て、そこでいろいろな物事が起こっているし、また、ときには、むこう側に自分の人生をおいて思い通りになっているかどうかと眺めています。このような「自分というものがまずそれだけで在って、それから自分の生活が始まると思っている」私たちのあり方を竹中先生は「幻想ですよ」とおっしゃられたのだと思いますし、今月の掲示板にある「かれ(彼)あれば これ(此)あり」とは、世界(彼)と自分(此)を切り離して、自分だけが単独で存在しているのではない、ということを教えてある言葉です。そのことを次の言葉では「子あれば 親あり」、子供が誕生することが、親が誕生するときであるという言葉でさらに開いてあります。
そのあとには、「亡き人あれば 生者あり」という言葉が続きます。これはどういう言葉でしょうか。私たちは様々な形で死にふれます。新聞やテレビで縁が遠い人の死にふれたり、親しく縁を結んだ人の死にふれることもあります。そこでの死へのまなざしはどうなっているかと問えば、やはり自分とわけ隔てた他者の死として映っているのでないでしょうか。「自分は生者 あの人は死者」というまなざしです。このことを問うのが「亡き人あれば 生者あり」という言葉でしょう。
蓮如上人の『御文』のなかに「疫癘の御文」とよばれているものがありますが、このようなことが語られています。「近ごろ、伝染病がはやって人が亡くなっていっている。だが、それは伝染病のせいで亡くなったのではない。死は生まれたことによって当然おこりうることだ。だからそんなにおどろくことはないのだ」それに続けて、「だがこんなときに亡くなれば、やはり伝染病のせいで亡くなったと皆思う。それももっともなことだ」と。
この『御文』に教えられることは、私たちが普段考えている「死因」はあくまで、死の縁であり、その縁、条件は無量無数で、「あの時こうしていれば」というような自己中心的な思い、計算が間に合わないものだということでしょう。そして本当の死の因は「生まれたこと」であるということです。「死は生まれて生きるものの身の上に必ず起こってくることである」このことを私たちは葬儀というかたちで、その道理をその身でもって教え、若くても年老いてもその人生を全うした人として大事に思い、その人を敬ってきたのだと思います。
残された私たちは、亡き人から、生きている私たちも、いつ死が訪れるかわからない身であることを知らされます。だからこそ、この世に生を受けた意味を明らかにしようという意欲が呼び起こされるのでないでしょうか。死者から、死と生は一枚の紙の裏表であると教えてもらった、その大きなまなざしのなかに生きるとき、本当に生きるという歩みがはじまってきます。
深草誓弥
日曜学校夏の集い
-- 夏休みの作品にぴったり 陶芸制作 --
今年の夏の集いは、陶芸制作を計画しています。陶器は生地作りから絵付けまで一日で出来ないために、2日間の制作を予定しています。原則、両日の参加が前提ですが、どちらか一日しか参加できない場合でも、作品が出来るように計画しています。指導は小串「肥前信窯」の吉崎昭信先生にお願いしております。2日目、絵付けをした後には桂米朝氏の「地獄八景亡者戯」という落語映像を観る予定です。とても楽しい落語です。どうぞご参加いただきます様、ご案内申し上げます。
●1日目 陶器の生地制作 (粘土でマグカップやお皿他、自由に制作します)
・日時:8月19日(金) 午後1時30分集合~4時解散(送迎をします)
・持参品:お勤め本、念珠、筆記用具、水筒、アルミの空き缶1個、中古歯ブラシ
●2日目 陶器の絵付け制作 (素焼きした生地に、絵の具で絵付けをします)
・日時:8月27日(土) 午後3時集合~6時40分解散(送りはしません)
・持参品:お勤め本、念珠、筆記用具、水筒、水彩絵の具、野菜(ジャガイモ、
にんじん各1つ)、お米(1人1合・参加されるご家族の分も持たせて下さい)
2日目 日程 午後~(お迎えに来ます)
3:00 集合 勤行
3:30 制作開始
4:30 制作終了~片付け
5:00 映写会(落語)*保護者の方、家族の方もご一緒にご参加下さい。
6:00 夕食 *家族の方も一緒に食べましょう。門徒会館で食べます。
6:40 解散 (送りはしません)
*絵付けした陶器は、次の日に本焼きをしてもらいます。出来上がった陶器は8月29日以降、夏休み中に寺に取りに来て下さい。
◎陶芸材料費:500円 *参加日当日にご持参下さい。陶芸をするための材料費です。
後から参加される家族の方の分は徴収しません。
◎申込み:8月12日までに参加の申し込みを、電話またはメールにてお願いします。
*保護者、ご家族の皆様の参加人数もお知らせ下さい。
連絡先 ・電話 82-2154
*2日目、夕方5時からの映写会・夕食には、保護者、家族の皆様もご一緒にご参加下さい。お子様と一緒に解散となります。終了後の送迎はしません。
「どこかに必ず光がある」
『遺愛集』という尊い歌集を遺している島秋人さんは、小、中学校を通じて成績がたいへん悪く、みんなからバカにされ、無視され、だんだん心が荒み、少年院に送られたこともある。ある雨の夜、飢えに耐えかねて一軒の農家に押し入り、二千円を奪い、そのとき、そこの家の人と争い、奥さんを殺し死刑囚となり既に処刑された。
死刑囚として獄中で、小・中学校時代ただ一度、中学校の絵の先生が「絵は下手だが構図は君のが一番いい」といわれたことが思い出され、懐しくなり、獄中から先生に手紙を出した。
先生からの返事に先生の奥さんの短歌が書き添えられていた。それを読んで、自分も歌が詠みたくなって、歌が生まれはじめた。島さんにも、尊い光があったのだ。
助からぬ生命と思えば一日の 小さなよろこび大切にせむ
安らかに笑みて受くべし殺めたる 罰受くる日のいつに来るとも
愛にうえし死刑囚われのたまわりし 菓子地におきて蟻を待ちたり
世のためになりて死にたし死刑囚の 眼はもらい手もなきかもしれぬ
人間にくずはない
人生にむだはない
(東井義雄)
八月の婦人会法筵は、講師に崎戸の真蓮寺御住職、寺本温師をお招きしまして、『仏説観無量寿経』について御法話をいただきます。尚、この法筵は、婦人会主催の法筵であり、会員皆様に限りませんので、御門徒皆様もお誘い合わせの上、御参詣くださいませ。
記
婦人会法筵
日時 8月6日(土)より8月7日(日)まで2日間 午前9時半開筵
法話 崎戸・真蓮寺住職 寺本 温師
盂蘭盆会法筵 日時 8月16日(火) 午前9時半開筵
納骨堂盆読経 日時 8月13日~16日の、午後6時
いのちは大事だと言う人は多い だが いのちを粗末にしていると気づく人は少ない
今月は作上がり法要のご縁が勤まりました。この法要は、田植えの稲作が一段落した後に勤まる法要です。自然(しぜん)のいとなみに目を向け、そのいのちによって生かされてきたことを感じ、それを人間の思いや計らいを超えた世界、自然(じねん)なる阿弥陀のはたらきとして受け止めてきた先達の方々が、作上がり法要という仏縁にして伝統されてきました。「いのちを考えるひと時」として大事に勤めていかなければならないと感じさせられます。
今月の言葉は、私達が日常生活の中で「いのち」とどう向き合っているかが問われています。「いのちは尊いのだ、大事にしなさい」と言う人は確かに多いです。昨今の無差別殺人や、爆弾テロなどの事件が起こる度に、この言葉は様々なところで叫ばれています。しかしよくよく考えてみると、実生活の私自身の姿は棚に上げて、言葉だけのきれい事で終わらせているように思います。そして実際は、自分自身がいのちを粗末にしている事には気づかないまま、生活しているのかもしれません。
お釈迦様のあるお弟子の話を通して、今月の言葉を考えてみたいと思います。
お釈迦様の弟子で、物やいのちを粗末にする人がありました。美しい服もすぐにクシャクシャにしたり、ごはんをいただいても、必ずお茶碗にごはんつぶを残したまま、放っておくようなお弟子でした。それを見かねたお釈迦様は、そのお弟子の服を全部脱がして町を歩かせます。町の人から笑われ、恥ずかしい目に会い、そのお弟子はお釈迦様に「どうか着物をお返し下さい」とお願いします。その時お釈迦様がお渡ししたのは、一束の綿の花でした。「これで着物を作りなさい」とおっしゃるのです。いくらお釈迦様からのおおせでも、お弟子にはその意味が分かりません。「魔法使いではありませんから、とても綿から着物は作れません」というお弟子に対して、着物を作る人のご苦労や出来るまでの行程、お米が出来るまでのお百姓さん達のご恩を、お釈迦様は丁寧にお話しされたそうです。「いろんな人のお陰を受けていることを忘れてはならない。いただいているご恩を忘れ、物やいのちを粗末にしてはいけません」とお戒められた、という話です。
考えてみると、私もこのお弟子と同じで、他の人々の御苦労をわすれ、全ての物やいのちを我が物顔にして生きている様な気がします。自分の手に入れば自分の物で、背景やお陰を感じる力が無く、「あってあたりまえ」の生活で「お陰さま」を感じるような生活をしていないのではないかと反省させられます。
以前紹介した、「いのちのまつり・ヌチヌグスージ」という絵本の作者、草場一壽さんの言葉にも、
時空を超えてつながっている「いのち」は目には見えません。
それを支えてくれている「おかげさま」も目には見えません。
見えないものを感じる力を育まなければ、
なぜ「いのち」が大切なのかも感じられないと思うのです。
とありました。この絵本は、先祖のお墓参りに来た子供が、先祖から受け継がれて来たいのちのつながりを、おばあちゃんから教えてもらうという話です。目には見えない多くのいのちに支えられ、恩恵を受けているのだということを子供達と一所に考えていける絵本です。
「見えないものを感じる力」とは、いのちに対する想像力や、そのものの背景を感じる感覚であります。逆にいのちを粗末にしてしまうということは、この感覚が欠如しているのが原因だとも教えられます。しかし、いのちを粗末にしている現実の姿を見つめればこそ、いのちを大事に、大切にしなければならないこころも生まれて来ます。
「作上がり」のこの時期、我が身の生活を振り返り、いのちをおろそかにしていないか、大事にしているのかを、もう一度点検してみたいと思います。 (貢 清春)
日曜学校バス遠足の案内
前略 皆様におかれましてはご健勝にお過ごしの事と拝察致します。また常日頃、日曜学校の会の運営にご協力、ご理解頂きお礼を申し上げます。
この度、日曜学校でバス遠足を計画しました。今年は隣町佐世保の正蓮寺様を訪ねます。みんなでたのしく勉強になる一日を過ごしたいと思います。
◎日 時 平成28年7月18日(月)海の日
9時 福浄寺集合
(いつもの時間にお迎えに来ます)
◎行き先 ・正蓮寺(佐世保市城間町280番地)0956-59-2051
・長崎バイオパーク 0959-27-1090
◎参加費 1人500円
◎持参品 お勤め本、お数珠、お賽銭100円、お弁当、水筒、ぼうし、おやつ
*車酔いをする人は、酔い止めの薬を飲んで来て下さい。
*当日、お子様に持たせるお小遣いは、1000円までにして下さい。
◎申込み 申込書に学年氏名を記入し、参加費500円を添えて申し込み下さい。
7月10日(日)締め切り、受付は福浄寺です。
◎日 程
9:00 福浄寺集合、出発 (いつもの時間にお迎えに来ます)
9:30 正蓮寺着 (お勤めをしてお話を聞きます)
12:00 昼食(お弁当)
14:00 長崎バイオパーク
16:00 出発
17:00 福浄寺着予定 (帰りは自宅まで送ります)
申込み
平成28年7月18日の日曜学校バス遠足に参加します。
( 年生) 名前 (年齢 才)
( 年生) 名前 (年齢 才)
緊急時の連絡先 氏名 電話( )
*お子様の生活上の注意点、持病、車酔い等ありましたらお知らせ下さい。
あいにくの雨 めぐみの雨
自我の思いが ひとつの雨を ふたつに分ける
六月になり、梅雨の時期になりました。春が終わり、夏になる過程でめぐってくる雨季ですが、同じ雨でもそれぞれの思いを通してみると、見え方が違ってきます。子供と外に遊びに行こうと決めていた私が見る雨は「あいにくの雨」になりますし、稲作をなさる農家の人からすれば、この時期の梅雨が「めぐみの雨」と見えるはずです。お酒が好きな人には、暑い日に目の前にあるキンキンに冷えたビールがとても魅力的に感じても、お酒が飲めない人にはそう魅力を感じるものではないでしょうし、むしろ飲みたくないものに見えるかもしれません。
こういうことを仏教では、「一水四見」(いっすいしけん)の譬えでもって説明をします。つまり、一つの水が、その生き方、その境遇によって、四通りに見られる、というのです。水は、われわれ人間にとっては、文字どおり水ですが、菩薩は、これを瑠璃の大地と見る。魚は、住家と見る。そして、餓鬼は、この水でもって咽喉を焼く、つまり火と見ると教えます。
餓鬼というのは、いつもガツガツしているもの。いつも、なにかたりないものがあって、満足するということがないもの。これが餓鬼ですから、これは飲んでも飲んでも満足できないで身を傷つけていくことを教えてあるのかもしれません。
ともかく、同じ水でも、いろいろに見られるのです。干ばつで困って、雨乞いをすることがあるかと思えば、洪水にあって、水を呪うこともあるでしょう。水がなければ生きてはおれないけれども、ありすぎても生きていられません。あるとかないとか、多いとか少いとかと、自分が置かれた境遇、縁にしたがって、一喜一憂します。
人間は、ああだとか、こうだとかと、いろんなことに出会うたびに、いろんなことを思いますが、おもったようにやってくるとはかぎりません。だから、そこでまた、妄念・妄想を描いていきます。おもいのままにならぬ人生に対して、「こうだったら」、「こうなってほしい」と妄念・妄想をさらに重ねていきます。
大切なのは見ている対象は一つなのだということです。私たちの「おもい」は、そのときそのときの条件次第で、様々に変わっていくものです。見る方の境遇が変わると、その見方がちがってくる。見方がちがうものだから、見ている対象までちがっているように思っていますが、そうでないのです。「あいにくの雨」も「めぐみの雨」も「一つの雨」だといわれている掲示板の言葉で教えてあることは、自分に与えられたり、めぐってきた事を自分の思いを通してみて、しかもその目を疑わない「自我の思い」です。
おもえば、ひとつの出来事を自分の境遇や思いによってしか受け取れていないことには「せまさ」を感じます。自分が見て、受け取っている世界だけが絶対でない、不完全だということを知っているかどうかが、「せまさ」を知り、他の人と出会っていくための大きな分かれ目でないでしょうか。それぞれがそれぞれに重ねてきた経験や与えられた境遇、その時の思いで見えてくる世界は変わってくるということにうなずければ、ひとつの事柄からたくさんのことを知っていくことができると思います。 深草誓弥 平成28年6月の「今月の言葉」随想
老をきらい 病をおそれ 死をかくせば 生もかくれる
お釈迦様は、老病死する姿を目の当たりにして、出家を決意されたと伝えられています。「四門出遊」という物語です。「人は何故、苦悩が絶えないのだろう」と悩むお釈迦様に、父の王は気晴らしに外出をすすめられました。東の門から城外に出ようとした時には老人を、南の門では病人を、西の門では葬儀の列を見かけました。「私もいつかはあの様になるのだ、この苦しみはのがれることが出来ない」と、暗い気持ちで北の門から出ようとしたとき、一人の聖者に出遇います。老病死の苦悩から解脱を求め修行する、その気高き姿を見たお釈迦様は出家を決意され、お城を出て行かれます。仏説無量寿経では 「老・病・死を見て世の非常を悟る。国の財位を棄てて山に入りて道を学したまう。」と記されています。
お釈迦様にとって老病死は、避けては通れない身の現実として直視されました。老病死が他人事ではない、自分の課題として切実な問いとなったときに、人生の意味を訪ね求めていく歩みが始まるのだと、この四門出遊の物語は伝えているのだと思います。
私達もお釈迦様と変わらず同じ様に、老病死の現実の直中に生活しています。しかし今月の言葉のように「老をきらい 病をおそれ 死をかくす」姿が現実の日常の生活ではないでしょうか。
アンチエイジングがはやる現代、大金を費やしてまでも若く美しい人がもてはやされ、「健康のためなら死んでもいい」と笑い話にもなるほどの健康ブーム。マスメディアもはやしたてるように若さと健康を美化し、大衆もその情報に流されています。テレビCMのほとんどは、健康食品と美容薬品の宣伝ばかりです。
そして厳粛な葬儀の現場では、火葬場で済ます直葬が増え、ますます生活の場から死が遠のき、見えずらくなっています。若く健康で快適な生活を求めてきた私達は、生の事実である老病死を生活から切り離してしまいました。その結果、みんなが明るく生きやすい社会になったかというとそうではありません。大人も子供も老人も暗く孤独な人が増え、人生に不安を抱えている人が少なくありません。「終活」という言葉が象徴するように、死後のことも自分で手配しなければならず、誰かに任せて死んでいくことが出来ないのです。それは同時に、安心して生きることが出来ない姿を現しているように思います。
清沢満之先生は「生のみが我らにあらず、死もまた我らなり」という言葉を残しておられます。これは仏教の教えによって育てられた生命感覚であります。お釈迦様も出家の際に深く悩まれたように、人生において生も死も同時に私の中にあって、老病死していく身をどう生きていくかが、人生の大きな課題としてあります。
仏教教団は、葬儀を大切にお勤めしてきました。それは亡き人を供養し成仏させるためではなく、生きている私達が死んでいく身をどう生きていくかを、身近な人の死を縁にして仏法に訪ねて来られたのです。そして亡き先祖の方々は私達に向かって「老病死する身の事実を受け止めて、限りあるいのちを生ききって下さい」と願いをかけて下さっているのではないでしょうか。 (貢清春)
亡き人を なぐさめ しずめると 思っていた私が
亡き人に 養われ 願われていた
今月の掲示板の言葉は、生きている私たちと、先んじて命を終えていった亡き人との関係について問う言葉です。まず初めに「亡き人を なぐさめ しずめると 思っていた私」ということが述べられています。
「しずめる」といわれていることは鎮魂ということです。たとえば葬儀の際、亡くなった人が出ると塩をまいたり、出棺の時棺を回したり、火葬場の道を変えたりということがいわれますが、これが鎮魂儀礼ということです。しかし、「安らかにお眠りください」という鎮魂ということの裏には、縁ある人の死に際して悲しみながらも、自分に死、不幸、悪いことが来ないようにという人間の自己中心的な意識が隠れているように思います。
次に「なぐさめる」といわれていることですが、これは「慰霊」ということを指しているように思います。死者の霊魂の存在を認めることのない仏教に、死者の霊を慰める儀式はありません。しかし、人間は純粋なものではありません。生前の関係のなかでの思いが亡くなった人を「なぐさめる」ということを求めます。孝行ができなかった後ろめたさがあったり、亡き人に対して申し訳ないという思いがあったり、ことによっては「恨みを持って死んでいったのではないだろうか」と思われたりもします。そこから、のろい、たたりを恐れて、霊を慰め、冥福(死後の幸福)を祈るという慰霊ということがなされてきました。そして「しずめる」、「なぐさめる」ことが亡き人を供養することだと受け取られていますが、はたしてどうでしょうか。
本来、供養とは、「仏・法・僧の三宝、及び父母・師長に食物・衣類等を供給すること」をいいます。「仏・法・僧の三宝」は私たちに真の生まれた意義と生きる喜びを見出させてくださる人生の宝です。「父母」は私の大切な心身を養育してくださった親です。そして「師長」は教えを授けてくださった恩師です。私たちは供養ということで、私たちの心身を護持養育してくさった大切な宝や人々を敬い、尊ぶということを大切にしてきました。
私が供養について考えていく一つの道しるべにしている言葉があります。
供養とは 亡き人に心配かけない生き方を見つけることなんだ。そのために仏法を聞くんだ。心配かけない生き方とは一人一人が自立していくことなんだ。 藤元正樹
亡き人を供養するということは亡き人が残してくださった無言の問いかけをうけ、真の自己に目覚めることでないでしょうか。亡くなった人は単に亡くなったのではなくて、人生の最後の相を白骨になって見せてくださっています。そこには「あなた自身はいつ何時亡くなるか分からないけれども、いつ命終えても生まれてきて本当によかったといえる生き方を見つけていますか」という無言の問いかけがあるのです。
「亡き人に養われ願われていた」という言葉は、仏法を聴聞するなかで、亡き人と今を生きる私と共通の根本問題に目覚めたところに聞こえてくる言葉でないでしょうか。私達が求めているのは、なんでも思い通りにいく世界ではありません。どういう人生であれ、賜った人生を人のせいにしたり、何かがたたっているからといわないで、ひとりだちしていける道をこそ、求めているのです。 深草誓弥
浄土を願うということは この世の懺悔である 金子大栄
1年の年中行事で、3月と9月にはお彼岸があります。春分の日・秋分の日を中日として前後3日間、計7日間を彼岸として各仏教寺院では法要が勤まります。彼岸とは読んで字の如く彼の岸、向こう岸の世界のことを表します。自然現象の中で彼岸の中日に太陽が真西に沈むことから、古来真宗の寺院では西方の浄土に心を向け、浄土からの呼び声を聞き取るための聞法週間として大切にお勤めされてきました。
彼岸なる浄土とは、自分以上の世界、私の考えや思い以上の世界であります。その浄土の言葉、教えにふれることによって、此岸にいる人間の迷いを破る智慧と、私の本当の願いが教えられます。それは浄土に生まれたいと願う心が知らされるのです。
ではなぜ私達は浄土を願うのでしょうか。仏説阿弥陀経には西方の浄土を「倶会一処」する世界、倶に出遇う世界であると説かれます。浄土とは、他人に対して思う好き嫌いや利害を超えて、全ての人と出会える世界です。沢山の諸仏方が、その浄土の世界に「念仏して往生しましょう」と呼びかけ勧められています。
また、仏説無量寿経には地獄・餓鬼・畜生(三悪道)の無い世界であるとも誓われてあります。これは何を意味するのかというと、この娑婆世界は三悪道の世界を作り出し、それによって苦しんでいる私達が生活している。他人との出会いを拒んでいる私達の現実があるということです。
浄土の世界「倶会一処する世界・三悪道の無い世界」を求めるということは、逆にこの世の現実を見させられ、救われようのない身の事実に頷いていくこととなるのです。
その身を深く頷き、懺悔するということは、後悔したり反省することではありません。反省や後悔はまじめな心ですがその心の底には、「絶対にしないと思えばしなくてもすむ。しようと思えば絶対出来る。」という我が身への強い自負がひそんでいます。
懺悔とは「こんなことをしでかすような私です。」と、自身の罪を自覚し、私自身の存在をまるごと受け止めるということです。それは浄土を願い、仏の光に照らし出されているこの身を知らされることなのです。しかしどの様な人であっても、見捨てずに摂め取ってくださるのが、阿弥陀如来のはたらきであります。だからこそ私達は、阿弥陀の浄土を願うのでありましょう。
浄土とこの世、彼岸と此岸は孤立し対立した関係としてあるのでは無く、互いに関係し合っています。一つの同じ事ではないですが、別々ではない「不一不二」の関係です。浄土を願い求めるということと、この世の姿を見させてもらうということは、同時であります。
現代、お彼岸中は気候も良く、連休にもなるため、「レジャー彼岸」だと思われていますが、人間の深い願いに応え、自己を知らせていただく、「聞法週間の彼岸」と受け止めていきたいものです。 貢清春
春彼岸会法要の御案内
今年も春のお彼岸がやってまいりました。お彼岸のお中日には太陽が真西に沈みます。赤々と沈む入り日には、頭の下がる厳(おごそ)かな気持ちになるから不思議です。お聖教に「生死(しょうじ)の彼岸に度(ど)せんと欲(おも)わん者」(『真宗聖典』三八○頁)とありますように、私たちはみな、迷い多き世界を超えて、深く豊かな世界に出会わずにはおれない祈りにも似た願いを、心の奥底に抱えています。
彼岸とは、「生死の彼岸」とお説きくださいますように、この迷い多き世界に向かってその彼方から呼びかけてくださっている阿弥陀さまの本願の世界をいいます。私たちはその彼岸にふれることで、もつれ糸のもつれの原因、つまり無明・煩悩の身の事実が知らされ、解きほぐされ、新しい天地に生きる身を回復してまいります。
現代人の抱える最も深刻な問題は彼岸の喪失にあります。したがってそれは、照らされてある此岸の喪失でもあるのです。今こそあらためて、出会うべき世界を彼岸として見いだし、限りあるこの人生を限りなき阿弥陀のいのちを生きるものとして、深く豊かに全うしたいと願わずにはおれません。 (東本願寺版「彼岸」より)
春の彼岸会法要を左記の如く厳修致します。お彼岸を通して諸仏となられたご先祖を偲びつつ、聞法の御縁にお遇い下さいませ。 合掌
日時 平成28年 3月17日(木)~23日(水)までの七日間、午前九時半開筵
講師 姫路 名和 達宣師(19日~22日) 他、寺中
○歎異の会(歎異抄を学ぶ会)
日時 3月28日(月) 20:00~
学習箇所 第14条を学びます
○法音の会(仏教讃歌を歌う会)
日時 3月15日(火) 19:30~
場所 福浄寺本堂
○仏教青年会
日時 3月11日(金) 19:30~
場所 福浄寺門徒会館
テーマ 「葬式、法事の意味について」
○日曜学校
日時 3月6日(日) 9:00~10:00
3月27日(日) 9:00~10:00
春季永代経法要御案内
春の永代経法要を来る2月20日から2月24日まで5日間奉修致します。
永代無量の経教に依って御先祖の遺徳を偲びつつ、報恩の誠を尽くさんがための聞法の御縁にお遇い下さいますよう、何卒お繰り合わせ御参詣下さい。
下記の日程でおときの用意を致しておりますが、都合のつかれる日でも構いません。おときは1回に限らず何回でもお座り下さい。
記
日程 平成28年 2月20日~24日 午前9時半開筵
法話 波佐見町西圓寺住職 武宮 真紹師
20日・・・木場、川原、石木
21日・・・大音琴、小音琴、口木田、数石、新百津、若草、旭ヶ丘、山手、東彼杵町
22日・・・中山、上組、野口、中組、宿、岩立
23日・・・下組、白石、小串、惣津、三越、上・下百津、栄町、城山、琴見ヶ丘
24日・・・五反田、猪乗、波佐見、その他の町外
生かされているということは 結論ではなく 出発点である
池田勇諦
人間はおよそ75兆個の細胞でできているといわれます。75兆個という数がどれくらいかというと、これはもう想像もできません。今も心臓が動いています。心臓は1日に10万回も動いているそうです。しかも1回たりとも自分で動かしている人はいません。さらに腎臓も肝臓も肺も自分では動かしていません。まして、自分で心臓や肝臓や腎臓を作って生まれて来た赤ちゃんは一人としていません。さらにその身体は他のいのちを殺して食べ、はたらくことができます。一人の人間が生まれ、そして生きているということは、とてつもなく大変なことであり、まさに有り難いいのちを生きていると医学的にもいえるのですが、この「生かされている」ということをどのように受け取るのかという問題を提示しているのが、この掲示板の言葉「生かされているということは 結論ではなく 出発点である」ということであるとおもいます。
生かされているということを結論にするということはどういうことでしょうか。自分が支えられて生きているということを知ることは豊かなことです。そのことを知ったところから生まれたのが「おかげさま」という言葉でしょう。しかし、「おかげさま」ということは仏法に遇わなくても、先に述べた医学的なことでもいえることでないでしょうか。生かされているということを結論とするというのは、「今日もおかげさまで生かさせていただきました」という感謝で終わってしまうことです。おかげさまで終わってしまう、そのことが実は自己満足でないのか、という問いかけが掲示板の「結論ではなく、出発点」ということでないでしょうか。
「私は生かされて生きている」で終わらないで、
「ではこのいのちは何を求めているのか。自分勝手に決めた満足でない、私を生かしているものも満足する、本当の満足は何か。」と問うこと。
「周りに支えられて生きている。」で終わらないで、
「私は私のために犠牲になっているもののことを顧みたことがあるだろうか。その責任を果たしているだろうか。」と問うところに、「生かされている」を結論ではなく出発点としていけるのでしょう。「生かされて生きている私は何を求めているのか」このメッセージに応えうるものが仏法です。自分の中からは自己満足の思いしか出てきません。
「礼拝はただこれ恭敬にして、必ずしも帰命ならず。帰命は必ずこれ礼拝なり」
親鸞聖人は『浄土論註』の言葉を大切に受け取られていますが、この文のこころは「礼拝(感謝)はうやうやしく拝むことではあっても、必ずしも帰命という意義を持たない。それに対して帰命(わがいのちを仏法に投げ出す。仏法に目覚め、仏法に生かされて生きる)は、必ず礼拝というすがたが伴う」ということです。「おかげさま」という感謝、礼拝がおこってくる背景には「帰命」仏法にいつも自己中心にしか物事が考えられない私が常に突き破られ、生かされているいのちが真に求めていることに目覚ましめるはたらきに遇うことがなければならないと教えられています。 深草誓弥
「正義は暗い」 いたみは明るい こまることは なくならない 「明るくこまる」
「図書館戦争」というマンガが実写映画化され、地上波で放映がありました。映画の中で、同僚の失態を厳しく指摘する姿を見た教官が 『正論は正しい。だが、正論を武器にする奴は正しくない』と、部下を諭すセリフがありました。
人間として正しい考えや意見を持つことは必要なことですが、教官が言うように、正しい事「正義・正論」を盾にして相手を追い詰め傷付けることは、正論であっても正しい事とは言えません。さらに人を追い詰めるときのその顔は、鬼の様な顔をしています。決して明るくはありません。
例えば、交通事故で子供を亡くなってしまった両親に向かって、「お前たちがちゃんと見ていなかったのがいけないのだ」と、追い詰めるようなものです。鬼のように責め立て怒ったとしても、子供が生きて帰ってくるわけではありません。逆に悲しむ親を更に悲しみのどん底へ突き落としてゆくだけです。正しさは外に向かう時には、暗さをもってはたらきます。この様に私達は常に、正義の位置に立ちたがり、他者の悲しみを「いたむ」心が欠けているように思われます。
阿弥陀仏の心は「大慈悲心」という言葉で表現されます。一切の衆生を慈しみ育て、悲しむ心です。悲しむ心は「悲痛」という言葉にも通じます。阿弥陀仏は衆生が流転し迷う姿があまりにも悲しくて、心を痛めておられるのです。その様な阿弥陀のはたらきを感じればこそ、私達は他者の苦しみに寄り添い「相手の心をいたむ気持ち」が生まれ出てくるのではないでしょうか。そして人を明るくさせ、心を開いていくのです。「いたみは明るい」とは、この様な意味があると思います。
また私達は、今月の言葉のように「こまることは、なくならない」生活をしています。生きていれば様々な災難にであったり、不都合なことにであったり、こまることが様々あります。そんなときには「こんなはずじゃなかった、なんで自分だけがこんな目に・・・」と下を向いてこまり果て、心も顔も暗くなります。
しかしよく考えてみると、この(身)は老・病・死する存在です。若く健康で長生きを求めますが、縁さえあればいつでもその理想は崩れ去ります。そしてこの環境(土)も思い通りにはなりません。気づいたときには私は生まれていて、望んでいなくてもこの環境(土)が与えられていました。今月の言葉の様に、生きるということはこまることばかりで、無くなりはしません。自分の思い通りにはならないけど、この身と土を生きているのが事実です。
「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり。されば、そくばくの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ」(歎異抄、後序)
と歎異抄の中で親鸞聖人は、本願念仏に出会えたよろこびを語られます。煩悩に悩む私を、「そくばくの業」を抱えてこまっている私を、いたみ悲しみ、たすけて下さる阿弥陀様の存在がありがたく「かたじけなさよ」と、表現しておられます。その救いのはたらきに出遇ったならば、人生に於いて生じる様々な困難を「明るくこまる」事が出来るのではないでしょうか。ひとりで困るのはつらいです。阿弥陀様と一緒にこまれば、けっして暗い人生ではないはずです。
こまることさえも明るく引き受けていく力が、本願念仏の力なのでしょう。 貢 清春
御正忌報恩講案内
「私が、私の存在の背景を知るということが知恩である」
私共人間は、恩波の上に漂っている小舟のようなものである。前も恩、後ろも恩、右も恩、左も恩、過去も恩、未来も恩、私がこの世に居るということの一切が御恩である。この御恩は返しても返しても加わって来る。私共の生活は恩をうくる生活であると同時に恩に報ゆる生活である。この事を教えて下さったのが親鸞聖人である。聖人の教えが無かったら私は恩の中に居ながら恩を知らないでいたことである。これによって思うに聖人が私のうけている御恩の根本である。
一年三百六十五日、一日として報恩の日で無いのはない。毎日が報恩講である。その報恩講の最も根本的なるものが親鸞聖人の御恩に対する報恩講である。聖人の報恩講を営むことによって報恩の生活が明らかになるのである。毎年十一月、聖人の報恩講に逢うごとに報恩の中に育って居る自分を明らかにして頂くのである。故に私は毎年の報恩講が生活刷新の根元であると信じて居る。毎年報恩講を営むことによって生活のよろこびと力とを鼓舞せられることである。
(暁烏 敏 『報恩講の案内状に添ふる言葉』から)
聖人の御恩徳を憶い、今年の御正忌報恩講を厳修させて頂きます。真宗門徒、又福浄寺にとりましても最も大切な法要でありますと共に、そのお荘厳(おかざり)にも多数の御門徒の願いと、ご苦労と、日にちがかけられた、寺門あげての仏縁です。
どうぞ真宗門徒の証を立てるべくお繰り合わせ御参詣聞法下さり、またご一緒に勤行唱和して下さいますようご案内申し上げます。
また、多くの方々の御縁をいただくことを願い、且つ、昔日の報恩講を偲びたく、粗餐でございますが、お昼のお齋を用意いたします。ご参詣の皆様、毎日お席について下さいますようお願い申し上げます。
一、日時 一月二十二日より二十八日まで
日中 午前九時半 逮夜 午後七時半
一、法話 福浄寺住職・若院(二十二日日中~二十四日日中まで)
北九州・徳蓮寺 伊藤 元師(二十四日逮夜~二十八日まで)
一、勤行 正信偈 真四句目下(大谷声明集 四五頁から五九頁)
念仏、和讃 五ッ淘、五遍反し 回向 願以此功徳
「聴聞」
聴くといいながら 人はたいてい 聴きたいこと、理解できることしか聴かない
聞こえてくるということがない
今月の掲示板の言葉は聴聞という語について教えられている言葉です。聴と聞はどちらも「きく」と読めますが、意味はそれぞれ異なっています。聴は「まともに耳を向けてきく」、「ききしたがう」という意味があるようです。それに対して聞は、字の成り立ちが「耳+門」ですから、「よくわからないこと、へだたったことが、きこえる」という意味です。
これらの意味を踏まえて聴と聞の意味の違いを考えてみますと、聴は「自分が意思してきく」ということであり、聞は掲示板の言葉にあるように「自分の意思を超えてきこえる」ということでしょう。
聴聞は「仏法聴聞」という言葉で伝えられてきています。蓮如上人も「仏法はただ聴聞に極まれり。」と語られています。なぜ聴と聞があわせて用いられるのでしょうか。それは私たちが日ごろ立場としている「私」に問題があるからでしょう。
「聴くといいながら 人はたいてい 聴きたいこと、理解できることしか聴かない」と掲示板にあるように、私たちは「私」に都合のよいことしか聴きたくありませんし、「私」の頭がうなずけるようなことでないと嫌です。仏法をきくといっても、聴としてあらわされる「きく」だけなら、「私」の都合に合うか合わないかできくのですから、もはやそれは教えではなく、私の身を飾る知識教養や私の思いを満たす道具でしょう。
浄土真宗の正依の御経はすべて「我聞如是」「如是我聞」からはじまっています。「我聞きたまえき是(かく)の如し」「私が聞かせていただいたことは、このようなことです」という意味ですが、仏が説かれる法、まことの語が、きいた人に至り届き、そのまことにきいた人が深くうなずいている。そしてきいたことがずうっと残っている。なぜ残るかといえば、思いもかけず私自身が仏の言葉によって言い当てられた。むしろまことであると語られたことを「まことだ」と聞いた人が証明している。そのまことに触れた心が御経を生み出してきました。そこに聞という字がもちいられているのです。
ですから聞くということは、興味があるから、自分の都合にかなっているから聴くということでない大切な意味があります。思いもしなかった、わかっていなかった自分自身を言い当てられたところに聞くということがあるのだと思います。
蓮如上人が「仏法はただ聴聞に極まれり。」と聴聞という言葉で語られたのは、蓮如上人自身が仏法にご自身を言い当てられた、その仏の教えをこころにかけて聴きなさい、こころにかけて聴くなかで、私たちが日ごろ求めている「自分の都合のいい、思い通りになる」個人的な、断片的な世界でない、数限りのない無数の人が「そうだ」と深くうなずいてきた世界が「聞こえてくる」ということをおっしゃっておられるのでないでしょうか。 深草誓弥
合掌 右手の悲しみを 左手がささえ 左手の決意を 右手がうけとめる (高田敏子)
高田敏子さんは1914年生まれ、東京出身の詩人。女性の日常生活に根ざした平易な作風から「台所詩人」「お母さん詩人」などと呼ばれ、沢山の人に親しまれます。74才、胃がんの病を受け亡くなられたお方です。
この詩のタイトル「合掌」とは、インドを起源とした礼拝の姿と伝えられます。両手を胸または顔の前で合わせる作法で、神仏への合掌礼拝は、対象への深い帰依や尊敬の念を表します。また古来からインドでは、右手は仏の象徴で清浄や智慧を表現し、左手は衆生を表し不浄として使い分け、その両手を合わせることによって仏と衆生が一体となり、非暴力・不殺生の心で生きることも表現されます。またインド人が食事をする時には、器用に右手を使って食し、不浄な左手を使って食べることはありません。
今月の言葉で高田敏子さんは、「右手の悲しみを 左手がささえ 左手の決意を 右手がうけとめる」と合掌していく中でいただいたこころを表現されました。これは本来の合掌の意味には無い、高田敏子さんの独自の受け止めであると思います。しかしどの様な場面、経験の中でその様なこころが湧き出てきたのでしょうか。
まず私たちの人生の中で、合掌する事が多い時はいつであるかを考えてみると、それはおそらく、身近な人が亡くなった時だと考えられます。亡くなったその瞬間、臨終の時から私達は合掌をしているのです。それから自宅に帰っての枕経、通夜、葬儀と続く仏事でも何度も合掌をします。身近な人の死のご縁が、生きている私達に合掌させるご縁をつないでいてくれます。
そして生きている時、亡くなったその方に対して拝む心が無かったとしても、死に別れてみると自然と手が合わさる事も不思議です。誰かに強制されている訳でもないのに合掌するこころが湧き出てきます。それは相手が煩悩はたらく人ではない、仏様に成られた功徳なのでしょうけれども、それだけでもない様に思います。
四年前の東北の震災当時の映像で、津波で亡くなった家族が住んで居られた場所や、墓標に向かい合掌をされる遺族の姿が映し出されました。様々な宝物を失った悲しみが、合掌される姿ににじみ出て、何とも言えない気持ちになったことがあります。しかし人間はその悲しみを支えていく何かがないと立って居れないのかもしれません。おそらくそれを「決意」と高田敏子さんは名付けたのではないでしょうか。
「決意」とは、人生の方向を定め、歩み出す力のことであります。様々な悲しみを抱えてはいるけれども、亡き人から生前頂いていたお育てを大事にして生きていこう。しっかりとこの大地に立って、亡き人の願いに応える生き方をしていこうと、自分の意思が決まっていくことを表しているのでありましょう。
その「悲しみ」と「決意」の両方が、合掌という姿をとって私たちの手の中で支え合っておられる。あたかもそれは、右手の仏様、左手の衆生が合掌して支え合っている姿、合掌の語源と一つになる様にも感じます。
いかなる宗教も合掌礼拝から始まります。私たち真宗門徒も朝夕のお内仏へのお参りを生活の基本姿勢としてきました。先祖の方々は、つらい経験や悲しみさえも仏様に手を合わせながら受け止めて来られたのだと思います。今月の言葉を通して、あなたは何を考えて合掌していますか。あなたの合掌はどんな意味があるのですか。色々なことを問われ、確認する事の出来た言葉でした。 貢清春
前略 皆様におかれましては日頃、日曜学校の会の運営にご協力、ご理解頂きお礼を申し上げます。この度、日曜学校のみんなと一緒にお寺の行事としてつとめられる門徒報恩講に参詣いたします。
親鸞聖人のご命日をご縁にしておつとめされる集まりが報恩講です。親鸞さまは「南無阿弥陀仏」の教えを、正信偈や和讃という「うた」で残して下さり、そのおみのりによって沢山の人が生きる喜びをいただいておられます。その親鸞聖人のご恩に感謝する、一年の中で一番大切な仏事が報恩講です。
今年は中山、上組、波佐見地区の方と一緒にお参りします。ご参加頂きます様、よろしくお願いします。
記
○日時 平成27年 12月13日(日) 10時~12時半まで
○日程 10:00 おつとめ
10:40 仏様のお話
後、被災地への手紙を書きます
12:00 お斎、お昼ごはん
(精進料理)
12:30 解散
○持ってくるもの
・お米1人1合 ・おさいせん100円 ・筆記用具 ・色えんぴつ
・他、いつも日曜学校に持ってくるものを持って来て下さい。
・ゲームやマンガ本は持って来ないでください。
○バス迎え時間
若院迎え 9:20松本自宅~9:25川口・中尾自宅
石木迎え 9:40喜々津自宅~9:45永田自宅下
貢迎え
① 9:10貢自宅下~9:10入籾自宅下~9:15塚本自宅
② 9:20田尻自宅下
③ 9:30靏野自宅~9:30切間自宅前~9:30長谷自宅
~9:35ふとっぱら前 ~9:40下五反田バス停
*いつもの送迎時間とは違いますので、間違えないようにして下さい。
*お昼のお斎(おとき)をいただいてからの解散です。帰りもバスで送ります。
*当日、出席できない場合は12月13日までに、連絡して下さい。
門徒報恩講案内
今年も愈々師走になります。
就きましては、一月の御正忌報恩講から始まり、また本年の最後のしめくくりの法要、「門徒報恩講」を例年の如く左記により勤めさせて頂きますので、皆様、宗祖親鸞聖人の御恩徳を憶い、報恩感謝の志をお運び下さい。そして各地区仕出し当番の皆様の、昨今では中々味わえない手作りの精進お斎をいただいて下さい。皆様のお繰り合わせの御参詣を念じます。尚、参詣日は一応の目安です。都合の付かれる日でもかまいません。
当日の勤行は正信偈三首引きでつとめます。御和讃は、赤表紙の勤行本五六頁「三朝浄土の大師等」からの三首です。ご一緒にご唱和下さい。
日程 (勤行は午前十時からです。)
十二月十日 木場講 (上、下)
十一日 川原、石木講(上、中、下)
十二日 音琴講(口木田、大音琴、小音琴、彼杵)
十三日 西講ノ上(波佐見、中山、刎田、岡谷、川良、野口)日校参加
十四日 西講ノ中(中組、宿、岩立、上百津、下百津)
十五日 西講ノ下(栄町、城山、数石、新百津、山手、旭ヶ丘、若草)
十六日 西講ノ西(下組、平島、琴見ヶ丘、白石、三越、小串、惣津、新谷)
十七日 五反田(上、下)、猪乗講 及び町外
御門徒皆様
人間に生まれた者は 必ず深い いのちの願いを 持っている (和田稠)
人間が他の生物と異なるのは、「意味」を求めるということです。英語では「Why」(なぜ、どういう意味があるのか)という問いです。私達が今日まで生きてきたということ、その事実だけで自分の存在の意味を感じたりしますが、「私がここにいる」ということの意味を求めるのが人間です。なぜ人間は意味を求めるかといえば、死があるからです。「他の動物にも死があるじゃないか」と思われるかもしれませんが、私達はどこかで自分は「死のある生を生きている」ことを学びます。死に向かって生きているがゆえに、逆に生きていることの意味を問わずにおれないのです。「なぜ生きるのか」という問いです。
死をどこで学ぶのかというと、自分の肉親、兄弟など縁のある方の死を通して、自分も死ぬのだと学ぶことがあります。葬儀を重く、大切に勤めてきたのは、死を学ぶことを通して逆に「自らが生きている意味は何か」という問いが掘り起こされてきたからだとおもいます。
日ごろ私達は「How to」(どう生きるか)という関心で生きています。「損得」損にならないように、得になることを求めます。「快不快」気持ち悪いことより、気持ちの良いことを求めます。「善悪」悪いことより善いことをしよう、と。大体毎日求めていることはこれで説明できるのでないでしょうか。
私達のその気分は「なぜ生きるのか」という問いを呼び起こす死を隠そうとしています。医療技術の発達は死を出来るだけ見えないように遠ざけました。かつての葬儀は地域ぐるみでした。死人が出れば墓場の土を掘り、皆で荼毘所まで運び埋葬していた様に、葬儀は地域の手助けを必要とし、死を身近に感じ取っていたのです。しかし現代では、直葬ということがいわれるように、直接火葬場に運ばれるようになりました。人間が作り出した文明は、進歩した、発展したといいますが、死を見えなくしたのかもしれません。私たちの日ごろの気分は「死の無い生」でいたいのです。しかし人間そのものは変わりません。死は絶対にあるのです。
「死のある生を生きる意味は何か」この問いこそ、掲示板の「人間に生まれた者は必ず深い、いのちの願いを持っている」といわれている「いのちの願い」とつながってくるのでないでしょうか。「死のある生を生きる意味は何か」この問いに魅入られた人は、その問いを持たなかった自分には戻れなくなるはずです。知らないふりや、隠したり出来ても消せません。そのことを象徴的にあらわしたのが、法名の「釈」ではないでしょうか。
仏教のさとりを開かれた釈尊は、インド北東の釈迦族という部族の出身でした。「釈」という文字は、釈尊の「姓」である「釈迦」の省略です。今から2500年以上前に王族の子として生まれ、何不自由ない生活をされていた一人の王子は、街に出て生まれる人、老人、病人、そして亡くなる人を見られ、自らも老いるべき若さを生きるものであり、病むべき健康を生きるものであり、死のある生を生きる者であると深くうなずかれました。そして道を求められます。「死のある生を生きる意味は何か」と。法名の「釈」は人間誰しもが釈尊と同じ問いを持つものであることを呼び起こす、深い願いをあらわしたものだと受け取れるのでないでしょうか。 深草誓弥
生者の身勝手が 亡き人を
餓鬼 畜生にする
常に飢えて、満足感のない境界を餓鬼という。常に束縛されて引きずり回されている境界を畜生という。
畜生は主体性なく、いつも責任を他に転嫁するからして、罪の自覚もない。したがって慚愧(ざんぎ)の心もない。ついには死者にも鞭をふり、神・仏をも恨むことになる。満足感のない餓鬼の根性は、限りなく欲望を追求して自分の都合のよい条件を満たそうとして、他人の気持ちをかえりみることがない。神・仏をも利用しようとする。
人間の親から餓鬼・畜生が生まれる道理はない。もし私自身が餓鬼・畜生として生きているとすれば、今は亡き父母たちは、餓鬼・畜生だと言わなければならない。
声なき姿なき親を前にして、我々は何を思うでしょうか。「亡き人が、亡き身をもって、何を語ろうとしているのか」という、声なき人の声に耳を澄ませる時、常に私を見守り続ける亡き人の「ねがい」が聞こえてくるに違いありません。
秋の永代経法要を左記の如く厳修致します。永代、無量寿の経教に依って御先祖の遺徳を偲びつつ、御恩の誠を尽くさんがための聞法の御縁にお遇い下さいませ。
記
日時 平成27年 10月16日(金)~18日(日) 午前9時半開筵
講題 「亡き人、先祖とは、その供養とは」
講師 日田、緑芳寺 河野通成師・及び住職
私たちはどうも、なすべき唯一のことをしていないときに、もっとも忙しいようである
エリック・ホッファー
昨年11月10日、83才で亡くなられた俳優の高倉健さんが、亡くなる前に出された手記が「文藝春秋」掲載されました。この手記で健さんが座右の銘としていた言葉が紹介されていました。
「往く道は精進にして、忍びて終わり悔いなし」
この言葉は比叡山延暦寺の大阿闍梨、酒井雄哉師からいただいた言葉で、映画出演を受けるか断るか悩んでいた時に、この言葉の後押しで出演を決定したとも伝えられています。
この言葉の語源は「仏説無量寿経」の嘆仏偈の一節「我行精進 忍終不悔」(我が行は精進にして、忍びて終わり、終に悔いじ)です。阿弥陀仏が法蔵菩薩の時に誓われたお言葉で、たとえどんな苦難にこの身を沈めても、さとりを求めて衆生を救わんとする我が修行は、最後まで耐え忍び悔いることはない、という言葉の意味です。
映画俳優は撮影に入れば、長い間忙しい期間が続くそうです。体調管理も大変でしょうし、プライベートの時間は無く、それこそ忙しさと苦難の連続でありましょう。しかし自分が今なすべき事、精進してがんばれる居場所が定まったならば、ただひたすら仕事に打ち込んでいけるのだと思います。この嘆仏偈の言葉の様に、苦しいことがあっても、辛いことがあっても、いつこの身が終わっても後悔はしない。そして常に精進を怠らない健さんの俳優業に対する姿勢が、法蔵菩薩のお心と重なるものを感じます。そしてこの言葉を大事にしてこられたからこそ、健さんの演技が人々に感動を与えていったのです。
振り返って自分の事を考えてみると、「忙しい・・・忙しい・・・」と口にするときは、「あれもせんば、これもせんば」と気持ちだけが先走って、どれから手を着けて良いかが分からず、本当はしなければならないこと以外の事を先にしてしまう事があります。優先順位がチグハグになり、時間だけが過ぎていって、しなければならなかったことが半分も出来ずに終わることがあるのです。
「忙」という漢字は、立心偏「忄」になくす「亡」と書きます。大事なこころ「忄」を「亡」くし他に心を奪われ、落ち着かない気持ちの状態のことを字で表現しています。「なすべき唯一のこと」が自分の中で決まっていない時はそれこそ「忙」心を亡くしているのでしょう。
忙しく働かせていただくこと自体は有り難いことです。しかしただ忙しさの中で自分自身を見失いながら終わっていくのであれば、人生空しいとしか言いようがありません。忙しく慌ただしいときには、この今月の言葉を思い返し、本当になすべき事は何なのか、悔い無しと言える生き方をしているのか、立ち止まり考えててみたいです。 (貢 清春)
「自分に非があること、自分の考えに誤りがあること、自分の視線が偏向していること、
これらを認めるのが大の苦手、自分の考えに固執する。」
「自分に非があること、自分の考えに誤りがあること、自分の視線が偏向していること」、これらを認めることが大の苦手の私。「私は正しい、自分の考えに間違いはない、みんな私が見て思うようなことを思っている」と何の疑問も持たずに真逆の「自分は正しい」、「わが身一つが可愛い」というこころに立って生きています。真蓮寺住職の寺本温先生はこのことを「茶碗の譬え」をもって、繰り返し語られています。
亡くなられたお父さんが寺本先生によく語られていたそうですが、「他人が茶碗を割ったときは「茶碗を割った」と割った責任者がはっきりするような言い方をするが、自分が割ったときは「茶碗が割れた」と犯人が不明確で、いかにも茶碗が勝手に割れたかのように言う」という話です。このように「私は悪くない」、「私は正しい」というこころは、もはや私の身にそなわったものです。自己正当化はいざという間際に飛び出してきます。「そういうことを思わないようにしよう」というような反省や後悔は間に合いません。
さらに掲示板の言葉にあるように「これらを認めるのが大の苦手」ですから、どれだけ自分に非があり、考えに誤りがあり、偏ったものの見方をしているとうすうす違和感を感じていても、認められず、「あなたは間違っていない」、「あなたは悪くない」といって、慰め、癒してくれるものを求めるのです。
しかし、この私のもつ「自分は正しい」、「わが身一つが可愛い」というこころは大きな問題をはらんでいます。私の「視線の偏向」、つまり好きなものはよく見え、嫌いなものは悪く見えるという偏見は排除行為と結びつき、差別となります。偏見は事実有るものを無いとし、無いものを有ると認識することです。排除は事実そこにいるのにいないようにしてしまうことです。この仕組みをもっているため、差別は差別する者の側に罪悪感を抱かせません。なぜなら、私たちが他者を傷つけ、「悪いことをした」と感じるのは、その他者の存在を「そこにいる」と認めるときのみだからです。
仏法はそのように差別を生みだす根っこにある自己正当化の思いを「自是他非」と教えます。「自分は正しい、他が間違っている」という、事実に反し、さかさまになった意識を言い当てる言葉です。このどこまでも自分ひとりを善きものとしてたてようとする限り、ときに「善きもの」でおれない私とも、事実目の前にいる他者とも出会わせません。いかに私の固執があるがままということに頷けさせない世界を作り出しているか。これが私のもっている罪でないでしょうか。
その様な私たちに、阿弥陀仏は念仏によって本願に遇うことを選ばれました。自分の誤りに頭を下げない、誤ることを拒否する私に対して「煩悩具足の凡夫、それがあなただ」と呼びかけ、純粋に批判することで、自(おの)ずからこの身の事実に頭の下がる世界を願われています。お内仏を中心とした生活を大切にしてきた歴史の意味を、大切に受け取らなければなりません。 (深草誓弥)
日曜学校夏の集い
--非核非戦カレンダー制作・親子映写会--
敗戦、原爆投下から70年の年となりました。あらためて核・戦と向き合う節目の年となりました。お寺の本堂には「非核非戦」という額を掲げ、この言葉を大事にしています。今もなお「核」であり「戦」である私達を仏様は悲しみ、見つめておられます。
今年の夏の集いは、非核非戦のカレンダー作りをして、夜には「対馬丸」のアニメーション映画を観る予定です。どうぞご参加いただきます様、ご案内申し上げます。
◎日時:8月20日(木) 午後2時集合~夜8:15解散
◎持参品:お勤め本、念珠、筆記用具、色鉛筆、ハサミ、のり、野菜(ジャガイモ、にんじん 各1つ)水筒、お米(1人1合・参加されるご家族の分も持たせて下さい)
◎申込み:8月12日までに参加の申し込みを、電話・メールにてお願いします。
夕食から参加される保護者、ご家族の皆様の人数もお知らせ下さい。
連絡先 ・電話 82-2154
*夕方5:30からの夕食には、保護者、家族の皆様もご一緒にご参加下さい。夕食に参加できない場合でも、6:30からの親子映写会には、途中からでもかまいませんので必ずご来場下さい。映写会終了後、お子様と一緒に解散となります。終了後の送迎はしません。駐車場は納骨堂や、河川敷をご利用下さい。
日程 午後~(お迎えはいたします)
2:00 集合、勤行、仏様のお話
3:00 カレンダー制作
4:00 夕食作り
5:30 夕食(カレー)
6:30 親子映写会 「対馬丸」
8:15 終了、解散
映画「対馬丸」とは
太平洋戦争中の1944年(昭和19年)、戦火の迫る沖縄の子どもたちを島外へ避難させるという、政府命令の学童疎開が行なわれた。輸送を行なうのは「対馬丸」。対馬丸が船出をする海は、アメリカの潜水艦によってすでに17隻が沈められていた危険な海だった。長崎を目指して出航したが、潜水艦の攻撃を受け沈没し、犠牲者数1,476名を出した。太平洋戦争末期に起こった学童疎開船の悲劇を描くアニメーション作品。1982年製作、小林治監督作品
○歎異の会(歎異抄を学ぶ会)
日時 8月31日(月) 20:00~
学習箇所 第13条を学びます
○法音の会(仏教讃歌を歌う会)
8月はお休みします。
○仏教青年会
日時 8月28日(金) 19:30~
場所 福浄寺本堂
テーマ 「非核非戦」 講師 福浄寺住職
○日曜学校
日時 8月6日(木) 9:00~10:00
8月20日(木) 14:00~20:15 「夏の集い」に参加します
盂蘭盆会並びに、非核非戦法要の御案内
今年、私たちは被爆70年、敗戦70年を迎えました。例年勤めております盂蘭盆会と、非核非戦法要をあわせて勤めさせていただきたいと思っております。
原爆によって、また先の大戦によって多くの尊いいのちが奪われ、生き残った人々も、今もなお苦しみ続けています。70年という時を経て、原爆、戦争を知らない世代が大多数となり、その体験は風化の一途を辿っています。
今を生きる私たちは「人類の英知」として核を持ち続け、原発事故によって新たな被爆者を生み出しました。敗戦後も民族、宗教の違いや経済格差による対立によって、世界各国で戦争が起こっています。そのなかであえて戦争の放棄を願った憲法第九条は戦争の悲しみをくぐって生まれたものではないでしょうか。
今、私たちは、原爆・戦争による犠牲者の苦しみ・悲しみを忘却し、それを引き起こした歴史への慙愧の心を放棄しているように思えます。
供養とは 亡き人に心配かけない 生き方を見つけることなんだ そのために仏法を聞くんだ。心配かけない生き方とは一人一人が「自立」していくことなんだ 藤元正樹
「非核非戦」とは、私たちの在り方を「非―あらず―」として、自己を見つめ問い直す道を指し示す如来の願いです。「非核非戦」の言葉の前に座して、私たちはどのような「生き方」を見い出すことができるでしょうか。戦争、核によっていのちを奪われた、全ての亡き人からの使命をうけとめ、ひきうけ、歩んでいけるものでありたいと願います。
何卒、有縁の皆様をお誘い合わせの上、御参詣下さいますように宜しくお願い致します。
日 時 平成27年 8月16日(日) 午前9時半より開筵
法 要 『仏説阿弥陀経』・『正信偈』同朋奉讃
法 話 福浄寺 住職・寺中
戦争は終わっていない。
なぜならば、戦争の罪が人間の根源的な罪として問われてこなかった。
人間の持つ無明の罪として。 武宮聰雄
今から20年前、長崎教区原爆50周年非核非戦法要が勤められました。その法要で正蓮寺前ご住職、武宮聰雄師が記念法話を勤められ、その講録が「非核非戦-法蔵菩薩の涙-」として本願寺出版部から再販されました。今月の言葉はその中の一節です。
武宮師が復員してから後は、住職が戦死されていた正蓮寺に入寺されました。初めての法務は戦死者の法事だったそうです。何度もそのご縁に出遇う中で、戦火に焼かれた方々の苦しみ、遺族の悲しみの声を聞き続けてきたと本の中で語られます。その中で「お前にとって戦争とは一体何であったのか」という問いを頂いたと、述懐されます。
私達は、第二次世界大戦が終結し、日本に平和が戻った記念日を8月15日「終戦記念日」として名付け、追悼の式典が各地で行われます。戦争は終わり二度と繰り返してはならないと、この平和な日本を守っていこうと語られますが、武宮師は「戦争は終わっていない」と叫ばれます。なぜならば戦争は、人間の知恵の根っこにある「無明」が起こしてきたからです。
「無明」とは、真実の智慧に暗く、仰ぐべき光(教え)を知らないということです。「無明」は人間の知恵を最高のものにして、人間の善悪の判断や価値観は間違いないものにしていくあり方を言います。いつでも自分の都合によって善悪を決め、悪は徹底して排除し、善き者だけを迎え入れる「自是他非」の心。そして自分だけは絶対に間違わない者だと思い込んでいる姿を「無明」と教えられます。それは戦争を起こす心そのものであります。
さらに人間は、起こす戦争が間違いないこととする為に、「聖戦」という言葉を使います。それは戦争の「罪」感じさせない、思わせない為の装置であります。それによって人殺しや暴力が正当化されていきます。戦地では残虐な殺戮行為が起きていても、それが正義になっていくのです。
戦争を起こす根源的因である「無明」がいつでも人間の中にあることを教えられれば、戦争は国のせいだとか、時代のせいだとか、他に責任転嫁することは出来ません。戦争を起こしてきた人間の罪「無明」を問わない限り「終戦」は無いのです。事実としては「敗戦」と言うべきであります。
親鸞聖人が仰がれた阿弥陀仏の智慧の光は、人間存在の深い闇「無明」を破るはたらきがあり、譬えれば太陽や月の光よりも超えている「超日月光」であると述べられています。真実の智慧のはたらきは、一切を照らし平等に迎え取る智慧です。その光に出会えばこそ人間存在の深い闇を知らされ、仰ぐべき光明の世界が人類に開かれていくのでありましょう。
福浄寺の本堂には「非核非戦」の額を掲げられてあります。この言葉は、私たちの「戦・核」の在り方を「非―あらず―」として見つめられ、自己を問い直していく阿弥陀仏の言葉です。私達は常にこの言葉を仏言として聞き続け、私自身が念仏申す人となることが願われています。 (貢 清春)
教室で子どもが質問した。「あーんと口を開けると、喉の奥に、上からさがってついてる、ぼくらが『ノドチンコ』と呼んでいるものが見えてきます。あれは、どういうはたらきをしているのですか」私は困ってしまった。そのはたらきを全く知らなかった。
調べてみると、食べものを飲み込むときには、あの「のどちんこ(口蓋垂・こうがいすい)」が、気管の入り口を、ピタリと蓋(ふた)をしてしまうそうだ。そのおかげで、まちがいなく食べたものは食道に進み、胃に進むというのだ。
それが解ったとき、天地がひっくり返るほど、ショックを受けた。そのはたらきを知らぬくらいだから、一度も、感謝したことなどない。お礼を言ったことも、もちろんない。それどころか、「ノドチンコ」のことひとつ解っていないのに、「唯物論」だとか「無神論」だとか、偉そうなことを言い、「傍若無人」に生きていた私だった。
このとき、私の生きているという底にあって、私を生かしづめに生かしている何ものかを強烈に感じたのだった。気がついてみたら「口蓋垂」だけではない。目も耳も手も足も、心臓も、みんなみんな、ただごとではない、不思議きわまることであったのだ。「生きてる」とばかり思っていた私が「生かされていた」のだ。頭の上がらぬ思いだった。
幼い時からずっとずっと、こういう私によりそって、はらたきづめにはたちいてくださったはたらき、願いがあったのだ。私が忘れているときも、背いているときも、おこっているときも、私の背後から、祈りづめに祈り、働きづめに働いていたのだ。それに気づいたとたん「助けてくだされよというに非ず、助かってくれよとある仰せに従うばかりなり」ということばが、有無を言わせず私を「仏」の前にひきすえた。
「仏さま」は、「私」の向こうにではなく、「私」の「いのちの根源」に、はたらき続けていてくださっていた。
(東井義雄)
八月の婦人会法筵は、講師に崎戸の真蓮寺御住職、寺本温師をお招きしまして、『仏説観無量寿経』について御法話をいただきます。尚、この法筵は、婦人会主催の法筵であり、会員皆様に限りませんので、御門徒皆様もお誘い合わせの上、御参詣くださいませ。
記
○婦人会法筵
日時 8月1日(土)~8月3日(月) 午前9時半開筵
法話 崎戸・真蓮寺住職 寺本 温師
○盂蘭盆会法筵
日時 8月16日(日) 午前9時半開筵
○納骨堂盆読経
日時 8月13日~15日 午後6時
場所 福浄寺納骨堂
○歎異の会(歎異抄を学ぶ会)
日時 7月23日(木) 20:00~
*第13条を学びます
○法音の会(仏教讃歌を歌う会)
日時 7月16日(木) 19:30~
○仏教青年会
日時 7月17日(金) 19:30~
場所 福浄寺本堂
*「茶色い朝」の輪読 学習
○日曜学校
日時 7月12日(日) 9:00~10:00
7月20日(月) バス遠足 (時津の萬行寺様へ行きます)
人間に独りで出来ることなんて まず ない
つねに 他に恵まれてこそ 人は在る 『折々のことば』
授かった子どもが大きくなるにつれて、様々なことが出来るようになりました。朝、目が覚めると自分でベッドから降り、「お母さんは?」、「パン、食べる」と言葉を発し、意に沿わないことは「嫌」といい、口に食べ物を運び、おまるでおしっこをし、歩いて保育園にいく。少し前までは出来なかったことです。
その姿を見ていて、単純に、「自分もこうやって両親から教えてもらって、今出来るんだな」と感じます。現在、毎日生活するなかで様々に行動し、言葉にし、思い考えることも、両親、祖父母、先生、友人など様々な影響を受けてしていることです。
私たちは「無有代者」「有(たれ)も代(か)わる者無し」(『大経』下巻 聖典60頁)と教えられるように、いつでもない今、どこでもないここに、誰かに代わってもらうことも、代わってあげられることもできない身を生きています。しかし、このことは私達が誰とも関係のないまま、孤立した存在としてあるということではありません。私たちは「無有代者」の存在として事実、「天にも地にも我ひとり」ですが、我一人であるがままに世界中のあらゆる存在と、直接、間接的に関係しあって生きているのも事実です。
ティク・ナット・ハンというベトナム出身の禅僧は「この一枚の紙のなかに雲が浮かんでいる」と語られました。万物の相依相待性をあらわす縁起の言葉です。一枚の紙の存在は、雲の存在に依存しています。雲なしには水はなく、水なしには樹木は育たず、樹木なしには紙はできません。紙を作るには木を切る人がいりますし、他にも太陽の光、土。様々なものが一枚の紙の中にあるといえます。
私もこの相互依存の関係のなかに生きていながら、そのことを見失っているのです。「自分のこと」と「他のこと」を区別し、自分だけを愛し、自分に関係あると思うことだけに関心を寄せ、生活しています。そこには掲示板の言葉にあるような「独りで出来る」、自分で自分を支えているという思いがあります。しかし、その「独り」は私のおごり、あなどりが生み出すものです。ですから身近な父母や友達にしても、親鸞聖人といい、蓮如上人といっても、決して私と無関係な存在ではありません。昨日食べた豚肉が、私の血になり、活動を支えています。
「つねに 他に恵まれてこそ 人は在る」
この事実を、道理を見失い、いつでも自我を中心とする「独り」に堕落し、生きている私。
「個人というのは幻想です。全員で往生するんですよ。」
と、おりにふれて語られた、竹中智秀先生の言葉を憶い起こします。事実は「共に生きている」のです。 (深草誓弥)
○歎異の会(歎異抄の学習会)
日時 6月16日(火)
*第12条を学びます
○法音の会(仏教讃歌を歌う会)
日時 6月26日(金)19:30~
○仏教青年会
日時 6月23日(火) 午後19:30~
場所 福浄寺本堂
*仏像について学びます
○日曜学校
日時 6月7日(日) 9:00~10:00
6月21日(日) 9:00~10:00
仏教の不殺生(アヒンサー)の教えは 生命(いのち)あるものを殺すな というだけでなく 自他の生命(いのち)を生かす、大切に生きるということである
仏教の戒律とは、悟りを求める修行に於いて自発的に守ろうとする戒めのことで、次の5つをお釈迦様はお定めになりました。
①不殺生戒、殺してはいけない。
②不偸盗戒、盗んではいけない。
③不邪淫戒、不道徳な性行為を行ってはならない。
④不妄語戒、嘘をついてはいけない。
⑤不飲酒戒、酒を飲んではいけない。
さて、これが基本的な五戒です。出家の比丘たちはこの戒を守る為に生活を律し、精進して生きてこられました。とくに第一項目の「不殺生戒」は徹底しています。雨期になれば虫を踏みつぶさないようにと外出は控え、安居(あんご)という聞法会を開きました。乾期になり、お釈迦様が各地へ御説法に向かわれる際には、すり足で歩いて大地の生き物を殺さない様に気をつけておられたと伝えられています。水を飲むときでさえ布で濾過していたそうです。
「いのちあるものを殺すな」という不殺生とは、その様な仏の慈悲心を生活の中で実践して生きていこうとする、具体的な生活規範です。しかし私達の実生活を振り返ってみますと、殺生をせずには生きられません。徹底して不殺生を実践したら何も食べられなくなります。それならばなぜ、お釈迦様は不殺生戒を定められたのでしょうか。
不殺生戒を語るときには「守れるか」「守れないか」が議論されます。そして結局「この戒は守れないから必要ない」と考えてしまいます。しかしお釈迦様の本意は、戒を保つことによって私達のいのちは「殺生」という事実の上に成り立っている、その事に気付いてほしい。そして一切のいのちを生かす者になりなさい、そして命を愛する人になりなさいと、この事を伝えたいのだと思います。不殺生戒を守れない自分を発見すればこそ、自他のいのちを殺さず大切に生かそう、大切に生きあっていこうと生きる力が湧いてくるのです。
お釈迦様が誕生したときに大自然が喜び甘露の雨を降らせた、という伝承があります。その話を基にして、誕生仏に甘茶をかける「灌仏会」花祭りの行事が始まりました。なぜ大自然が喜んだのでしょう。それは、自然のいのちを我が物顔にして、むやみに殺したり粗末にしたりしない、そういう慈悲の人が生まれたのだ。その人「釈迦」の教えは、いのちを尊び愛する人を生み出していく。その事に大自然が喜んで雨を降らせたのだ、と解釈して良いのではないかと思います。
不殺生戒があるからこそ、私達が生きている喜びと悲しみが明らかになるのだと思います。だからこそ、多くのいのちをいただいていることの申し訳なさと、感謝の気持ちを感じていけるのでしょう。 貢 清春
本当の自分がわからない人は 他人を責める 本当の自分がわかった人は 他人を痛む
今月の掲示板の言葉は、日ごろ無意識に「自分」と「他人」を分けて見て、いつでも自分は是、「私は悪くない」、他は否という立場に立ち、外を責め立てる私に対して、「あなたは本当の自分がわかっているのですか」と問いかけてくる言葉です。
「本当の自分がわかる」とはどういうことでしょうか。「諦観」という言葉があります。一般的には「諦」は「あきらめる」と読み、悲観的なものの見方のように感じますが、「諦」は「サッティヤ」という、「真実」を意味するサンスクリット語の漢語訳です。ですから仏教が教える「諦観」は「あきらかにみる」「あきらかに真実を観る」ということです。誤魔化さないで、足し算も引き算もしないで自分自身をはっきり見つめること。簡単そうですが、難しいことです。「化粧」は「化けるためのよそおい」という語から成り立ちます。考えてみると私には他者にはいいところだけ見せたい。醜い、悪しきこころは隠しておこうとする、そういうこころがあります。つねに鎧を着て、弱点を見せまいとしているのです。「私はつまらないものですから」といっていながら、他人からそういわれると事実でも腹を立てる。これも芝居をしているにすぎないためです。
「他人を責める」ということは、本当の自分はこういうものだと受け止める余裕がなく、恐れ、隠し、自分を善しとするところからなされるために、当然他者を悪と思うことになります。 親鸞聖人はそのような私たちのあり方が「自力」という精神だと教えられます。
わがみをたのみ、わがはからいのこころをもって、身・口・意のみだれごころをつくろい、めでとうしなして、浄土へうまれんとおもうを、自力と申すなり。
『親鸞聖人血脈文集』 真宗聖典五九四頁
阿弥陀仏の眼からみそなわされた私こそ、「本当の自分」でしょう。自分の思いを中心にすえ、やればできると思い上がり、自分の心で後悔や反省をし、立派な人間になって、都合のよい世界に生まれようとするあり方です。この自力のこころこそ、いつでもない今、どこでもないここ、誰でもない私を生きさせないこころだと阿弥陀如来から悲しまれている、そのはたらきを他力と教えられています。そしてその悲しみは、自力のこころをもつ、すべての人間にそそがれています。逆に言えば、どんな人であっても、抱えている課題は、一つです。
「本当の自分」は、自分で自分のこころをコントロールできるような者でもなく、自分の都合のいいように他者も世界を変えることもできません。思うようにならない出来事の前で、「こうであったらいいのに」と右往左往するのです。教えに照らしてみれば、私達が本当に欲しているのは、都合のいい他者、世界ではないでしょう。わが思いは都合のいいものだけを自分としようと分別しています。しかし、その全体をになって現実に今ここに生きている私がいます。
「本当の自分がわかった人は 他人を痛む」ということは、如来の悲しみに遇い、真の自分の相に目覚めたものは、同じ悲しみが他者にもそそがれていることを知るものであることを教える言葉です。自分のこととして他人を痛むことは、大悲のうえでしか成り立ちません。「本当の自分」に目覚め、「他者を痛む」。それは御本尊阿弥陀如来の御前において開かれる真の人間関係です。
深草誓弥
父の骨からこのような言葉が聞こえてきた
「ここからもう一度、お前がしておることを考えてみろ」 宮城 顗
今まで、お墓参りを何度もしてきましたが、私自身先祖とどう向き合ってきたのだろうか、どんな言葉をお骨から聞いてきたのだろうかと考えさせられた言葉です。
皆さんは墓参り代行業があることをご存じでしょうか。若い世代は仕事が忙しくて遠方の墓まで行けない、高齢の方は行きたくても体調不良で行けず、頼める親戚もいない。そういう方への墓参り代行サービスです。料金を払えばお墓の清掃、献花、線香あげまでしてくれて、その状況の風景写真をメールに添付して報告してくれるという、大変便利な業者です。
「先祖様はそんなことで喜ぶはずが無い、けしからん」や「先祖に対する暖かい心づかいだ」など賛否両論。現代の生活では墓を管理する事の大変さを感じますし、お墓に参る意味は何なのだろうかと考えさせられます。
しかし、自分がお参りしても代行に頼んだとしてもお参りが済んだら、「これで気持ちがスッキリしました、ほっとしました」と胸をなで下ろし、私達が安心する訳です。先祖が喜ぶためと思ってしていることは、結局自分自身の気晴らしの為にしている様な気がします。
今月の言葉の宮城先生は、大事なお父様が亡くなり遺骨と真向かいになった時に、「ここからもう一度、お前がしておることを考えてみろ」という言葉が聞こえてきたと仰います。お墓に参られてスッキリしたという事ではなく、逆に自分の人生に問いかける声に出会ったのです。骨になる死の世界から私の今の人生が厳しく問い直されたのであります。
お念仏を頂いてこられた先達の方々は、その事を「後生の一大事」として受け取ってこられました。「後生」とは「今生」に対する言葉で、命終わった後の生という意味ですが、死んだ後が大事だとか、死んだ後のことだから今は関係ないということではありません。後生という世界から今生が照らされていくのです。
どのような人でも終わっていく、骨になっていく身を生きています。その後生を一大事として生きるということは、後生の世界から見つめられている今をどう生きていくのですか、お前がしておることを考えてみろと、問いかけとしていただく事なのでしょう。
逆に実生活では、「忙しいから」と目先のことに振り回されて大事なことを忘れながら生きている様に感じます。忙しいという漢字は「忄」こころを「亡」なくすと書きます。まさに文字通り私の姿を言い当てた漢字の成り立ちになっています。
お墓で亡き人を拝み骨と対面するという事は、先祖の求め願われたことを訪ね、私の中に生き続ける問いとしていく事なのだと今月の言葉から再確認させられました。 (貢 清春)
自分自身の驚きや疑問や違和感を大事にして
思考を停止しない 考えつづけることが 今 求められている
ハンナ・アーレントという人物をご存知だろうか。1906年にドイツで生まれ、75年にアメリカでなくなったユダヤ人政治哲学者である。『全体主義の起源』などが代表的な著作だが、私も先日彼女を主人公にした映画『ハンナ・アーレント』のDVDを見るまではその思想、生涯に触れることはなかった。
映画は、アーレントの生涯ではなく、彼女の著作で言えば『イェルサレムのアイヒマン』に焦点を絞ったものだ。1960年、数百万人のユダヤ人を強制収容所に移送した責任者アドルフ・アイヒマンがイスラエルによって捕らえられる。アーレントは雑誌『ニューヨーカー』に裁判の傍聴記を書きたいと申し出て、イスラエルに向かう。
裁判でアイヒマンは「命令に従ったまでです」と語る。アーレントは「アイヒマンは想像したような凶悪な怪物ではなく、平凡な人間だったのではないか」と考え、「悪の凡庸さ」について書く。「数百万人のユダヤ人を強制収用所に送り、殺害したナチスドイツ。その一翼をになったアイヒマンはさぞかし冷酷無比な悪魔のような男に違いない。だれもがそう思いたがった。イスラエルの検察官もその悪魔としてのアイヒマンのすがたを暴こうと躍起になった。ところが裁判を通して浮かび上がったのは、組織の歯車として働く小役人のような男だった。」とアーレントは語った。
記事は「アイヒマンを擁護するのか」とバッシングを受ける。それにたいしてアーレントは学生に対する講義のかたちで反論を試みる。講義の中でアーレントは「人間であることを拒否したアイヒマンは、人間の大切な質を放棄しました。それは思考する能力です。」
「思考ができなくなると、平凡な人間が残虐行為に走るのです。」と語った。
アーレントがアイヒマンの中に見た「悪の凡庸さ」は私たちの中にもあることだ。掲示板の言葉にある「自分自身の驚きや疑問や違和感」という感覚を私は日ごろどうしているだろうか。「おかしい」と感じても、「自分ひとり悪者になりたくない」、「皆がそういっているなら、私もそうしよう」、そうやってその感覚にふたをして、何事もなかったかのように同調していく。そしてそのようにすることが美徳のようにさえ考えている。自己保身のために、ただ大きな流れに身をゆだねていく。しかし、そこにアイヒマンと同じ「思考を停止して、考えることを止めた」者が誕生する。このことはフランク・パヴロフの『茶色の朝』の物語にも描かれている。
アーレントの訴えた「悪の凡庸さ」への危機感はそのまま現代の日本に通じる。政治への無関心は投票率の低下が物語る。外務大臣は先のISによる人質殺害事件を受けて、「人間のすることではない」と語ったが、果たしてそうなのか。そこで思考停止してしまうことが、はたして、後藤さんが危険を冒して、彼らを理解したい、世界に伝えたいと思ったことと、はたして同じ感情なのか。
今、私たちは久遠の昔に傷付けあい、殺し合いである地獄からの解放を、人間に誓われた如来の本願に「あなたはどのような世界を願い求めるのか」と問われている。 (深草誓弥)
春季永代経法要御案内
春の永代経法要を来る2月21日から2月25日まで5日間奉修致します。
永代無量の経教に依って御先祖の遺徳を偲びつつ、報恩の誠を尽くさんがための聞法の御縁にお遇い下さいますよう、何卒お繰り合わせ御参詣下さい。
下記の日程でおときの用意を致しておりますが、都合のつかれる日でも構いません。おときは1回に限らず何回でもお座り下さい。
記
日程 平成27年 2月21日~25日 午前9時半開筵
法話 長崎市三重町 正林寺住職 松林大師(23日~25日)
福浄寺 住職 (21、22日)
21日・・・木場、川原、石木
22日・・・大音琴、小音琴、口木田、数石、新百津、若草、旭ヶ丘、山手、東彼杵町
23日・・・中山、上組、野口、中組、宿、岩立
24日・・・下組、白石、小串、惣津、三越、上・下百津、栄町、城山、琴見ヶ丘
25日・・・五反田、猪乗、波佐見、その他の町外
「一切衆生 悉有仏性」 ということは、ほんとうのことを話せば、だれにもわかるということです。(金子大栄)
今月の言葉は「涅槃経」のことばのこころを味わっておられます。「一切衆生 悉有仏性」とは、我々一切のいのちあるものは仏になる性、可能性をもっているという意味です。
金子先生は、「ほんとうのことを話せばだれでも分かる」と言われますが、「ほんとうのこと」とは一体何なのでしょう。そのことを考えていく前にまず確かめておきたいことは、私の中に「ほんとうのこと」「真実なること」があるのか、ということです。
親鸞聖人は我が身、この世界の姿を
「煩悩具足の凡夫・火宅無常の世界は、よろずのことみなもって、そらごと、たわごと、まことあることなきに...」 (歎異抄)
と、煩悩にまみれた私達凡夫が作る世界は、全てが真実からかけ離れ、まことなることは一切無く、その時々の自分の勝手な都合だけを大事にして生きていると教えられます。
また、私は一体何に成りたいのか、何を求めて生きているのかも分からず、今の自分に足りないものを探しては「あれが足りない、これが足りない」と、むさぼりの心で過ごしているのが実状です。仏教では、貪欲の煩悩にはせ使われている姿を「餓鬼」と教えられますが、そういう生活をしている私にさとりを開くこころや、仏に成るような性があるとは信じがたい事です。
そういう生活をしている私達にも金子先生は、「ほんとうのことを話せば、だれにもわかる」と言われます。それは、人間の欲望の奥底には真実まことに反応する心がある、まことを求める心がある、という事ではないかと思います。清沢満之先生の言葉に
「人心の至奥より出づる、至盛の要求の為に宗教あるなり」
という言葉があります。人間の心の最も奥底からわき出てくる最も盛んな要求の為に宗教があるというのです。生活の中で起こってくる時々の、様々な欲望を満たす為に宗教があるのではない。心の底から願っている要求に応えて下さるのが宗教です。
その心の底から願っている要求とは、「私は仏になりたい」「成仏したい」ということです。成仏と言ったら死ぬ事と同じ意味に捉えられますが、成仏するということは、人間の迷い苦しみの根本である生死を超え、出離解脱することを意味します。よく命終えられたご遺体を「ほとけさん」ということがありますが、それは苦しみを生じさせる煩悩が既にはたらかなくなったお方である、苦しみから解放された安らかな姿である為そういう呼び方をするのです。
だからといって、死ねば苦の問題が解決するのだから今は関係ない、という事ではありません。限りあるこの人生を空しく過ぎたくない、今の私を満足できる生き方をしたいという深い願いがあります。この人類の願いに応えて阿弥陀如来はご本願を建てられました。そのご本願は、凡夫が浄土へ往生する唯一の道として、念仏をお勧め下さっています。真の満足をいただくということは、念仏し成仏する道であります。
仏教の話はよく分からない、難しいという声をよく聞くことがあります。私達坊主の法話に問題があるのかもしれませんが、人間がほんとうに求めている「仏に成りたい」という深い願いがはっきりすれば、その心に応えて下さる様にも感じます。 (貢 清春)
御正忌報恩講案内
恩に報ゆる生活
私共人間は、恩波の上に漂っている小舟のようなものである。前も恩、後ろも恩、右も恩、左も恩、過去も恩、未来も恩、私がこの世に居るということの一切が御恩である。この御恩は返しても返しても加わって来る。私共の生活は恩をうくる生活であると同時に恩に報ゆる生活である。この事を教えて下さったのが親鸞聖人である。聖人の教えが無かったら私は恩の中に居ながら恩を知らないでいたことである。これによって思うに聖人が私のうけている御恩の根本である。
一年三百六十五日、一日として報恩の日で無いのはない。毎日が報恩講である。その報恩講の最も根本的なるものが親鸞聖人の御恩に対する報恩講である。聖人の報恩講を営むことによって報恩の生活が明らかになるのである。毎年十一月、聖人の報恩講に逢うごとに報恩の中に育って居る自分を明らかにして頂くのである。故に私は毎年の報恩講が生活刷新の根元であると信じて居る。毎年報恩講を営むことによって生活のよろこびと力とを鼓舞せられることである。
(暁烏 敏 『報恩講の案内状に添ふる言葉』から)
聖人の御恩徳を憶い、今年の御正忌報恩講を厳修させて頂きます。真宗門徒、又福浄寺にとりましても最も大切な法要でありますと共に、そのお荘厳(おかざり)にも多数の御門徒の願いと、ご苦労と、日にちがかけられた、寺門あげての仏縁です。
どうぞ真宗門徒の証を立てるべくお繰り合わせ御参詣聞法下さり、またご一緒に勤行唱和をして下さいますようご案内申し上げます。
また、多くの方々の御縁をいただくことを願い、且つ、昔日の報恩講を偲びたく、粗餐でございますが、お昼のお齋を用意いたします。ご参詣の皆様、毎日お席について下さいますようお願い申し上げます。
記
一、日時 一月二十二日より二十八日まで
日中 午前九時半 逮夜 午後七時半
一、法話 福浄寺住職・若院(二十二日日中~二十四日日中まで)
北九州・徳蓮寺 伊藤 元師(二十四日逮夜~二十八日まで)
一、勤行 正信偈 真四句目下(大谷声明集 四五頁から五九頁)
念仏、和讃 五ッ淘、五遍反し 回向 願以此功徳
拠り所なくしては 人間は生きていない 広瀬 杲
今月の掲示板の言葉は「よりどころ」ということについて語られたものです。人間は必ず何かを拠り所として生きているということですが、日ごろ私たちは何を拠り所として生きているのか。そういうことを問いかける言葉ではないでしょうか。
私たちの暮らす文明社会は、人間の知恵が作り出した社会です。より早く、快適な生活を目指して、知恵を振り絞って作り上げてきた社会です。
日ごろ私たちは自分の理性、自分の知恵、知識というものを拠り所として生きています。ですから、一般的に理性的に物事を考えること、つまり私達が自分の知恵を十分に働かせることが賢いことであると思っています。その逆に十分に知恵を働かせないことは愚かなことだとされます。私たちは自分の知恵を拠り所とし、自分の思いに従って色々な行為、生活をしています。
しかし、その人間の知識には大きな闇が潜んでいるのです。ひとたび戦争になれば、その知恵、知識はたくさんの人を殺戮するために使われ、そしてあたかもそれが正義、正しい行いであるかのように正当化するのです。同じ人間である他の国の人びとを殺戮するために人知の限りを尽くして核兵器を作り出し、その抑止力で安全を守る。安全を求めるこころが破壊を求めるこころとなる、まさに矛盾が現実に現れているのです。人間の知恵は不可解としかいいようのないものです。
阿弥陀の智慧の光は人間の知恵を超えているという意味で、不可思議と教えられます。それゆえに人間の知慧のもつ闇を照らし出し、人間の愚かさを知らせます。法然上人は自らを「愚痴の法然房」といい、親鸞聖人もまた「愚禿親鸞」と名告られました。「智慧第一の法然房」と人びとから讃えられた法然上人自ら「愚痴の法然房」と語られたことは、人間の知恵を超えた阿弥陀の光をうけて、その光の中で自らの愚かさをよくよく知ったということを示すものです。人間が自らの知恵を誇り、拠り所とすることの悲惨さ、その愚かさを知った名告りです。
そのことを受けて親鸞聖人は最晩年の88歳の時に書かれたお手紙に
故法然聖人は、「浄土宗のひとは愚者になりて往生す」と候いしことを、たしかにうけたまわり候いし (『真宗聖典』603頁)
(今は亡き法然聖人が「浄土の教えに生きる人は愚者になって往生するのです」といわれたことを確かにうけたまわりました。)
と語られています。そして自分の愚かさを照らす十二の光に「帰命せよ」と和讃をおつくりになられました。
人知の闇に気付かぬ限り、私たちは飽くなき富の追及「貪り(むさぼり)」と戦争「瞋り(いかり)」のこころに捉えられてしまいます。ときに人知の驕りは厚い壁となり、一切の人びとを照らす阿弥陀の光に触れることを妨げます。その私たちにこそ、親鸞聖人は阿弥陀の智慧の光を仰ぐ者となることを念じておられるのです。深草誓弥
自分に都合がよければ 相手の悪も善にみえ
自分の都合が悪ければ 相手の善も悪にみえる 毎田周一
自分に都合のいい人は「良い人」だとほめ、自分に都合が悪くなると「悪い人」だとけなして言うように、その時々の自分なりの評価をして相手を価値付けをしてくこころがあります。人だけでは無く自然環境にも同じ様に、畑に種まきした後の雨は「恵みの雨」で、あまりにも降り続けば「悪天候」です。さらにおもしろいのは、同じ事実なのに受け取り方が人それぞれ違うという事もあります。恵みの雨と悪天候が同時に他人の中で起こるということです。何が良くて何が悪いのかは「考え方の違い、その時の都合」でバラバラになるのです。
何故この様なことが起こるのでしょうか。私達はそれぞれの過去の経験を基準にして「良し悪し」を決め、その事実が今と未来にどのような損得をもたらすのか、その価値付けを瞬時に判断します。そしてその良し悪しの価値付けを、「自分のものさし」として独自に造り出し、その「自分のものさし」を常識として大事にしながら生きているのです。
それが人間として当たり前の姿としてあるように思いますが、このこころを当たり前にしてしまうと、良し悪しという自分の評価・ものさしだけが大事で、実際に目の前で起こっている事実が認められなくなるのではないでしょうか。
そして自分にとって都合の良い相手、都合の良い事実は受け入れますが、都合の悪い相手や現実に対しては、拒否し排除しようとします。都合が良かった時には自分の手柄にして傲慢になり、都合が悪ければ恨みと愚痴しか出てきません。一つ一つの事実が受け止められず、一瞬一瞬の出会いが尊い出会いにならず、何に対しても向き合うこと無く過ぎてしまいます。存在自体は自分の都合の善し悪しを超えて現実を生きているのですが、こころは認めていないのです。
仏陀を「自在人」という名で呼ばれることがあります。何も縛られることがない、自由自在なこころを持つもの、という名前です。よく他人によって縛られていると云いますが、不自由にしているのは自分自身のこころではないでしょうか。良し悪しのこころによって自分自身が縛られている、そのこころを仏陀は「煩悩」であると教えられ、仏陀はその煩悩の絆を断ち切った自由な人、という意味で自在人なのです。
その時々で自分の都合の良し悪ししか思わない私達に、「今の現実を生き、向き合いましょう」と呼びかけるはたらきがお念仏です。お念仏したから、仏法に出会ったから、その御利益で良し悪しを分別するこころが全て無くなるわけではありません。お念仏のはたらきに会えば、良し悪しのこころに固執していることは、何の頼りにならないと気付かせてもらうのです。そしてそれぞれの事実が私を育てはぐくむ「ご縁」として頂戴できるのではないでしょうか。貢 清春
み仏に 救われありと 思い得ば 嘆きは消えむ 消えずともよし
伊藤佐千夫
伊藤佐千夫氏は正岡子規に師事し、アララギ派として明治、大正時代を生きた短歌歌人、小説家です。この歌を詠まれた背景には、わが子を不慮の事故で亡くしたということがあったといわれています。佐千夫は13人の子宝に恵まれていますが、5人は生まれて間もなく亡くなっています。明治42年、七女の七枝ちゃんは数えの3歳、満の1歳10ヵ月で亡くなってしまいました。その時のことを、左千夫は『奈々子』という小説に書いています。
左千夫が出かけていたら、長女と女中がやって来て、「お父さん大変です。七ちゃんが池へ落ちて」と知らせに来た。驚いた左千夫は飛んで帰ってみると、妻が台所の土間で火をたいて七ちゃんを温めようとしている。そのうちお医者さんが来たけれども手遅れだった。池にあおむけになって浮いていたと聞き、子どもが池に落ちたら危ないと思っていながら、どうして早く池を埋めてしまわなかったのか、と左千夫は悔います。近所の人や親類がやって来て、お葬式をどういうふうにするかと話し合っている。それを左千夫は不快に感じ、妻はたまらなくなって、「今夜はあなたと二人きりでこの子の番をしたい」と訴えます。左千夫は「自分はもう泣くより外はない。自分の不注意を悔いて、自分の力なきを嘆いて泣くより外はない。美しい死顏も明日までは頼まれない、我が子を見守って泣くより外に術はない」と書いています。その時に詠んだ歌が、
み仏に 救われありと おもひ得ば 嘆きは消えむ 消えずともよし
という歌です。七枝はお浄土へ帰っていったというけれど、大丈夫だろうか。仏様の国に生まれているだろうか。もし仏様に救われた確信が得られたならば、嘆きは消えるだろうか、安心できるだろうか。いや、「消えずともよし」、嘆きが消えなくてもいい。私は生涯かけて七枝のことを思い続けていく。それが左千夫の歌にこめられた意思ではないでしょうか。愛する子どもを亡くした親の気持ち、嘆きは「月日がたてば癒される」というような話ではないということを歌ったのです。
現在、「亡き人を偲ぶ会」という告別式が盛んに行われています。その底に流れているのは亡くなった人、「死」とのつながりを見失い、悲しみ、嘆くことが苦しく、嫌悪すべきことだという意識でないでしょうか。私たちは「悲しんでばかりいられない」と忙しくし、悲しむ人には「早く元気出せ」と励ますように、悲しみを苦しみとして、その厳粛な事実から逃れようとします。しかし、「悲しみ、嘆き」ということこそ、亡き人の存在から呼び起こされてくることではないでしょうか。
左千夫の歌には、念仏のなかで、自らのこころにおこる嘆きと正直に向き合おうとする精神が込められています。悲しみ、嘆きの深さが、逆に亡き人との関係の深さを証明するのです。そのこころを「消えずともよし」とする。我が身におこったこころを受け止めていこうとする姿勢です。困難に直面すれば、その苦しみを避け、空想の世界に閉じこもろうとする人間に、仏が事実を引き受ける智慧、「如実知見」をもたらすのが念仏です。 (深草誓弥)
○歎異の会(歎異抄の学習会)
第6回 真宗入門講座 まんが「宗祖親鸞聖人」に学ぶ
この度、第6回目の真宗入門講座を開催いたします。講座の内容は難波別院発行のまんが「宗祖親鸞聖人」をテキストにして、宗祖の御生涯を学んでいきます。講師に、京都東本願寺で真宗教学を専門に学んでおられる鶴見晃師をお迎えします。御多忙とは存じますが、お誘い合わせ御参加下さいますよう御案内申し上げます。
日時:平成26年
10月7日(火)午後19:30~
10月8日(水)午前9:30~
場所:福浄寺本堂
講師:鶴見 晃師
(真宗大谷派教学研究所研究員)
【前回までのあらすじ】
親鸞聖人33才の時、師法然上人の主著、『選択本願念仏集』の書写を許され、浄土へ生まれ往く存在としての確信と同時に、念仏者として「伝える」事の使命感を身にいただかれていきます。
また、門徒内で「一念義」と「多念義」の対立が次第に溝を深め、聖人は信行両座の会座を開かれます。門弟の誰もが行の座に着く中、親鸞聖人他、少数の門弟は信の座へ。最後に法然上人が信の座に着き、阿弥陀仏の本願を信じる事が、浄土往生の因であると示されました。
専修念仏の教えが京都に広まる一方、他宗からは和国の存立を脅かす存在と蔑視されました。その為、南都興福寺は念仏者達の九箇条の過失を取り上げ、朝廷に訴える事態となります。それからというもの、法然門下は他宗からの風当たりが厳しくなっていき、破門せざるを得ない門弟まで出る事態となり、その後、念仏宗の弾圧につながる事態へと展開していきます。
「我、今、帰するところ無く、孤独にして同伴無し」
源信僧都
今月の言葉は、源信僧都の「往生要集」に記されています。地獄の最も底「無間地獄(阿鼻地獄)」に落ち行く罪人が、地獄の苦を目の前にして泣き叫びながら詠む詩であります。そしてこの無間地獄から他の地獄を見れば、天での生活を楽しんでいるかの様にも見えると言われ、それほどに苦しみは想像を絶し、苦しみが暇無く、永遠に続くと説かれます。
地獄には「我、今、帰するところ無く」今の自分は安心して落ち着ける場所も無く、待っていて下さる人も無く、「孤独にして同伴無し」ひとりぼっちで連れ添ってくれる友もいない、そういう世界であります。
かつて私が少年だった頃に、機動戦士ガンダムというアニメを見ていました。今、再放送を子供と一緒に見るのが楽しみです。最終話で、敵対するシャアとの激戦の後、勝利したアムロはコアファイターという戦闘機で脱出、かろうじて大爆発の中から生還します。アムロは仲間達が待つ宇宙船を発見し、
「僕にはまだ帰れる場所がある・・・こんなにうれしいことは無い・・・」
という言葉を残し、涙しながら話が終わっていきます。広大な宇宙空間でどれだけ戦果を挙げても、帰還する宇宙船(帰る場所・迎え入れてくれる場)を見失ったら孤独のまま死を待つしかありません。今まで生き抜いてきたことの意味を失い、空虚のまま終わっていかなければなりません。
実生活の中でその事を考えてみると、私達の生活も帰る場所によって支えられている事を知らされます。帰る家があるから安心して仕事も出来ますし、旅行も楽しめます。そこで私を待ち、思っていてくれる人が居るからこそ、仕事の苦しさや旅の寂しさも耐えられるのです。帰る場を見失った状態は、永遠と続く地獄そのものなのかもしれません。
近頃、新しく出来た造語で、「圏外孤独」という言葉を知りました。「天涯孤独」をもじった造語で、携帯電話による交流が絶たれた孤独な状態を云います。自分が圏外にいると、メールの返事を返せない為に仲間はずれに、孤独になってしまうのではないか、と怯えているのです。電波で仲間とつながっているという安心感は、自分一人だけが取り残され、排除されるのではないかという不安を生み出しているのです。
沢山の人がそばに居ても、そこが圏外ならば居場所を失い孤独になっていきます。そこも地獄なのかもしれません。
今年も彼岸の時期になりました。真西に沈む夕日に向かい合掌し、「彼の岸」向こう岸の世界、「浄土」を感じる時期でもあります。人間が真に帰るべき方向を「彼岸の浄土」だと教えられてきました。孤独を感じ、人生の不安を感じる現代だからこそ、帰るべき「彼岸の浄土」という方向が必要なのです。その世界を発見し、共に歩む「同伴」して下さる人を見出せばこそ、生きて往く中で「こんなにうれしいことは無い・・」と喜びを実感するのでありましょう。 (貢清春)
亡き父母を 縁(えにし)に出遇う 無量の寿仏(ほとけ)
今年もお盆をむかえることになりました。毎年のようにテレビでは、故郷へ向かう帰省ラッシュが報道され、町内でも他府県のナンバーの車をよく見かけます。広く人びとの習俗に根ざした、このお盆という行事ですが、『仏説盂蘭盆経』からおこったと伝えられます。
この経には、次のようなことが語られます。盂蘭盆とは梵語ウランバナの音写で、意味は「さかさにつるされる」ということです。
釈尊の弟子に目連という人がおられました。神通第一といわれ、あらゆるものごとを見通す力を持っておられたといわれます。
その目連が神通力をえて、最初にしたことは、亡き母のことを見ることでした。目連が亡き母のことを見ると、母は餓鬼道に落ちて苦しんでいることがわかりました。
深く悲しんだ目連はすぐに鉢に飯を盛って母に捧げましたが、喜んで母がそれを食べようとすると、その飯がたちまち燃え上がり、食べることができません。
目連は母を救えないことを悲しみ、「どうしたら母を救うことができるでしょうか。」と釈尊に訪ねました。お釈迦様はそれに対して「それは、そなた一人の力ではどうにもならぬ。この七月十五日に、飯、百味、五果などの珍味を十方の大徳衆僧に供養しなさい。布施の功徳は大きいから母は餓鬼道の苦難からまぬがれるだろう」と語られたそうです。目連が、その釈尊の仰せにしたがったところ、母はたちどころに餓鬼道を逃れることができたということです。盂蘭盆はこの目連の故事から先祖供養の日となり、今日のお盆となっているのですが、一体これは何を教えていることでしょうか。何故お盆が人々のあいだで大切にされてきたのでしょうか。
私は「亡き人を念ずる」ということの深さを教えていることだと思います。念ずることは、自分勝手に念じたり、やめたりできることでなく、亡き人の存在が呼び起こしてくる不思議なはたらきです。目連も、亡き母の存在から呼び起こされて、母を念じたのでしょう。しかし、亡き母は餓鬼という、いつまでも満足を得ることができない境遇にあったといわれます。今日では施餓鬼という風習で、亡き人にお膳を施すことが伝えられていますが、私はこのことを、「亡き母が目連を念じて、安心できなかったのだ」とよみたいと思います。供養とは 亡き人に心配かけない 生き方を見つけることなんだ。 そのために仏法を聞くんだ。 心配かけない生き方とは一人一人が自立していくことなんだ」とある先生は供養について語られたそうです。
目連の物語では、母をたすけるために、仏、僧伽に供養をする、ということが説かれます。「さかさにつるされ」て、苦しむのは目連の母だけではないでしょう。迷いを迷いとも知らず、自分の思うことを「真実」と思い込み、自分ひとりで生きているように振舞う私たち。「亡くなった無量無数の者も、あなたも、いのちの底から求めてやまないことは何か。」そのことを明らかにすることをこそ、阿弥陀のいのちは願っているのでないでしょうか。
深草 誓弥
8月の「婦人会法筵」「盂蘭盆会法筵」の御案内
文明が文明を終わらせ、人間が人間を滅ぼす。人間が人間だけではなく、総ての生き物を殺す。この根本的な矛盾・悲惨・苦悩から人間は如何にして解放されるのか?人類の一人一人に荷わされている、この課題は深く、重い。
八月の婦人会法筵は、講師に崎戸の真蓮寺御住職、寺本 温師をお招きしまして、『仏説観無量寿経』について、『現代の聖典』に沿って御法話をいただきます。
先の児玉先生の言葉にあるように、日本は今当に、この深く、思い課題に直面しているのではないでしょうか。
『仏説観無量寿経』の序文では、ある国の王妃で、今まで何不自由ない生活を送っていた韋提希夫人が、実の我が子によって牢獄に幽閉されるという物語が説かれています。初めて苦悩の現実に直面した韋提希、しかし、その苦悩によって、「私は何のためにうまれてきたのか、この現実をどう背負っていけばいいのか」という自分自身のあり方を問い、浄土を願う身となっていきます。
先日の学習会において、「いのちは尊い」と本当に思っているのか、という話がありました。「自分のいのち」は大切、でも、自分のいのちを脅かそうとする者のいのちは大切ではない、だから戦争が起こるのだと。それは、果たして「自分のいのち」を大切に思っていることになるのだろうか。集団的自衛権が閣議決定し、日本はこれからどのような方向に進んでいくのでしょうか。戦争を引き起こしていくのは、他ならぬ自分の思いを頼りに生きている私たちです。このことを、『観経』の教えをいただきながら、自分自身のあり方を問うご縁にしていきたいものです。尚、婦人会法筵は、婦人会主催の法筵であり、会員皆様に限りませんので、御門徒皆様もお誘い合わせの上、御参詣くださいませ。
婦人会法要
日時 8月1日(金)~3日(日)までの3日間 午前9時半開筵
法話 崎戸 真蓮寺住職 寺本 温 師
盂蘭盆会法要
日時 8月16日(土)午前9時半開筵
法話 寺中
死 それは 生を脅かす 暗い影なのか
それとも 生を純化する 透明な光なのか
「直葬」(ちょくそう・じきそう)という言葉をよく耳にします。病院で亡くなられた方を、家には連れて帰らずに直接火葬場へ送るという葬儀の形です。家族や身内のみでのお別れとなり、住んでいた地域の人には知られることも無く、半ばひっそりと式が執り行われます。お葬式という場が開かれない為に、生前に縁のあった人達にとっては最後のお別れも出来ません。都会では1~2割が直葬だそうですが、今後、田舎でもこういう形のお別れが多くなれば、日常の場からお葬式という儀式も姿を消していき、「死」を身近に感じる場が少なくなるのではないでしょうか。
福浄寺で執り行われる葬儀では、もちろん高齢の方が多いですが、若い方の突然の死も時折ご縁があります。そのどのような葬儀の場でも、家族の方は死を悼み別れを悲しみ、沢山の方々が涙を流しながらお見送りをされます。
近年、弔辞としてお孫さんのお別れの言葉を読まれる時があります。自分を育ててくれた事のお礼や、生活の中での思い出話。叱られた事や応援してくれたこと、その人の存在に対しての感謝が綴られます。生きている時には言えなかった言葉が不思議にも、亡くなってから初めて言うことが出来ます。そして亡き人の存在が、より一層大きくなっていくものです。
死は会いたくないご縁ではありますが、愛する者と死別した人達にとってはその人との出会いを深め、自分の生き方が大きく問われるご縁でもあります。
お葬式は、亡くなった人をご縁として、無常を感じ、自分自身が「生きる」「生きている」事実を感じる仏教の行事です。平穏に日常を生きる私達は、生きることに慣れてしまい、『生かされている』ことを考えること無く、当たり前の様に生活しています。しかし「死」という非日常的な出来事に遇うと、日常とは変わった目線でものを考えるようになります。当たり前が、当たり前で無かったといただけることもあります。もっと日頃の出会いを大事にしなければならない、と思うこともあります。
つまり、「死」を考えるということは、今の「生」と向き合うことと繋がっているのです。それは今月の言葉の「生を純化する、透明な光」が表しているのではないでしょうか。純化ということは、濁りが除かれるということです。日常で濁らされた眼が「死」という光に照らされて、本来のあるべきいのちの姿を見せられていく、そういうはたらきがあるのでしょう。
無縁社会が拡大していけば、益々「直葬」が増えていくと思われます。「死」を身近に感じる場が少なくなり、より一層「死」は暗さを増し、自分には全く関係ない遠い未来のこと、となってしまうでしょう。皆で死を悲み、涙を流せる「葬儀」という場が昔あったと、未来の歴史教科書に載らないように願います。 貢清春
人のわろき事は、よくよくみゆるなり。わがみのわろき事は、おぼえざるものなり。 『蓮如上人御一代記聞書』
今月の掲示板の言葉は、『蓮如上人御一代記聞書』に収められている言葉です。
「人のわろき事は、能く能くみゆるなり。わがみのわろき事は、おぼえざるものなり。わがみにしられてわろきことあらば、能く能くわろければこそ、身にしられ候うと思いて、心中を改むべし。ただ、人の云う事をば、よく信用すべし。わがわろき事は、おぼえざるものなる」由、仰せられ候う。
(現代語訳)
「他者の悪いところはよく目に付くが、自分の悪いことは気づかない」と蓮如上人は語られます。この言葉のとおり、私たちの眼は常に外に向いていて、それぞれが評論家のように、自分の目の前の出来事、人物に対して、様々に評価を下しています。しかし、私の眼球が外は見えても、私自身を見るときには鏡が必要であるように、自分自身のことはなかなか問題にできないのです。
私は「わがみのわろき事は、おぼえざるものなり」というこの言葉が、親鸞聖人が「自力」として教えておられることと深く関係していると思います。聖人は、『一念多念文意』のなかで、自力について、
自力というは、わがみをたのみ、わがこころをたのむ、わがちからをはげみ、わがさまざまの善根をたのむひとなり
と語られています。自力は自分の力ということでなく、「我が身、我が心、我が力、我が行為」を依頼し、正当化して生きる、私たちの自己絶対化のこころです。
この自己正当化、自己絶対化という内容をもつ自力のこころで、私と他者を分け、私が「よかれ」と思った善意のこころで人を傷付けたり、無意識に人を踏みつけるのです。
私の妻がまだ妊娠中のころ、生まれてくる子供に「五体満足で生まれてほしい」と思ったことがありますが、そのこころは障害をもって生きている人に対しての強烈な差別心であるのです。その差別心は障害をもって現に生きている人から照らし出されるのです。
「ただ、人の云う事をば、よく信用すべし」、「人が教えてくれることに耳を傾け、素直に聞き入れなければならない」と蓮如上人が続けて語られていることは、「あなたの自力のこころの冷酷さを照らし続ける声なき声に耳を傾けなさい」ということであるとおもいます。 (深草 誓弥)
自由とは 不自由なことが 苦にならないこと
自由とは、自分を縛り付け支配されている「不自由」から解放された状態を言い、自分の思うがままの姿を言いますが、今月の言葉は不自由さが無くならず、不自由なままで苦にならない状態を「自由」と説いてあります。
一体何が本当の自由なのか、自分が自由になるとはどういう事なのか、考えてみましょう。
こういう書き込みを見つけました。タイトルは「早く自由になりたい、単身赴任になりたい」
投稿は30代後半で2人の小さい子を持つお父さん。仕事からの帰宅は早く、育児と家事を一生懸命こなしてこられたそうです。妻は専業主婦で小さ な子を抱えて睡眠不足の状態。妻には相手にされず、しょうが無いと分かっていても寂しい。正直家に帰りたくないのが本音で疲れ果てた状態。「早く自由にな りたい、単身赴任になりたい」という相談でした。
「分かる、その気持ち」と言うお父さん達も多いでしょうし、「子供の面倒見る私の苦労も分かってよ、私にはほとんど自由な時間なんて無いのよ」 と言うお母さん達の怒りの声も聞こえる気がします。子育ては生活スタイル全てが子供中心になり、自分のしたいことは二の次です。食べるものも寝る時間も子 供中心、泣いたらだっこしてあやし、遊び場が危なくないように気を使い、等々・・・体がきつくても休む暇は無く、付きっ切りで相手をしなければなりませ ん。今まで自分の事だけに費やしてきた自由な時間はほとんど無くなっていきます。
この様に、子育ての現場では自分の時間がそぎ取られ、不自由を感じている人が多いと思われます。しかし本当に子供が原因で不自由をしているので しょうか。不自由させている子供がいるのではなく、本当は目の前にある現実を受け止められない、子供と生活している今、その「時」を受け入れられない、と いう事が原因としてあるのではないでしょうか。
不自由と感じているときは、他に楽で良い場所があるはずだと、いつも思い通りになる世界を外に求めていきます。しかしそのような人は結局どこに 行っても「自分の居場所はここじゃ無い」と、この境遇に文句と不満ばかりを言い、愚痴をこぼして苦しんでいくのです。自分の人生であるはずなのに主人公に なれず、自分はいつもお客さんです。そうして何時までも、ここでは無い思いが叶う別世界を夢見ながら人生が空しく過ぎてしまうならば、これほど悲しいこと はありません。
阿弥陀の本願のはたらきは、人間に「転成」という利益をもたらします。本願のはたらきは、この様な私の空しさを超えさせ、不自由だと感じている 現実を積極的に受け入れていける者へと転じていくのであります。転じるということは、今現在の状況が変わることではありません。不自由さがなくなるのでは なく、不自由なままでも目の前の事に向き合いながら生きて行ける、そういう自由な人を生み出し続けるのであります。
東井義雄先生がすばらしい言葉を残してくださっています。
雨が降ったからといって
天に向かってぶつぶついうな
雨の日には 雨の日の
生き方がある
九州は梅雨の時期に入りました。雨降りの不自由な中でもちゃんと生きていける大地があるじゃないか。その様に勇気づけられる言葉です。 貢 清春
人は迂闊にも思っている 「自力で生きている」と。
他力の信心とは 「生かされている自分」と
「生かしてくださる仏」に出遇うことである
今月の掲示板の言葉にふれて、先生から教えていただいた言葉を思い起こしました。
「近代の人間は、自分というものがまずそれだけで在って、それから自分の生活が始まると思っている。そしてその自分の生の幸福を、その内容の充実を求めてやみません。」
(『人間の「原点」とは何か』 滝沢克己)
滝沢先生はキリスト教徒ですが、私たちが抱えている問題の根をいいあてておられます。「自分というものがまずそれだけで在る」、私たちは、日ごろ自分というものがまずこちら側にあって、その自分のむこう側に世界があり、そこに他の人々が居て、そこでいろいろな物事が起こっているし、また、むこう側に自分の人生をおいて眺めています。
こちら側で「まずそれだけで在る」としている自分こそが、自力のこころに生きる自分です。その自分は、よきもので、正しいものであることを思い込んで疑いません。ですから、自分のむこう側にいる他者は、その思いにかなっているものならば、認めて友とよびますが、自分の思いを満たさない、あるいは役に立たない者は、追い払うか居ても居ないことにします。自分の人生も、その思いにかなわなければ、「こんなはずではなかった」といわざるを得ません。
私たちは事実、「いま、ここ」に生きているにもかかわらず、私たちは事実と思いを対立させて、「ここではない、今ではない」と事実に背を向け、自分の思い通りになる世界を、「自力で生きている」自分の居場所を求めるというかたちで迷っているのです。
掲示板の言葉にある「迂闊」とは、私たちは誰もが安心しておれる居場所を求め、苦労するのですが、その求めが「自分というものがまずそれだけで在る」とする自力のこころから起こる限り、かえって自分の生きる場所を見失わせていることを知らずにいることを教えてあるのだと思います。
私たちは、思いにかなわない自分を見捨て、思い通りにならない場所は牢獄のような不当な場所として感ぜずにおれない自力のこころを、よりどころに生きています。しかし、その自力のこころから、見捨てられ、居ても居ないものにされてしまうような自分でも、事実、いま、ここに生きています。苛立ちしか感じない、思いにそぐわない場所でも、そこにいる私に声をかける人がいます。
「他力の信心」とは、私たちが求めている本来の願いに深くうなずく心です。我が思いを中心にして生きて、あたかも牢獄を逃れるごとく事実からの逃避を試みる私に、阿弥陀仏は「あなたはそこにいる。そこがあなたの場所だ」と呼びかけます。
「生かしてくださる仏」とは、自己中心的な我が思いしか持ち合わせていない私をあわれみ、悲しみ、真実に生かそうとする阿弥陀仏です。その仏に大悲されている私が「生かされている自分」ではないでしょうか。念じたもう仏を念ずる。そこに、事実の自分を自分とする人生が始まります。
深草誓弥
終わりの時
生死の苦しみを逃れようとして
生死に苦しんでいる これが迷いである (曽我量深)
仏教語で生死は「しょうじ」と読み、人間の生き死にという意味「せいし」ではなく、「生老病死」の四苦における始めと終わりの意味で、その苦しみの人生を繰り返していく迷いの姿を表現します。
命の姿としては当たり前の「生老病死」がなぜ苦しみとして感じるのでしょうか。それは自分の思い通りにはならない、人間のはからいで操作できない領分だからです。
生まれる事から思い通りにはなりません。生まれた時代、場所、家族の環境、国、男女等々、何故こんな所に生まれたんだろう、選べるならもっと良い所に生まれればよかったと、生まれた我が身がいただけない事があります。そこに苦しみの根本があります。
そして老いは時間と共に誰しもが平等にもらうものでが、自分の若かりし頃と比較しては「つまらんものになった」と気分がめいり落ち込むことがあります。また老いに伴い体が思い通りに動かなくなり、家庭や社会の中で相手にされなくなり、よってだんだん寂しくなっていく、その事も老いの苦しみとしてあるでしょう。
病むことは老若に関係なくやってきます。 どれだけ健康に気を付けていても、病気になる時は成ります。病気になると思っていた生活ができない、快適な人生を送れず健康な人が羨ましく思われます。
そして死ぬ事。今まで築きあげた全部を捨てて、この世を去って行かなければなりません。どれだけお金を持った長者でも、権力者でも平等に命終わっていきます。また死は人生の中で何度も訪れる様な事ではありません。他と違い体験した時が終わりの時となります。その事を考えると死苦とは、死ぬその時の苦しみよりも、死ななければならない自分を苦しむ、その事が大きな事と考えられるでしょう。
この様々な苦しみをどう解消すればいいのかと、人間は苦しみの消去方法を求めます。苦しみから逃れようとして、苦しみの無い快適な方向へ向かって対処していきます。
しかしお釈迦様は「なぜ苦しみが生じるのか」と苦しみの原因を見つめて行かれます。それは「生」この世に私が生まれてきたからだと教えられます。
赤ちゃんが生まれた時、家族や知人には大きな喜びがあり、母親は出産時の陣痛も忘れてしまうくらいの感動と喜びをいただくと言います。しかし一方の赤ちゃんは泣きながら生まれてきます。人が誕生したという事は、苦しみを感じる体をいただいてこの世に出てきたということなのでしょう。要するに、その体が無くなるまでは苦しみからも逃れられないという事、それが道理なのだと諦かに教えられなければなりません。
道理に立ち、自身の事実に立ち、苦から逃げずに受け止めていこう、その事を曽我先生のこの言葉から頂きました。 貢清春
念仏申すということは
念ぜられている自分のいのちに
出遇うということ 宮城 顗
今月1月22日より7日間、親鸞聖人の命日を縁として御正忌報恩講が厳修されました。親鸞聖人の御命日を縁として勤められる法要ですが、釈尊から親鸞聖人にまで、そして、親鸞聖人から私にまで到りとどいている念仏の歴史に遇うことが願われ、大切につとめられる御仏事です。
『歎異抄』の第二条において親鸞聖人は、関東の同行たちを前にして「親鸞におきてはただ念仏して弥陀にたすけられまいらすべしとよきひとのおおせをかぶりて信ずるほかに別の子細なきなり。」といいきられます。
関東から親鸞聖人をたずねた同行たちの関心は「念仏は浄土に生まれる種なのか、それとも地獄に落ちる悪業なのか」ということにありました。念仏の品定めをしているのです。「念仏していつの日にか浄土に往生して仏になる」と、階段を上るような、自分を向上させるための手段として念仏をとらえていたのでした。その手立ての念仏がいろいろな風評、自分自身の自信のなさで揺らいでしまうと、往生も成仏も夢物語になります。「念仏がたしかな手段なのかはっきりさせなければならない。」そういう焦燥感にかられ、京都の親鸞聖人をたずねてきたのです。
しかし、関東の同行を待っておられたのは念仏についてその利益、効果や有難いいわれを講釈するのでなく、ただ、仏の教えにしたがい、「よきひとのおおせ」に生きる親鸞聖人でした。法然上人と出遇い、「生死出ずべきみちをばただ一筋に仰せられ候いし」、人間として生きることはどういう答えを持っているかでなく、本当に自分自身に深く頷いて生きていけるかという問いをもち続けること、その言葉に出遇い、念ぜられている自分のいのちの問いかけに真向かいに生きておられる親鸞聖人でした。
『御伝鈔』に記されている親鸞聖人の臨終を伝える、「ついに念仏の息たえましましおわりぬ」という言葉は、生活の片手間に念仏をされていたことをあらわしているのではありません。念仏を物のように自分の前において品定めされていたのではありません。念ずる仏のはたらきのなかで、念仏の空気の中で念仏の呼吸をして生き、命終えられていったことをあらわしているのではないでしょうか。
『念仏は「えらばず、きらわず、みすてず」の阿弥陀仏のこころが私たちのもとにきて、南無阿弥陀仏の念仏となって私どものために跪(ひざまず)き、率先して念仏しているのです。』 狐野秀存先生
掲示板の宮城先生の言葉は、私たちが念仏申すということは、救われる手段としての念仏ではなく、「どんな境遇であっても、あるがままを自分の本当の人生として選び取りなさい」と呼びかける仏の御名に願いを聞くという、念仏の中で生活された親鸞聖人の姿勢を表す言葉です。
深草誓弥
恩に報ゆる生活
私共人間は、恩波の上に漂っている小舟のようなものである。前も恩、後ろも恩、右も恩、左も恩、過去も恩、未来も恩、私がこの世に居るということの一切が御恩である。この御恩は返しても返しても加わって来る。私共の生活は恩をうくる生活であると同時に恩に報ゆる生活である。この事を教えて下さったのが親鸞聖人である。聖人の教えが無かったら私は恩の中に居ながら恩を知らないでいたことである。これによって思うに聖人が私のうけている御恩の根本である。
一年三百六十五日、一日として報恩の日で無いのはない。毎日が報恩講である。その報恩講の最も根本的なるものが親鸞聖人の御恩に対する報恩講である。聖人の報恩講を営むことによって報恩の生活が明らかになるのである。毎年十一月、聖人の報恩講に逢うごとに報恩の中に育って居る自分を明らかにして頂くのである。故に私は毎年の報恩講が生活刷新の根元であると信じて居る。毎年報恩講を営むことによって生活のよろこびと力とを鼓舞せられることである。 (暁烏 敏 『報恩講の案内状に添ふる言葉』から)
聖人の御恩徳を憶い、今年の御正忌報恩講を厳修させて頂きます。真宗門徒、又福浄寺にとりましても最も大切な法要でありますと共に、そのお荘厳(おかざり)にも多数の御門徒の願いと、ご苦労と、日にちがかけられた、寺門あげての仏縁です。
どうぞ真宗門徒の証を立てるべくお繰り合わせ御参詣聞法下さり、またご一緒に勤行唱和をして下さいますようご案内申し上げます。
また、多くの方々の御縁をいただくことを願い、且つ、昔日の報恩講を偲びたく、粗餐でございますが、お昼のお齋を用意いたします。ご参詣の皆様、毎日お席について下さいますようお願い申し上げます。
一、日時 一月二十二日より二十八日まで
日中 午前九時半 逮夜 午後七時半
一、法話 福浄寺住職・若院(二十二日日中~二十三日逮夜まで)
北九州・徳蓮寺 伊藤 元師(二十四日~二十八日まで)
一、勤行 正信偈 真四句目下(大谷声明集 四五頁から五九頁)
念仏、和讃 五ッ淘、五遍反し 回向 願以此功徳
門徒報恩講案内
今年も愈々師走になります。 就きましては、1月の御正忌報恩講から始まり、また本年の最後のしめくくりの法要、「門徒報恩講」を例年の如く下記により勤めさせて頂きますので、皆様、宗祖親鸞聖人の御恩徳を憶い、報恩感謝の志をお運び下さい。そして各地区仕出し当番の皆様の、昨今では中々味わえない手作りの精進お斎をいただいて下さい。皆様のお繰り合わせの御参詣を念じます。尚、参詣日は一応の目安です。都合の付かれる日でもかまいません。
当日の勤行は正信偈三首引きでつとめます。御和讃は、赤表紙の勤行本五六頁「三朝浄土の大師等」からの三首です。ご一緒にご唱和下さい。
日程(下線印は仕出し当番) 勤行は午前10時からです。
12月10日 木場講 (上、下)
11日 川原、石木講(上、中、下)
12日 音琴講(口木田、大音琴、小音琴、彼杵) 口木田、大音琴
13日 西講ノ上(波佐見、中山、刎田、岡谷、川良、野口)
14日 西講ノ中(中組、宿、岩立、上、下百津)
15日 西講ノ下(栄町、城山、数石、住宅) 日曜学校参加
16日 西講ノ西(下組、平島、琴見ヶ丘、白石、三越、小串、惣津、新谷
17日 五反田(上、下)、猪乗講 及び町外
後ろめたい事を 秘密にしつづけると
いつの間にか 正しい事にしてしまう
だから いつも鏡が必要なのです
今、国会では「特定秘密保護法案」の成立が急がれる一方、世論においては法案成立に不安感や不信感が急速に広がっています。
首相は法案成立によって「国民の安全が守られる」と連呼しておられますが、この法案では何を秘密にするかも秘密にされ、その秘密を知ろうとしたり、他人に教えたり、大衆に呼びかけたりするだけで連行され、処罰される可能性もあるといわれています。
「国民の安全」を守る法案によって、私達の生活が不安になり脅かされるのならば、本末転倒です。また、国家の秘密によって日本の平和や国民の安全が支えられているのならば、この国の平和、安全は非常に不安定なのかもしれませんし、今まで日本は安全ではなかったのだろうかと不審に思う次第です。
どうか、議員の方々には後ろめたくない、公開された政治を行ってほしいと思いますが、今月の言葉の「後ろめたい事」は私達の生活の中にもある事ではないでしょうか。例えば、つい悪い事をしてしまって他人には言えない。その事が家族にばれたら大変なことになる・・・。その様な時は「後悔」という感情が生まれます。自分のしたことが悪かったと悟ったら、今度からは絶対にしないと心に誓います。その心が「謝罪」という、他に対して自分の行為をわび、許しを求めていくこともあります。
しかし人間にはもう一つ「肯定」の感情が生まれる時もあります。色々言ってもしようがない、仕方がないんだと。自分は間違っていないんだと開き直り、自分を正しい事にしてしまう心です。その時には罪を公開することはせず秘密にしていきます。そしていつの間にか、秘密にしている事に何の罪の意識も無くなり当たり前になっていきます。
その様な人間の心を悲しみ、自分自身の本当の姿に目覚めてほしいと、立ち上がった仏様がおられます。それが阿弥陀如来です。その阿弥陀の教えとは、如何なる教えでありどのようなはたらきがあるのかという事を中国の善導大師は「経教はこれを喩うるに鏡のごとし。しばしば読み、しばしば尋ぬれば、智慧を開発す」と仰います。
お経という鏡の前に立てば、その者の心の姿や身の事実を偽りなく映し出され、その人間の心によって作り出している娑婆の姿も映し出して教えて下さるといわれるのです。お経を拝読するということは、先祖を供養するための道具でもなければ、自分の都合の良い様に欲望を叶えてくれる魔法の杖でもありません。お経はどこまでも自身を知らしめるはたらき、智慧そのものであります。
だからこそ「しばしば読み、しばしば尋ねる」必要があるわけです。「しばしば」とは、時々たまに等の意味ではなく、何回でも、たびたびという意味です。何度も何度も教えによって自分自身の姿を確かめていかなければ、いつでも自分の行為だけが正しいのだと開き直り、あやまちに気がつかないで生きてしまいます。どんな時も私を映してくれる鏡があれば、間違いが間違いとして知られ、迷いが迷いと知られて生きていけます。
ネクタイが曲がっている事は自分では気がつきません。教えてくれる人や鏡がなければ、まがったままで自分自身が恥をかきます。鏡を見ても、注意されても言うのでしょうか、「いいえ、これは国民の安全のためです」と。 貢 清春 平成25年12月
第5回 真宗入門講座 まんが「宗祖親鸞聖人」に学ぶ
この度、第5回目の真宗入門講座を開催いたします。講座の内容は難波別院発行のまんが「宗祖親鸞聖人」をテキストにして、宗祖の御生涯を学んでいきます。講師に、京都東本願寺で真宗教学を専門に学んでおられる鶴見晃師をお迎えします。御多忙とは存じますが、お誘い合わせ御参加下さいますよう御案内申し上げます。
日時:平成25年 11月11日(月)午後19:30~
11月12日(火)午前9:30~
場所:福浄寺本堂
講師:鶴見 晃師 (真宗大谷派教学研究所研究員)
【前回までのあらすじ】
京都吉水の法然上人の門下に入り、ようやく唯念仏の教えにたどり着いた親鸞聖人。そこで様々な人々との出遇いによって、情熱的な浄土の仏道の学びを進めていかれます。法然上人が説かれる念仏の教えは男女貴賤の隔てはなく、何の条件もなく平等に阿弥陀の本願に救われていく教えでした。しかし、吉水で念仏の声が広まると同時に、専修念仏の教えを曲解して身勝手な言動をする者も中にはいました。その様な人々の思いもよらぬ振る舞いが、やがて比叡山からの「元久の警告」となり、吉水教団の活動自粛を迫られる事態へと展開していきます。その様な時に法然上人の主著「選択本願念仏集」の書写を許された聖人は「善信」と名を改め、より一層の浄土教の研鑽につとめられました。
何の為に生まれて 何をして生きるのか
答えられないなんて そんなの嫌だ
何が君の幸せ 何をして喜ぶ
解らないまま終る そんなの嫌だ やなせたかし
この詩を作られたのは「アンパンマン」の原作者、やなせたかしさんです。やなせさんは「手のひらを太陽に」の作詞をされた方としても知られています。先日、10月13日にやなせさんは94歳で亡くなられました。アンパンマンは1973年の絵本雑誌掲載から40年、1988年のテレビアニメ放映開始から25年が経った今も、子供たちを中心に大人気で、誰もが知っているといっても過言ではありません。
私も小さいときからこの「アンパンマンのマーチ」に親しんできました。あらためて立ち止まってみると、やなせさんはいのちの根源の問いをアンパンマンを通して私たちに呼びかけておられたのでした。「何の為に生まれて 何をして生きるのか 答えられないなんて そんなの嫌だ」という言葉は、「あなたの本当に欲しているものは何か?いのちがけでほしいものがあきらかになっているのか?」という問いかけです。
私たちは日ごろ様々なものを欲して、頼りにして生きています。車、お金、家、地位、名誉。しかしこれらは生きるための手段としての宝には違いありませんが、「いのちがけでほしいもの」といわれると言葉に詰まってしまいます。日ごろ欲しているものは生活の境遇、暮らしを豊かにしようと求めているものです。しかし、はたしてその日ごろ欲している、そのもののために私は生まれ、生きて、いのち終えていくのだと胸をはって言えるでしょうか。
臨床医師として多くの方々の死を見取られたキューブラー・ロスさんは「私はいい生活をしてきたけれど、本当に生きたことがありません」という、死を前にしたひとりのアメリカ人の言葉を紹介されています。この言葉を残された方は、自らは死ぬるいのちを生きているものだと、死と直面し、人生全体の意義が問われる中でこの言葉を残されたのだと思います。この言葉は、やなせさんの言葉「答えられないなんて そんなの嫌だ」と相通ずるものがあります。この二つの言葉の根底に流れているのはいのちのさけびです。
私たちのいのちは、煩悩というものをもって、いつでも自分自身を偉い者であるとか、幸せでなければならないと、理由も無く思って腹を立てたり、嫉妬したりして生活しています。しかしそういう自我意識と、「あるがままの自分を生きていきたい」という意欲があります。私たちは「本当」を求めずにおれないような、いのちのさけびを生まれたときから具えています。それが願というものです。
『無量寿経』に説かれる法蔵菩薩の物語は、自分の外に存在の根拠を求める国王だったものが、世自在王仏に出遇い、仏を信ずるこころがおこったという物語が説かれます。仏は自在人と訳されるように、どんな境遇にあっても与えられた境遇において、「自らここに在り」と満足しておる者です。ここでの仏との出遇いは「あるがままの自分自身を喜べていますか」ということでありましょう。「~のために生きる」というのではなく、私がこのいのちを受け止め生きることが本当の幸せであり、歓びであることを、「信心歓喜」という言葉が気付かせてくれます。
深草誓弥
「空過」
もし健康と長生きだけが幸せだとするならば
最後は死という不幸で終わっていく
そこに本当の幸せがあるだろうか
私達が日頃から大切にしているものの一つに「健康」があります。しかしこれも度を過ぎると「健康のためなら、死んでもいい」となるそうです。冗談の様ですが、健康を獲得し維持する為に死にものぐるいで様々な健康法を試し、健康食品を買いあさっていく。よくよく考えると、健康が崩れ去る恐怖に怯えながら生きなければならない、その様な姿は傍から見ると「不健康」なのかもしれません。
しかし、自分もいつかは死ぬのだという事を忘れているわけではありません。でも死を迎える瞬間は「ピンピンコロリ」を望んでいると聞きます。息が切れる直前まではピンピン元気で、誰にも迷惑をかけず、苦しみもせず、コロリと一瞬で逝きたい。笑い事のようですが、そう願っている人は少なくはないと思います。
この様な言葉が生まれてきた背景には、生きること健康にのみ意味があって、老いること・病むこと・死ぬことは敗北だとする現代の価値観が、そう言わせているのかもしれません。
そういう価値観が生まれる原因の一つとして、日常生活の現場から老・病・死が姿を消しているということがあげられます。核家族化が進み老人とは別居。病気で寝込むこと事があれば病院へ。死に逝く姿、臨終の場面でも自宅で身内に囲まれながら看取られる事はほとんど無くなりました。現代に於いて老・病・死はすでに家の外の事で、肌身で感覚し確かめる場面が少なくなったのだと思います。しかし、どんなに我が身体に執着して健康に気をつけても、死は自ずと訪れます。「人生は長生きに意味がある」「健康こそが第一だ」という価値観は本当なのでしょうか。
お釈迦さまは、生後わずか1週間ほどで母マ―ヤ夫人と死別され、29才の四門出遊という場面では、老・病・死という人間の苦しむ姿を見て出家を決意したと記されています。死別の悲しみ、老病死する不条理な姿を見られたお釈迦様は6年後、悟りを得て仏陀となり「諸行は無常であり、すべて移り変わる」と教え示されました。無常の我が身は老・病・死し、自分の思い通りにはならず、苦しみの人生を生きるのだとも教えて下さいました。
そう教えられていながらも、我が身の「無常」という、老・病・死の人生の事実に立つことができず、「無常」の事実に対して善し悪し、好き嫌い、苦か楽か、幸か不幸といった分別を加えてしまいます。
その様な私達に親鸞聖人は、「本願力にあひぬれば むなしくすぐるひとぞなき」と和讃されています。あなたの人生を不幸のままで終わるんですか、空しく過ぎない人生がすでにお念仏によって開かれていますよ、お念仏に遇いましょう、本願のはたらきに出遇いましょう、と呼びかけて下さっています。
本願のはたらきに出会えば、無明の闇がやぶられると教えられます。無明とは、真実に暗く、人生を指し示す明かりがなく、本当でないことを本当にして生きている姿を言います。その無明の闇が破られるということは、自分の考えを絶対とする在り方や、自己中心の分別で生きる自らの我執が知らされるということです。
思い通りにはならなくても、どのような苦難の人生でも、我が身を救わんとする如来の本願のはたらきに頭が下がることがあれば、老・病・死するわがいのちを不幸と決めつけずに、生き抜いて行けるのだと思います。それこそが人生における幸せであり、空しく過ぎない生き方ではないでしょうか。
貢清春
永代経法要の御案内
亡き父母を 縁(えにし)に出遇う 無量の寿仏(ほとけ)
仏壇の中のお母さん (小学校三年男児)
『ぼくは、あかんぼうのときおとうさんをなくしたので、きょうだいもなくお母さんとふたりきりでした。そのお母さんまでがぼくだけひとりおいて、お父さんのいるおはかへいってしまったのです。いまはおじさん、おばさんのいえにいます。まいにち学校にいくまえに、お母さんのいるぶつだんにむかって、いってまいりますをするので、お母さんがすぐそばにいるようなきがします。お母さんはぼくのむねの中にいて、ぼくのことをみています。』
生きているものだけがただ出会うだけでなくて、なくなった方でも、ちゃんと常に出会っている。生きていらっしゃった時よりも、もっと本当に出会っている。これが仏様の願いに答える出会いの世界じゃないだろうか。 (東井義雄)
声なき姿なき親を前にして、我々は何を思うだろうか。「亡き人が、亡き身をもって、何を語ろうとしているのか」という、声なき人の声に耳を澄ませる時、常に私を見守り続ける亡き人の「ねがい」が聞こえてくるに違いない。
秋の永代経法要を下記の如く厳修致します。永代、無量寿の経教に依って御先祖の遺徳を偲びつつ、御恩の誠を尽くさんがための聞法の御縁にお遇い下さいませ。
記
日時 平成25年 10月18日(金)~20日(日) 午前9時半開筵
講題 「亡き人、先祖とは、その供養とは」
講師 福浄寺、住職及び寺中
生死一如 片方ばかりみているから まちがう
生死一如という言葉は、私たちが「生きる」ということは、「死のある生」を生きているというあるがままの姿を教える言葉です。「一如」の一は二つに分けられない絶対を意味し、如は異なることのない真実そのものを意味します。
私たちは「死の無い生」ではなくて「死のある生」だということは、身近な人の死にあって、見て、知っているはずです。しかし私たちは死を恐れ、死のことを忌み嫌い、見ないようにして「死の無い生」、自分は死なないもののようにして生きています。
そのあり方がはっきりと現れてきているのが、現代における葬儀の形骸化という問題です。亡くなった人との関係を、「お別れの会」をすることで断ち切っていこうとします。「悲しんでいてはいけない、早く忘れて元気にならないといけない」という発想は、亡くなった人は「無くなった人」であり、生きているということにしか価値を見い出せないということを表します。生と死を分離して、自分にとって都合のいい「生」をもとめ、自分にとって都合の悪い「死」を遠ざけようとします。掲示板の言葉の「片方ばかりみているから」という片方は自分にとって都合のいい「生」です。その「片方ばかりみているからまちがう」私たちのあり方を蓮如上人は
『ただ今生にのみふけりて、これほどに、はやめにみえてあだなる人間界の老少不定のさかいとしりながら、ただいま三塗八難にしずまん事をば、つゆちりほども心にかけずして、いたずらにあかしくらすは、これつねの人のならいなり。あさましといふもおろかなり。』
蓮如聖人「御文」二帖目一通
「今生にのみふけりて」、今の生を延ばすことしか考えないで、自分の都合にあう物事だけを追い求め、「いたずらにあかしくらす」、空しく日々を送っていると歎いておられます。中陰、逮夜のお勤めの際に「白骨の御文」を拝読していますが、その最後に
『たれの人もはやく後生の一大事を心にかけて、阿弥陀仏をふかくたのみまいらせて、念仏もうすべきものなり。あなかしこ、あなかしこ。』
蓮如聖人「御文」五帖目十五通
とあります。亡くなった人、白骨を前に、どんな人もただ今の問題として、阿弥陀仏の尊前で、亡くなった人と自らも同じ「死のある生」を生きる者として、「この死のある生をどう生きることが真実にかなうことか」と問うべきであると蓮如上人は語られます。先に命を終えていった人も、今を生きる私たちも、このいのち自身が持っている課題、「後生の一大事」は、死が終わりとなるような生を超えることです。自分の都合の善し悪しを拠りどころとしない。そのことに目覚ましめる呼びかけが、「生死一如」です。
深草 誓弥
○歎異の会(歎異抄の学習会)
やりなおしのできない人生とは知っている
しかし分かったように生活はしていない
「諸行無常、老少不定」・・・度々法話で紹介する言葉です。「一日一日が大事で取り返しの付かない、やりなおしのできない日々を暮らしているのです」と、偉そうに法話として話していますが、その様に自分が確かに理解し、生活しているかと問われると、そうではありません。大事に一日を過ごしているどころか、しなくてもいい事を率先して行い、今しなければならない事を先延ばしにして生きているように思います。まさにこの今月の言葉がぴったりと自分の姿を言い当てています。
今月の言葉を通して思い浮かぶ言葉が二つあります。まず一つ目は「解学・げがく」です。教えの言葉を学んで、知識として知っていくという学び方。知識的了解を表すもので、仏教を学問や教養として学んでいくという意味があります。
そして2つ目は「行学・ぎょうがく」です。それは仏教を生活の中で学んでいくという在り方です。人生を通して教えを確かめていこうという了解で、生活に即して仏教を学ぶという意味があります。この二つが仏教の学び方だと言われています。
今月の言葉でいえば、前半が解学に相当し、後半は行学に相当すると考えられます。そして、私達が仏様の教えをどの様に聞いているかを問われている言葉でもあります。お寺に足を運び、講師の先生の話に耳を傾け、その時だけは分かった気になることがあります。しかし実際の生活では教えどころではなく、善し悪しの自分勝手な分別で過ごし、仏様を拝む様な生活は全くしていない。それは本当に仏法を分かったこと、聞いている事にはならないのかもしれません。
一見して「行学」が良くて「解学」を否定しているようにも感じますが、そうではありません。私たちの仏道の歩みは、解学として知ることから始まります。そこで知った仏語が、現実の生活の中で苦しみや悩みが起こった時に「そうだった、この事を言われていたんだ」と気づかされることがあります。言い当てられる言葉がないと、苦悩がただ通り過ぎてゆくだけになってしまいます。自身を明らかにしてくださる言葉や法を解学として学んでいればこそ、自身の苦悩から逃げ出さずに、行学としての歩みを生きていけるのではないでしょうか。解学があってこその行学であります。自身の姿が教え(法)によって知らされればこそ、もう一度精進して道を求めようという心が芽生えてくるのでありましょう。
貢清春
故郷に帰れないから帰らないのと
帰れるけれども帰らないのとは違うのです 伊奈教勝
この言葉を残された伊奈教勝氏は1922年に真宗大谷派の寺院に生まれられます。しかし、1945年にハンセン病を発病され、「らい病は恐ろしい伝染病、遺伝病である」と誤った考え方にもとづく当時の法律、「らい予防法」によって、1947年から長島愛生園で隔離された生活を余儀なくされました。
伊奈氏は故郷を奪われ、人間としての存在を否定される強制隔離政策をうけ、故郷の家族に迷惑がかからないように、本名を捨てて「藤井善」と名前を変えて生活されます。「らい予防法」はハンセン病が薬で治るようになっても、1996年に廃止されるまで存在し続けた法律です。救済という名のもとにハンセン病患者を隔離し、共に生きる願いを放棄して存在そのものを隠してしまう法律です。伊奈氏は1989年に一度捨てた姓名を再び名告り、ハンセン病の正しい理解と知識を人々に訴える活動を始められます。本名を名告ることについて、伊奈氏は次のように述べられています。
「人間とは関係としての存在であります。お互いに「いのち」の尊厳を侵さないことが基盤でなければなりません。本名を名告るということは、私の「いのち」の尊厳を明らかにし、人間解放への宣言であります。それはまた同時に、他者の「いのち」の尊厳を確認することでもあります。」
差別は本質的に排除行為です。名前を奪うことは、その人がそこにいるにもかかわらず、そこにいないもののようにして排除することです。アニメ『千と千尋の神隠し』のなかでハクという少年が、「名前が奪われると帰り道が分からなくなるんだよ」と語るように、名前は故郷、私の存在の大地と深く結びついています。「故郷に帰れないから帰らない」と伊奈氏が語られていることは、故郷を奪われ、自ら「藤井善」と名を変えなければならなかった、強制隔離という差別の歴史を物語っています。「帰れるけれども帰らない」という言葉はどいう意味をもつのでしょうか。伊奈氏は公の場で本名を名告り、苦悩の末に故郷に帰ることを選ばれます。
「私にいつ帰ってきてもいいよと故郷が回復した時、私は療養所の仲間と一緒に納骨堂に入ろうと思った。心から安心できた。帰る自由と帰らない自由が私に与えられた」
安田理深先生は「存在の故郷」という言葉で浄土を教えておられます。「いつ帰ってきてもいいよ」という私の存在を受け止める故郷が回復したことで、伊奈氏は安心して、願いのかけられた自身のいのちを生きるという自由を獲得することができたのです。
私たちにとっての一大事の問題は、いつでも私は私自身でありうるか否かということに尽きます。現代という時代は人間のつくった価値観が人間を支配していく時代です。この時代のなかで、どのような私であっても、あるがままを私自身とすることのできる法が浄土真宗の法です。伊奈氏が本名を名告ることを選ばれた背景には、私と他者の「いのち」の尊厳を回復したいという願いがあります。その願いは名を奪うことによって、私が私自身である権利を奪う差別への深い悲しみから生まれているのです。それは「国に地獄、餓鬼、畜生なからしめん」とする法蔵菩薩の願心と通ずるものです。互いが互いを照らしだし、証明しあえる人間関係を実現したいという名告りです。
深草誓弥
第4回 「真宗入門講座」 開催
この度、第4回目の真宗入門講座を開催いたします。講座の内容は難波別院発行のまんが「宗祖親鸞聖人」をテキストにして、宗祖の御生涯を学んでいきます。講師に、京都東本願寺で真宗教学を専門に学んでおられる鶴見晃師をお迎えします。御多忙とは存じますが、お誘い合わせ御参加下さいますよう御案内申し上げます。
日時:平成25年 6月10日(月)午後19:30~
6月11日(火)午前9:30~
場所:福浄寺本堂
講師:鶴見 晃師 (東本願寺教学研究所研究員)
○歎異の会(歎異抄の学習会)
日時 6月20日(木) 午後8:00から
場所 福浄寺門徒会館
○法音の会(仏教讃歌を歌う会)
日時 6月14日(金) 午後7:30から
場所 福浄寺本堂
○仏教青年会
日時 6月 日( ) 午後7:30から
場所 福浄寺本堂 *講師に河野通成先生をお迎えする予定です。
○日曜学校
日時 ① 6月9日(日)9:00~10:00
② 6月23日(日)9:00~10:00
あなたのなかの
ほとけさまが
わたしのなかの
ほとけさまに
微笑みかける
祖父江 文宏
この言葉を残された祖父江文宏さんは、長年、児童養護施設「暁学園」の園長を勤められた方です。祖父江さんは子供を尊重し、「子供」と言わず、「小さい人」と呼んでおられたそうです。体を張って虐待をうける子供を保護してこられた、その姿勢は子供たちに伝わり、子供たちから親しみをこめて「園長すけ」と呼ばれていたとも聞いています。この掲示板の言葉は、その祖父江さんの姿勢をつらぬく芯のようなものではないかと思います。
この言葉を見たときに私が思い起こしたのは、『仏説大無量寿経』にある「仏仏相念」という言葉でした。この「仏仏相念」という言葉は釈尊を、仏弟子阿難が光と仰ぎ、仏と仰ぐこころがおこったところに語られている言葉です。阿難は釈尊の高弟で釈尊が亡くなるまで常に傍につかえて話を聞いておられたため、「多聞第一」と呼ばれた方ですが、「未離欲」とも呼ばれ、情が深いために、なかなか目醒めることができなかったとも伝えられます。
『仏説大無量寿経』では、釈尊はその阿難に対して、阿弥陀如来の本願の教えを説かれます。そこで阿難は「ほとけさま」としての釈尊と、「ほとけさま」とならしめている仏法と出会い、その仏法に共に深くうなずく無数の人々に出会っていくことになります。釈尊も法に出会い「ほとけさま」となられたのです。ですから釈尊はその法を説くことができるのですが、阿難に対してその法を説くのは、自分と同じように苦悩する衆生に、苦悩の本は自我意識、「自分の都合でえらび、きらい、みすてるこころ」であることを知らせ、「自分も他者も、えらばず、きらわず、みすてずに生きよ」という阿弥陀如来の本願の教えこそ真実だと知らせんがためです。
「仏仏相念」という言葉は「仏と仏とが相念じる」世界、「あなたのなかにも仏になりたいというこころがある」という本願のこころに互いににうなずき、尊敬しあえる世界です。それに対して私たちの「我が思いの世界」は、閉鎖的で、恨み、蔑みばかりで、人を光り輝くように見れる世界ではありません。この掲示板の言葉で大切なのは、「あなたのなかの ほとけさまが」と、「わたし」ではなく、「あなた」からはたらきかける「微笑み」があるのだというところです。
私事ですが、近頃、四ヶ月になった息子の弘樹がよく笑いかけてくれるようになりました。この「微笑み」というはたらきは、かたくなな「わたし」の思い計らいを破り、私に対しての無条件の信頼を表しておるように思います。
(深草誓弥)
4月28日、日曜学校の時に撮った記念写真です
満開のオオヤマミツバツツジの前で、みんな笑顔での撮影になりました。
今年度の日曜学校の申し込み参加人数は、45名になりました。
次回はお釈迦様の花祭りになります。その頃にはこのツツジも散っていることでしょう。
境内、本堂の正面にある、オオヤマミツバツツジの花が咲き始めました。
まだ、2分咲きぐらいですが、連休中には満開になります。
5月15日の花祭り敬老会まで咲いてくれればいいのですが・・・
満開になりましたら、写真をアップします。
○歎異の会(歎異抄の学習会) 今月は休みです。
○法音の会(仏教讃歌を歌う会) 今月は休みです。
「人間は 自分は絶対に正しいと思い込んだ時に 最も残酷な事をする」
司馬遼太郎
今も昔も、親は子育てに悩むものです。自分が親に育てられた体験はあっても、自分の子供の教育となると何でも初体験となります。子育てで分からない事があれば、今まで子育てをしてきた自分の親や、子育ての先輩に相談し、育児の悩み事を聞いてもらいながら親として育てられていきます。しかし現代は核家族の生活や、横のつながりが希薄なために、育児書やインターネットが相談役を務めてくれます。もっとも情報が多すぎて何が正しい事なのか分からない事がありますが、その時々の最善の選択をし問題を解決しようと試みます。しかし、思い通りには行かない事の方が多いようです。そんな時、自分自身はどんな姿をしているでしょうか。
私自身も経験のあることですが、他から得られる情報や今までの経験、その時々の善悪の判断で「正しい」と思ったことが相手(子供)に通じなかった時に、一瞬にしてカッとなり「阿修羅」に変貌します。「我を忘れる」とはこの事を言うでしょう。罵声を浴びせ、以前しでかした失敗までも持ち出し、徹底的にやっつけようとします。それでも言うことを聞かない時には手が出ることも・・・。
その様に、自分の「正しい」という思いが相手に伝わらず、思い通りにコントロールできない子供に対して、叩いてしまう場合があります。その時子供は一時的に親の言うことを聞きますが「(親の)正しい理由さえあれば叩いても良い、残酷な事をしてもかまわない」ということが伝わるのです。そしてその子が、他人との関係の中で思い通りに行かなかった時には「叩く」という関わり方をしてしまう。「よい子、やさしい子に育つように」と願いながらも、実際は人を傷つけることを教えているのが自分自身ではないかと知らされます。
今月の掲示板の言葉を通して、自分勝手な正義を振りかざしながら、他を傷つけていることも気がつかない、その自分の姿を知らされました。また、これまで日本や世界で起こってきた戦争・弾圧・差別の歴史もまさに「自分は絶対に正しい」と思い込んだ人間の歴史そのものであります。自分は絶対に正しいという思い込みが強いほど、他人の悲鳴や叫び声が聞こえなくなる、そういう恐ろしさを知らなければなりません。
それでは一体何が「正しい」ことなのでしょうか。決して「正しいと思い込むことをやめましょう」と言うのではありません。本当の「正しい」こととは、私を私以上に見つめ、私を知り通して下さる教えそのものを言うのだと思います。しかし残念ながらその教えは、人間の智恵の中からは出てきません。人間の知恵を超えた仏陀(覚者)の教えこそが、私たちの本性を照らし出します。そして私自身の残酷な姿さえも包み隠さず教えてくださいます。
親鸞聖人はその教えを阿弥陀の光明として、「智慧の光明はかりなし」と和讃されています。私たちのたのむべき世界は阿弥陀の光であり、それこそが真実の依り処となるのであります。そして念仏は、弥陀の光明を日常の中で確かめさせて頂く、仏様からの呼びかけでもありましょう。
(貢 清春)
ここに居て 喜べず
ずい分 よそを捜したが
ここをはなれて 喜びは どこにもなかった 浅田 正作
今月の掲示板の言葉は、私たちが「ここ」という、依って立つ場に、世界に、私がどのように関わっているかを問いかける言葉です。
私たちは当たり前のように、「私は今ここで生きている」と思っています。そして自分の思い通りになることを空想して「ここ」だといっています。もしその「ここ」が自分の思いにそぐわない場所であったり、「ここ」に思いもしないことがおこってくると、途端にそこは「ここ」でなくなります。自分の思いのあてが外れるのです。
「自分はこんなところにいるべきものではない」と、現実に無関心になったり、自分を不快な目にあわせる人と「ここ」に一緒に居ることに耐えられず、攻撃的に他者を排除しようとします。
「ここに居て 喜べず ずい分 よそを捜したが」という言葉は、自分の思いを通して「ここ」を傍から眺め、品定めをして、「喜べず」、「よそ」に自分の思いを満たしてくれる場所を探している姿を教えているのです。あるがままに満たされず、その「悪し」とするここに居る私に背中を向け、より「善き」自己の実現を、未来のどこかに求め、さまよう、自分の思いに固執する者です。
『大無量寿経』では、「ここ」を自分の都合のいいように変えなければ、「喜び」はない、と自分の思いが満たされることを求めるものを「国王」と名付けています。
しかし、国王になりたいと求めつづけ、国と財と位を手に入れた豊臣秀吉は、命を終えていくときに「露と落ち 露と消えにし 我が身かな なにわのことも 夢のまた夢」という句を読んだといいます。国王となったが、その喜びは、はかなく、露のような人生だったといわなければならなかったのです。「ずい分 よそを捜した」けれども、満足を得ることはなかったのです。
救いは、苦しみから逃れることにかかりはてる、幸福の追求のところにあるのではありません。『大無量寿経』には、その「国王」が世自在王仏(この世において「我、ここにあり」と名告る仏)の説法を聞いて、敬い、大いに喜ぶ、「法蔵」という新しい自分に目覚めていく話が説かれています。
信心歓喜はわたしが何かを歓ぶ体験ではなく、実は、はじめてこの自分自身を歓べる体験なのです 宮城 顗 『真宗の本尊』
「ここをはなれて 喜びは どこにもなかった」。この言葉は、外に自分の思いの満たされることを求める私を「ここ」に呼び返す言葉です。呼び返されて振り向けば、「ここ」は私も人も共に生きることのできる出会いの場所です。「あなたはそこにいる」といのちの願いに呼び覚まされるところに、願いに生きる生活が始まります。
(深草誓弥)
春彼岸会法要の御案内
救われるということは 場所を給わること。 (宮城(みやぎ) 顗(しずか))
今に生きる子どもたちにとって耐え難いのは、居場所がないということでしょう。その居場所とは、自分を深く見つめ、他の人と語り合うことのできる精神的場所を意味します。
本来は家庭、あるいは学校が、生活の中で一番の居場所であるはずです。ところが、安心できるはずの家庭でいらいらしている。親子兄弟の心の疎通が持てない。学校は一番友達と出会えるチャンスがあるにもかかわらず、その学校で孤独であり、いじめの恐怖におののいているというのです。それは大変なストレスを感じると思います。
宗教的に見たら、本当の救いとは、浄土を見いだすことと言ってよいでしょう。その浄土とは、あなたとわたしが、当たり前の人間としての愛と優しさをもって関わり合える場所です。浄土がわたしの身と心に見いだされたとき、安心して娑婆(泣いたり笑ったり怒ったりしている現実の世界)に生きることができるのです。
宮城(みやぎ)顗(しずか)先生は、「救われるということは、そういう浄土の場をいただくこと」と言われるのです。 (中村薫)
春の彼岸会法要を下記の如く厳修致します。お彼岸を通して諸仏となられたご先祖を偲びつつ、聞法の御縁にお遇い下さいませ。 合掌
記
日時 平成25年 3月17日(日)~23日(土)までの7日間、午前9時30分開筵
講師 小松市 日野 賢之師 (19日~23日)
福浄寺 住 職 (17日・18日)
苦しみがなくなるということは、苦しみを生かしていくことができるということ (蓬茨祖運)
お釈迦様は、”一切皆苦”(すべてはみな苦である。)と、私たちが人間として、いのち与えられて生きる現実を示しておられます。つまり、苦を避けて生きるということは出来ないのです。しかし、苦しみは、どこか外にあるのでは無く、現実を見ず、何でも自分の思い通りにしようとする、私たちの”執着”に原因があると教えられています。では、「苦しみを生かしていく」とは、どのようなことなのでしょうか。
今月の言葉と向き合う中で、故郷のあるご門徒さんのことを思い出しました。この方は、自坊のご門徒さんではないのですが、長年にわたり、自坊のお世話をして下さっておられたようです。私の幼い時の記憶なので、はっきりとはしていないのですが、その方は、片足で自転車に乗っておられました。後で、両親にその方のことを聞くと、生まれつき身体が不自由で小柄でしたが、いつも自転車を使って外出しておられたようです。晩年、病気を患い、病院に入院されたようですが、”家で死にたい”と言い、自宅に移り、療養されていたそうです。
そんなある時、お連れ合いのおばあさんに、正信偈の本を持ってくるように言い、布団に横になったまま、おばあさんと一緒に正信偈を読んでおられたそうです。しばらくして、ふとお勤めを止めて、寝ている布団の足元の方を差して、”そこに、お迎えに来とられる”(富山県の方言)と、つぶやいたそうです。一緒に読んでいたおばあさんは、突然のことにびっくりして、その方が差す方を見て、必死にそのお迎えをどこかと探したそうです。しかし、何も見えないおばあさんが、”どこけ?”と、その方に声を掛けると、”ごめんもらうちゃ”(これにて失礼させていただきます)と言って、間も無く息を引き取っていかれたそうです。
不自由な身体で大変なご苦労をされたと思います。それは、他人には言わない、また言えない、苦悩もたくさんあったに違いありません。長い歩みの中で、なぜ自分だけこんな目に遭わねばならないのか、と悩まれたこともあったでしょう。しかし、おばあさんに、”ごめんもらうちゃ”と言った一言には、深い感謝の気持ちがあるように思います。それは、苦労を共にしたおばあさんに対しても、自分自身に対してもと思います。長く辛い人生の中で、お念仏の教えに出会い、自分の身体や病気と向き合い、そのことすべてが、与えられた尊い身として、うなづいていかれたのではないでしょうか。
親鸞聖人は、教行信証の冒頭に、「円融至徳の嘉号は、悪を転じて徳を成す正智」と、九十年の生涯を通して、聖人ご自身が体得なさったお言葉があります。”お念仏は、自分にとって都合の悪い事を、私を育ててくださるものへと転換してくださる大きなはたらきである”と、断言したその姿勢は、まさしく、今月の言葉に繋がるのではないでしょうか。 (立白法友)
私が 私の 存在の背景を知るということが 恩を知るということである
幼な児がお盆にお茶をのせてヨタヨタと運んでいる。後ろからは母親が付いて回り、背後から幼な児のお盆を持ってお茶をこぼさないように手助けをしている。幼な児はきゃっきゃっと笑いながらお茶を運んでくる。このような姿をお参りの時に目にすることがあります。
大変ほほえましい光景です。幼な児は自分でお茶を運んでいる事が嬉しく、楽しくてたまりません。しかし目の前のお茶のことで精一杯で、自分を支えている背後の親の働き、心配などは気付きもしません。
この幼子の姿を通して私の日常を知らされる気がします。いつも自分の力だけで何でも出来て、その事を誇りに思い、背後で支えているはたらきに全く気付こうとしない。「自分が働いているから飯が食えるんだ」「自分が我慢しているから家が丸く収まるんだ」等々・・・。「自分が○○しているんだから」と、いつも慢心を起こし、傲慢な生き方しかしていない私の姿が知らされます。その様な思い上がりの心では、今ここにある自分を成り立たせておる歴史や背景を見失ってしまいます。
では、私の存在の背景を知るにはどうすればよいでしょうか。振り返って見ればいいのですが、自分の目で、自分の知恵才覚で知ろうと思ってもそれは容易ではありません。自分の力で「見た、分かった、知った」としても、分かったところは自分の思いや知識の範疇であって、それ以上のことは分かりません。狭く浅いところしか見ることは出来ません。
私たち真宗門徒は、聞法を生活の基調としてきました。仏法を聴聞し教えを聞き開いていくことは、人間の知識や常識を超えて、仏の目線から私や世間の姿を知らせていただくことであります。聞法を重ね、仏によって我が身を教えられていくことが、私の存在の背景も知らされていくことになるのでしょう。その営みにおいてこそ、私を成り立たせている全ての背景を恩としていただけるのだと思います。
身に受けているご恩の数は、数えることが出来ないくらい深く広いものです。この娑婆に生まれてきた事も、お念仏のご縁に出会い称えさせて頂いている事もご恩です。親鸞聖人は我が身を照らし、念仏の教えに導いてくださるはたらきを「如来大悲の恩徳・師主知識の恩徳」と尊ばれ敬われました。そのはたらきに目覚める中で、ご恩に応えていこうという生活の歩みが始まります。
この度、1月に勤まりました御正忌報恩講のご案内の中には、暁烏敏師の言葉として
「一年三百六十五日、一日として報恩の日で無いのはない。毎日が報恩講である。その報恩講の最も根本的なるものが親鸞聖人の御恩に対する報恩講である。・・・・毎年報恩講を営むことによって生活のよろこびと力とを鼓舞せられることである。」
とありました。この一年間も、お寺として沢山の法要を勤めて参ります。福浄寺の一年間の法要は、1月の御正忌報恩講にはじまり、12月の門徒報恩講に終わるという行事日程です。同じ様に、一日一日も報恩にはじまり報恩に終わる、その様な毎日を送って参りたいです。
(貢清春)
春季永代経法要御案内
春の永代経法要を来る2月22日から2月26日まで5日間奉修致します。
永代無量の経教に依って御先祖の遺徳を偲びつつ、報恩の誠を尽くさんがための聞法の御縁にお遇い下さいますよう、何卒お繰り合わせ御参詣下さい。
下記の日程でおときの用意を致しておりますが、都合のつかれる日でも構いません。おときは1回に限らず何回でもお座り下さい。
記
日程 平成25年 2月22日~26日 午前9時半開筵
法話 長崎市三重町 正林寺住職 松林大師
22日・・・木場、川原、石木
23日・・・大音琴、小音琴、口木田、数石、新百津、若草、旭ヶ丘、山手、東彼杵町
24日・・・中山、上組、野口、中組、宿、岩立
25日・・・下組、白石、小串、惣津、三越、上・下百津、栄町、城山、琴見ヶ丘
26日・・・五反田、猪乗、波佐見、その他の町外
御 正 忌 報 恩 講 案 内
恩に報ゆる生活
私共人間は、恩波の上に漂っている小舟のようなものである。前も恩、後ろも恩、右も恩、左も恩、過去も恩、未来も恩、私がこの世に居るということの一切が御恩である。この御恩は返しても返しても加わって来る。私共の生活は恩をうくる生活であると同時に恩に報ゆる生活である。この事を教えて下さったのが親鸞聖人である。聖人の教えが無かったら私は恩の中に居ながら恩を知らないでいたことである。これによって思うに聖人が私のうけている御恩の根本である。
1年365日、1日として報恩の日で無いのはない。毎日が報恩講である。その報恩講の最も根本的なるものが親鸞聖人の御恩に対する報恩講である。聖人の報恩講を営むことによって報恩の生活が明らかになるのである。毎年11月、聖人の報恩講に逢うごとに報恩の中に育って居る自分を明らかにして頂くのである。故に私は毎年の報恩講が生活刷新の根元であると信じて居る。毎年報恩講を営むことによって生活のよろこびと力とを鼓舞せられることである。
(暁烏 敏 『報恩講の案内状に添ふる言葉』から)
聖人の御恩徳を憶い、今年の御正忌報恩講を厳修させて頂きます。真宗門徒、又福浄寺にとりましても最も大切な法要でありますと共に、そのお荘厳(おかざり)にも多数の御門徒のご苦労と日にちがかけられた、寺門あげての仏縁です。昨年は当寺で宗祖の御遠忌法要を厳修致しました。その法要を勝縁として新たに更なる聞法の歩みを始めたいと思います。
どうぞ真宗門徒の証を立てるべくお繰り合わせ御参詣聞法下さり、またご一緒に勤行唱和をして下さいますようご案内申し上げます。
また、多くの方々の御縁をいただくことを願い、且つ、昔日の報恩講を偲びたく、粗餐でございますが、お昼のお齋を用意いたします。ご参詣の皆様、毎日お席について下さいますようお願い申し上げます。
合掌
記
一、日時 平成25年 1月22日より28日まで
日中 午前九時半 逮夜 午後七時半
一、法話 福浄寺住職・若院(22日日中~24日日中まで)
北九州・徳蓮寺 伊藤 元師(24日逮夜~28日まで)
一、勤行 正信偈 真四句目下(大谷声明集 四五頁から五九頁)
念仏、和讃 五ッ淘、五遍反し 回向 願以此功徳
煤はきて 心の煤は かへり見ず
越智越人
今月の掲示板の言葉を見て、思い起こしたのは年末の大掃除でした。いつのころから大掃除や煤払いが歳末の年中行事となったのかはわかりませんが、一年の汚れを落とし、新たな気持ちで新年を迎えるために、年末に行われるのでしょう。お世話になった場所や物に対する感謝ということもあるかと思います。
掃除をして綺麗になり、透明になった窓ガラスを見ていると、なにか晴れやかな気持ちになります。澄むことによって、さえぎりが無いかのように見通すことができます。内から、外から、物がはっきりと見えるようになります。
透明になる窓ガラスのように物事をはっきりと、あるがままに見る眼をもっているでしょうか。あるがままでは満足しないこころをもって見る眼しか持ち合わせていないようです。必ず自分の都合という色眼鏡を通して外を眺めています。綺麗に磨いたところが人から汚されようものなら、途端に自分のした仕事を台無しにしたと腹を立てますが、自分も含めた皆の場所ですから、自分も汚していますし、汚れるのです。だから掃除をするわけですが、掃除をして、綺麗な窓に酔いしれ、その窓を汚す人を排除するという、さかさまになった自分中心の心が起こってくるのです。掲示板の言葉のように、私には外の汚れしかみえないのです。
親鸞聖人は
罪業もとよりかたちなし
妄想顛倒のなせるなり
心性もとよりきよけれど
この世はまことのひとぞなき
と述べられています。試みに訳をしますと、
聖道の思想では「罪業というのは人間の執れにすぎない。罪業はもともと無いのであってこころの本来は清い。修行して汚い面を取り除いて清い姿にもどる」と教えている。しかし、その聖道の思想のもとにあるのは都合の善い、悪いと裁いている自分の思いを信頼しているこころがある。悪をやめて善を修めるというが、自分は善、正しいものだというところから罪悪を許さない、といっている、自力のこころを立場とした発想でしかない。
そのような自力のこころを立場として、そのように廃悪修善しようと努めて、綺麗なこころでいきている人がいるか、一人もいないではないか。
私たちはいろいろなことを問題にするが、その問題をあれこれと問題にする自分自身を問題にすることがなかなかできないのです。阿弥陀如来はその自分の思う潔癖な善悪の倫理がいのちを切り刻む刃であることを教え、「自分の思いでなく、事実をはっきり見なさい」
と語りかけます。
まことに如来の御恩ということをばさたなくして、われもひとも、よしあしということをのみもうしあえり。 『歎異抄』
深草 誓弥
現在の自分が、 今の如くあるのは、 これまで どのような出会いをしてきたのか、 の結果。
よき人と出会いたい。 (平野修) 平成24年12月
人間は出会いによって、その生き方が変わるということを、改めて思うことがあります。最近、幼い子供と接する機会が増え、その姿に照らされて、自分の幼いころの事をよく思い出すことが多くなってきました。そんな思い出の中に、中学一年生の終わりごろ、小学校の低学年から仲良くしていた友達からの電話の後に、「兄ちゃんはYくんと話すとき、口調も眼つきも悪くなる」と、母親から突然言われたことがありました。
自分では、意識して変えているわけではないのですが、どうもその友達と遊んだり、話したりしている自分が、普段家にいるときの姿と違うようなのです。そのことに、私は「そんなことはない いつものようにしている」と言い返しましたが、そのときに、なにか心につっかえをおぼえました。確かに、その友達と居ればなんだか楽しい、何でもできるような気がするのでした。
そんなことを思いながらも、そのYくんと関わりを続けていましたが、中学を卒業して高校に入学するまでの休日の間に、遊ぶ機会があり、いつものように遊んでいると、Yくんの持っている携帯電話の私の登録名が”日本猿”という明記になっていることに気づき、なぜそんなことをするのだろうと悲しみをおぼえたことがありました。そのとき、以前に母親に言われたあの一言が思い出されて、やっぱり関わってはいけない友達だったんだと、深く反省したことがありました。
今思うことは、心優しく育って欲しいと心から願っている母親が、横道にそれていく我が子を悲しみ、声をかけてくれたんだと思うのです。しかし、なかなかそのことに、聞く耳を持てないものを未だに抱えているように思います。また、なぜYくんが、私を動物に喩えて表現することしかできなかったのか、その心に潜む課題、向き合わなければならない問いを、与えてくれたように感じるのです。
蓮如上人の教えに、「『人のわろき事は、能く能くみゆるなり。わがみのわろき事は、おぼえざるものなり。わがみにしられてわろきことあらば、能く能くわろければこそ、身にしられ候うと思いて、心中を改むべし。ただ、人の云う事をば、よく信用すべし。わがわろき事は、おぼえざるものなる』由仰せられ候う。」と、わがみの事を、一番知っているのは、誰でもないこの私と思い込み、自分が間違っているなど疑いもしないで生きている日頃の姿が、どれほど迷いを深めているかを教えてくださっている言葉です。
私は当初、声を掛けてくれた母親が間違いだと思っていました。楽しく遊べる友達を見極められないのは、母親の方だと嘲笑っていました。しかし、それが間違いでした。Yくんのことを考えてみても、他人を影で笑う憎い存在としか思うことが出来ません。しかし、よく考えてみると、私も同じことを母親にしていたのです。そのことを知ったとき、Yくんを見る目線が変わって来たように思います。
今月の言葉は、よき人、”師”という存在が私たちにとって必要だということを言っていると思います。親鸞聖人は、師の法然上人を”よき人”と呼び、その出遇いを、
「曠劫多生のあいだにも 出離の業縁しらざりき 本師源空いまさずは このたびむなしくすぎなまし」
と、和讃に詩っておられます。”よき人との出遇いがなかったならば、この生もいたずらに過ごし、空しく終わっていただろう”と、師に出会う大切さを語っておられます。自分を知ったこととし、それで間違いないと決めつけ、”どうせ”と言いながら、自分と他者を比べて、ふてくされて生きる生き方を問い、与えられた身の事実と向き合い、その身のまま生き切ることの大切さを教えて下さる存在です。
”後生の一大事”という言葉を、蓮如上人は御文の中でしきりに使っておられます。それは、今の生き方で本当に死んでいけるのか、悔いを残さず命終えていけるのか、ということを示しています。ある先生は、”迷いの最後生を遂げる”ことができるのかという言葉で表しておられます。私は、母親には常に反抗してきました。こうしなさい、ああしなさいと言われるたびに、苛立ちを表に出し、声を荒げて”そんなことは分かっている”の一点張りで刃向ってきました。しかし、今回、幼い子供と向き合う中で、真実に人として生き切って欲しいと願う、親の願いが痛いほどわかりました。私の荒々しい言葉に、心痛めながらも、声を掛け続けてくれる母親の尊さを身にしみて感じました。どうでもいいことだと思っていた親からの呼びかけは、私がこの生において、迷いを超えていく確実な一歩であることを今月の言葉と向き合う中で、確かめることができたと思います。よき人という存在は、持つべき大事な存在です。それは、自分にとって都合のいい存在ではなく、常に自分の生き方を問い、悲しみ、育んでくださる存在です。どこかに居られるのではない、いま目の前にいる尊い存在が、私にとってかけがえのない”よき人”となっていく、そんな学びを続けていきたいと思います。 (立白法友)
門徒報恩講案内
今年も愈々師走になります。
就きましては、1月の御正忌報恩講から始まり、また本年の最後のしめくくりの法要、「門徒報恩講」を例年の如く下記により勤めさせて頂きますので、皆様、宗祖親鸞聖人の御恩徳を憶い、報恩感謝の志をお運び下さい。そして各地区仕出し当番の皆様の、昨今では中々味わえない手作りの精進お斎をいただいて下さい。皆様のお繰り合わせの御参詣を念じます。尚、参詣日は一応の目安です。都合の付かれる日でもかまいません。
当日の勤行は正信偈三首引きでつとめます。御和讃は、赤表紙の勤行本五六頁「三朝浄土の大師等」からの三首です。ご一緒にご唱和下さい。
日程(下線印は仕出し当番) 勤行は午前10時からです。
12月10日 木場講 (上、下)
11日 川原、石木講(上、中、下)
12日 音琴講(口木田、大音琴、小音琴、彼杵)
13日 西講ノ上(波佐見、中山、刎田、岡谷、川良、野口)
14日 西講ノ中(中組、宿、岩立、上、下百津)
15日 西講ノ下(栄町、城山、数石、住宅)
16日 西講ノ西(下組、琴見ヶ丘、白石、三越、小串、惣津、新谷) 日曜学校参加
17日 五反田(上、下)、猪乗講 及び町外
如来様は 私たちに 「生きてよし 死してよし どことても み手のまんなか」
の世界を お恵み くださっている 東井義雄 平成24年11月
死は、誰一人として避けられない問題です。生まれたときから約束された事実ですが、その死はいつ来るかはわかりません。しかし必ずやってきます。しかも老少不定と教えられる様に順番がありません。そう教えられていながらも、
「後生をばかつてねがわず、ただ今生をばいつまでもいきのびんずるようにこそ、おもいはんべれ。」(御文4帖目、第2通)
と蓮如上人が仰るように、自分だけは何故か特別で、いつまでも長生きできるであろう、今の状態がいつまでも続くであろうと考えています。そのことを親鸞聖人は「わがみをたのみ、わがこころをたのむ」自力の姿として教えられています。その様な自力に生きる、「生き延びたい、死にたくない」という私の日常の心からは「死してよし」という心は生まれて来ません。
我が身をたのむ自力の心は、生きる事だけに執着しているため、死はイヤな事であり、恐怖であるため避けて通ろうとします。さらに死を連想させる「四」という数字さえ、病院やホテルに使えないほど徹底しています。世間の常識でも死はマイナスのイメージしか無く、口にする事もはばかれるという認識です。
東井義雄さんは「生きてよし、死してよし」という安心をいただいておられます。それは人間の自力のはからいから出て来た言葉ではないようです。如来が摂取不捨する、大慈悲のおはたらきによるものです。そのはたらきは、老若男女を問わず、才能の有無や世間の地位も関係なく、どの様な人でも包み込む世界、無条件に摂取して捨てないはたらきです。この身このままが、如来様の恵みの世界の中にあって、自力で右往左往している私でさえ、如来様の手の中で受け止めてくださっている。その様な、あらゆる者を救い遂げようと、はたらき続けている世界に目覚められた言葉であると思われます。
しかし如来様に出会えば、摂取不捨のはたらきに出会えば、浅はかな自力の根性が無くなるという訳ではありません。また、「死にたくない私」が「死が覚悟できる、殊勝な私」となる訳でもありません。そういう自力をたのむ我が身がそのまま「み手のまんなか」で支えられ、信じられ、敬われている。だからこそ「生きてよし 死してよし」と如来様に身をまかせ、人生を託して生きていける。その様にはたらく世界を恵まれるのであり、その世界を親鸞聖人は「浄土」と教えて下さいました。
死は、誰一人として避けられない問題です。死を問う事えば、自然と今の生き方が問われてきます。この人間の切実な問いの為に、如来様の教えが説かれているように思います。今月の東井義雄さんの言葉は、私の生死観を大きく問う言葉としていただきました。
貢 清春
称えさせて下さる お方がなくて
この罪悪のわが身が
どうして佛のみ名を 称えることができようか
徳龍
この度、10月26、27、28日と、福浄寺において親鸞聖人750回御遠忌法要を厳修いたします。御遠忌法要をお迎えするにあたり、「親鸞聖人とは誰であったのかを確かめながら、聖人の遺教に自身の相をたずね、言葉になった聖人に遇い、念仏もうす身とならせていただくことが、御遠忌という仏事を勤めるということの意義である」と、先学から教えられていることを、あらためて噛み締めています。
親鸞聖人は、浄土真宗を「本願を信じ、念仏をもうさば仏になる」教えであると顕かにされました。
念仏は念じたもう仏を念ずることです。「我が名を称するものを迎え取らん」という阿弥陀如来の摂取不捨の本願が念仏として私に届けられ、その念仏にいかにいきることが空しくない生を生きることになるのかを聞く。如来の本願は「しからしむる力」、私たち一人ひとりの存在が根源から求めている、「いのちの願い」です。
掲示板の言葉にある「罪悪のわが身」とは、その「いのちの願い」に背く私たちのすがたを「罪悪」と教え示されている言葉であろうと思います。私たちは「邪見驕慢悪衆生」と『正信偈』に教えられるように、自分の考えに固執して、このうえないと思い、他を理解せず、断絶を起こす「邪見」をそなえ、他人と自分を比較し、自分を愛し守り続けようとする「驕慢」の心をもっています。
その「邪見驕慢」の心が、生活をおろそかにします。自分の思いを中心として善し悪しと分別し、「こうなればいいのに」とその思いの満たされることを求め、自分の思うようにならないときは「これは自分ではない」と思いの世界に沈み、思いどおりになるときは何もかもが自分の思うようになるようにふるまいます。これらの生き方はどちらも「自分の思いの世界」を生きるもののことで、その自分の「えらび、きらい、みすてる」思いが自分も他者も傷つけていきます。
「称えさせて下さる お方」とは、そのような自分の思いを信じて生きる者に、その自分の思いが自分も他者も生きさせない原因であることを知らせ、阿弥陀如来の摂取不捨の本願、「えらばず、きらわず、みすてず」の心こそが真実であるとうなずく南無阿弥陀仏という信心こそが、どのような現実であっても引き受けて、生きていくことのできる、存在そのものがもつ力であることを呼びかけてくださる人です。
その呼びかけを竹中智秀先生は「現実に目をつむるな、逃げるな、現実を受け止めて、踏みとどまって、そこで本当にしなければならないこと、したいこと、できることを確認し、そのことに力を尽くして苦労して生きていけ」と教えられました。その先生の呼びかけをうけて、私も念仏を申そうと思うのです。 (深草誓弥)
○歎異の会(歎異抄の学習会)
10月は御遠忌法要の為中止します
○法音の会(仏教讃歌を歌う会)
日時 10月4日(木) 、9日(火)、16日(火)19:30より 御遠忌法要の練習です。
場所 福浄寺本堂
○仏教青年会
10月は御遠忌法要の為中止します
○日曜学校
日時 10月6日(土)9:00~10:00
秋季彼岸会法要の御案内
不治の病床に身をよこたえた幼な子が、母に尋ねた。「お母さん、死んだらどうなるの」と。ただ口先ばかりの 慰めの言葉をくり返すことの空しさに耐えかねた母は、祈るようにして答えた。「坊や、仏さまの国へ往くんですよ。お母さんも、きっと後から往きますから、 待っていてね」と。幼な子は、つぶやくように言った。「うん、待っているよ、きっと来てね」と。数日の後、幼な子は死んだ。わが子に先立たれた悲しみのな かで、残された母は自らに語る。「私は、坊やとの約束をはたさねばならない。でないと、坊やをだましたことになるのだから……」と。
親鸞は、ひたすらに語りかける。「ひとえに往生極楽の道をといきかんがためなり」と。 (廣瀬杲『滴々抄』より)
拝 啓 異常な暑さが続きますが、皆様ご健勝にお過ごしのことと拝察いたします。さて、今年もお彼岸の時期となりました。毎年この時期になると彼岸参りが恒例 となっています。しかし、そのお参りが単なる墓参りや供養としての通過儀礼で終わっているような気がしてなりません。亡き人を通して、自分自身の生き方を 見つめ直す大事な御縁としていきたいものです。
秋の彼岸会法要を下記の如く厳修致します。何卒、有縁の皆様をお誘い合わせの上、御参詣下さり、聞法という御縁にお遇い下さいませ。
合掌
記
日時 平成24年 9月19日~25日の7日間、午前9時半開筵
講師 姫路 明泉寺若院 名和 達宣師 (20日~23日)
福浄寺住職 (19日、24~25日)
川良山 福浄寺
御門徒皆様
福浄寺夏の集い開催
「手作りロウソクをを作ろう」
溶かしたロウソクをを牛乳パックで固めて、絵を描いて自分だけのロウソクを作ってみよう。
日時8月22日(水)9:30集合
[日程]
9:30~ 集合 ロウソク作り(1)
10:00~ おつとめ
11:00~ ロウソク作り(2)
12:00~ お昼ご飯 (カレー)
13:00~ 仙台の方に手紙を書きます
14:30~15:00 片付け 解散
○日 時:平成24年8月22日(水)9時30分~
○場 所:福浄寺本堂
○参加対象:小、中学生
○参加費:無料(当日、さい銭100円を持ってきてください)
○持参品:勤行本(赤いおつとめのほん)、お数珠、、水筒、筆記用具、色鉛筆、クレヨン、牛乳パック(500mlのもの)、軍手(厚手のもの)、野菜(にんじん、じゃがいも、玉ねぎ 各1つずつ)←(無いところは、結構です)、お米 1合
*当日、出席の方は事前にお電話をお願いします。
福浄寺 ℡ 82-2154
福浄寺仏教青年会 公開講座
テーマ 「原発・震災とお寺(仏教)の役割」
今回、福浄寺仏青の8月のテーマ「原 発・震災とお寺(仏教)の役割」と題して公開講座を開きます。講師には、福島県相馬市で今当に原発の問題に直面されている、正西寺の若坊守、八幡祥子さん を迎え現状報告と、八幡さんが考えるお寺の役割についてお話をいただきます。八幡さんは仙台仏青でボランティアに携わり、福浄寺日曜学校とも手紙支援で交 流を続けているお方です。その後、住職より原発の問題から、長崎教区が掲げる「非核非戦」について話をいただきます。自分自身を問い直す大切なご縁にして いただきますよう、どうぞお誘い合わせの上御参詣下さい。
日時 : 平成24年 8月31日(金) 午後7時半~10時
場所 : 福浄寺本堂
講師 : 八幡 祥子師 (福島県相馬市正西寺若坊守)
「福島からの声」 ~現状報告とお寺の役割~
深草 昭壽師 (福浄寺住職)
「非核非戦」 ~原発を通して考える~
○歎異の会(歎異抄の学習会)
日時 8月28日(火)
場所 福浄寺門徒会館
学習箇所 第4条
○法音の会(仏教讃歌を歌う会)
日時 8月21日(火)19:30より
場所 福浄寺本堂
○仏教青年会 公開講座
日時 8月31日(金)
場所 福浄寺本堂
講題 原発・震災とお寺(仏教)の役割
講師 八幡 祥子師 (福島県相馬市正西寺若坊守)
「福島からの声」 ~現状報告とお寺の役割~
深草 昭壽師 (福浄寺住職)
「非核非戦」 ~原発を通して考える~
○日曜学校
①日時 8月6日(月)9:00~10:00まで
②日時 8月22日(水)9:30~15:00まで
夏の集いでローソクを作ります
平成24年7月
過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となる
暑くなり8月が近づいてくると、原爆・戦争の体験談や、当時の白黒の映像がセミの声と同時に蘇ってきます。また終戦記念の月でもあり、67年前の日本の事を感ぜずにはおれない時期でもあります。
ここ数年、特に感じることですが、民放テレビの放送で原爆や戦争に関係する番組は、皆無に等しい事に気づきます。それほど日本人の戦争、原爆に対する関心がないということです。8月15日であってもお笑い番組やクイズ番組を見て夜の時間を過ごし、全く変わらない日常を過ごしてしまう。67年前のあの惨劇に一時でも心を傾けてゆくような時間さえも持てない現代人を、原爆被災者、戦争体験者はどのように見ておられるでしょうか。
人間の過去の過ちの歴史に目をつむり、日常の快楽だけに翻弄される生き方はまさしく「迷い」であり、現在の生き方をも見失っていく様をヴァイツゼッカーは「過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります」と演説されました。
この言葉は、1985年5月8日、戦後40年の節目の年。当時の西ドイツ大統領ヴァイツゼッカーが国会で行った演説の中の一言であります。ドイツは第二次世界大戦中、ヒトラーの独裁政治の下、ユダヤ人を大量虐殺した過去の歴史を抱えています。ヴァイツゼッカー大統領はその「負の歴史」の真実に真向かいとなり、間違いを犯した過去に一人一人が責任を負う事の大事さを「罪の有無、老幼いずれを問わず、われわれ全員が過去を引き受けねばなりません。だれもが過去からの帰結に関わり合っており、過去に対する責任を負わされております」と演説されています。
しかし私自身の実体は、失敗した過去の事にくよくよしたり、無かった事として覆い隠すような事があります。「明日があるさ、明日を信じて前向きに」と、今のこの現実に目をつむり未来に夢見て、現在を直視しない事も多いように感じます。「非人間的な行為を心に刻もうとしない者は、またそうした危険に陥りやすいのです」ヴァイツゼッカー大統領はドイツの過去の歴史を直視した上で謙虚に学び、同じ過ち「非人間的な行為」をこの現在に於いて繰り返してはならないと叫ばれます。
現代における様々な社会問題、いじめや差別、幼児虐待、自死問題、原発事故、等々についても同じ事が云えるのではないかと思います。まずは問題の歴史(負、過ちの歴史)を学ぶ事を通して現在が方向付けられていくのではないでしょうか。
過去を学ぶ事は、人間(自分自身)を学ぶという事だと思います。自分はそんな事してないから関係無いという事では無く、同じ人間が犯した過ちとして、どこまで我が身の事として掘り下げていけるか、その事が問われれています。
(貢清春)
「罪の有無、老幼いずれを問わず、われわれ全員が過去を引き受けねばなりません。だれもが過去からの帰結に関わり合っており、過去に対する責任を負わされております。
心に刻みつづけることがなぜかくも重要なのかを理解するために、老幼たがいに助け合わねばなりません。また助け合えるのであります。
問題は過去を克服することではありません。さようなことができるわけはありません。後になって過去を変えたり、起こらなかったことにするわけにはまいりません。しかし過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります。非人間的な行為を心に刻もうとしない者は、またそうした危険に陥りやすいのです。」
「荒れ野の40年」ヴァイツゼッカー大統領演説全文 永井清彦訳(岩波書店)より抜粋
8月の「婦人会法筵」・「盂蘭盆会法要」の御案内
一りんの 朝顔に
かすかな 呼吸のような風 ―山村暮鳥―
田舎駅のホームに朝顔の花が清々しく咲いていた。毎朝掃除に来るお婆ちゃんの丹精の賜物である。そばに立て札があった。表には「美しく 咲きます」とかわいい字で書いてあり、その裏には「美しく 咲かせます」と書いてあったという。
「咲かせます」はお婆ちゃんの自信であり、切なる願いであろう。「咲きます」は朝顔の生命の願いであり、それはやむにやまれぬ生命の純粋意欲である。
咲きたいという内なる願いと、咲かせたいという外からの願いが成就して一輪の朝顔の花が咲く。そよ風は、目には見えないが、そっとささやく。「ほんとうによかったね」
毎年八月は、原爆投下、終戦、お盆と、いのちについてあらためて考える大切な御縁となる月です。二度の世界大戦を経験した今でも、世界各地で戦争がやむこ とはありません。だからこそ、戦争でなくなった方、親、御先祖を思い、私達が今ここに生きている意味を今一度問い直し、いのちのつながりやひろがりを感じ ていく事が大切なのではないでしょうか。
この「婦人会法筵」は、婦人会が開いて下さる福浄寺の法要です。会員皆様に限りませんので御門徒皆様もお誘い合わせの上、御参詣下さい。
婦人会法要
日時 8月3日(金)~5日(日)までの3日間 午前9時半開筵
法話 崎戸 真蓮寺住職 寺本 温師
盂蘭盆会法要
日時 8月16日(木)午前9時半開宴
法話 寺中
納骨堂読経 8月13日~15日午後6時
7月の「作上がり法筵」の御案内
拝啓 梅雨の季節となりましたが、皆様御健勝にお過ごしのことと拝察いたします。
さて、今年も「作上がり法筵」を迎えることとなりました。
かつては、梅雨を迎え田植えが終わる頃になると、土に、雨に、草木に大小の生き物に眼を向け、自然(しぜん)の働き・恵みを、自然(じねん)の世界として 受け止め、人間の思惑、分別、はからいを超えた世界を実感してきました。その思いを私たちの先祖は、「作上がり法筵」という、仏縁として大切にしてきまし た。
去年3月11日に起こった東日本大震災と東電福島原発事故を通して、私たちは自分の思い通りにはならない生老病死の現実を目の当たりにしま した。来る10月にお迎えします宗祖親鸞聖人750回御遠忌法要を勝縁として、宗祖のお言葉と先人たちの声に耳を傾けながら、いのちの厳粛さを確かめなけ ればならないのではないでしょうか。
何卒、有縁の皆様をお誘い合わせの上、御参詣下さいますように宜しくお願い致します。
日 時 平成24年 7月6日(金)より7月8日(日)
午前9時半より開筵
法 話 福浄寺住職・若院・貢・立白
春季永代経法要御案内
春の永代経法要を来る2月22日から2月26日まで5日間奉修致します。
永代無量の経教に依って御先祖の遺徳を偲びつつ、報恩の誠を尽くさんがための聞法の御縁にお遇い下さいますよう、何卒お繰り合わせ御参詣下さい。
下記の日程でおときの用意を致しておりますが、都合のつかれる日でも構いません。おときは1回に限らず何回でもお座り下さい。
日程 平成24年 2月22日~26日 午前9時半開筵
法話 22日、23日 大村市 西教寺住職 田中顕昭師
24~26日 長崎市三重町 正林寺住職 松林大師
22日・・・木場、川原、石木
23日・・・大音琴、小音琴、口木田、数石、新百津、若草、旭ヶ丘、山手、東彼杵町
24日・・・中山、上組、野口、中組、宿、岩立
25日・・・下組、白石、小串、惣津、三越、上・下百津、栄町、城山、琴見ヶ丘
26日・・・五反田、猪乗、波佐見、その他の町外
御正忌報恩講案内
恩に報ゆる生活
私共人間は、恩波の上に漂っている小舟のようなものである。前も恩、後ろも恩、右も恩、左も恩、過去も恩、未来も恩、私がこの世に居るということの一切が 御恩である。この御恩は返しても返しても加わって来る。私共の生活は恩をうくる生活であると同時に恩に報ゆる生活である。この事を教えて下さったのが親鸞 聖人である。聖人の教えが無かったら私は恩の中に居ながら恩を知らないでいたことである。これによって思うに聖人が私のうけている御恩の根本である。
一年三百六十五日、一日として報恩の日で無いのはない。毎日が報恩講である。その報恩講の最も根本的なるものが親鸞聖人の御恩に対する報恩講である。聖人 の報恩講を営むことによって報恩の生活が明らかになるのである。毎年十一月、聖人の報恩講に逢うごとに報恩の中に育って居る自分を明らかにして頂くのであ る。故に私は毎年の報恩講が生活刷新の根元であると信じて居る。毎年報恩講を営むことによって生活のよろこびと力とを鼓舞せられることである。
(暁烏 敏 『報恩講の案内状に添ふる言葉』から)
聖人の御恩徳を憶い、今年の御正忌報恩講を厳修させて頂きます。真宗門徒、又福浄寺にとりましても最も大切な法要でありますと共に、そのお荘厳にも多数の御門徒のご苦労と日にちがかけられた、寺門あげての仏縁です。
どうぞ真宗門徒の証を立てるべくお繰り合わせ御参詣聞法下さり、またご一緒に勤行唱和をして下さいますようご案内申し上げます。
また、多くの方々の御縁をいただくことを願い、且つ、昔日の報恩講を偲びたく、粗餐でございますが、お昼のお齋(とき)を用意いたします。ご参詣の皆様、毎日お席について下さいますようお願い申し上げます。
合掌
記
一、日時 一月二十二日より二十八日まで
日中 午前九時半 逮夜 午後七時半
一、法話
北九州・徳蓮寺 伊藤 元師(二十三日日中~二十六日日中まで)
大瀬戸・光明寺 武宮 學師(二十六日逮夜~二十八日まで)
一、勤行 正信偈 真四句目下(大谷声明集 四五頁から五九頁)
念仏、和讃 五ッ淘、五遍反し
回向 願以此功徳